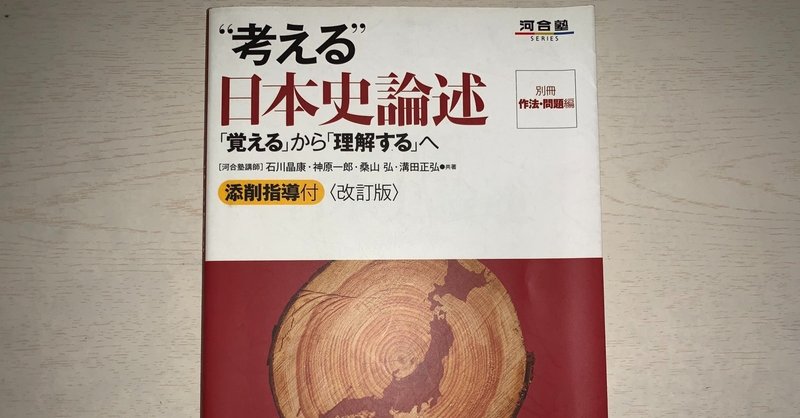
【参考書レビュー】''考える’’日本史論述
基本情報
書名:''考える''日本史論述
著者:石川晶康・神原一郎・桑山弘・溝田正弘(共著)
出版社:河合出版
ジャンル:問題集
ねらい:論述の基本(作法)を身につける
対象:論述問題が課される大学志望の受験生
前提レベル:センター8割以上安定くらいの基礎知識/論述の経験はなくてもよい
強み
まず、「作法」にあたる「Chapter1 日本史論述へのアプローチ」の存在が挙げられます。これは、「教科書の論述的読み方」という文章から始まり、論述問題に挑む受験生が知っておくべきことを体系的に示した章です。論述初学の受験生にとっては一発では理解できませんが、やっていく中で理解しましょう。
次に、解説の丁寧さです。要求をつかむことから始まり、解答に至るプロセスを丁寧に書いてある上に最後に採点基準がついています。これなら論述独学も可能でしょう。
また(この接続詞は「作法」で否定されていますが)、添削例が4つ掲載されており、それがなかなか辛口で鋭い添削なので、受験生が陥りやすいミスを体感することができます。受験生の印象に残るための工夫が随所に施されていると言えましょう。
注意点
この本を手に取ると、「作法」にあたる「Chapter1 日本史論述へのアプローチ」を熟読してから問題に入らなければいけない、という謎の義務感を持ちがちですが、実際に問題に取り組むことなしに内容を全て入れることは不可能です。「これはすぐにできそうだから気をつけよう」というところだけ印をつけつつ一通り読んだところで演習を進めましょう。あとは演習を進めながら定期的に見返して、理解できるところから身につけていきましょう。経験を積むごとに、ピンとくる箇所が増えてくるはずです。
使い方(あくまで一例)
東大志望者であれば、「高2のうちに通史が終わってしまい、過去問へのつなぎとなるような論述の問題集が欲しい」という場合にうってつけです。他の大学志望ならばこの本を秋までやって、あとは過去問で仕上げ、くらいでも十分いいと思うのですが、東大の場合その独自の形式に慣れなくてはならないので夏にはこの参考書は終わらせて&見切りをつけて、過去問演習に入りたいです。
作法部分との付き合い方については、「注意点」で述べた通りです。基本的には前から「例題」「参考例題」を解いて行って、解説に採点基準がついていますからそれに則って採点する、という流れになります。志望大学に相当偏った傾向がない限り、全ての問題を解くつもりでいましょう。「問題見ただけで大体答えがわかるな」という問題でも、実際に手を動かして書きましょう。
※なお、志望校の過去問が掲載されている場合、過去問演習のことを考えて飛ばすのはこの限りではありません。
添削問題については、東大志望者が提出するのはコストに見合わないと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
