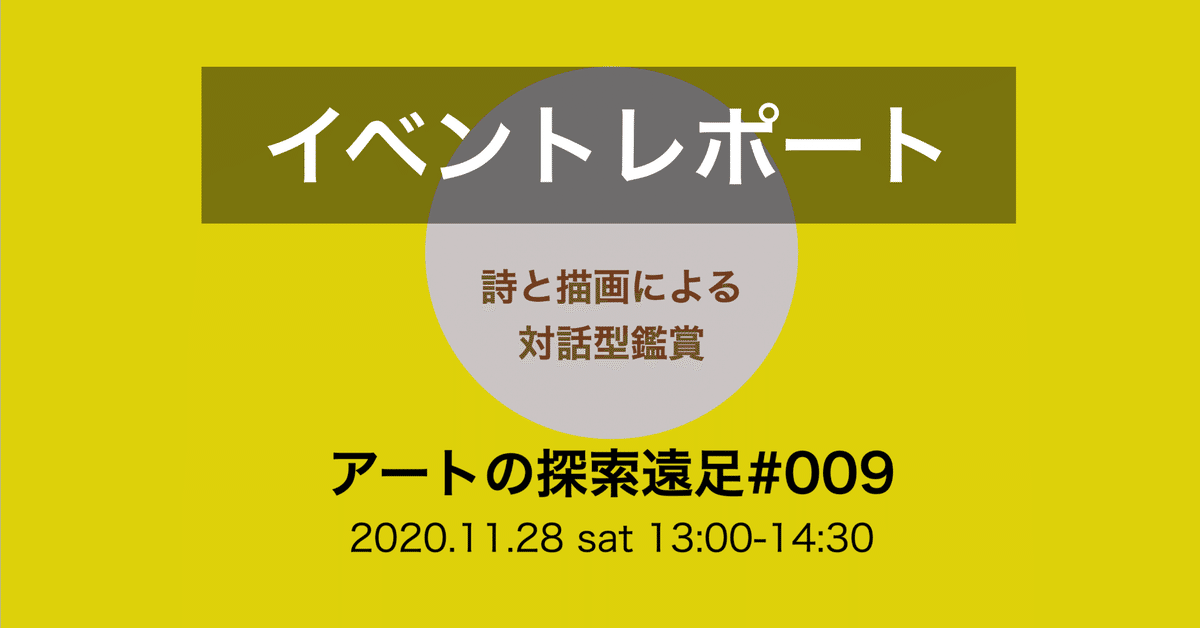
「詩と描画による対話型鑑賞」とはなにか?
こんにちは、臼井隆志です。今日は「詩と描画による対話型鑑賞」イベントのレポートを更新します。
このマガジンは、アートワークショップを専門とする臼井隆志が、ワークショップデザインについての考察や作品の感想などを書きためておくマガジンです。週1~2本、2500字程度の記事を公開しています。
ご購読はこちら👇
ーーーー対話型鑑賞の方法への2つのアレンジ
11/28(土)、ある作家の詩を題材とした対話型鑑賞のイベントを行った。といっても、従来の方法に大幅にアレンジを加えたものである。
従来の対話型鑑賞と言われる方法では、言葉による発話をメインとする。
「何を感じる?」「どこからそう思う?」といったファシリテーターの問いかけに対し、参加者は「優しい雰囲気を感じた」「花の輪郭がぼんやりしているから」というふうに言葉を使って話をしていく。
今回はそこに加えて、2つアレンジをした。1つは、鑑賞して感じたことを言葉にする前に、紙に線やイメージ、オノマトペを使って書き出してみるという表現手段を提案した。
もう1つは、目を開けて絵画を見るのではなく、目を閉じて詩を聞くというふうに鑑賞方法に変えた。目を閉じることによってさまざまな感覚の記憶が呼び起こされることを「虚体験」のワークショップを通じて知ったことに影響を受けている。企画の背景はこちらのnoteに詳しいので、ご興味のある方は是非読んでみてほしい。
ワークショップには、子どもとのワークショップを主宰されている方や、手話通訳をされている方、画家や研究者、デザインや執筆に関わる方々など、多様な方々が集ってくださった。
ワークショップの流れ
ワークショップは、以下のような流れで進行した。

冒頭にある「触発とデュアルフォーカス」とは、創造性の研究者である石黒千晶さんに教えていただいた概念だ。
「触発」とは、他者の表現や行為をみることで、新しいアイデアやイメージ、モチベーションの高まりを感じることだ。その触発は「デュアルフォーカス」、つまり『他者作品の評価』と『自分の創作への省察』を行き来すること、その2つの視点で作品を鑑賞することで起こりやすくなる。
ここに加えてぼくは、1つの仮説を立てた。単に作品を論理的・分析的に評価するのではなく、感性的・情動的に味わい、感じたことを非言語メディアで表現しながら探索することで、より触発が起こりやすくなるのではないか?というものだ。そのため、オノマトペや描画という活動を加えた。
チェックインでの「あなたの気分をオノマトペで表すと?」という活動から、空気が変わり始めた。


オノ・ヨーコ作品をめぐる3つの問い
選んだ作品は、オノ・ヨーコ『グレープフルーツ・ジュース』の一節だ。詩というよりも言葉をメディアとしたアート作品である。

是非このレポートを読んでいる皆さんにも目を通し、どのような印象をおぼえるか、オノマトペや描画を通して描いてみてほしい。
ぼくがこの一節を選んだり理由はおおきく3つある。
1つには、ティシュー、ゴム、といった「素材」を想起させることだ。詩の途中で、想起させる素材が変わる。ティシューからゴムへの素材の変化が起こるときに起こった感覚とはどのようなものか。
2つめに、ひろがる、ちぎる、つるすと「動き」を想起させること。オンラインワークショップにおいて乏しくなりがちな身体の運動感覚が、これらの言葉によってどのように想起するのか。
3つめに、「命令形」であるということ。オノ・ヨーコ作品の代名詞とも言える「命令形」だ。「想像しなさい」は、英語で言えば「Imagine」である。そう、ジョン・レノンのかの曲を触発したのがまさにこの命令形の作品のありかただった。このように命じられることによる鑑賞者への介入は、どのような力をもつのか。
素材・身体の感覚を命令形によって想像させるアートが持つパワーを知りたい。その言葉のあり方が、コロナ禍においてリモート状態になっているぼくたちの心や体のあり方を、新たに変える可能性をもつと思うからだ。
参加者が描き出したイメージ
詩を読んだ後に眺めてみてほしい。

☝️こちらは、線グラフのように左から右へ軽さ、重さが表現され、そのまわりに感覚をあらわすオノマトペが書かれている。細い線から太い線に変わった場所は、「ティシュー」から「ゴム」に素材が変わったことが表されており、真ん中に強く書かれた目は、「命令形」によって生まれた「見られている」印象を描いたものだ。

☝️こちらは、「すー」「さわさわさわ」と横に書かれ、次に縦に「すー」と書かれている。横に書かれたオノマトペは「ティシュー」のように広がる感覚を示し、縦に書かれた「すー」は、「ベッド」のそばに「ゴム」が吊るされたときの重さの感覚が縦方向に現れている。

☝️こちらは、方々にひろがる水玉のような模様は、「ティシュー」のように広がる様が現れている。空間への広がりは、社会や世間といったものを想起させたとのこと。左下にある赤や黒の水玉は、他者がおなじように「ティシュー」のように広がってきた様が示されている。中央にいる人は、「ベッド」という言葉から私的な空間に戻ってきた穏やかさが表されている。
対話のキーワード:受容と拒絶
参加者の方々の、詩との関わり方は多様で面白いものだった。要約として、3つのキーワードをあげたい。
1つめは、「受容と拒絶」である。
オノ・ヨーコの命令形に対する反応だ。すんなりと受け入れられる人もいれば、「みられている」ということに対する恐れや緊張の感情をおぼえる人や、「想像したくない」と拒絶する人もいた。
ティシューのようになって気持ちよく広がっていたのに、ゴムを想像するなんて無理。気持ちよくいさせてほしい。
普段から筋トレをして強い体を目指しているのに「ティシューのようになる」などいやだ!
このような拒絶の反応だ。なぜ拒絶したいという衝動にかられたのか、拒絶しながらも想像しようとしたことは何か、といった問いで対話がなされた。
オノ・ヨーコの命令形の文体は、鑑賞者に良くも悪くも強く働きかけることがよくわかった。その働きかけ方が「声/朗読」によるものだったことも影響が大きいかもしれない。
対話のキーワード:触覚性
2つめは、「触覚性」だ。
ティシューやゴムの手触りを感じながら、身体が軽くなったり重たくなったりするのを感じた人もいた。「ベッド」という言葉から、安らぎを想起する人もいた。
興味深かったのは、ティシューの部分では、身体が横方向に広がっていく一方で、ゴムの部分では、身体が縦方向に重さを持って落ちる感覚があったという語りだ。こうしたさまざまな身体感覚があたまのなかでシミュレーションされたことがわかった。
オンラインでも身体・運動感覚の想起は十分に可能であることもよくわかった。スポーツのように身体を動かす感覚というよりも、ダンスのような審美的・感性的な身体感覚に近い。それを、実際に身体を動かすことなくイマジネーションのなかで可能にしていたのが、オノ・ヨーコの言葉の作品の強さなのかもしれない。
同時に、一言に「ティシューのようにひろがる」といっても、想起されたものが異なった点も興味深かった。いまここにはない「風」や「水」あるいは「エイのような生き物が泳ぐ」という景色を想像した人もいた。言葉がトリガーになって、さまざまな記憶が想起され、コラージュされ、イメージがつくりだされたことがわかった。
対話のキーワード:他者との重なり
3つめは、「他者との重なり」である。
ティシューのようにひろがった先に、他の人もいるように感じられた
作品から、自分と他者の境界を問いかけられているように感じた
他者を包摂できるのかを問われていると思った
このような語りがあった。
命令をする人(オノ・ヨーコ、あるいはそれを朗読する臼井)と、鑑賞する人との重なりだけでなく、この世界に生きる、もしくは生きた人たちとの重なりのような、大きなものを感じた人が多かった。
感じたことを「あたためる」重要性
ワークショップの最後は
「あなたが自分自身の表現方法を用いて、この作品に問いかけられていることを表現するとしたら、どのように表現するかを、心の何処かにとどめ、あたためたまま生活してみてもらえたらうれしいです」
と締めくくった。
ここで「こんな風にできるとおもう」と仮説を語ってもらうより、今回のワークショップを通じて湧いた感覚やイメージを、身体の中に「あたため」てもらい、いつか芽吹くことを期待している。
この「あたため」とは、創造性研究におい重視されるプロセスで、一定程度試行錯誤したあと、一時的に創作や問題解決活動から離れる段階(=あたため/incubation)を経ることで「ひらめき」に至るとされている。無意識領域に根ざす謎多き概念だが、安易に言葉で意識化しないことが重要であるとされている。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcss/17/1/17_1_225/_pdf
たしかに、安易に言葉で経験したことを片付けてしまうと、その後忘却/冷却されてしまうことが多い。そうではなく、心の中に生暖かいモヤモヤしたものを抱えたまま、ことあるごとに思い出すような状態でいたほうが、ひらめきにはつながりそうだ。
まずは作品を模倣するところから・・・?
一方、さまざまなアーティストによるワークショップをリサーチしていると、鑑賞しじっくり感じてあたためながら、まずは作品を表面的に真似してみることを手がかりとするものも多い。
ホンマタカシ『たのしい写真3 ワークショップ編』、MoMAの『How To Paint Like…』シリーズ、あるいは『スクリプトドクターの脚本教室』など、他者の作品をトレースしながら個々人のオリジナリティを探索する方法がありそうだ。
このあたりを、次回以降のワークショップで探求してみたい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、赤ちゃんの発達や子育てについてのリサーチのための費用に使わせていただきます。

