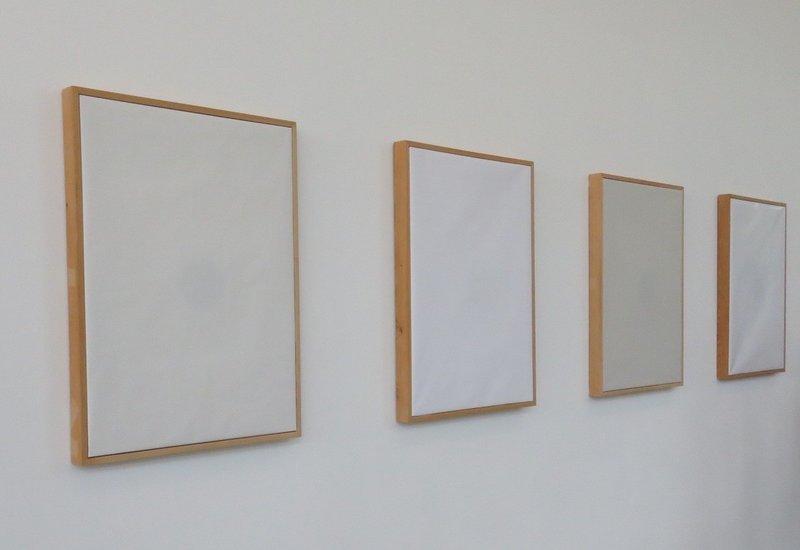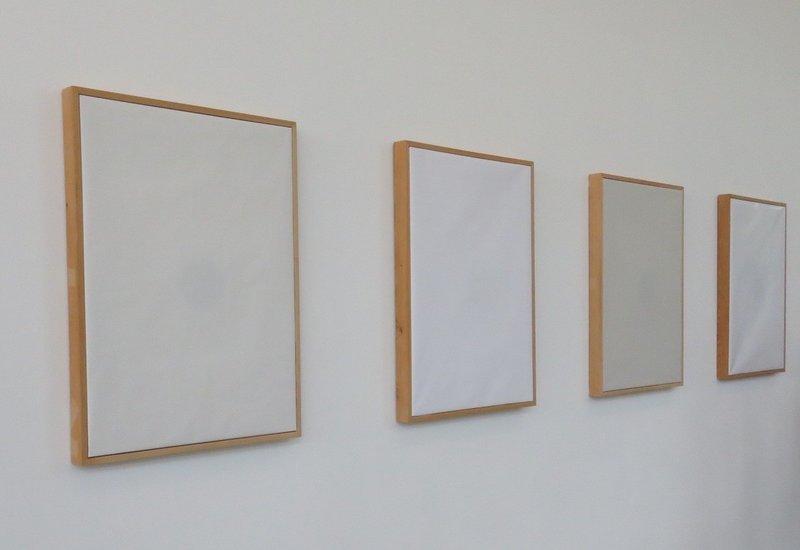「人間ではない他者」に語る実験に参加する ーチェルフィッチュ『消しゴム山』の感想
「子どもに向けて難しいことをわかりやすく説明をした本は、実は大人がよく読む」という話を聞くし、実際にわかりやすい。『14歳からの社会学』とか『子どものための哲学』など、わかりやすい言葉で丁寧なことが書かれている。
このとき、ぼくたちはこれらの本の想定された読者ではない。いや、もしかしたら子ども向けと見せかけてぼくたち大人を読者として想定しているのかもしれない。
いずれにせよ、著者が子どもにむけて語る言葉を読んで、大人のほうが「いいこと言うなぁ」とか「なるほどそういうことか