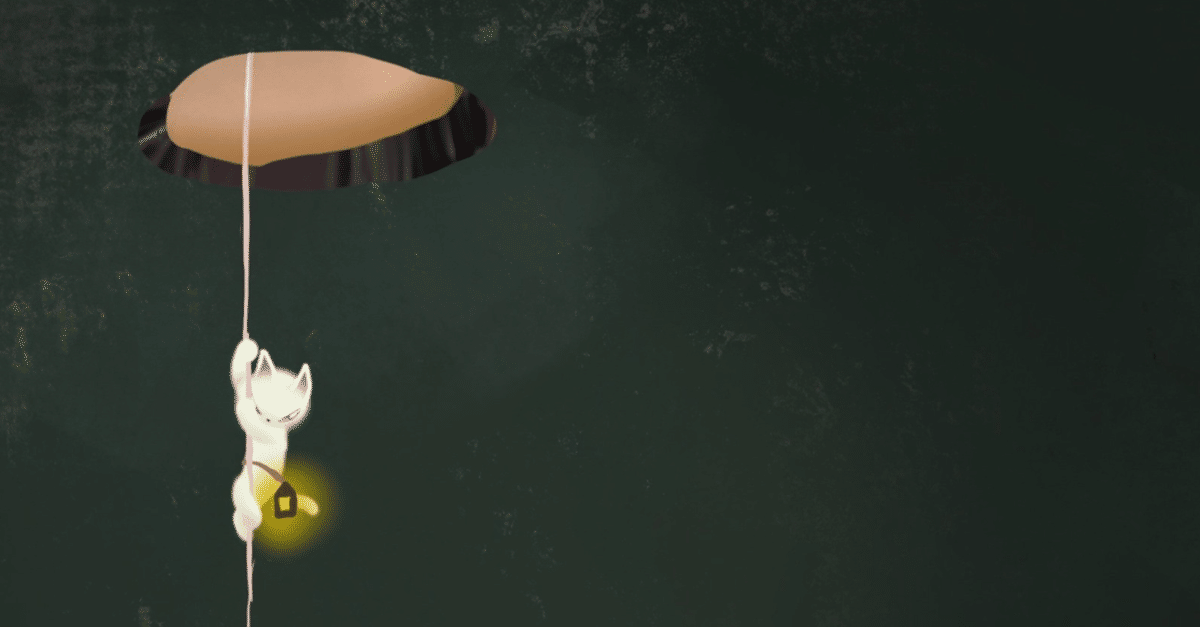
「良い」デザインって何だろう? #291
パーソンズ美術大学・Transdisciplinary Designの卒業制作において、「良いデザインとは?」「倫理的なデザインとは?」という問いを考えています。というのも、Dark PatternやDeceptive Designなどの言葉が生まれているように、ユーザーを欺くようなデザインの存在が指摘されているからです。
もちろん、ハンロンの剃刀が示すようにデザイナーが悪意をもってデザインしていると考える必要はないのですが、結果的に悪影響を及ぼすデザインをしてしまっている例は枚挙に暇がないのです。
Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.
無能で十分説明されることに悪意を見出すな
こうした問題に対して、どうすれば悪影響を及ぼさないデザインができるのか? どうすれば倫理的なデザインができるのか? そもそも倫理的なデザイン、良いデザインとは何か? と考えるようになっていきました。
グッドデザインは、良いデザイン?
日本で良いデザインの証と言えば「グッドデザイン賞」。Edgar Kaufmann Jr.らによって1950年から1955年にMoMAで開催されたGood Design Programに起源があるとされています。
当時のアメリカでは見た目をかっこよくすれば機能が平凡でも売れるという商業主義的なデザイン(スタイリング)が主流であり、そのアンチテーゼとして機能主義的なものが本当に良いデザイン(グッドデザイン)だという提案だったわけです。
そのコンセプトが日本に輸入されて生まれたのがグッドデザイン賞なのだそう(現代日本のグッドデザイン賞は「グッドデザイン賞だから知名度や売り上げがアップする」という商業主義に絡めとられている気がしないでもないですが)。
商業主義に対する機能主義を「よいデザイン」と定義して始まった歴史があるグッドデザイン。では、今でも機能主義的なデザインを指しているのでしょうか? グッドデザイン賞を主催している日本デザイン振興会には以下のように定義されています。
誰かの生活を真に豊かにすること、またはその可能性があること。それを達成しているものごとを我々は「よいデザイン」と考えます。
「誰かの生活を真に豊かにすること=よい」ということに異論はないでしょう。でも、「真に豊かとは何を指しているのか?」という新たな疑問が湧いてきます。現代で豊かさを測る指標として共通の理解を得られるのは経済的豊かさ(GDPなど)くらいだと思いますが、経済的豊かさ以外の豊かさをどのように評価すればいいのでしょうか? この問いに対して「時代による」と答えるのが精一杯なのかもしれません。
この60年の間に社会や我々が向き合うべき課題も変化し、それに伴いデザインに求められる役割も変化してきました。そして今もなお、我々が向き合うべき課題やデザインに求められる役割は刻一刻と変化しています。グッドデザイン賞も、このような状況変化に対してその仕組みを柔軟に変化させてきました
https://www.g-mark.org/about/

https://www.g-mark.org/about/
そのため、グッドデザイン賞の選定は極めて慎重に行われています。対話型審査などによってデザインの目的やプロセスを深掘りしたり、審査員はデザイナーだけでなく異分野の専門家も招いて全会一致になるまで議論をしたりしながら受賞作を決めているそうです。
審査は投票による多数決ではなく、審査員同士が議論に議論を重ね、各ユニットの全会一致で受賞作を決めていく。多領域のプロフェッショナルがお互いの視点を共有し、納得するまで話し合わなければ“グッド”は選べない。
https://note.designing.jp/n/n35268c964ba5
ただ、「グッドデザイン賞に関する調査」の2019年度版を見てみると、グッドデザイン賞を受賞したことを示すGマークのイメージは「魅力的なかたち(外観)をしている(68.7%)」が第一位であり、Gマーク受賞企業のイメージは「センスが良い企業(62.6%)」が第一位であるという結果だそうです。

デザインの背景を聞き取りしたり専門家が議論に議論を重ねてグッドデザインを認定したりしたとしても、Gマークを見る消費者の受ける印象が「センスがいい企業がデザインした見た目が美しい商品」というのは、グッドデザイン賞が意図するところとはズレていて残念な気もします。何が良いデザインかを議論するのと同時に、「デザイン」という言葉の一般認知度を高めていく必要性を感じます。
価値判断を保留すること
さて、私がTransdisciplinary Designで倫理的なデザイン、良いデザインとは何かと考えている中でたどり着いたことの一つは、「何がよいかなどは評価できるものではない」ということです。
ある人にとっては良いデザインも、別の人にとってはそうではない。その時代では良いデザインでも、時代が経てばそうではなくなることなどよくあることだからです。逆に、悪いとされる存在が反面教師として良い影響を与えたなんてことだってあるでしょう。
塞翁が馬という言葉があるように、ある時点では悪く思える出来事も後になったら良い出来事のきっかけになるかもしれない。無用の用という言葉があるように、木材として利用できない歪な形の木だからこそ切り倒されることなく長生きしたり、木陰をつくって他の生き物の助けになることだってあるのです。
こうしたことわざを知っていると、特定の商品やサービスを「良いor悪い」などと評価することは、視点次第で恣意的に変わってしまう儚いものなのだと思えてきます。そのことを自覚して、「このデザインって良いなぁ。いや、そうとは限らない」と思い直すことが大事なのではないかと思います。
空の思想
私は卒業制作の中で禅の精神をデザインに取り入れるために、「Zen-Inspired Ethical Guidelines for designers(デザイナー向けの禅にインスパイアされた倫理ガイドライン)」を考えています。特に在家の仏教徒向けの戒律である五戒の一つの不飲酒戒に着目し、「中毒性のある商品をデザインしない(ドーパミンハックをしない)」という考え方を提案しようと考えていました。
つまり、私は「中毒性のある商品=悪い、中毒性のない商品=良い」という価値観でいたのです。しかし、僧侶の方と不飲酒戒について話をした時に、「全ては毒にも薬にもなる」という言葉を頂きました。たとえば、現代のデジタルドラッグとも言えるSNSは時間の無駄遣いを招く恐れがあると同時に、大切な人との連絡手段にもなり得ます。
特定の物事に善悪が内包されているという考え方は避けるべきというのは、まさに空の思想であると感じます。物事自体に良いとか悪いといった性質があるのではなく、それを見る人の認識次第で良いものにも悪いものにも見えるということなのだと理解しています。
ジャックデリダのパルマコン
物事は両義的であるという考え方は、東洋思想に特有というわけでもありません。たとえば、現代思想で有名なジャックデリダが脱構築を唱えるために使うパルマコンという言葉があります。パルマコンとは「毒にも薬にもなる」ことを意味する古代ギリシャ語の言葉。「西洋哲学では二項対立を設定してどちらかを良い、もう一方を悪いと定義するけれど、それって本当?」という投げかけを行っているようなのです(私の浅い理解ですが)。
男性と女性、西洋と東洋、話し言葉(パロール)と書き言葉(エクリチュール)など、何かを二項対立で並べた時になぜか優劣が生まれる。その優劣を生んでいる視点や価値観に気づく試みを脱構築と呼んでいるのだと解釈しています。ジャックデリダは二項対立という最も基本的な思考の枠組みから議論を始めることで、価値判断の決定不可能性を鋭く指摘しています。
まとめ
「良いデザインとは何か?」を考えていく中でたどり着いたのは、「良いor悪いという価値判断を保留することが重要なのでは?」という結論だったというお話でした。
「何が良いかは決められない」というのは一見すると思考停止に聞こえますが、「これが良いものだ」と決めつける方が思考停止だと思うのです。特に自分や自社のデザインは自動的に良いと思い込んでしまうもの。それこそが最も陥りやすく危険な思考だと思います。「これは良いデザイン(仮)」という(仮)の部分を常に忘れないことが重要なのでしょう。
というわけで、私の卒業制作を通しての学びはこちらです。
Be the devil's advocate in order not to design devil's products.
(悪魔的な商品をデザインしないために悪魔の代弁者であれ。)
ちなみに、「悪魔の代弁者」とは議論を活性化させるためにあえて反対意見を述べる人を指す慣用句から引用したもの。全会一致の幻想(満場一致のパラドックス)を防ぐ効果があるとされている存在です。多くの人が「これは良いデザインだね」と思っている状況に対して、「本当に良いのか?」とあえて異を唱えること(価値判断を保留すること)が必要なのではないかと思うなど。
"If a perfect result seems too good to be true, it probably is."
完璧な結果があまりにも良すぎるように思えたら、多分良くない。
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
