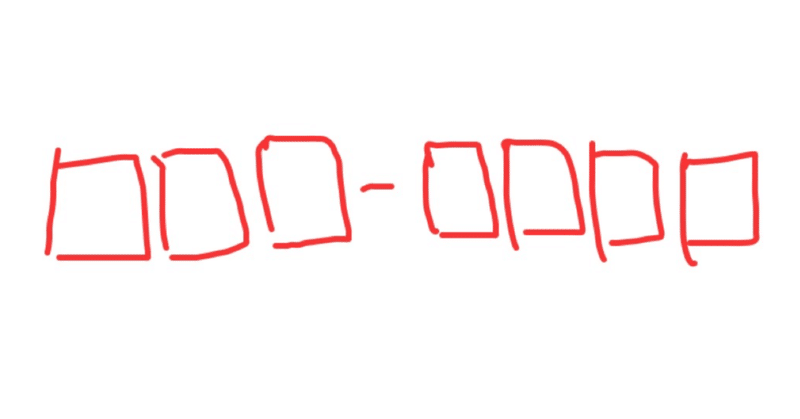
携帯小説『ギフト』
熱っているのに時々鳥肌が立つような寒気が背中を走る。雛は四十度近い熱にうなされていた。どこが痛いのかも分からない身体の痛みと頭痛。これは流行り病ではないかと思うには十分な症状だった。
一日の疲れを癒すベッドが病床に変わると途端に心細くなる。しかし自分は今、明らかな病人で療養することが唯一できること。到底、いつも通り仕事にはいけない。自他ともに認める外の世界と隔離されるべき存在なのだと思うと心細さは一変して心地の良さになった。
翌日になると微熱は残るがだいぶ回復された。昨晩は苦戦した枕元に横たわるペットボトルのキャップは簡単に捻ることができる。喉元を通る塩分混じりの水が乾いた身体に浸透する。食欲は湧かず、冷蔵庫にあったパックのゼリーをぎゅっと一握りして数回噛んでから空っぽの胃に落とした。
放置してあった携帯を開くといくつか通知が来ている。職場からの連絡と下着ブランドのセールの告知、そして祖母からの三件。
職場には大事をとって今日も休みます、と返信をして祖母からの文章を読んだ。
「雛ちゃん元気にしていますか今度里羽村のギフトをおクルネ」
句読点のない一行。変な変換ミス。最後にはハートマークの絵文字があった。
黙っていてもギフトやらは家に届くのだし、と返信する気力がなくなった指は電源をオフにした。
食欲も取り戻しもうすっかり身体は元気になったが流行り病の可能性を効力のある免罪符として一週間も使った。三日間くらいはただのズル休みだ。
四月に入社してからというもの、夏までのここ半年間、休みという休みはなかった。朝方から深夜までパソコンに向かう。
バンドやアーティストのミュージックビデオをつくりたい。憧れだった映像の仕事は、蓋を開けてみたら広告の編集ばかりでやりがいを感じられないままただただ放られた仕事を納期に追われながら仕上げる灰色の世界だった。あまりの付き合いの悪さに大学時代の友人達からの誘いは一件もこなくなり、たまに開くSNSはみんなが社会人生活を有意義に過ごしている様子が眩しく映ってみなくなった。誰も私が苦しいことなんて知らない。
一週間も休んだ後の出勤はかなり腰が重い。化粧を雑に済ませて家を出ようとすると玄関のチャイムが鳴った。
片目をつむりドア越しに鳴らした相手を確認すると宅配会社の制服を着た男性が右小脇にダンボールを抱え、右手で首に巻いた白いタオルで額の汗を拭っている。ドア越しに、そこに置いといてください、と声を張ると、はーい。ここ置いときます。チルドなのでお願いしまーす。と言い去っていった。
雛は祖母からのメッセージを思い出した。
なんでこの時間のないタイミングで、と苦い顔をした。ドアを開けてダンボールを部屋の中に入れて、べったりと貼ってあるガムテープを手早くキッチンバサミの片面で縦と横に切り込んだ。里羽村ギフトなるヨーグルトやチーズ、タッパーに詰まった手作りハンバーグや煮物、シチューを冷蔵庫につっこみ、レトルト食品は段ボールに入れっぱなしのまま家を出た。
会社に到着し、散らかったデスクの上に座ると、先輩から体調大丈夫?という気遣いの言葉をかけられ、もう大丈夫です。すみません。と頭を下げて顔を上げると、「じゃあ、これよろしく」と早速仕事が押し付けられる。はい、と返事をする前に先輩は自分の定位置に戻っていった。休み中、自分が他の社員に何を言われていたのか大体想像がついた。いちいちこんなことでは泣きそうにすらならない。鉛のように重い腕をキーボードに向かわせた。
終電間際の電車に間に合った。なまった身体はホームを走り抜けるだけで息が上がる。家に到着する頃にはすぐにでもベッドに倒れ込みたいほどに疲労していたが空腹も気になる。
そういえば。レトルトがいくつかあったなと段ボールをみた。カレーやシチューの箱、レンジで温めるご飯の横に何かが挟まっていた。赤の四角が七つ並んだだけの細長い茶封筒。横幅を軽くしぼって膨らますように中身を除く。壱万円札と重なった一枚の白い紙を開いてみる。
雛ちゃんへ
元気かな。東京は猛暑が続いているようで心配です。雛ちゃんがやりたかったお仕事につけて、ばあちゃんも嬉しいです。季節外れだけれど雛ちゃんの好きなシチューを作ったので食べてね。忙しいと思うけれど、たくさん食べて、たくさん眠って、楽しく元気に過ごしてください。いつでも帰っておいで。大好きだよ。
句読点がきちんとある。達筆で綺麗な文字。
雛は眠たい目をこすった。
いただいたサポートは創作活動につかわせていただきます!よろしければ新たな芸術を生み出すサポートをお願い致します🙇♀️
