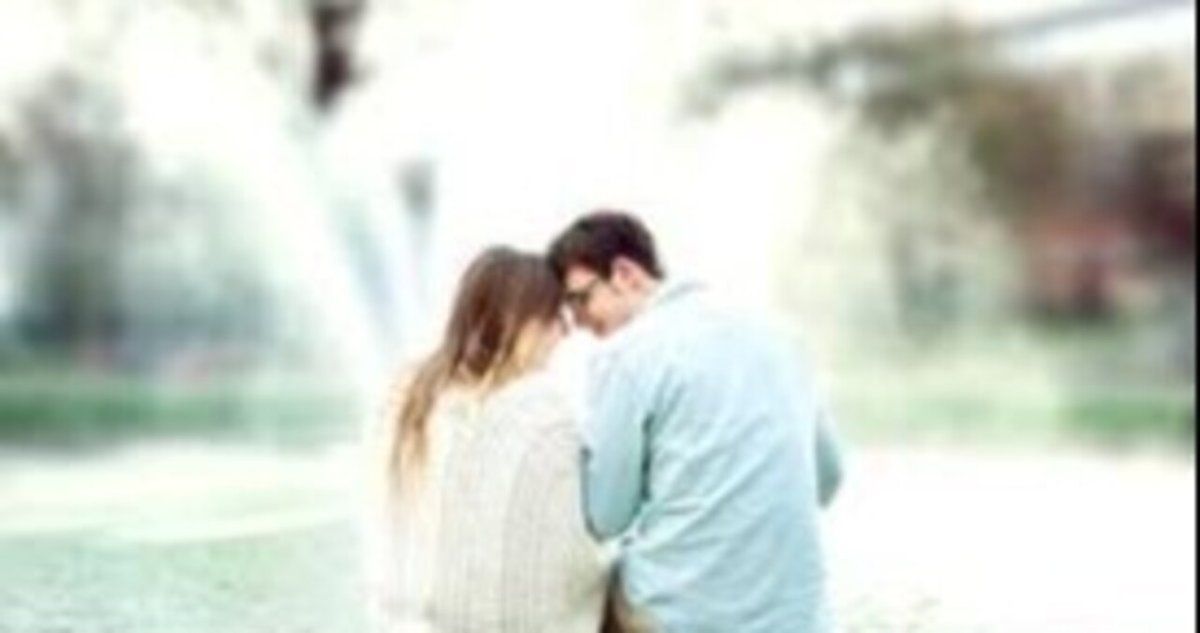
若者論考察
この2つの記事を読んだが中々面白いものだと思った。先に後者のDaiGoの記事を読んでおり、その後前者を読んで俺の中でリンクした。
前者の考察は中々面白い。
「エンタメに対して“心が豊かになること”ではなく、“ストレスの解消”を求めれば、当然そうなります。心に余裕がない、完全にストレス過多なんですよ、特に若い世代は」(森永氏)
この傾向は確かに感じる。彼等は余りにも恵まれ過ぎ、いや、忍耐を経験することが少なかった為、苦痛への忍耐力が余りにも弱い。そして忍耐力か無いから先回りして転ばぬ先の杖を排除することに躍起になる。そして結果として余裕が無くなるのだ。
彼等は転び方も立ち直り方も知らない。だから転ばないことに細心の注意を払う。そしていざ転べば立ち直り方が分からず過不足が生じたりする。或いは絶望し、或いは攻撃的になる。その不安から楽観的に構えることができず、常に怯えているのだ。
心を豊かにするには自分自身が打たれ、回復、成長し、勁くならねばならない。
そう、筋トレのように破壊が必要なのだ。破壊し、吸収し、勁くなるのだ。
筋肉は裏切らない。
しかし彼等はその経験がないから冒険できない。常に守りに入ってしまう。
実に勿体無い。
一日中、したくもない仕事をしてストレスを溜め込んで帰ってきて、あるいはLINEグループの人間関係に疲れ果てているのに、考えさせられるドラマなんぞ観たくないのだろう。だからこそ、TVドラマにもスポーツ番組にも、ストレス解消という機能を求めるというのは、わかる。自分にとって快適なものだけを摂取したい。それを突き詰めると、「自分にとって快適な視聴方法で観たい」になるのは自然なことなのかもしれない。不快だったり退屈だったりするシーンは飛ばしたい。見たくない。
これは、このストレスは分かるな〜。社会そのものに希望がない。そんなLINEグループ世間みたいなのは俺は知らないが、仕事や社会に憧れがない。あるのは常に強く、多数な権力者が好き勝手に暴れていることの、尻拭きをさせられている感。しかもそいつ等より有能だと思っても処遇は悪いし、何なら偉くなってもそいつ等の相手をするか同類にならなければならないと言う絶望感。でもそんな消費材で自分の人生を浪費するのも勿体無い。視野を広げるだけでムカつく上司先輩の観察の仕方が変わるのに。
関連する話をしよう。いま、映画評論本が売れない。これは、そちら方面の出版関係者なら重々承知だろう。 念のため説明しておくと、「評論」とは、「物事の価値・善悪・優劣などを批評し論じること。また、その文章」(「デジタル大辞泉」より)。つまり、良い点も悪い点も指摘し、公平かつ客観性をもって論じることである。「批評」も、ほぼ同様の意味だ。ちなみに「批判」も本来は同じ意味だが、どちらかといえば否定的に使われることが多い。
批評は後から述べるが、この批判へのネガティブイメージは俺も不思議な気持ちがある。俺の独断と偏見だが、批判の「ヒ"ハン"」と言う「音」が、「反」と重なるから否定的なイメージを持つのではないのか?本来は「判定」「判断」の「判」だから善悪の前段階の話だと思うが、どうしても「反」がチラつくのだろう。
どんなに名の通った大御所評論家の評論集でも、気鋭の論客による渾身の著作でも、かつてほどは売上が見込めない。見込めないから、出版社で企画が通らない。だから刊行点数も少なくなる。一方で、人気作や出演俳優の「ファンブック」はよく売れる。ファンブック、すなわち、作品を絶賛する出版物。
これ、本当に絶望的な気持ちになるが現実だと思う。そしてこれは若者に限らないと思う。大人、企業こそ自身への負のイメージを持たせない為に操作していると思う。言ってしまえば皆がイエスマンを求めている。勿論企業としてもマーケティングの結果としてこう言う戦術を採用しているのだろう。若者は少子化の影響もあり常に少数派だからそこは大体置き去りにされて当たり前なのが今の全年齢的サービスの基本だ。
それから、ここでDaiGoの記事と繋がるが、批判と言うのは他人の自分への侵略と認識されるのが今の基本のようだ。
自分が間違っている可能性を考えたくないのだろう。間違いは彼等の中では一種の許されざるタブーだから。彼等は間違うことをいけないことだと教え込まれてきた。
自己肯定感が彼等にはかなり不足している。つまりそもそも自分自身が自分の足で立つのが精一杯で他人の要求を受け入れるキャパがない。
だからそんな人々とコミュニケーションをとる場合、DaiGo式のやり方が必要になる。
選択肢を提示した上で、それ以外も含めて意見を求め、合意に至ると言うプロセスだ。
DaiGoの言い方がこちらの意図する方に仕向けると言うニュアンスを含む為、非常に嫌らしいと思う人もコメ欄には多いようだが、俺からしたらそんなことを言ってる奴等こそ利己主義者にしか見えない。
そもそもDaiGoの言うやり方は既に述べた通り、選択肢の提示と選択権の共有だ。
例えば食事をどうするか、と言う時に最も嫌われるのが
「何でもいい」であり、更に最悪なのはそう言っておきながら提示を否定することだ。
そう言う事態を一旦防ぐ為の手法が案を一つ提示するやり方だ。
「俺はカレーが食べたいけど何食う?違うのでもいいよ」
そこで相手がまずカレーと言う選択肢を認識した上で検討でき、その上でカレーは嫌だ、となればまた話し合えばいいだけの話(頭にカレーがよぎらないことはある)だが、
コメ欄的には「カレーを押し付けられた」と捉える奴がいるようだ。いや、もしかしたら見出しの先入観で本文を誤読したか未読なのかも知れない。何れにせよそんな奴等は正直論外でありどうしようもないが。
とは言え、そんなアホ(関西的、愛すべき意図を込めた)は普通にいる。俺もそんなアホをやらかす。
現代の問題は、そのアホがアホであることを認めたがらないことにある。
だから若者とのコミュニケーションは難しい。
「アホか!(笑)」が通用しない。
「私はアホではありません!あなた失礼ですね!」となる。
結局若者は傷つく経験が足りな過ぎるのだ。だからそれを笑いに昇華する無意識の技術も持たない。
自分は一人の大人として認めて貰わねばならない。
だがそれは彼等にとってそう言う資格を持とうと言う意思ではなく、他人が自分を認めねばならないと言う要求なのだ。
無菌状態で傷もなく生きてきた人間はこうも脆く儚い。いざ危機が訪れると過剰反応を起こす。
人間の社会への耐性がこうも脆くなった世の中には危機感を覚える。
コロナ禍人災の異常も、同根だと俺は思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
