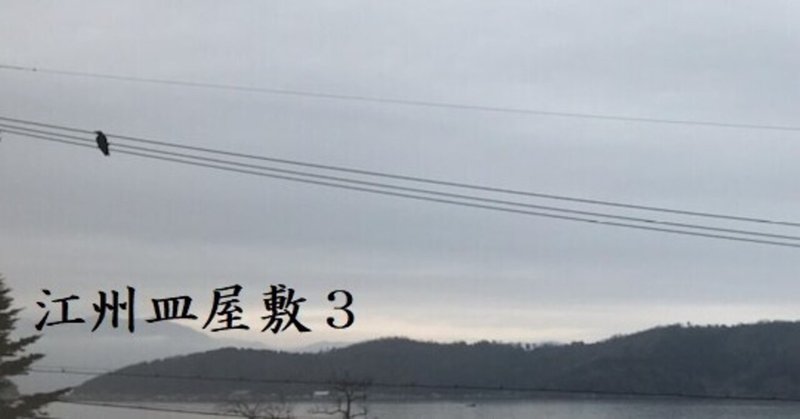
江州皿屋敷3
〈井戸の傍〉
正徳元年、四十五年ぶりに彦根に戻った。この間にたくさん将軍様は変わり、世の中は様変わりした。戻った理由はたくさんあるが、お役御免となった夫の甚右衛門が、近江の地で余生を送りたいと希望したのが大きな理由だ。孫にも恵まれ、江戸は故郷以上に長く住んだ土地ではあったが、生まれ故郷江州の琵琶湖の水が恋しくなったのかもしれない。
父が一人で住まう平田町の実家に夫と三人で住むことになった。下の姉には、すっかり染みついた関東訛りをからかわれたりもした。
ここで初めて姉、菊の葉月の法要にも参加することができた。養春院では、先代の息子が住職を継いでいた。法要が終わり翌日になってから、御礼のために寺院を訪ねると、座敷に通された。世間話の後、こう切り出した。
「寄進帖は桜様がお集めになったのだとか」
「もう四〇年近くも昔の話。しかも私だけでなく、多くの人の助力あってのことです」
若い住職は、少し逡巡したのちに切り出した。
「実は、お父様にはお伝えしたのですが……」
聞けば、皿は毎年葉月の法要の日にしか一般の人の目に触れるような場所には出さないという。ところが、今年はしまう段になって九枚になっていることに気付いた。つまり、一枚盗まれたのだ。しかもそれは、姉が欠いたものだという。これは、残された九枚の皿すべてに大きく割れ目がついていることからそうだと考えられた。神君家康公から賜ったものだから、茶道の関係者にでも出せばそれなりの金子(きんす)になると考えたものがいたのではないかというのが、若住職の考えだった。
現時点では奉行所などどこにも報告せず、知り合いなどを通じて探している最中なのだという。
これと相前後して別のうわさが耳に入ってきた。
今は誰もいなくなった孕石邸に、夜な夜な女の幽霊が出るというのだ。しかも、その幽霊は、菊だといわれていた。それゆえ誰いうともなく「皿屋敷」と呼ばれるようになっているという。
結局、長月に入っても皿が見つかったという話は聞こえなかった。
ある月の明るい夜中、目が覚めた。暦の上では秋だった。陽が落ちると過ごしやすくなってきており、一度眠るとそうそう目覚めることはなかった。のどが渇いたので、土間へおりて湯冷ましを口にした。障子越しに月光がぼんやりと入っていた。
呼ばれたような気がして、寝巻のまま外に出る。二つほど浮かんだ雲の合間から十六夜の月が姿を現していた。そのまま裸足で町を歩きだした。丑の刻にかかろうかという時間で昼間には多くの人が見える城下も、猫の子一匹見当たらない。普段はうるさい犬たちも、夢の中なのか。
気付くと、孕石邸にいた。苔むした庭石も、毎年春に花を咲かせる八重桜も生えるに任せた雑草の中に埋もれている。そのまま歩を進める。秋の虫の音がかしましく、自身の足音さえも聞こえない。
屋敷を回り込み、月明かりに照らされた井戸の横に、姉がいた。いつも着ていた小袖を着てぼんやりとたっている。その顔に表情はない。
姉は少しこちらに目をやると、手を上げた。下がっていろということか。背の高い草の後ろに回ると、ほどなくして男が庭に来た。随分と年をとっているが、明らかに見覚えがある。
あのとき、江戸で私を襲った男だ。
「毎晩枕元に立ちやがって」
腰のものを抜き、上段に構えた。あの時の力強さはなく、刃も錆だらけだ。振り下ろした抜き身が、井戸の傍、つるべを支える柱に食い込む。その反動で力なくその場に腰を下ろし、悪態をついた。
「もうやめてくれ。曰く付きのものだっていうから貰ってやったのに」
懐から白磁の皿を出し、井戸の傍に放り出した。姉の背がぼんやりと見える。
「お前らに関わったがために、台無しだ」
錆びた刀を杖代わりにして、よろよろと立ち上がる。その右手には小指と薬指がないのが月明かりの下でもはっきり見えた。あの時、甚右衛門が切った時のままだ。そのまま、屋敷を離れていく後姿は、随分と小さく見えた。
井戸に駆け寄る。
「菊姉ちゃん」
姉がそっと指した先には、白磁の皿があった。今は、おぼろげながら表情がある。あの日、私の髪を梳るときの一重の目を糸のようにして微笑んでいた顔だ。菊は、手を合わせてゆっくり頭を下げたかと思うとその姿が薄くなっていた。最後に顔を上げた時、口が少し動いたような気がしたが、声は耳に届かなかった。
私は皿を懐に入れて家路についた。姉が切られたあの日、泣きながら歩いたのと同じ道を。今宵は少し微笑みながら。
一つ気になることがある。
江戸で「番町皿屋敷」という歌舞伎が好評を得つつあることだ。事件の場所は江戸の番町、細川家の話になっており、菊は細川家の政争に巻き込まれて井戸に投げ込まれたことになっている。姉の事件は、随分と流布したため、そこから着想を得たものと思われる。まさかあの浪人崩れがいいふらしたとも思えないが。
しかも、麝香揚羽の蛹が、歌舞伎の劇中でお菊が吊るされた格好に似ており、それは菊の怨念が虫の形に形を変えたお菊虫だという話が面白おかしく物語にしたてられているらしい。しかし、姉はそんな形で亡くなってはいないし、政争に巻き込まれてなどいない。姉の悲恋について多くの人に知ってもらうのはうれしいことだが、このような形での話が歌舞伎の演目の一つとして好評を博してしまうのは複雑な胸中だった。後の世の人はどう受け止めるのか。
翌年の夏の法事は、大護摩の法会が行われる横で、白磁の皿が奉納され、永代供養の経文が読まれていた。大護摩の中心となる供物は、仏事の様式にのっとって赤と白で揃えられている。一方で、お皿への供物は餅から器まで黄色と白で統一されていた。これは、姉の菩提を弔うためなのだと若い住職が教えてくれた。
皿はきちんと一〇枚そろっていた。養春院では今後、供養の時だけでなく、普段の保存の折も新たにしつらえた桐箱に入れて保管をしてくれるという。
ふと、目の前を黒い蝶がよぎった。護摩の炎の熱にあおられて飛びにくそうに見えた。そういえば、今年も麝香揚羽の季節は終わりだ。姉が蝶のようだとほめてくれた漆黒の髪は、今は見るかげもなくほとんどが白いものになってしまった。
あの晩、姉の声は聞こえなかった。けれども言いたかったかったことはきっとこうだ。
「幸あれかし」
〈了〉
よろしければサポートのほどお願いいたします。いただいたサポートは怪談の取材費や資料購入費に当てさせていただきます。よろしくお願いいたします。
