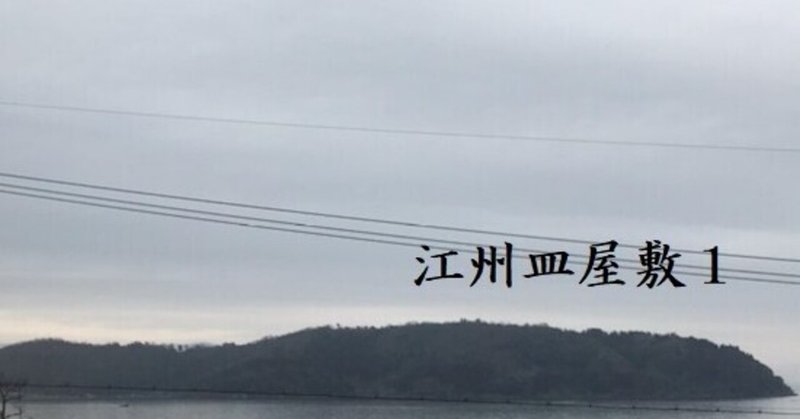
江州皿屋敷1
押し入れの中
母代わりだった姉は、いろいろなことを教えてくれた。例えばゆったりと舞う黒く大きな蝶を指して、「あれは麝香揚羽といって、雄の蝶はお腹から麝香のような匂いがするのよ」あるいは「幼虫はお歯黒草を食べるの」といったことだ。お使いなどの帰り道、姉と善利(せり)川の傍をこうしてゆっくり歩いたのは、今も胸に残る思い出だ。
だからお城に黒い揚羽蝶が舞う頃になると、あの初夏を思い出す。
寛文四年、水無月に入り、梅雨もすぐそこに感じるようになったころ、私は母からお使いを頼まれた。住み込みで侍女をしている姉の菊へ、夏物の襦袢を持っていくようにとのことだった。
一回りも年が離れた姉は、病がちで体の弱い母に代わり、末妹の私の世話をみてくれた。四人兄妹の中では一番仲が良かったと思う。
ずいぶん昔、寺子屋で「足軽の子」と馬鹿にされた私が泣いて帰ったことがある。いじめた男の子を捕まえて、その子の家と何の遜色もないということを自家の功績と出自について滔々と語り聞かせたこともあった。また、読み書きについても分からないところをも丁寧に教えてくれた。あの頃は、姉が寺子屋の先生ならどれほどよいかと思っていた。
そんな姉は京町小町とも呼ばれ、一昨年から井伊家の武官、孕石家に侍女としてお勤めに出ていた。若い当主の政之進様の覚えもめでたく、お盆と正月に家に帰って来る時には毎回決まって家まで送ってもらっていた。
何より、姉が政之進様の話をするときには、薄く頬を紅に染めることから、その想いを容易にはかることができた。
昼を過ぎてから、お使いの風呂敷を持って出た。井伊さまのお城が青空の下でくっきりと見える。姉をまねて伸ばしつつある黒髪を吹き抜ける湖からの風が気持ちいい。外堀を越えて、西馬場まで少し歩く。孕石のお屋敷はお城の琵琶湖側に延びる大通りの西側だった。
おずおずと扉を開け、声を上げた。
「もうし、ごめん下さい。平田町から参りました桜と申します。菊さまはいらっしゃいますでしょうか」
玄関は、外の光の強さと相まって、いつもより薄暗い気がした。
「はーい、お待ちください」
奥から声がして、たすきを外しながら菊がやってきた。「菊姉ちゃん、持ってきたよ」と風呂敷包みを渡すと、微笑んで「ちょっと待っててね」と奥へ向かった。
孕石様のお屋敷はうちと比べてずいぶんと広いせいか、ほとんど人の気配はしない。
しばらくして、水が入った桶と手拭いを持ってきた。草履を脱がせ、足に着いた埃を洗い流してくれる。渡された手拭いで足を拭いていると、もっと幼かったころ、家に帰った私から一日の出来事を聞きながら足を洗ってくれたことを思い出した。うれしいことがあると「よかったね」と喜んでくれ、辛いことがあると「桜なら大丈夫」と励ましてくれた。この短い会話がどれほど私を元気づけてくれたことだろう。そして決まって「幸あれかし」と口にした。意味を聞くと、一重瞼の目が線になるほど微笑んで、「元気でそして幸せでいてほしいということよ」といってくれたものだ。
ぼんやりと昔を思い出していると、「桜、ちょっと桜」と声をかけられた。我に返って顔を上げると、「草履、少し湿っているわね。ここに掛けておくわ」と菊が玄関の横の釘に返し輪をひっかけた。
礼とともに「静かだね」というと、「今日は、爺も出ているからお屋敷には私一人なの」と返ってきた。
「いただきものだけど、ところてんがあるから。食べるでしょ」
黒光りする廊下を姉について歩き出す。お屋敷には幾度も上げさせてもらっているので、屋敷のつくりはわきまえている。台所へ向かっているようだ。廊下は今思い出しても冷やかな印象だった。もちろんそれは、この後起こることに深く関係しているとは思うが。
台所で冷たいところてんと白湯をもらった。
年に数度しか会えない姉に、寺子屋で流行しているすごろく、鳥居本宿で夏に作られる西瓜糖の甘さ、母の病状が少しずつ良くなってきていることなど寸暇を惜しんで話す。姉は、微笑んでうなずくだけで、細かく質問などはしない。
一瞬間が空いた。
突然、「かくれんぼしよう。姉ちゃんが鬼ね」といいだした。
なぜそんなことを口にしたのかわからない。久しぶりに会った私が少しつまらなそうな顔をしていたのか。あるいはお屋敷に二人だけという状況がそうさせたのか。
今考えれば、もしかすると姉は自らの最期の姿を妹に見せたいと思っていたのかもしれない。
当時の私はもうかくれんぼを楽しむ年齢を抜けつつあったものの、姉が柱に向かって数を数え始めると、うれしくなってその場を駆けだした。
目指すは離れ。何度も入らせてもらっている政之進様の書斎だ。玄関の脇から伸びる一間ほどの短い渡り廊下を越えてすぐに襖があった。そっと開けて中をのぞくと、部屋の真ん中に白い皿が並べてあった。横には桐箱がある。
部屋に入って左手にある押し入れを開けると、うまい具合に私一人分ほど空きがあった。入ろうとしたときに、遠くで、男の人の声がした。
政之進様だ。
すぐに姉が足を洗うための桶を持って、玄関へ向かうのが分かった。咄嗟に襖を閉めると、狭い空間を闇が支配した。
いい年をしてかくれんぼなどしていてよいのか。あるいは、見つかったらどうするのかといった考えが脳裏をよぎらなかったわけではない。それでも、生ぬるい暗さは、私の行動を一歩遅らせた。
部屋の襖を開け、人が入ってきた。畳の上に重いものを置く音がする。刀だろう。まだ若い、この家の当主の顔を思い出す。
「お菊、ここへ」
続けて、もう一人が部屋へ入る気配がした。
「今日、何故に私が出かけていたのかわかるな」
全身が耳になる。
「はい、政之進様。私が家宝の皿を割ってしてしまいまして……」
血の気が引いた。体が固まる。
「ここに九枚ある皿は、神君・徳川家康公から井伊直政様、ひいてはわしの祖父孕石昭之介が先の関ヶ原の大戦での戦功によりいただいた濱文様の白磁じゃ。よく話を聞かされていたと思うが」
「はい。存じ上げております。先代の御屋形様も亡くなるまで大切にされておられました由」
「日々、この家を支えてくれてありがたく思う。そなた、この家に仕えてこれまで一枚でも皿を、いや、器物を壊したことがあるか」
「ございません」
「ではなぜ、よりにもよって、この家宝の皿を割ったのだ」
沈黙。初夏をいろどる蝉の音も今は止んでいる。
「今年の夏、お盆に備えて政之進様のご両親の墓前に……」
「それは聞いた。しかし、まだふた月以上もある。また、特別な年忌でもないのになぜに」
再度沈黙。かなり、重苦しい雰囲気であることが容易に想像できる。
そうした中、かすれる声で姉が絞り出す。
「政之進様は、志乃様のことをどのようにお思いでしょうか」
「その話か。亡くなった両親が決めた許嫁だが、きちんと婚約を破棄し、菊と比翼の鳥、連理の枝となるというておるではないか」
「何度もおうかがいしており、わたくしのような身には本当にありがたいことと」
「拙者を試したのか」
「そういうつもりでは」
大きな音がした。
「こんなものが、こんなものがあるゆえ!」
笑顔しか見せたこのない、温厚な政之進様からは考えられないような大声が聞こえた。
「家宝の皿を! おやめください」
「離せ、刀の錆になりたいか」
焼き物が割れる音が響いた。
「これで気が済んだか」
大きく息をついている。
三度の沈黙。
「それでも、わたくしのような足軽の娘ではなく、志乃様とでしたら家格も釣り合いますし、今春は志乃様のお家の花見の会に……」
「まだ言うか、菊!」
風を切る音と同時に悲鳴が響いた。
開けたい。襖一枚隔てて、すぐ一間先の様子がどうなっているのか。
しかし、汗ばんだ体は意に沿わず、動かない。心臓の音が大きく響く。このままでは外にもれ聞こえてしまいそうだ。右手で口を押えた。
どれほど経ったか、一刻といわれればそうも思えるし、一瞬だと諭されればそうも思える時がたった。
「菊……。目を開けてくれ」
かすれた声がした。小さな声がする。襖の裏側に耳を付ける。
「政之助様……、お慕い申し上げて……」
「お菊!」
しばらくして、重いものを引きずる音がし、人の気配がなくなった。
そっと襖を開けると目の前には、バラバラになった白磁の皿が血の海の中に散らばっていた。抜き身の刀も転がっている。同時にひどい臭気が鼻を襲う。
姉の姿はない。
あわてて縁側から外へ回る。太陽は、ずいぶんと西へ傾き、影が長く伸びる頃合いになっていた。初夏の風が髪を揺らした。
そのまま家へ帰ろうとして、気が付いた。裸足だ。そっとお屋敷の前に回る。
玄関を見て、草履が見当たらないことに気付き、すこし肝が冷えたが、横に干していたことを思い出す。できるだけ体が中に見えないようにつかもうと手を伸ばす。
「誰ぞおるのか」
男性の声が聞こえたとたん、指先に藁の感触が触れた。切れる音がしたが、強引に引っ張って家路を駆けだした。気が付くと顔が濡れていた。それが涙だと気づいたのは、半分以上乾いてからのことだった。
家に帰ると、母は心配していたものの久しぶりに会った姉との時間を大切にしたと思ったのか、小言を少しいわれた程度で済んだ。この日のことは、私一人の胸の内に納めた。
しかし、ずっと心に留めるのは辛い。そこで、習字帳に拙い文章で書きつけた。それでも誰かに読まれてしまうのは不安だったので、その年の年末の掃除の折にふすまの下貼りに貼り込んだ。
二日後の水無月一二日、変わり果てた姿で姉がもどってきた。遺骸は筵(むしろ)に巻かれ、すでに息をしていなかった。理由は、家宝の皿を不注意で割った咎でお手討ちにされたと説明された。
両親が孕石家からの老使者と話しており、座敷から遠ざけられたため詳細は分からない。けれども死に装束に変えるとき、左の肩口から袈裟に切られた跡を丁寧に縫合してあることが印象に残った。
併せて、割れた孕石家家宝の皿も一〇枚渡された。皿は白磁で、ポツポツと黒いものが浮かんでいるが、肌に吸い付くような質感を持ったものだった。姉が割ったというものは少し端がかけた程度だったが、その他の九枚は少ないものでも真っ二つ、細かいものは四つもに割られており、政之進様の憤りの強さが推し量られた。下賜された皿は、姉とともに弔うようにとの申し出だった。
<続く>
よろしければサポートのほどお願いいたします。いただいたサポートは怪談の取材費や資料購入費に当てさせていただきます。よろしくお願いいたします。
