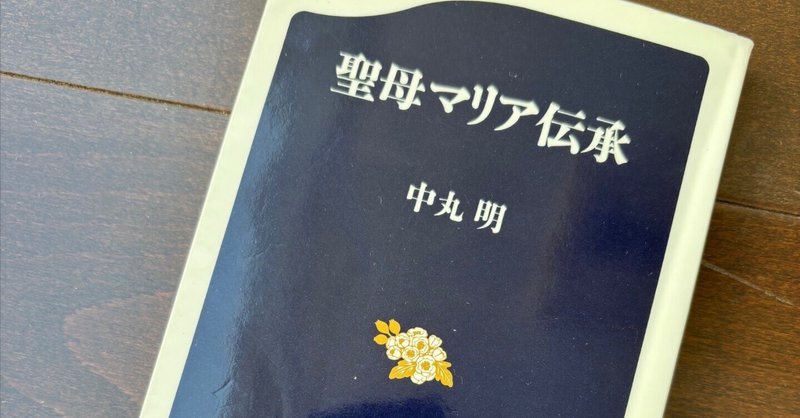
中丸明著『聖母マリア伝承』文春新書
この本が出た2000年頃、メディアで中丸明さんをよく見かけた気がする。なんの記事だったか思い出せないのだが、とにかくスペインに詳しくて、スペイン愛を語る人という印象がある。この本もその系譜にあるもので、冒頭の「セビリアの復活祭」の描写から圧倒される。
「まだほとんど暗闇といってもいい夜明けの街を、眠れぬままにさまよい歩いていると、一団の影が、音もなくひっそりと、まるで亡霊のように通りすぎてゆく・・・。と、おごそかなその沈黙のかたまりから、そっと手拍子(パルマーダ)を打つ音が聞こえてくる。(中略)
セビリアっ子だけが知っている古い歌の、乾いたビートをそっと手拍子でとるのだ。(中略)
と、通り過ぎる伊達男(マホ)・伊達女(マハ)たちが、それに短いスタッカートで合わせる。(中略)
そして、その音が完全に消えてしまわないうちに、また別の沈黙のかたまりが現れて、暗い空にそっと手を打つ。」
中丸さんでなくとも「寒疣(さぶいぼ)が立つような感動」が伝わってくる。大学の先生だった藤沢さんや寺田さんとは異なり、中丸さんの文体は、荒っぽいかもしれないが「好きだあ!」というラテンの叫びが聞こえてくるようで生々しい。
で、この本はというと「聖母マリア」に焦点をあて、なぜに聖母マリアがこれほどに愛されているのか?ということを、その非科学的な側面からも逃げないで描こうとしている。
そもそも「処女懐胎」という、トンデモないところからスタートする「聖マリア伝説」だが、従姉のエリザべツも「処女懐胎」だったり(生まれたのは、イエスに洗礼を授けた「バプティスマのヨハネ」)、イエスに弟妹がいたり、さらに物語が続いている。あげくの果てに「聖母マリア」は世界中に現れ、近代に入ってからも、あの有名な「ルルドの泉」では1858年2月11日〜7月16日に14歳の少女に「目撃」され、ヴァチカンも認定しているそうだ。その「霊泉」は不治の病を癒すものとして長崎・大浦のコルベ神父記念館でも売られている。
中丸さんは、恐ろしいことに「聖母マリア」に尾張・名古屋弁を話させる。イエスに死刑が言い渡されたときのリアクションである。
「どえらけにゃあ(大変な)ことになってまったがね」「あーもー、世間さまに顔向けでけんでかんわ」
というのも中丸さんによれば、聖母マリアが話していた言語は、ヘブライ語(文章用語)ではなく、カナン(パレスティナ)語の土俗語であったアラム弁であり、アラム弁の残るシリアのマルーラ村を訪れた言語学者によると「アラム弁の響きはなんとなく、みゃあみゃあしているらしい」。
というわけで、だんだんカオスに入ってくるわけだが、ポイントは「なぜ、神の子=イエスより、聖母マリアが愛されているのか」ということであり、どんな非科学的根拠であろうと、それを必要とした人々の心の問題であろう。この本は、学問的には足りないのかもしれないが、逆に人は「正しいこと」だけでも足りない。なぜそのようなことが起きているのか?という興味を掻き立ててくれれば十分ではないだろうか。「なんのために本を書くか」という意味でも、大いに参考になる本であるように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
