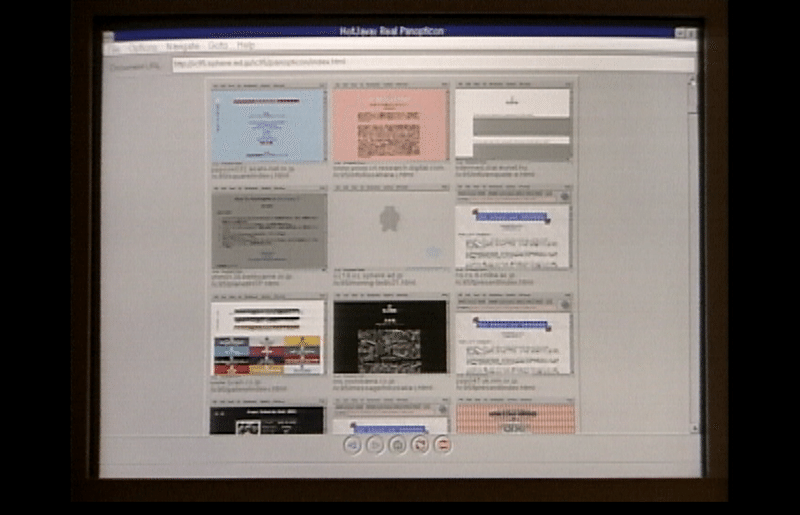ネット上の「経験」はいかに残せるか——インターネットアートと参加型アートより学ぶ
(約9,000字)
この記事は自由に価格を付けられます。
https://paypal.me/ukiyojingu/1000JPY
はじめに
2000年代、その中でも特に2000年代初め~中頃をインターネットが最も活発だった時期と主張してしまうのは、いささか早計だろうか。1990年代生まれの自分にとって、90年代末に初めて目にしたデジタルなものとの遭遇は、幼稚園の頃に買ってもらった「デジヴァイス」だった。2000年代には2ちゃんねるが台頭し、「恋のマイアヒ」を通し本格的にフラッシュ動画の爆発的な人気上昇を知った。そしてニコニコ動画と初音ミクの世界的な支持を見ながら、2010年代以降になって本格的にネットの世界を知った。自分にとって、特に1990年代から2000年代にかけてのネット文化は後から知ったものであり、当時の熱狂的な空気(があったことを正確には語れないが)は書かれた文章や映像でしか体験できなかった。初めてiPhoneを手に入れ自分専用のノートPCを手に入れた大学生のころには、すでにインターネット環境は2000年代のような熱狂的空気感を失い、どこか小綺麗に整備されていたのだ。そんななか、当時の空気感——恋のマイアヒが地上波に流れ、初音ミクがまだメルトを謳っていなかった時代——を記録することは、どのようにできたのだろうか。そもそも、そのようなことは可能なのだろうか。もちろん、HDD上に一度記録されたデータはHDDそのものの物理的破壊によってのみ完全に消去できないように、情報社会において一度流通した言葉や映像、その他の多くの記号化可能な要素は完全には消えない。しかし、コンピュータが記録するのはあくまで記号化可能なデータであり、コミュニケーションの背後にあるユーザーたちの熱量そのものは、今日の技術では記録化できない。だとすれば、どのような考えを巡らせることができるだろうか。初音ミクの最初期を知らない自分にとって、そういった問題意識はつねにどこかにあり続けた。
そうした問いに対し、メディアアートの手法に注目することは決して的外れな思考ではないだろう。メディアアートは常に対象のメディア特性を思考し続け、それはコミュニケーションがその本質ともいえるインターネットの哲学を作り上げてきた。本論では「メディアアート」からはじめ、今日「参加型アート」といわれる一連のアートの議論を参考にしながら、インターネットアートの保存——専門的な言葉を用いれば「アーカイブ」といわれるもの——とは何かを思考する。それを通し、ネットワーク上で展開された多種多様な実践や会話そのものを保存するとは何か、そしてそれは保存できるのかという問題について考えてみたい。それにあたって、メディアアートに固有の問題として、これまでの現代アートとの間にある「断絶」があることを専攻する議論より抽出する。そのうえで、断絶を乗り越える手段としてのソーシャリー・エンゲイジドアートと「アーカイブ」の問題を取り上げていく。そして最後に、インターネットアートのアーカイブ化の問題に関する本議論をまとめ上げ、私たちがインターネット上で「経験すること」そのものの保存がいかに可能かについて、不完全ながらも一つの方向性を提示してみたく思う。
「メディアアート」という枠組み
メディアアートは新しいメディアが有する特性をアートとして創造する試みとして、20世紀に登場した。それらは対象とするメディアが多様であるがゆえ、多くのサブジャンルに分かれ様々な問題が議論されている。その一つとして、メディアアートの定義に関する問題がある。メディアアートの巨大なデータベースを作成しているRhizome.orgの創始者マーク・トライブは、1990年代にはもはや新しくなくなったメディアが使用されたアートを「メディアアート」と称し、1990年代以降の「ニューメディアアート」と区別した [1]。一方で、クリスティアン・ポールは「ニューメディアアート」という言葉をトライブが「メディアアート」よりも古い概念であるとした「デジタルアート」という概念と同じものだといい[2]、ここに「メディアアート」という概念をめぐる定義の不一致が見られる。メディアアート専門機関ZKM(Center for Art and Media, Karlsruhe)のベルンハルト・ゼレクレはこの状況を見つつ、メディアアートやその類似概念が研究者間で明確に定義化されていないこと、また異なる言語間での対応関係もないことを指摘している[3]。このような定義上の問題は日本においても同様であり、他国との定義のすり合わせが十分になされずに「メディアアート」という言葉が「ニューメディアアート」と同様に用いられている。また、近年ではこれとは別に「メディア芸術」という言葉も生み出され、さらに複雑な状況が展開されている。
以上のような研究状況を概観したうえで、メディアアート研究者の馬正延および久保田晃弘は、メディアアート研究はこれまですでに述べたような定義の統一を図るよりも、メディアアートと現代アートの間に存在する「断絶」を前提とし、その特有の美学を論じるものが多かったと主張する[4]。馬と久保田はこの「断絶」の理由をメディアアートが現代アートに対してのオルタナティブとして生まれてきたからであると指摘したうえで、両者を「アーカイブ」という共通する問題意識から解消することを試みた。その際、メディアアート作品の技術進化に伴うバージョンアップというメディアのハード的側面から、アーティスト三上晴子の作品群を対象に考察を行っている[5]。
本論はこの馬および久保田の「アーカイブ」という手法から現代アートとメディアアートとの「断絶」を乗り越えるという問題意識は共有しつつも、メディアの物質的特性ではなく、むしろ非物質的特性に焦点を当てる。それにあたって、本論では「インターネットアート」を対象に据える。1990年代のWWWの世界的な一般化が契機となり登場したインターネットアートは、インターネットが持つメディアの物質的特性をアートとして創造を行うのみでなく、全世界が同時にコミュニケーションを行うことができるというインターネットの非物質的特性に注目しアートを創造することもあった。特に後者のようなネットユーザーの「参加」を前提とするアート作品は1990年代末から2000年代にかけて多く作られ、社会情報化に伴う新たな在り方を提案したものが多かった。このような「参加」を前提とするアートの形態は、同じく1990年代末に議論が活発化した「参加型アート」と称される現代アートと共通項が見出せる。両者は共に「参加」が重要概念であり、この共通点については先述の馬および久保田も指摘している[6]。インターネットアートは先述したRhizome.orgや「文化庁メディア芸術データベース」などのデータベース機関により多くの作品が保存される一方で、「Yahoo!ジオシティーズ」や「Yahoo!ブログ」などの初期ネット文化の一翼を担ったサーバーの相次ぐ廃止によって、ウェブコンテンツが失われている状況もある[7]。このような状況下で、インターネットアートは早急な保存とアーカイブが必要とされている。
以上より、インターネットアートをいかに保存するかという問題に対し、「参加」という共通項を持つ参加型アートの議論を手掛かりに考察する。それにあたって、初めにインターネットアートにおける「参加」を詳しく見ていく。次に参加型アートにおける保存の問題を「アート・ドキュメンテーション」という概念から考察する。最後にインターネットアートに立ち返り、その保存のために何が必要かを考察する。それによって、馬および久保田が懸念していた「断絶」を克服する方法を別の視点から提供する。以上の観点を踏まえることによって、インターネットアートの視点も含めた複数のメディア・イベントと称されるアートの経験がいかに可能となるかに対し、一つの示唆を提供したく思う。
インターネットアートとは何か
先述の通り、1990年代に登場したインターネットアートには、ネットユーザーの「参加」というインターネットの非物質的な特性をその創造過程に組み込んだ作品がある。このようなアートは社会の情報化に伴い世界中で展開され、特に国内では1995年にNTTインター・コミュニケーションセンター(ICC)の開館プレイベント「InterCommunication ’95 “on the web”——ネットワークの中のミュージアム」展が代表的である。インターネットアートをブラウザ上で直接表示した本展覧会は、その後の展開において重要な貢献を果たすアーティストが多く登場し、また多くの作品が作られた。その例として、本論では江渡浩一郎《RealPanopticon》(1995)を紹介したい。
江渡浩一郎《RealPanopticon》(1995)
本作品は「ネットワークの中のミュージアム」展のどのページにネットユーザーがアクセスしているのかを、ユーザー各自のブラウザ上で一斉に提示している。ユーザーはサーバーにアクセスすることにより作品に「参加」し、ブラウザ上で提示される画面の一つになる。本作品は通常はサーバー管理者にしか見えない「アクセス状況」=人々の行動を可視化することによって、特権的な管理者の視覚的支配を顕在化している。それは2000年代中盤にアントニオ・ネグリおよびマイケル・ハートが問題提起したグローバルな主権による〈帝国〉の問題を、それに先駆けて提示したといえよう[7]。このように、江渡はインターネットに内在する問題意識に対し、ネットユーザーが「参加」すること、およびそれによる視覚的支配を受けることによって提示している。「参加」が重要となるこれらのインターネットアートを、江渡は後に「ユーザー参加型芸術」と称し、ウェブユーザーの多くが協調しながら「参加」することで生じる集団的な創造性を肯定的に論じている 。
このような「参加」に価値を置くインターネットアートは、「参加」というその特性ゆえに保存と再現が困難である。「ネットワークの中のミュージアム」展はその後図録として販売され[9]、図録に掲載されたスクリーンショットなどからから当時の状況は推測できるが、現在はページが削除されており、ブラウザ上から状況を知ることはできない[10]。また、ネットユーザーの参加と経験に価値を置くインターネットアートはその性質ゆえに、その環境を完全再現したとしても、作品の持つ意味は大きく異なったものになる。なぜなら、「ウェブ2.0」という概念が流通し、インターネットが最早インフラの一部となった現代と、それが最新テクノロジーとされていた90年代当時とでは、我々がインターネットに対して抱く印象が全く異なってくるからだ。では、我々は当時の環境や「参加」の経験も含むインターネットアートの保存を、どのように考えるべきなのだろうか。これに対し、同じく「参加」とそれによる参加者の「経験」が重要な要素となってくる参加型アートの議論を参照してみたい。
参加型アートと「アート・ドキュメンテーション」
1990年代にその活動が顕著になった参加型アートは、美術教育家のパブロ・エルゲラ曰く「プロセス・アート」であり、かつ「社会的相互行為」が組み込まれたアートである[11]。ここでは参加型アートの代表的批評家であるクレア・ビショップの議論に取り上げられた《オーグリーヴの戦い》(2001)、およびその3年後に設置されたインスタレーション《オーグリーヴの戦いのアーカイブ(一人の痛みは全民の痛み)》(2004)を参照しながら、考察を行う[12]。

ジェレミー・デラー《オーグリーヴの戦い》(2001)
《オーグリーヴの戦い》はイギリス人アーティスト、ジェレミー・デラーによって企画されたSEAであり、1978年に実際に起こった鉱山労働者と機動警官との衝突事件の状況を「再演」という形で現代に再現したものである[13]。本作品における「参加者」は歴史リエクナメント(過去の歴史イベントを再現する有志の集団)と、実際に1978年の事件に参加していた労働者と警官たちである。本作品は実際の事件を経験した当事者間の対立や、全く当時の事件に関与していない第三者である歴史リエクナメントとの対立関係など、多くの対立が「参加」によって露わにされており、この点において「参加」や「経験」が重要な要素となっている[14]。

ジェレミー・デラー《オーグリーヴの戦いのアーカイブ(一人の痛みは全民の痛み)》(2004)
本パフォーマンスはその後、《オーグリーヴの戦いのアーカイブ(一人の痛みは全民の痛み)》(2004)として、インスタレーションの形式で展示がされた。展示はパフォーマンスに際して作成されたバッヂやポスタージャケット、暴動鎮圧の楯や複数の絵画と、壁面に展示された事件の一時始終の年表で構成された[15]。タイトルから見るように、本作品は2001年のパフォーマンスを受け作成されたが、作品タイトルには「一人の痛みは全民の痛み」という、オリジナルには無かった副題が付けられている。ビショップはこのインスタレーションを「二重のアーカイブ」と称し、「17年後にパフォーマンスとして行われたこれらの出来事に対する、アーティストの再解釈の営為である」と論じている[16]。本作品は1984年に生じた事件を再現した2001年のパフォーマンスを、その実施から3年が経過した2004年にて再解釈し、それを表象したものであるというのだ。そして、《オーグリーヴの戦いのアーカイブ》は2001年の《オーグリーヴの戦い》の再解釈であるゆえ、2001年のパフォーマンスの純粋なアーカイブではないと、ビショップは考える。
この考え方は、批評家ボリス・グロイスの「アート・ドキュメンテーション」という概念との関係が想定できる。「生成時時代の芸術」と称された論文で、グロイスは芸術を記録し指し示す「アート・ドキュメンテーション」には、過去を想起するタイプと、記録という手段を用いずには決して表現できないタイプの二つがあると論じた[17]。グロイス曰く、後者のアート・ドキュメンテーションにて展開されるのは「日常生活への複雑で多様な芸術的介入、入り組んで手間のかかる議論と分析のプロセス、非日常的な生活環境の創出、さまざまな文化や環境における芸術の受容についての芸術的な探求、政治的動機による芸術行為」であり[18]、これらの展開によって露わになる「生の形式」が記録される。石田圭子はドキュメンテーションが「美術館」という中立空間で展示されることで新たな文脈が生成されると主張するが[19]、この問題は《オーグリーヴの戦いのアーカイブ》でも同様だ。《オーグリーヴの戦いのアーカイブ》は2001年のパフォーマンスから生まれたものではある一方で、それは2001年のパフォーマンスとは別個のインスタレーションとして位置付けるべきなのだ。
二種のアートにおける断絶を乗り越える
ここまで《オーグリーヴの戦い》のアーカイブと「アート・ドキュメンテーション」について議論を展開した。以上の議論は、同じく「参加」という概念を共有しているインターネットアートにおいても、同様に言及できるのではないだろうか。江渡の作品から見ていったように、インターネットアートのなかでもネットユーザー間の「参加」を前提とする作品——江渡が「ユーザー参加型芸術」と称したような作品は、その「参加」こそ作品の価値であり、それなくして論じることはできない。この点は、参加型アートにおいても同様である。しかし、参加型アートの場合はこの「参加」という性質ゆえに、その保存は「アート・ドキュメンテーション」という形式にならざるを得ない。その際、ドキュメンテーションは「再解釈」として議論される。これを踏まえると、「参加」という非物質的なメディア特性を組み込んだインターネットアートは、同じく「参加」の形式をとる参加型アートにおける「アート・ドキュメンテーション」の手法のように、その保存には「再解釈」が必ず必要なものとなってくると結論付けることができるだろう。
以上より、どのようなことが主張できるだろうか。再度、馬および久保田の論文に注目したい。彼らはメディア・アーカイブ研究者であるマックス・エルンストの議論を参照しながら、メディアアートのアーカイブはその多様性、可変性に能動的に取り組むべきであると主張している[20]。ボーン・デジタルであるメディアアートはその多様性と可変性ゆえに別様の意味がアーカイブによって獲得されると主張したエルンストは、メディアアートの保存は歴史的な保存修復学における「保存conservation」ではなく、積極的な保存修復を含めた「保存preservation」であるべきだという[21]。馬と久保田はこの議論に同調し、メディアアートの保存におけるハードウェアの側面に注目したが、本論では「参加」というメディアアートの別の側面に注目し議論を行った。「参加」という形式をとるためそのままでの保存が不可能なインターネットアートは、積極的な再解釈を含めた「保存preservation」でしか残すことはできないといえよう。この点で、筆者の議論は馬および久保田と問題意識を共有しており、また「アート・ドキュメンテーション」という保存の手法を参加型アートと共有している。以上のような共通項の発見は、冒頭に述べた「断絶」を乗り越えるための、一つの手がかりとなりえないだろうか。
おわりにかえて
本論では「アーカイブ」という議論を手掛かりに、メディアアートと現代アートとの間にある断絶を乗り越えるための手法についての考察を行ってきた。本稿で扱ってきた「アート・ドキュメンテーション」という考えは参加したというアートの経験そのものの保存ができないことを踏まえたうえで、記録された文書そのものがもはや別個の作品であることを肯定している。芸術理論から見出されるこの指摘は決してインターネットアートのみならず、あらゆるネットワーク上での経験においても主張できるのではないだろうか。2010年代以降でしかネット文化に本格的に参入できなかった私にとって、2000年代のインターネット上での様々な熱狂を十分に理解できないというのがここでの結論になるだろう。しかし、この身近な論考では「経験」の哲学については十分に触れられず、もっぱら芸術学の議論を参照したゆえ、まだ深く考える必要のある箇所もいくつかある。それらについては今後の問題としたうえで、議論を一度終わりにしたく思う。
―————
[1]Mark Tribe, Reena Jana, New Media Art, Taschen, pp.6-7.
[2]Christiane Paul, ed., A companion to digital art, John Wiley & Sons, Inc., 2016, p.1
[3]Bernhard Serexhe, “Born Digital-But Still in Infancy,” in Bernhard Serexhe, ed., Preservation of digital art: theory and practice: the project digital art conservation, Ambra V, 2013, p. 26
[4]馬正延・久保田晃弘「メディアアートのための生成するアーカイブ試論(前編)」『多摩美術大学研究紀要』2017年、31号、93頁。
[5]当研究では三上晴子《Eye Tracking Informatics》(2011)が主に扱われている。
[6]馬・久保田、前掲書、94頁。
[7]アントニオ・ネグリ+マイケル・ハート『〈帝国〉——グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』(水島一憲・酒井隆史・浜邦彦・吉田俊実訳)、以文社、2003年。
[8]江渡浩一郎「ユーザー参加型芸術と集合知研究」、西垣通(編)『ユーザーがつくる知のかたち——集合知の深化』KADOKAWA、2015年、65頁。
[9]NTT出版インターコミュニケーション編集室(編)『ネットワークの中のミュージアム』NTT出版、1996年。
[10]前注にて紹介されているリンクは以下。http://www.ntticc.or.jp/ic95
[11]パブロ・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門——アートが社会と深くかかわるための10のポイント』(アート&ソサエティ研究センターSEA研究会訳) フィルムアート社、2015年。
[12]クレア・ビショップ(大森俊克訳)『人工地獄——現代アートと観客の政治学』フィルムアート社、2016年。
[13]以下のサイトにて映像記録を鑑賞することが可能である。
[14]ビショップ、前掲書、62頁。
[15]作品画像を参照。
[16]同上
[17]ボリス・グロイス「生成時時代の芸術」、『アート・パワー』(石田圭子・斎木克裕・三本松倫代・角尾宣信訳)、現代企画社、2017年、92頁。
[18]同上。
[19]石田圭子「ボリス・グロイスにおけるアートと政治の交差について」『神戸大学大学院国際文化学研究科紀要』2018年、51号、100頁。
[20]馬・久保田、前掲書、95頁。
[21]Wolfgang Ernst, Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press, 2012, p.29.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?