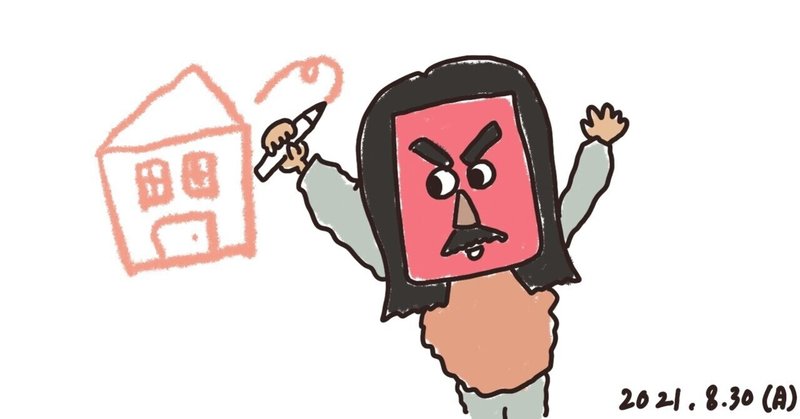
防災活動レポ~早稲田地区でのワークショップ~
ご無沙汰しています。しもおかです。
やっとやっと、修士論文が終了し、note再開します‼
6月、7月は修士論文の大詰めで、研究以外の事は考えられず、一時はほんとうに投げ出しそうになりましたが、何とか、周りの人に支えられ、ここまで来ることができました。感謝感謝です。
さて、今回は、修士論文が無事終了したしもおかの防災活動のレポートです!私の視点で書いていますので、もしなにかあればしもおかまで!
この地域のこと
今回おじゃましたのは、広島県の早稲田地区!こちらの地域では、地域の防災士の方を中心に何度も会議を重ね、地域の防災プランを作成しています。(とても素敵な取り組み…)
防災プランの仮案を少し拝読させていただきましたが、「災害が発生してどんな対応をするか」、また「将来の防災教育」まで、とても充実した内容で感動…。災害時計画していても、うまくいかないことはありますが、事前に考えておくことはとても重要です。
今回は、こちらの地区の防災士の方がたを中心に行われた、勉強会に参加させていただき、その様子をグラフィックで記録させていただくお仕事をいただきました。
この場でグラフィックを用いる目的としては
・地域の他の方々にも勉強会の様子を少しでも感じ取ってもらいたい
・いろんな年代の人にも伝わるように記録していきたい
・防災に対してまだできることはある!というポジティブな様子を伝えたい!
以上の目的を設定して、グラフィックを用いました。
ワークショップの内容
今回の勉強会では、鍵屋先生をお招きし、「高齢者・障がい者等の個別避難計画~高齢者・障がい者等と支援者の命と尊厳を守るために~」という題目でお話をしていただき、そのあと、ワークショップを行うというものでした。
ではでは、講演会でのハイライトを、ぐらレコを見ながらレポート!
軽く運動することから始まった、講演会。和やかな雰囲気ではじまりました。

さて、最初に始まったのはコロナ禍での話。
コロナ禍で、人々の不安やストレスが積もる中、自分の心理状況を見つめることが大切です。
特に、私たちは情報によって気持ちも左右されます。情報をいろんなところから収集すると、心のストレスも溜まると思います。
関する情報は、信頼のある情報元からの情報だけを毎日同じ時間に見ることで、安定した心理状態を保ちやすいです。
さて、ここからどんどん防災の話に入っていきます…鍵屋先生の講演をお聞きしたことがある方はご存じかもしれませんが…先生の講演にはある、地域の神様の使いの話が出てきます。
そう、サムネイルにもあるように
「なまはげ」が出てきます(笑)
ぐらレコにもたくさん登場していますが、なまはげは秋田の男鹿半島周辺で行われてきた、年中行事です。なまはげは、本来神の使いと考えられているようですが、この防災の文脈だと、地域の「避難支援者」ともとらえることができます。
なまはげの主な活動を見ていくとそれがわかります。
「泣ぐ子(ゴ)は居ねがー」「悪い子(ゴ)は居ねがー」と奇声を発しながら練り歩き、家に入って怠け者や子供、初嫁を探して家に入ってきて、家の様子を見て、家族の様子を聞き出す(Wikiより)
その後なまはげ台帳に記入→これが見事、要支援者リストに
神の使いなので、神社までの道を綺麗に整備する→避難所とされる神社を守り、避難経路も守る
といった感じで、なまはげは限りなく、避難支援者に近い活動をしている…。
もっと、分かり易くいうと、なまはげさんは「近所のひと」と、「福祉関係者」の間の人なんですよね。
なまはげさんみたいな存在が、各地域にも必要ですよね…。
さて、話は変わり、最近の災害のエピソードから、2021年は福祉防災元年である話まで…。

近年では、気候変動の影響もあり、これまで経験したことのない災害規模の災害がこれまで想定されていなかった地域にまで発生してます。
その中で、増加しているのが、車避難。東日本大震災では、渋滞が発生し、これまでの防災では原則歩いての避難を言われてきました。しかし、現在では、早めの避難であれば、高齢者や要支援者の事を考えると、車避難も1つ重要な手段です。
しかし、そこで新たに問題となるのが、エコノミー症候群。窮屈な座席などで長時間同じ姿勢でいると、血の流れが悪くなり、血管の中に血の塊ができ、痛みを感じたり、最悪の場合死に至る恐ろしい病気を引き起こす可能性もあります。
しかし、簡単に車から出にくいのが高齢者の方。避難という非日常の場面では、すぐにその場所に慣れ、対応し、車から出て運動することも難しいのです。
そこで、重要なのが「胃袋をつかめ!」
おいしい羊羹や、和菓子などが避難所に届いたら、すかさず伝え、取りに来てもらうことで車から出てもらい、運動するきっかけを作ります。
(この話、とても良くて、今回のnoteで抜粋して紹介させてもらっています)
また、災害時いろんな人が困っている人を助けたいという思いを持つことがありますが、それを実際に災害時に確立することは難しくパワーのいることです。
そこで重要となるのが、
・地域との支えあいの連携を事前に結んでいること
・個別避難計画を作成すること
は大変重要になってきます。
さて、ここで「個別避難計画」とは?という話ですが
個別避難計画とは避難行動要支援者(高齢者、障害者等)ごとに、避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画。
(デザインはあれだけど、制度の変遷なども書いてあるので、ぜひ見てみてください:内閣府 高齢者・障害者等の個別避難計画に関する
防災と福祉の連携について)
要支援者の名簿を作ることは以前から議論に多く上がっていましたが、近年では、あらかじめ支援を必要とされる方にどこに避難してもらうかを計画することが考えられているようです

さて、先生のお話もラストスパート!
今後の福祉避難所の方向性についてお話してくださいまいした。
先ほど紹介した、個別避難計画では、事前にその人にどこに避難してもらうかを事前にマッチングすること!事前にマッチングを行うことで、災害時に迷うことなく、その避難者も安心して避難所に向かうことができます。
また、避難所側からも、「ここの避難所では、高齢者を受け入れますよ~」とか、「障がいがある子供でも避難できますよ」などの、受け入れる人を限定する公示が重要になります。障がいのある子どもさんは、避難所ではなかなか安心して過ごすことができません。そのため、親御さんも一緒に避難所に行くことをためらったりするそうです。避難はみなしていいはずです。そのためにも、避難所からの受け入れられる人の発信も重要になってきます。
さらに誰もが避難できる一般避難所の設置も重要になってきます。先ほどの話は、事前に決めておき、その人達はしっかり受け入れる、そんなスタンスのように見えますが、災害時それ以外の方も避難にきます。そんなとき、考えたいのが、ゾーニングです。例えば、学校が避難所になった際に、1階を高齢者の方にするなど、階やスペースで考え、避難所での過ごしやすさにもつなげます。
最後に、このようなルールや計画を決めたとしても、実際の災害時に機能しないと意味がありません。
実効性についても期間をおいて見直しながら、一歩づつ計画を立て、実行をしていくことがとても重要になると、改めて勉強になりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、その後、過去の災害エピソードをみて、もっと事前にどんなことをすればよかったかを考えるワークショップが始まりました。
エピソードには、災害から間一髪で逃げることができた話などがあり、それを見て参加者のみなさんは、もっと事前にどうすればよかったかを考えました。
出てきた中でも、
・気象について知る機会をつくる(まちをあるきながらとか、気候変動についてとか)
・避難基準を自分たちで決める(JRが止まったらとか)
など、「たしかに!」の策がたくさん出てきました。
(これを基に研究とかできそうとか思ったのは秘密(笑))
防災での議論では、日ごろからにつながりと作りましょう~、とか、避難所の事を知りましょ~うとか、抽象度の高い話で、結局具体的な話に至らないことが多いのですが、このワークショップでは具体的な案まで発表されていて、すぐに地域の計画やアクションに移しやすいなと思いました。
それにしても終始穏やかな雰囲気で、議論もしっかりされていて、こんな素敵な地域と出会うことができてとても嬉しかったです。

ぐらレコで参加してみて
今回この勉強会に参加して、感じたことは
「もっと広島で防災のワークショップにぐらレコで入っていきたい!!!!」
それに尽きます。
防災の地域のワークショップってだいたい
①誰か講演する(防災リーダーとかアドバイザーとか)
②それに関するワークショップする
③まとめる→できるものは地域の計画とかに入れる
感じだと思うのですが、結構講演の内容が長くて疲弊したり、内容はいいけど、ワークショップでのモチベーションまでつながらなかったりすると私は考えています。人それぞれ背景があって、そこにいるわけで、必ずしもモチベーションが一緒ではありません。
また、そもそも講演会やワークショップに参加した人が、その内容を話すことでまた防災が広がる、という可能性があるのも関らず、なかなかシェアしようと思う人は少ないと思います。

その中でも、ぐらレコを入れると、
「話の内容はよくわからんところもあったけど、こんな感じなんだ」
とか
「これ写真とってフェイスブックにあげていいですか?」
と声をかけてくださる方もいて、防災をじわじわ拡げていく1つの手段になるのではないかと思っています。
正直、防災を考えることは最終的に命にもかかわってくることだと思います。描く責任はあると思いますが、このぐらレコでの防災の拡がりを加速させていくためにも、もっと地域で描いていきたいです!
今後の展望
地域での活動で、グラフィックを入れたい!という方はぜひご連絡ください。一緒にお仕事させていただければと思います。
宛先はこちらまでお願いいたします!
オンラインでも、オフラインでもお待ちしております!
(近日これまでのぐらレコまとめも出そうと考えています!)

今回は、防災活動記録~早稲田地区でのワークショップ~についてのおはなしでした!
また、次回、気が向いたころにやってきます!
その日まで!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
