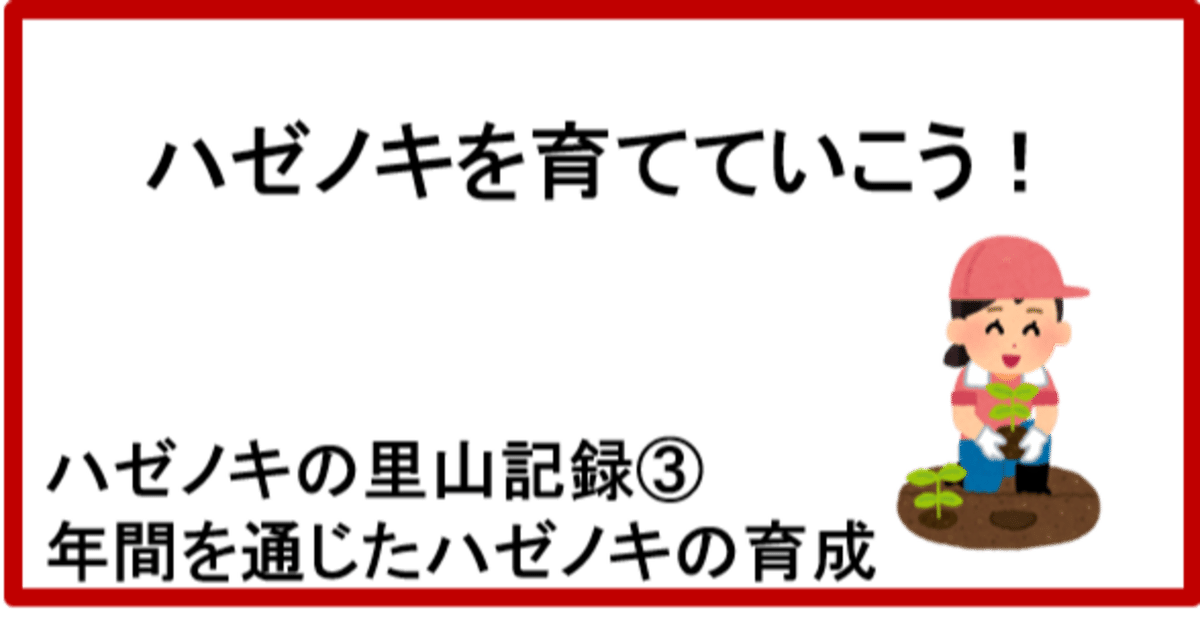
ハゼノキの里山記録③ 年間を通じたハゼノキの育成
こんにちは!3回目になりました「ハゼノキの里山記録」です。先週はハゼノキの植樹方法に関してかいてみました。ぱっとみあまり難しい感じはしなかったのではないでしょうか?実際に、ほとんどの樹木の植樹方法と大きくは変わらなかったりします。そんな前回の記事はこちら!
今週は植樹後の話をしていこかと思っています。ハゼノキの里山、最初の3年間を振りかえって日常的に取り組んでいることや気づいたことを今週は書いていこうと思います。毎年の事ですが、新しい発見や植物の力強さに感動したりと、実際の育ててみるとわかることがたくさんありました!
■草刈り
1,草仮刈の頻度と目的
ハゼノキの里山は南から西向き傾斜のすり鉢状の地形をしています。全体的に日当たりがよく、ハゼノキだけでなく雑草も大変よく伸びる土地でもあります。そのため、定期的に草刈りをしておかないとすぐに1メートルを超えるくらいまでに育ってしまいます。ざっくりですが、1年目の変遷です。③の直後ですが、4月30日に一度②の状態に戻しています。④の時には長い雑草は1mを超えるくらいになっていました。

場所や苗の大きなによっても変わりますが、ハゼノキの里山で1年目は特に苗が小さかったことから、このようなタイミングで草刈りをしています。基本的に雑草がハゼノキの苗を超えないよう、定期的に草を刈ります。
・2月下旬(植樹場所確保のため)
・5月中旬(植樹場所以外も含めてすべての場所)
・7月中旬(植樹場所のみ)
→乾燥防止のため、刈った草を苗木の下にひいて対策します。
・9月中旬(植樹場所のみ)
・11月中旬(成長の確認のため)
→後述しますが、背の低い苗の周辺は刈らないようにする。
2,草を刈らなかった場合どうなるか?
実証も兼ねて全く草を刈らずに山として育てる場合、どうなるのか?という事も試しています。結論としてはどちら枯れることはすくないのですが、写真を見ての通りですが、日当たりの悪い場所は雑草に負けてしまい。ほとんど成長していません。日当たりの良い場所は育つのですが、樹冠以外が雑草で隠れてしまうため、より上に伸びてしまうため、実の採取用に育てる場合は高くなりすぎないようにある程度の高さで草は刈るようにした方が良いです。つまり、いずれにせよ草は刈った方がベターです。

■獣害対策
非常に運の良いことに、ハゼノキの里山は鹿が出ません。最も警戒すべき鹿対策をする必要がないので、他の地域に比べて少し獣害対策は楽です。そのため獣害対策は主に2つです。
1,イノシシ
鹿がいなくてもイノシシは沢山います。ほかの地域のお話をお聞きしてかなり警戒していたのですが…実はこの3年間特に被害が出ていません。不思議なことになぜかハゼノキを避けるように穴を掘っていきます。水俣などでお話をお聞きしている限り、巻き込まれる可能性が高いと思っていましたが、現時点でイノシシの被害は0本を継続中です。

ただし、これはかなり運が良かっただけだと思いますので、根本的な対策は必要と考えています。イノシシの進む進路は結構わかりやすいので、そこに罠をはるなど対応できます。
2,野ウサギ
ハゼノキを植樹する前、植え始めるとウサギが嫌いになるよ。と聞いていたのですが、植樹したばかりの新苗に関してはイノシシよりもこちらの方がはるかに厄介でした。冬の間に新芽をかじられてしまい、春に新芽が発芽せずそのまま枯れてしまったりします。

野ウサギは植樹1年目の苗に限られる話ではあるのですが、数も含めて対策が難しく、冬季の草刈りの際にハゼノキ周辺に草をあえて残したままにして、低い位置の新芽が隠れるようにして放置しみました。結果として2年目の春(今年)は被害をかなり軽減することができました。ただし、低い位置に新芽がなければ特に問題がないので、そのまま放置でも対処可能です。
3,その他
ハゼノキの里山特有の問題かもしれない、かつハゼノキに特に被害があるわけではなのですが、アナグマが結構いるので作業中に落ちないように警戒しています。獣害になりそうな動物は以上です。

■肥料と水やり
本日最後は肥料と水やりです。「植樹」のところでも少し触れました、水をやるときは、植樹直後と長期間降雨がない場合に限ります。基本的にはそのままで十分育つので、特別な対応をする必要はありません。ただし、途中で苗を植え替える場合には植え替え直後に水を上げるようにしてください。
肥料に関してですが、ハゼノキの里山ではまだ使っていないのですが、成長に合わせて1年に2回肥料を使うと良いとされています。
1,3月上旬(新芽が開く前。春の成長期)
2,6月中旬~7月中旬(梅雨明すぐ。実の成長期)
どちらも生長点に合わせて、肥料をまくのが効果的です。ただし、最初の3年くらいはほとんど実がつきませんので、肥料を使わずそのまま育てても問題ないと思います。4年目以降は比較的実の付き方が良くなります(ハゼノキの里山は3年目から劇的によくなりました)ので、早く実の収穫量を多くしたい場合は肥料を使うようにしましょう。
※ちなみにハゼノキの里山は鶏糞を使っています。

最後に量をまく位置に関してですが、樹木の大きによってことなりますので、成長に合わせて調整してみてください。幹に中心からだいたい50センチ~1メートルの円周に溝を掘り、その中に肥料をいれて埋めておきます。この際の注意点は肥料が直接根っこにつかないように気を付けましょう!
せて、今回はハゼノキを育てる中で日常的に行っている育成方法を書いてみました。まだまだ育てはじめたばかりですので、さらに多くの事をこれから学んだり試したりすることになりますが、初期の育成として少しでも役立てていただければ嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
