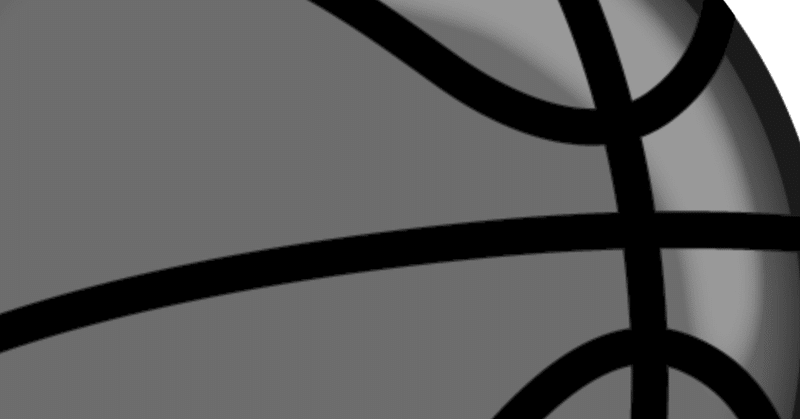
マンツーマンプレスについて①
最近、マンツーマンプレスを調べてみようと思った。
数年前に調べたことはあったけど、改めて。
どうしてマンツーマンプレスなのか
いま関わっているチームでは、激しいディフェンスを目指している。
でも、なかなか激しくプレーができない。
全体的にみんな上手なんだけど、激しいDF出来る選手と、そうでない選手が大きく分かれている。
そんなある日、少し時間があったから、この動画をみんなに見せてみた。
なんとなくその場しのぎで、時間があったから、見せてみた。元から準備したわけじゃない。
ただ、見ながら、多少わかる範囲で解説して、質問にも答えて、そういう時間を15分くらい作った。
そうしたら次の日、DFが大きく変わった。
今までも伝えたことのあったプレー。動き。考え方。
でも、なかなか変わらなかった。
映像を見せたら、次の日に変わった。
たぶん彼らに、イメージが出来たんだと思う。
言葉だけでは作り上げられなかった、プレーのイメージが、15分で出来上がった。
もちろん、ある程度の過程を経て、言葉による指導を経て、要求を経て、彼らの中にも思考と試行の蓄積があったから、はまったんだと思う。
そういう彼らを見て、もう一度自分も、勉強してみたいと思った。
そういう次第で、いまはマンツーマンプレスに興味関心が向いている。
映像はこれを見せてイメージさせつつ、細部のTIPSやその整合性を私は理解しておかないといけないと感じた。
だから、何個か調べて、何個か書いてみて、そこから共通の要素や仕組みを考えてみたい。
今日はその1つ目
参考元はこちら。英語のサイトなため、翻訳と、意訳と、解釈とを混ぜ合わせて書く。
その1:Havoc double-fist press
(ここからは、翻訳意訳解釈になるので、文章構成や言い回しはテキトーです。許してください。また、参照元には画像もあるけど、さすがにそれを直接使用することもどうかと思うので、画像無しで行きます。)
ダブルフィストはマンツーマンのプレスで、NCAAのシャカスマートのプレスです。
3種類のトラップがある。
ちなみに、「フィスト」は、トラップを行わないマンツーマンプレスの事らしい。
基本の考え方
インバウンダーのDFを、マッドマンと言います。
パサーに覆いかぶさり、パスを苦しめるよう、狂喜乱舞する笑
一番近いレシーバー以外のDFは、ボールが入るまではOFの内側に位置取り、くっつく。深く走られたり、引きはがされたりしないようにする。
Havocとは、シャカのチームの全体的なプレイスタイルを言う。
フルコートプレスでDFを始めるが、ハーフコートでも勿論プレッシャーをかける。
ハーフコートに簡単に進まれることを好まず、何度も何度もトラップを狙い、パスをディナイする激しさを求める。
プレッシャーをかけ、ボールを奪い、早いトランジションOF(6-7秒)で、シュートを狙い、相手にダメージを与えることを好んでいる。
プレスの目的
ターンオーバーを狙う。そこで相手を倒す。スティールを狙う。
焦った早いシュートや、体勢の悪いバッドショットを強いる
オフェンスチャンスを作る(回数+TOからの速攻という質の高いOF)
試合のテンポを上げる
プレスの対策は難しく、それを相手に強いる。
相手選手が快適にプレーできないようにする。
相手に疲労を蓄積させ、弱気にさせる。
多くの選手にプレータイムを与えたい。そのためにも、激しくプレーし、何回も交代を用いる。
10分で9-11人は使う。
3-5分もこの激しいスタイルを同じメンバーで維持するのは難しい
エキサイティングで楽しい
チームカルチャー、アイデンティティとして使用する。
大切なこと
エナジーを出す。5人が常に動き回っていること
ファウルのし過ぎに注意する
コミュニケーションを取って、素早い連携を保つ
トラップの瞬間、2人目(トラッパー)が合図を出す。3人目のスティール・寄りを引き出す
ディフレクションを狙い、賞賛する。1分間で1回はディフレクションをしたい。
チームで戦うこと。個人で戦うのではなく、連携を重視する。
各選手の基本役割
①ボールマンDF(X1)
ボールマンのDFがプレッシャーをかける。
②自陣寄りオフボールDF(X2,X3.のちのインターセプター)
ボールより前にいる選手は、フロートする。ピストルスタンスでフラットトライアングルを取り、スペースキルをする。
ただし、頭上をパスを通されることは許さない。すぐに戻れるようにする。
また、ボールマンDFがプレッシャーをかけ、ボールマンが苦しんでいるときは、ポジションニングをさらにボールに近づけても良い。
③インバウンダーDF(X4)
インバウンダーのDF (あるいは、ボールと同じ高さにいるOF のDF)は、同様にフラットトライアングルを取る。
ボールマンが自分の方向に進んできているときは、スタントをする。
足と手を使って、取りに行くようなそぶりを見せ、すぐにポジションに戻る。これを繰り返して駆け引きをする。
ボールの移動に合わせて、自分の位置を調整し続ける。
後ろに戻るようなパスは許容する。一方で、裏を取られるパスや、頭上を通され大きく前進されるパスは許さない。
もしそのような状況になったら、素早くボールラインに戻る。
ちなみに、オフボールDFは、全員スタントを徹底してトライすること。
④自陣ゴールに一番近いDF(X5)
一番下にいる選手(自陣のゴールに一番近い選手)は、フラットトライアングルポジションではなく、
相手OFの一番先頭にいる選手と同じラインまで下がる。
頭上を通され、簡単なシュートを打たれないために、同じラインまで下がることを重視する。
トラップを仕掛けるの条件と、その種類
トラップを仕掛ける3条件
トラップを仕掛ける良い状況は、次の状況であり、選手は理解しておいてほしい。
ボールへのプレッシャーがあること。ボールマンDFが相手に触れられるほど、間合いを詰めている状況であること。
奇襲、驚かせるタイミングであること。見えないところから行く。ターンの瞬間に行く。
良い場所であること。コーナーはベスト。サイドライン周辺で仕掛ける。ラインを味方に付ける。
この3つの要素のうち、2つ以上が満たされるときにトラップを仕掛けたい。
0~1個の時は、トラップを仕掛ける状況ではない。
①ターンに対して、トラップする
ボールマンDFがサイドラインへディレクションをかけ、ライン際に誘導する。サイドラインを踏めるくらいまで誘導できるといい。
X4(ボールマンと同じ高さにいたDF)は、ボールマンの後頭部が見えたら、後ろからトラップを仕掛ける。
トラップ時にはファウルをしないこと。
※ただし、ニュアンスとしては、「下半身でファウルする」というらしい(?)。手や上半身は大きく広げるだけ。壁を作る。下半身で近づき、下半身でファウルをする。
トラップの間を割ろうと狙ってきたら(スプリット)、チャージングを狙い、進行方向に立ちふさがる。
他の3人のDFは、トラッパーの意図をくみ取り、連携すること。
自分のマークマンに固執せず、ボールマンの目線や肩の向き、トラッパーの動きを読んで、次の動きをする。
閑話休題:だれにトラップを仕掛けるか
ちなみに、 シャカスマートのチームの場合、ガードにトラップを仕掛ける。ビッグマン・センターの選手がボールマンの場合、トラップは仕掛けない。
この場合は、ボール運びが苦手であり、この選手に運ばれてもハーフコートOFが崩れたまま始まるので、気にしない。one-man trapといい、ビッグマン自身に運ばせ、通常のボールマンDFでプレッシャーをかける。
ビッグマンにトラップを仕掛けると、パスを出された後の相手はハンドリングが上手な選手になるので、好まない。
ビッグマンに持たせたまま、苦しめることを好む。
①の続き:インターセプターの役割
ボールマンDFをX1、トラッパ―X4とすると、パスを狙うインターセプターは2人いる(X2,X3)
サイドライン際でトラップを仕掛けたとして、
前方へのパスのスティールを狙う選手(前方のインタセプター)
中央へのパスのスティールを狙う選手(高いインターセプター)
と、それぞれに役割がある。 (ここを図解無しで説明するのは難しいな。)
少し中央に寄り、高く位置取り、「1人で2人を守る」を2人分=2人で3人を守る態勢を作る。
コート中央へのパス(斜めの前進パス、ダイアゴナルパス)は一番脅威となるので、全員がコート中央に意識を置き、そのパスは特に注意を払う。
トラッパ―のポイント
トラッパ―の2人には重要なポイントがある。
ボールマンのピボットを誘導し、パスの狙いを明らかにさせることである。
ピボットを踏ませ、そしてさらにそれを固定化させることで、インターセプターがパスの出先を予測しやすくさせる。
後ろに戻すパスか、前方への縦パスか、を明らかにさせること。
中央へのダイアゴナルパスは出させないように苦しめる。
(この封じ込め方と、インターセプターの予測は、練習で磨く必要がある)
FIX:中央へのパスは緊急事態
中央へのダイアゴナルパスは、緊急事態として捉える。
ボールより高い位置にいる選手が多い状況となるので、素早くボールラインまで戻ること。
可能ならばバックチップ等で相手の態勢が崩れることを狙う。
バックチップが成功すれば、非常に強い形成逆転となる。(1試合で4-5回は狙っていきたい)
緊急事態になったら、Fixを試みる。つまり、体勢を立て直す。
ダイアゴナルパスをレシーブした選手が、バックチップを受けるような選手でない(=上手な選手)の場合は、素早くFixする必要がある。
DFは、近い選手が素早くボールを止め、他の選手は素早くボールラインまで下がる。
そして、各OFにマッチアップし、DF陣形を作る。必ずしも、最初のマッチアップである必要はない。
自分の役割を声に出し、指差しをし、スタンスを作り、ボールに対して適切なポジショニングを取る(フラットトライアングル)
Fix状況では、ボールマンには必ず1人がマッチアップすること。
0人ではいけないし、ただし、2人以上でも良くない。ここはコミュニケーションで解決する必要がある。
時として、アウトナンバーを守る状況も多く出てくる。
2on1状況で守ることを練習する必要がある。
また、同様に1on2の守り方(トラップの仕方)を練習することも大切になる。
②クリアアウトに対して、トラップ
トラップを仕掛けるプレスディフェンスに対して、多くのOFは、インバウンダーを先に走らせ、トラッパ―がいない状況を作り出そうとする。
このようなときでも、Havocのダブルフィストでは、あえてトラップを狙う。
インバウンダーがスペースを作ろうと試み、前に走り出してFTラインを超えたときに、トラップを発動させる。
X4は、この状況になったら"クリアアウト"と叫ぶ。これがコミュニケーション。トラップへの合図。
X1は、これを聞いたら、ボールマンをコート中央から追い出し、相手の前に回り込み、ターンを強要。トラップを仕掛ける状況を作る。
③サイドライントラップ(前方からトラップを仕掛ける)
多くのチームは、ボールマンがサイドライン沿いをドリブルで進もうとすると、その前方にいるOFはスペースを空けるよう前進するでしょう(ある程度賢いチームなら)
もし、前方の選手が動かず、悪いスぺ―シングになる場合は、前方のDF(X2)がトラッパ―となり、仕掛ける。
1-3歩のスライドステップで到達できる距離感になったら、仕掛ける。
その場合、X5が縦パスのインターセプター、X3がゴールを守る。X4が下りてきて、中央へのパスに対する高い位置のインターセプターになります。
ちなみに、このトラップはボールマンが前方への視野を保っている時には行わない。その場合は、スタントをし続け、良いポジションを取り続ける。
相手の視野が下に向き、油断や苦しみが見えたとき、前方からのトラップを仕掛ける。
マッドマンのアレンジ
インバウンドパスに対しての守り方もアレンジできる。
徹底的にディナイする場合もある。(Double fist face)
例えば、試合後半に負けている状況。
①インバウンダーにDFをつけ、ディフレクションを狙う
または
②インバウンダーのDFをコート中央(FTくらい? )に置く。
②の場合は、インバウンドパスが雑になることを誘発する。
インバウンドDF が、レシーバーにプレッシャーをかける際には、
相手の内側に立ち
前腕で相手の腹部に触れるような間合いを取る
もう片方の手でスペースを消すディフェンスをする。
前方に深く走ろうとしたら、ついていく。
ボールミートに来たら、最低でもキャッチの瞬間には、マッチアップが完了している必要がある。
ギャンブルはしない。ギャンブルしてボールを持たれたら、やられてしまう。
プレスの狙い(おまけ?)
また、このマンツーマンプレスは、ターンオーバーを誘発したい目的の他にも、相手に優秀なハンドラーがいて、その選手がからボールを手放させたいときに使用することもある。
最後の感想
翻訳・意訳・解釈をしてみて、面白かったことは何だろうな。
one-man-trapの考え方がよかったかな。ちゃんと意識してトラップに行かないということも選んでいるというのが分かった。
トラップの仕掛け方として、下半身でファウルする、というのも良かった。まあ、この解釈が合っていれば、だけど(笑)
ファウルをするな、というと激しさが減る傾向があると思うので、激しさを担保しつつ、不要なファウルを無くすために、上半身や腕でのファウルは無くしつつ、下半身で間合いを詰めて、プレッシャー・激しさを担保するというアイディアは伝えやすいと思った。
目的、条件、ポイントなどが整理されているので、実際にやってみながら、必要に応じて伝えていくのがいいなあ、と感じた。
一回目にはとてもいい機会だった。
おわり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
