
「美食倶楽部」実験店舗@六本木。オープン1ヶ月の数字と手ごたえと。
「美食倶楽部」スタートの経緯
縁あってスペインのバスク地方に通っている。滞在するたびに各所で体験して惚れ込んだのが、「Sociedad Gastronomica / 美食倶楽部」という会員制のシェアキッチン/ダイニングだった。
バスクは近年「世界一の美食の地域」として注目を集めている。中心都市のサンセバスチャンのミシュラン星つきレストラン密度に加え、今年のWorld`s 50 best Restaurantsでの躍進(国としてのフランスやイタリアよりもバスク地方単体で入選が多かった)も記憶に新しい。美食倶楽部は、そんなバスクで地域の食文化の礎として100年以上前から続く伝統と言われている。

美食と聞くとゴージャスなグルメという印象を持つが、僕が現地で体験したのは、なんともほっこりとしたシェアキッチンスペース、言い方を変えると共同の台所だった。老若男女が集い、自由きままに料理をして、飲んで食べている。つくる料理も高級料理というよりも家庭料理に近い。
では美食倶楽部はどんな場所か?
誰もいない飲食店を想像してほしい。限られた会員だけがそこの鍵を持っていて、会員たちは好きな時に自由に自分の家族や友人をつれてきて、料理をして、食べる。食材は各自が持ち込み、ドリンクは冷蔵庫から勝手に飲んで後精算。

(おもむろにエプロンをまとい、広々とした業務用キッチンで料理を始める友人たち。もちろん飲みながら料理)
そして感動したのが、クリーニングサービス。使い終わったキッチンの鍋やフライパン、食べ終わった皿やグラスなどは、決まったスペースに下膳するだけで後はすべて倶楽部が雇用するスタッフが洗ってくれる。手ぶらBBQのキッチン版、といったら良いのかもしれない。

(終了時間近くになってどこからか現れた快活な女性。テキパキと洗い物や清掃を進めていく。今回お邪魔した倶楽部では3人を常時雇用しているとのことだった。)
六本木の実験店舗の誕生
僕はそんな美食倶楽部にぞっこんになった。まずは「一緒に料理する」という行為のもつ、人と人をつなぐ力(現地の美食倶楽部で何人の友人をつくったか!)。肩書きや言葉を超えて、仲良くなる。楽しい。これはシンプルに素晴らしい。
それと、その場のもつ絶妙な空気感。バスクの美食倶楽部は「自分が自分の好きな人と良い時間を過ごすための場」というプライベート感がベースにある。部室のような(ちょっと汗臭いか笑)。でも、複数の会員が一緒に使い複数グループが一緒に使うこともあるちょっとしたオープンネスがまた良い。

あーこんな場所が近所にあったらなあ。。
最初はそんな考えから、いやでもこれって他の人にもニーズはあるよなあ、と言うかこれからの日本は・・・(以下略)、と妄想が広がり、構想になり、イベントで反響を見たら異常な手応えで、、、を繰り返し、六本木で美食倶楽部を運営するにいたった。(はしょった経緯は一度どっかでしっかり書きたいが未定)
場所は六本木の駅前、もともと「六本木農園」だった店舗をお借りした。クラウドファンディングで限定50名の会員を募ったところ、予想外の反響で2日で定員を達成。2019年8月1日より店舗の運営を開始した。

1ヶ月の成績表
さてやっと本題に突入します。
運営開始から早いもので1ヶ月が経過。せっかくなので経営状況とか、手ごたえとか、課題とか、さらけ出していきたいと思う。
まずは数字

(実際の数字を出したかったが、いろんな兼ね合いで出せず・・・)
初月から黒字達成!決済用のカードリーダーやiPad、包丁一式からラミネーターまで、様々な初期投資も含めて吸収できた。小さな数字だけど、これはまず嬉しい。
ただし見てすぐ分かるが、固定収益および固定費の割合が大きい。伸び代はあるのか?それはどこなのか?
ドリンク
バスクでは稼ぎどころであり、ユーザーが感じるメリットの大きな1つはドリンクだった。しかしこの1ヶ月、あまりドリンク販売が伸びなかった。僕のだいすきなクラフトビール「ベアレンビール」や、バスクからハンドキャリーで持ち帰ってきたチャコリ(バスクの白ワイン・下写真)をかなりお得な価格で用意していたのに。
目の前にコンビニがあり「持ち込みOK」としているのが理由なのだが、その中でもできることとして、見せ方からコミュニケーションから改善をまわしていく。そしてもちろん、「この美食倶楽部はドリンクで利益を追求すべきなのか?」も考えていかなくてはならない。
サービス
サービス売上の多くは、会員が友人を連れてきたときのゲスト利用料(アミーゴ使用料と呼んでる)。いま1人あたり800円に設定している。1日あたり10人のアミーゴなのか、20人なのか。ここは原価が基本的にかからないので、大きく収益に貢献する。どこまで相席/予約密度があがるのか。そのためのコミュニケーションはどうすべきか。
また、まだ本格的に展開できていないがニーズが顕在化しているのが、食材案内だ。自身で手配した食材をお店で受け取るサービスはやっているが利用はそこまでなく、やはり食材の提案や「もう冷蔵庫に用意してある」ところまでパッケージ化されたものにしていければと思う。
消耗品
調味料やラップ、ペーパーなどの消耗品は基本的には店舗で用意している。ただし、例えばバルサミコ酢とかスパイスなどは用意していない。もう少し投資することでユーザー満足度につなげられる気がする。
利用ツール・サービス
仕組みやシステムまわりはフリーのものを基本にまわしている。会員とのコミュニケーションはLNE公式アカウント。施設の予約管理はgoogleカレンダー。レジはスマレジ。管理系はgoogleスプレッドシート。いろんなことを初期コストなくチャレンジできるよい時代を僕らは生きていることを実感している。
ユーザー評価
数字より大切なのは、もちろんユーザーからの評価だ。
毎回、「実験店舗」の名前を楯に、利用した会員の皆さんにはアンケートの入力をお願いしている。そしてほとんど答えてもらっている(ありがとうございます)。その答えがこちら。


「美食倶楽部そのもの」については100%最高評価もしくは高評価だ。とてもとても、満足していただいている。嬉しい。そして数字には現れないけど、現場での盛り上がり!笑い声!!この手応えは強い。


利用シーン

ユーザーの利用シーンを見ると、会社の同僚や仲間とのプライベートな集まりがほとんどだ。先日は企業内のチームビルディングとしての活用も。(六本木の企業さん、いかがですか?)

(つい先日はご近所のメル◯リの方がチームビルディングに使って頂きました)
ユーザーコメント
フリーワードもいくつか紹介したい。
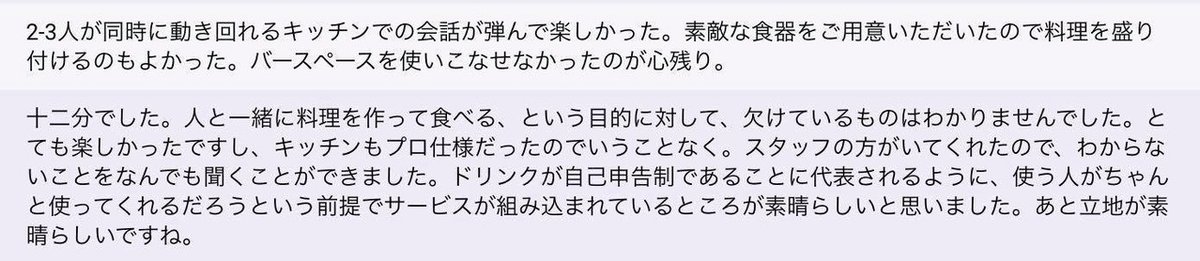

さらに、こんなちょっと本質的なコメントまで。ありがとうございます。

月イチの会員イベント
月に一度、会員限定のイベントも開催している。初回は元Tirpse、現在Mr.Cheesecakeも話題の(クラウドファンディングで2200万円!)田村浩二さんをゲストに一緒に料理&飲む食べる。各所から絶叫に近い「美味い!」「なんじゃこりゃあ!」が聞こえてめっちゃ盛り上がった。

まだ使ってなかった会員の体験の場にもなり、また会員同士の横のつながりにもなった。毎月頑張って企画していこうと思う。
会の様子はこちらの写真アルバムをご覧ください。Photo by Yasunobu Tamari
課題:スマートロック
当然だけど課題もいくつか見つかった。まず、個人的な肝いりで始めたスマートロックについては、運用を取りやめることにした。スマホを取り出すと鉄のドアがウィーンと開く。Appleのような「最高の顧客体験」のためにこれ以上ないと思って導入した(サービスはbitlockを選択。これは有償だったのに!)。
が、事前にスマートロック側のサービスへ登録してもらう必要があり、かつキーを渡すためのやりとりも必要。UX(顧客体験)が逆に悪くなった。またユーザーは会員だけでなくバラバラ来るので結局ドアを開けっぱなしにすることになったりと、活躍の出番が少なかった。1ヶ月まわして、継続運用を断念した。
課題:複数グループ同時利用
他に複数見られた課題は、複数グループが同時に利用する場合のもの。

同時利用は「貸切のイベント会場」ではなく「シェアキッチン」である美食倶楽部の醍醐味だと考えている。会員同士の横のつながりもそうだし、会員制のセミプライベート感の雰囲気、それと当然ビジネスとしてのコスト最適化のために。
備品の追加購入や共同利用時用の事前案内メッセージの運用など、細かいところから対応を続けている。下のような嬉しい声もあるが、共同利用自体も価値になるようなコミュニティに育てていくためにも、改善を続けたい。

----------
この「美食倶楽部」を全国に広げ文化にするために
以上、ざーーーと1ヶ月の振り返り。
手応え十二分。対処すべき課題も見えてきた。3ヶ月の実験期間を終え11月以降の検討も開始している。
そしてなんといっても、この店を運営している一番の目的は、「日本版美食倶楽部」のナレッジを貯めて、全国にいる自分の場所でコミュニティをつくりたい人に、美食倶楽部を活用してもらうことだ。
そんな未来へ向けて、引き続き進みます。引き続きよろしくお願いいたします。
※運営や全国展開に携わりたい仲間募集!
https://bosyu.me/b/CT8fAj1U1Bo
※自分の街でつくりたい、やってみたい、そんな方は下記よりお気軽にご連絡ください!
http://nav.cx/g623iHk
2019.10.17追記:↓新しくWebサイトができました!↓(写真をクリック)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

