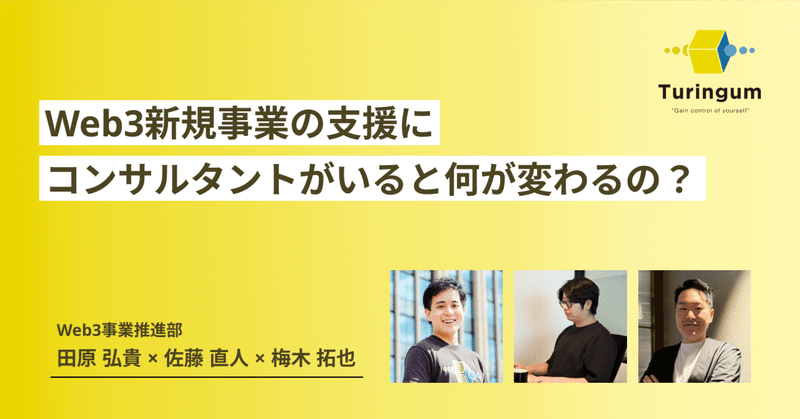
Web3新規事業の支援にコンサルタントがいると何が変わるの?
チューリンガムはWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げ支援や、既存のWeb3事業を推進するサポートをしています。日本でも有数のトークン上場実績を持っており、その第一線で活躍するのがWeb3コンサルタントのメンバー達です。
コンサルタントは新規事業を立ち上げたい企業に対して、企画立案からトークン発行の支援まで幅広い業務を行う必要があり、Web3業界への深い知見やプロジェクト推進力が求められる仕事です。
今回は実際にコンサルティングをするメンバー3名にインタビューをしました。日々どのように企業の支援をしているのか、またプロジェクト支援におけるコンサルタントの役割をどう考えているのかをご紹介します。
プロフィール
田原 弘貴 - 代表取締役 CTO(@_namahagesan)
東京大学文科一類入学後、在学中に中小企業診断士に合格。東京大学大学院学際情報学部在籍中にTuringum株式会社を設立。ブロックチェーンエンジニア及びリサーチャーとして技術部門を統括し、2023年5月より代表取締役に就任。親会社クシム取締役CTOを兼務。
佐藤 直人 - チーフコンサルタント(@2309Sn)
異能vation 2019企業特別賞受賞。フリーランスエンジニアとしてXR及びブロックチェーン領域で複数のアプリケーション開発を行う。Turingumではシステムコンサルティング部門を統括し、DeFiやGameFiにおけるトークンエコノミクス設計及びブロックチェーンシステム開発を国内外ともにリード。
梅木 拓也 - コンサルタント
LINE BITMAXでプロダクトマネージャとして勤務し、暗号資産関連サービスの立ち上げを経験。Turingumではプロダクト設計を担当。
コンサルタントの仕事の役割
ー まずは皆さんがどんな業務をしているのかを教えてください。
佐藤:Web3に関する新たな事業を始めたい企業に対して実現するためのサポートをしています。
NFTプロジェクトの支援やウォレット開発など開発案件もありますが、実績がある事業者が少ないことからトークン発行が必要な新規事業の支援をすることが多いです。この場合だと企画から実現まで1年ほどいただいてます。
ー 1年というのは結構長いですね。
田原:トークンを発行する場合は、その前にサービスのファンを増やす必要があります。企画や開発に1年かかるというわけではなく、サービスを育てるための仕込み期間が必要になるんです。
佐藤:大まかな目安にはなりますが、新規事業の立ち上げなので3,000〜5,000万円くらいは予算を見ておくと良いと思います。最近は海外取引所に上場するための上場費用も高く、1,000万円ほどかかる場合もあります。トークン発行するプロジェクトはスタートアップを1社立ち上げるような感覚だったりするんです。
ー プロジェクトのキックオフから実現までの流れを教えてください。
佐藤:トークンを発行するプロジェクトを例にお話しします。まず企画段階ですが、自社のIPを使ってWeb3事業に参入したいとか、ブロックチェーンゲームをやりたいなどクライアントにはアイデアがあります。そのアイデアを深堀り、実際にクリプトマーケットに受け入れられるかを検討していくことから始まります。
次にトークン発行に関わる下地づくりですね。発行する会社をどこにするか、トークン発行をした時にどう利益を受け取るか、といったスキームの話があります。スキームを整えていくプロセスは結構時間がかかるところです。
この後に取引所とのコミュニケーションなど、上場周りのことに移っていくといった流れです。
ー Web3事業に関わるのが初めてのクライアントさんも多いと思いますが、コンサルタントの役割はどのように説明されていますか?
田原:私たちコンサルタントはプロジェクトを収益化するところまで持って行く、そしてその収益をできるだけ伸ばしていくサポートをする役割だと思っています。
ただアドバイスして終わりではなく、プロジェクトがWeb3上で収益上げられるように伴走していくことがポイントかなと。
ー 収益化までサポートすることが重要とのことですが、Web3プロジェクトを立ち上げること自体は簡単なんですか?
佐藤:クライアントの性質にもよりますよね。Web3にそこまで詳しくない一般の方でもNFTを作成して販売することなどは簡単にできます。でも僕らが対峙してきた上場企業のクライアントの場合は企業として行うにはこれだけだと不十分です。
田原:事業としてやるかどうかの違いだと思います。株式会社でも上場して10年間、事業を継続させるのってものすごく難しいじゃないですか。でもただ株式会社を作ろうと思ったら書類を提出して、登記料を支払えば会社は設立できますよね。そういう違いだと思います。
チューリンガムのコンサルタントは一般的にコンサルタントと言われてイメージするような「事業コンサルタント」の役割と「証券会社の主幹事」のような役割の両方を担っています。
株式会社の場合は、事業を支援する人と、上場を支援する人が分かれていますが、クリプトの場合はビジネスとトークンの取り扱いというのが明確には分かれていないため、両方を行います。
ー 一般的にコンサルタントがプロジェクトに参画する際は、成果を判断するためにもゴールやマイルストーンが明確にあると思います。Web3プロジェクトの場合はどうでしょうか?
佐藤:確かにそこは難しいですね。通常コンサルはプロジェクトが終わればお客様との関係も終わりますが、私たちの支援の場合は、立ち上げたサービスが続く限りある程度伴走し続けるので関係性に違いがあります。期末テストのように成績がどうだったか見られるわけではないんですよね。
ー なるほど。例えば生産性を改善するようなプロジェクトだったらゴールが分かりやすいですけど、サービスの立ち上げ支援だとそういったプロジェクトとは性質が違いますね。
佐藤:ただマイルストーンとして重要なことはいくつかあります。まず一つはトークンを上場した際の調達額は大きなチェックポイントだと思いますし、その手前にあるサービスリリース時にどれだけマーケットに受け入れられたかというのも重要な指標になると思います。

Web3コンサルタントの腕の見せ所は?
ー コンサルタントの腕の見せ所はどこだと思いますか?
佐藤:コンサルタントから見た時、クライアントは2種類います。依頼主であるクライアントがまず存在しますが、その先には今後提供するサービスのエンドユーザーもいるんですよね。優先順位はありますが、両方を満足させられるかは腕の見せ所だと思います。
チューリンガムはBtoBでビジネスしているので、もちろん目の前のクライアントが重要ですが、エンドユーザーに利用され、満足してもらうことがプロジェクト成功には必要で、その結果クライアントの利益に繋がっていくので、両者に満足してもらえるようにするのが重要です。
ー 梅木さんはどう思われますか?
梅木:単に事業のコンサルティングをやろうと思えば別にクリプトに詳しくない人でも一応できると思うんですけど、Web3コンサルタントっていう観点で言うとどれだけクリプトを知っているかがバリューになると思うんです。クリプトは情報のアップデートも早いですし、どれだけ調べてもわからないこともある。
あと、クリプトの世界は既存のビジネスとは商習慣が異なることも多いんです。
ーどのように異なるのでしょうか?
梅木:例えばゲームやアニメなどコンテンツを持つ企業は自分たちのIPを保有しているじゃないですか。こういう権利は会社の資産として守られているものですけど、クリプトの世界だと権利を放棄する文化もあるんです。
また、マーケティング活動も異なっていて、通常新規プロダクトをリリースする際は、まずプロダクトを発表してからマーケティングをしますが、クリプトの世界だとプロダクトを出す前にマーケティング活動をするのが一般的なんです。
佐藤:クリプトの世界に馴染みがないと意味がわからなくても、クリプト業界ではスタンダードになっていることが多いんです。考え方に結構違いがあって、こうした部分はお客様にもお伝えしたり、コンサルタントとして助言しています。
ー Web3のエッセンスも入れつつ顧客の叶えたいイメージのバランスをとっていくって難しいと思うのですが、理想はWeb3に寄せてくことなんですか?
梅木:理想はやっぱりWeb3の習慣にのっとる方がトークン上場はやりやすいと僕は思います。
佐藤: 良い取引所で上場するという観点で見たら絶対そうなんですが、でもお客様としても曲げられない部分もあるんですよね。お客様の事業ドメイン上譲れないこともあるので、それも取り入れつつ、クリプトのユーザーにも受けるようなものを作っていくという難しさがあります。
ー 知識を知っているだけではなく、Web3世界の感覚が体に染み付いてないと難しい仕事なのではないかと感じました。
梅木:そうだと思います。いかに身銭を切ってクリプトの世界で活動していたのかの違いはありますよね。ちゃんとかかとすり減らしてクリプトストリート歩いてるのかみたいな。やっぱり長く関わっているとクリプトユーザーに受けるか、受けないかは直感的に判断がつくようになります。
佐藤:Web3プロダクトを触っていないとわからない事って結構あるんですよ。そうしないとユーザー視点で考えられないですからね。
ー 田原さんはコンサルタントの腕の見せ所はどこだと思いますか?
田原:三つあると思います。Web3業界は規制や法律が絡みますし、業界の特殊性が非常に高いビジネスなので、Web3の新規事業を支援するコンサルとしては「論点を整理しきる力」がまず大切だと思います。
何が障壁になっているのか、障壁をクリアするためにはいつまでにどんなアクションをしないといけないのか、というところの論点を明確に整理しきることですね。これはWeb3に限らず腕の良いコンサルタントに共通するスキルではあります。
二つ目は顧客が本当にやりたいことを実現させる力。プロジェクトが動き出すと想像していなかったことが起こったり、反対にお客様側のやりたいことがどんどん増えていくこともあります。そんな中、当初想定していた施策がうまくいかなくても代替案を提案することや、コンセプトに沿わないものをやらないようにする取捨選択もコンサルタントの腕の見せ所です。
三つ目はコンサルタントとして当たり前の話ですが、スケジュールをきちんと抑えること。そのためにも論点整理して、それぞれのタスクにどれぐらい時間がかかるかを正しく見積もることが必要です。
コンサルタントがいないリスク
ー 反対にコンサルタントが不在もしくはスキル不足の場合、どんなリスクがあると思いますか?
田原:新規事業の立ち上げでは何かしら障壁はあるものですが、課題にぶつかった時にプロジェクトが進まなくなってしまうリスクがあると思います。
チューリンガムではプロジェクトの途中から支援に入ることも多いのですが、プロジェクトの途中で依頼されるお客様は大体何かにつまずいて先に進めなくなった方です。
Web3の新規事業だと暗号資産を会計上どう計上するのかといった管理体制であったり、暗号資産交換業に当たらないようにすることなど規制の理解が重要ですが、これらは経験が少ない方や専門性が不足していると障壁になりやすいです。
また、壁にぶつかって先に進めない状態が続くと、スケジュールがどんどん遅れていき、結果的に収益タイミングも遅れるし、プロジェクトに参加している人たちの人件費が余分に発生します。
チューリンガムのようなコンサルタントに支援を依頼することはコストではありますが、プロジェクトが進まなくなった時の方が高いコストが発生します。そういう意味では優秀なコンサルタントを最初から巻き込んでおくことは大事なことだと思います。
ー 佐藤さんはどのようなリスクがあると思いますか?
佐藤:コンサルタントの能力はWeb3の専門知識とプロジェクト推進力の2種類に分けられると思っていて、田原さんは推進力の話をされていたので、僕は専門知識側の話をしたいのですが、専門知識が不足すると単純にWeb3のユーザーがついてこないプロダクトができあがってしまうリスクがあるんです。
梅木:プロジェクト自体は進んでも完成したプロダクトを出す時に困ると思います。周りの話を聞くと“Why Blockchain?” みたいなプロダクトになることってまだまだよくあるなと。そうするとやはりWeb3ユーザーに刺さらなくなってしまいます。
ー 例えばブロックチェーンゲームを出す際、ゲームのユーザーは意識して設計しても、クリプトユーザーのことは意識できていない、といった場合はどんなリスクがありますか?
佐藤:元々ゲームを作っている会社がブロックチェーンゲームを新たに作るとします。ゲームには詳しいから既存のゲームユーザーは獲得できてアプリ内課金はあるが、トークンは一向に買わないし暗号資産の取引もしないとします。この場合、課金のおかげで収益はありますが、Web3では流行っていないのでわざわざブロックチェーンゲームにした意味はなくなってしまいます。
一般のゲームユーザーが暗号資産を買うのはハードルが高いですよね。英語で書いてあるサイトで本人確認をしたりしないといけないので。そうするとWeb3で流行らせるにはすでにクリプトを触ったことあるユーザー層も獲得する必要があります。こうしたユーザーを獲得するためにもWeb3への知見が必要なんです。
ー なるほど。先ほど梅木さんが “Why Blockchain?” というのはこういうことをさしていたんですね。
佐藤:専門的な話になりますが、新規のトークンを発行する際は取引所に上場することが必要です。取引所にとって嬉しいユーザーとは、どんなユーザーかというと取引を何回もしてくれる人です。そういったユーザーを連れてきてくれるプロジェクトは取引所から評価されるんですよね。
ー 取引所からの評価は大事なんですか?
佐藤:大事です。そもそも上場するにしても取引所に断られるケースもあります。上場費用が用意できても、取引が見込まれないと思われる場合は断られるんです。
また、取引所には上場廃止基準もあって、例えばデイリーで一定額の取引が30日間連続ないと廃止される、ということもあります。
トークンを触ったことない人にとって取引するハードルは高いので、経験があるユーザーをちゃんと連れてこないとプロジェクト自体がクローズするリスクがあります。
ー 既存のクリプトユーザーに興味を持ってもらうことは大切なんですね。コンサルタントがいる意義がよくわかりました。
その上でチューリンガムのコンサルチームの強みは何ですか?
佐藤:上場企業のように管理体制の水準が高い企業がトークンを発行するスキームを持っているところですね。
田原:チューリンガムは専門性がきちんとあるところが一つ大きいかなと。まずそれなりの規模の新規事業でも、立ち上げて収益化するだけでものすごく大変ですし、担当者の方々は責任もあるので大きなストレスがかかると思うんですけど、チューリンガムは過去何社ものWeb3新規事業を立ち上げて収益化まで導いてきた実績があります。
そのため、担当者の方々の不安なところや大変なことはすでに経験していることが多いので、何か心配事だったり不安なことがあったとしても自信を持って対応することができます。
専門性も経験もあるので、不安で何が正解かわからなくて自信がない方にとっては私たちは非常に心強いんじゃないかなと我ながら思います。
ー 確かに担当者の方の悩みをもう経験しているのは大きいですね。担当者の方とは悩み相談とか深いレベルまでお話しされるんですか。
田原:結構飲みに誘ったりとかしますよ。プロジェクトの責任者も大変なプレッシャーがありますが、僕らは記事には書けない大変なこともたくさん経験してきているので、それも経験ありますよって話をしてます。僕は日本にいる時は週3、4日くらいでお客様とご飯にいってますね。
良いコンサルタントの条件
ー 最後に良いコンサルタントはどんな人だと思いますか?
佐藤:コンサルタントの腕の見せ所と重複しますが、目の前のクライアントとエンドユーザー、2つのクライアントがいるってことを意識して支援できることですね。
梅木:僕は会社員を7、8年経験して起業したキャリアなのですが、仕事ができるかどうかも大切であるものの、結構「エモ」の部分が重要だなと思います。
会社員やってた時はタスクを漏らさずにやることや仕事の精度を高めることに集中していましたが、結局のところ人と人のぶつかり合いなので、明るいとか前向きとかそういうのとかもすごく重要だと感じています。
最終的には人間力というかまたこの人と仕事したいなと思ってもらえるのが大事じゃないですかね。
佐藤:確かにそうだなと思って、コンサルタントは「こんなこともできるので追加で予算をください」といった交渉をします。これってコンサルタントやそのコンサルタントがいる組織にもう一回仕事を依頼したいって思われないと通らないじゃないですか。だからお客様から信頼されることは重要だと思います。
田原:クライアントと同じ目線でプロジェクトを推し進めてくれる人がいいコンサルタントだと思います。反対にいくら専門知識があっても高みからアドバイスするだけの人はいいとは言えない。顧客のことを理解した上で、自分事化して「こうしていきましょう!」と推進できる人がいいコンサルタントですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
