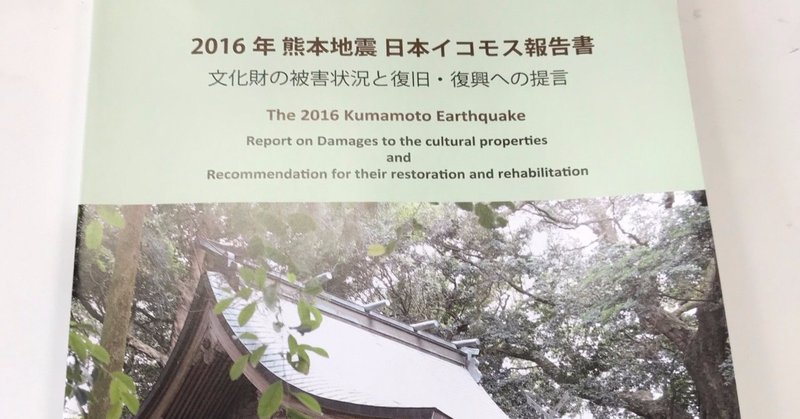
第374回 文化財を我がこととして考える
1、職場にご恵送シリーズ 37
今回ご紹介するのは
2016年 熊本地震 日本イコモス報告書
文化財の被害状況と復旧・復興への提言
イコモスって世界遺産に認定されるかどうかの判定に
大きな影響を与える調査機関ですよね。
その国内委員会という位置づけだそうで、恥かしながらこのような活動をされているとは全く存じませんでした。
この冊子によると熊本地震の災害そのものとその後の復興への努力の情報を調査研究してきた、ということ。そのレポートがこの冊子という位置づけです。
2、記録と記憶
目次
1 地震と被害の概要
2 被害状況と復旧
3 歴史文化遺産の活用とまちづくり
4 復旧に向けた支援制度、支援活動
5 復興に向けた道筋
6 被災文化財の復旧・復興と今後の保存・活用の健全な発展への提言
これをご覧になればおわかりかと思いますが、地震の概要から説き起こして、文化財がどのように被害を受けたか、が豊富な写真とデータで記録されています。
ふと画質が悪い写真があるな、と思うとそれは市民から寄せられた地震発生直後の写真。逆に当時の緊迫感や混乱を伝えてくれています。
そして、単に壊れたものを元どおりに直すだけではなくて、地元の人たちが文化財を再び蘇らせるために知恵を出し合って、試行錯誤している姿が行間から浮かび上がってくるような報告書になっていてとても貴重。
とくに紹介したいのが
3-4 益城町 の部分。
執筆者は松野陽子氏で益城町文化財保護委員会副委員長とのこと。国の役人でも大学の教授でもなくて、地元の歴史に詳しい一市民かとお見受けしました。
益城町は熊本市のベットタウンとして発展した人口三万人ほどの町で、熊本地震の震源地として名が知られるようになってしまいました。
松野氏は地震発生後、わずか二週間後から同じ歴史講座の仲間とともに集落を巡って仏堂が倒壊し雨ざらしになっている仏像を救済したり、転倒した地蔵などの石造物の散逸防止活動を実施したことがさらっと書いてあります。
さらに被災した文化財所有者が集まって悩みや不安を語り合う場も、行政主導ではなく、人の輪を通じて作り上げていったのは非常に画期的です。
益城町には専門職員が一人しかいない、他の業務に忙殺されている、その状況を目の当たりにして彼女ら文化財保護委員を中心に「益城の歴史遺産を守る会」を発足させたとのこと。解体される家から史料を救済しようと町の広報やチラシを配布する活動をしています。
公的な「文化財レスキュー」が始まる前からの活動ということで、東日本大震災直後になにもできなかった我が身を振り返ると正直感服してしまいます。
そして、自ら画期的な事例と記していますが、倒壊した神社の復興のため、災害後に文化財指定を行って公的支援を投入するという形がとられています。
通常は修理が完了した段階で、文化財の価値が十分把握されて初めて指定に、という流れですが、ある意味逆転の発想です。
古民家についても応急危険度判定と公費解体制度によって解体が進められていくなかで、所有者に丁寧に話を聞くと、申し込み期限に迫られて解体を決めようとしていたものの、本音では迷っているという例がいくつもあることを発見しています。
これは次の
3―6 西原村 の事例 執筆者 小谷桂太郎 前 村文化財保護委員
でも同様です。
西原村でも「自主解体」という、本来は公費解体の制度が整うまでの応急対応だったものを行う中で、所有者が思い入れの強い梁や柱などの部材を守ることができたことを紹介しています。
また、役場の公費解体担当課との連携を行ったおかげで、情報が共有され、基金制度を使って修理費用が援助されることを知り、解体申請を取りやめるなどの事例もあったことが報告されています。
3、文化財を守るのに一番大切なこと
いかがだったでしょうか。
具体的な内容をご紹介できたのはほんの一部ですが、この記録は必ずや後世に有益なものとなっていくことだろう、と思えるものでした。
それに比べて東日本大震災のことを思うと忸怩たる気持ちになります。
被害がより広域だったことや、揺れだけでなく津波被害があったこと、いまだ復興途上であることを考慮しても
もっとやれることがあったのではないかと後悔しきり。
話はすこしずれますが先のGW中にあわや国の重文が被害を受けそうになった火災の報道がありました。
記事によると、仏像などは近所の人たちの協力で運び出され、無事だったとのこと。
古民家を解体するときに文化財部局に連絡が来るかどうかも
火急の時に一体となって文化財を守ってくれるかどうかも
やはり普段から信頼関係を構築できているかどうかが鍵ですよね。
前項で紹介した事例はどちらも学識経験者だったかもしれませんが、行政でも大学でもない、一地域住民が自ら行動して文化財を守っています。
この精神に感銘を受けたので、ぜひ皆さんにもシェアしたくなりました。
ぜひご感想、ご意見をお寄せください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
