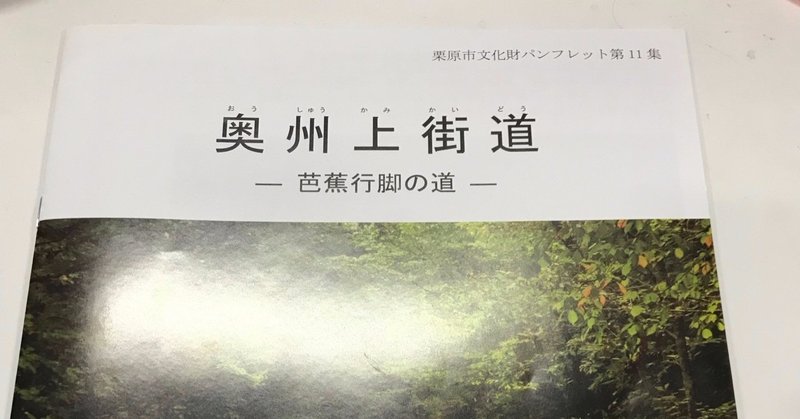
第396回 古道を保存する
1、職場にご恵送シリーズ 38
栗原市文化財パンフレット第11集
奥州上街道―芭蕉行脚の道―
国の史跡に指定されている陸奥上街道(かみかいどう)は、奥州街道一関(岩手県一関市)から栗駒(宮城県栗原郡栗駒町)、真坂(同郡一迫町)を通って岩出山(玉造郡岩出山町)に出て、出羽街道に至る道です。
この名称の初出は安永2年(1773)の『風土記御用書出』で、
古くは「松山道」と称されており、『陸奥話記』、『吾妻鏡』に使われているのが確認できます。
『陸奥話記』は平安時代に成立したとされる軍記物で、前九年の役を描いたものです。
『吾妻鏡』はいわずと知れた鎌倉幕府の公式記録。
文治5年(1189)8月21日条には、
「爰2品経松山道、到津久毛橋給」と記されているようで、
源頼朝の軍勢が奥州藤原氏を討伐するため、多賀城の国府を出て玉造郡
に向かい、奥州藤原氏の拠点であった城を攻める場面です。
藤原泰衡はすでに逃げており、頼朝は玉造郡より葛岡郡に出て、松山道を経て平泉に向かったのという文脈で登場します。
ちなみにここに出てくる「津久毛橋」は松尾芭蕉に同道した曽良の日記にもみえ、中江川(栗原郡金成町)にかかる橋だそうです。
そう、この道はかの俳聖、松尾芭蕉が通った道なのです。
(おくのほそ道には記述ないけど)
2、史跡と名勝
先述のとおり曽良日記の記載を信じれば、芭蕉は平泉で引き返して山形方面に向かうために本街道を通ったことになります。
国の史跡になっているのは大崎市岩出山周辺の2.8kmで、「天王寺一里塚」は道の両側に一里塚が残っているのは希少な例です。
さらに千本松長根と呼ばれる1500mの長さで松並木が続いているところがあ
るなどよく往時の景観を残しています。
一方で松尾芭蕉が立ち寄った歌枕の地の多くは2014年に国の名勝「おくのほそ道の風景地」に指定され、その後も追加指定を繰り返して11県24カ所に広がっています。
名勝地が所在する自治体は連携して普及活用事業に取り組んでおり、終着地点である大垣市を中心にスタンプラリーなどを展開しているようです。
史跡にしても名勝にしても国から指定されたことをブランド力に変えてPRしてこうというところでしょうか。
3、デジタル公開の必要性
さて、栗原市では国指定の名勝や史跡には指定されていませんが、旧道の雰囲気を残す場所があったり、今は失われてしまった場所と古写真を比較してみたりと、工夫を凝らしたパンフレットとなっています。
ですが、市のHPでもデータで公開されているかと思って探してみましたが見つけられませんでした。
パンフレットやマップガイドこそネットでダウンロードできないともったいないですよね。
まあまだ刊行されたばかりですので、今後に期待ということかも知れません。
いやシリーズ第11集ということはすでに10種類作られているんですよね。
ますます解せない。
私が見つけられないだけだったら申し訳ありません。
お役所仕事ですから、紙で関係者に配る分は作らないといけませんし、
保管・保存という意味合いではまだ紙ベースの必要性が高いので
紙のパンフレット需要はありますが、普及という意味では公開してなんぼの世界でしょう。
ぜひこちらのサイトで公開して欲しいところです。
ちなみに全くの余談ですが、
わが町は「おくのほそ道風景地」には指定されていません。
これにはいろいろ事情があるのですが、当時文化庁からはお叱りに近いことを言われたことを思い出しました。
みなさんは「おくのほそ道」好きですか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
