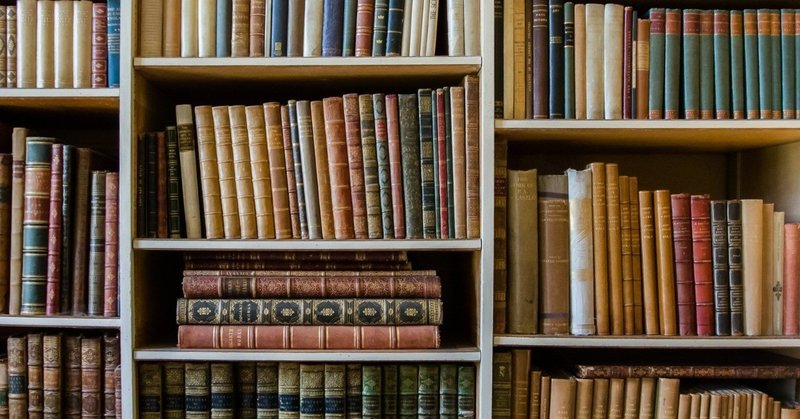
「格差」を認識できているか。
おはようございます。今日も本の紹介です。こちら!
「教育格差」読了。2019年から引き継いで年またいでようやく。
— つっち~🌪️私立小の先生📮📚️ (@tuchiblanka) January 3, 2020
前半戦は淡々と、驚くほど淡々とデータ&データ&データ&データ。(正直心折れそうになった笑)
終盤にきてこれからの展望や、考えるべき視点などが述べられていてとても参考になった。また、noteにでも少しまとめようかな。 pic.twitter.com/8Z56ovHH0z
いやー重い!とにかく著者が集めたデータによる様々な視点からの格差が前半・・・いや、全ページの3分の2を占めているので、途中何度やめようと思ったか。笑 しかし、読み進めていくと、データ部分は要約をきちんと押さえていけば良いと気づき、ざっと読み進めることができました。
突き刺さる後半部分
この本の肝は圧倒的なデータ量はもちろん、そのデータから「じゃあこれからどうするよ?」をきちんと語ってくれていること。昨今の教育問題は簡単に因果関係を見いだせるものではなく、一個人が簡単に解決できるものでもない。ただ、そこで諦めたくないよなぁ・・・ってがんばってる先生がいて、それはそれでとても素晴らしいんだけど、その中でそれぞれの思想や実践をもとに主張が生まれ(誰もが実体験をもっているので、自説をもちやすいし)、時に対立したり、カルト的になったり(あえてこの言葉で)。また議論をしても「まぁ、それぞれで課題が違うもんね」的な感じでぼんやりまとめが行われ、結局目の前は何も変わってない なんてことになってやしないかな?と悩んでいたところに、著者は「建設的な議論の4ヵ条」を挙げてくれています。(以下の見出しは本からの引用)
①価値・目標・機能の自覚化
「何に価値を置き、どのような目標を設定し、それがどのように機能するかについて自覚的であるべきで、自分の実践の「正しさ」に酔ってはいけない。(過剰な偏りは危険ということかな?)」→お互いが自分の立場に自覚的でそれぞれのメリット・デメリットがきちんとわかっていれば、議論を通してどちらの良いところも生かすようなより多くの子ども達を救うようなアイデアが生まれるのだろうなと思います。
②「同じ扱い」だけでは格差を縮小できない現実
「『扱いの平等』には限界がある。」→小学校入学時に確かに「格差」はあるということを考えれば「皆一緒に」だけでは押し切れないのは当然だろうな・・・。
③教育制度の選抜機能
「現行の教育システムは、多くの人間の職業的な地位や所得、財の配分を決定する『競争』が『教育』を通して行われていて、教育が社会的選抜の担い手となっている。」→この事実を忘れてはいけないですね。
④データを用いて現状と向き合う
「分析可能なデータの継続的収集・効果測定による実践の漸次的改善を通して、一人でも多くの子どもの可能性を最大限に開花させよう。」→この本に言われると重みが違う。本当に意味のある調査と、継続的な改善、見つめ続ける目が大事!。
終わりに
とりあえず自分なりに要約してみたけど、それでもかなり時間がかかってしまった・・・。4ヵ条挙げてみたものの、いざ要約し、内容を振り返ってみると①が一番目の前に広がる課題の解決に繋がると思います。自分のポジション、取り組み、思想に対する「自覚」と対話をしようとする「姿勢」を大事に、3学期に向かいたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
