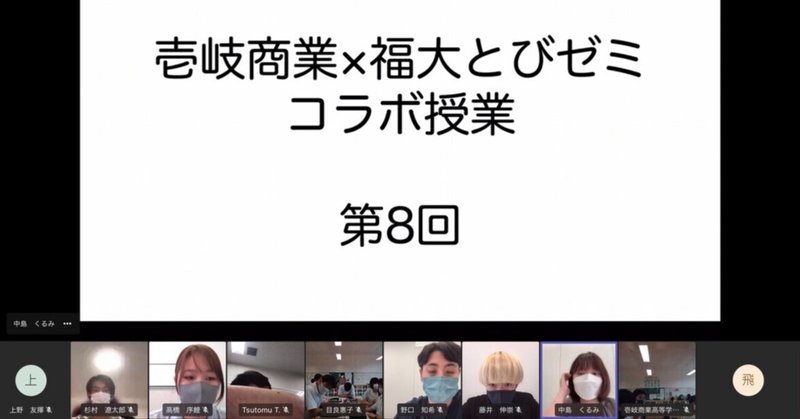
他者が見た壱岐の姿から異なる視点を導入する|2022壱岐商業高校×とびゼミコラボ授業⑩
今日は夏至。6月もあっという間に21日になりました。今日は壱岐商業高校3年生10人へのアントレプレナーシップ教育の授業日。これまでの「知識のインプット中心」から「8月末の出店に向けた準備」にフェーズが変わった。
ただ,出店するにしても単純に外から島に商材を持っていっても面白くはない。今回のイベントに来場する顧客を誰に定めるのか,その人は何を求めてくるのか,壱岐だからできること,高校生だからできること,自分たちだからできることは何かを言葉にしておきたい。
そこにはストーリーが必要だ。そのストーリーを高校生が作ることに意味がある。そこで,今回の授業はそのストーリーを作るために壱岐らしさとは何かを考えてもらうためのワークを仕掛けることに。果たしてどんなワークになるのでしょうか。
これまでの授業は以下のマガジンをご参照ください。
いや,学生頑張った。よくできました。
1コマ目:壱岐で「働く」人たちの目線から壱岐の魅力を知る
まず1コマ目。今回は壱岐に暮らす100人にインタビューをした「壱州人辞典」をもとに,移住して壱岐で事業を始められた方5人をピックアップし,高校生には事前課題に取り組むように指示。では,どんな5人なのか。それぞれ個性的で壱岐という舞台でご活躍の起業家のみなさん。

「壱州人辞典」は壱岐市が作成した移住支援サイトにある特集で,このダイジェスト版が冊子になって配布されている。島内でも人気の冊子だそうで,置いておくとすぐに無くなるらしい。こちらのネット記事の方が詳しい記事になっているので,興味がある方はぜひご一読ください。
今回ここから取り上げたのは以下の5名の方。
1人目は芦辺にあるゲストハウス「みなとやゲストハウス」を営む大川さん。漁師と海女の夫婦が営む(尖った)宿を経営され,築100年以上の古民家(元遊郭)を改修してゲストハウスにされたそう。高校生からすれば,存在は知ってるあるいは聞いたことがあるけど,どんな人が経営しているのかは知らなかったのではなかろうか。

2人目は地域おこし協力隊であり,わたしたちの活動でも大変お世話になっている合田さん。壱岐に行った際には本当に温かく迎えてくださり,こちらの無茶苦茶なオーダーにも応えて下さる。とにかくいつも明るい合田さん。

3人目は芦辺でチリトリ自由食堂を営む小野さん。先日,壱岐に行った時,ランチに伺ったのがこのお店。当日伺ったときも平日であるにも関わらずほぼ満席で,ひっきりなしにお客さんが来られていた。それも壱岐の地元の人だけでなく,壱岐に観光に来た人がわざわざ目当てに来るような印象。そのバックグラウンドを聞けば「うまいのがアタリマエ」ともなってしまう。うん。

4人目はイチノ珈琲焙煎所のオーナーである草野さん。いつか訪れたいとは思いつつも,なかなかタイミングが合わず。ただ,一度はコーヒーを飲んでみたいということで,福岡から取り寄せで豆を購入。今の我が家の豆はこちらで焙煎されたルワンダとエチオピア。妻氏お気に入りのルワンダですが,妻氏もうまいとご満悦。

そして,最後は今回の出店でもご協力頂くパンプラスの大久保さん。元々は福岡県春日市の出身ですが,お祖父様の地元が壱岐。いわゆる「孫ターン」で壱岐に戻り創業したのがパンプラス。壱岐島内だけでなく,福岡県那珂川市や京都市にも店舗を持ち,壱岐牛カレーパンでも著名になったお店。

それぞれ個性的で壱岐で活躍されている方々ばかり。恐らく高校生にとって「働く人」は両親,親戚と学校の先生くらいしかいない。自営業であれば別だが,通常は多くの高校生にとって働くをイメージするのは難しい。このプログラムの目的の1つには,高校生がこの講義での学びと実践を通じ,自分自身で付加価値を創造する,そのために働くということを意識できるようになることがある。そして,それが地域での暮らしと結びついている,結果的に地域で暮らすということにつながっていくことを期待している。
そういう意味では,この「壱州人辞典」は強力な教材となりうる。壱岐市役所,Good Jobです。けど,高校生はこうした冊子の存在を知らなかったそうで,今回の授業を通じて自分たちの島にはさまざまな働き方をしている人がいるんだと知って興味を持てるようになると授業目的が達成できたと言えよう。
が,1コマ目のワーク。記事を読んで何が書いてあるかはまとめられるが,ここから何を議論して良いのかがわからない。ディスカッションをリードする学生が焦っていろいろと投げかける。しかし,反応が薄い。焦る。この時に焦ってはいけない。高校生が気づくのを待つか,うまく補助線を引いてあげる必要がある。この補助線が引けるようになると授業が狙い通りにスムーズに進むようになるが,まだそこまでには至らない。これが一方向的な知識伝達型授業とコミュニケーションを通じた創発的な学習を目指すプロジェクト型授業の違いである。
かくして私も同席していたグループではモヤモヤを残しながら1コマ目終了。
2コマ目|自分目線と他人目線をすり合わせて気づきを得る
10分の休憩後,2コマ目に入るのだが,その前に学生にアドバイス。
調べることはできる。が,それをジブンゴトにつなげて考えるところまでは至らない。だから,他者の視点を導入して,自分では気づかないことを他者の言葉で認識できるかどうかってとても重要。何に気づいて欲しいかを答えを与える形ではなく,答えにたどり着けるような問いの投げかけ方を工夫した方がいい。それと,我慢して喋らないことも重要。
このアドバイスをもとに高校生の気付きが掘り出せたのが2コマ目の展開。ちょっと水を向けるといきなり高校生の気付きが爆発する。

2コマ目は「壱岐らしさ」という曖昧な言葉をより明確にするためのワーク。
ここでの狙いは,前の時間に調べた5人のロールモデルが壱岐の魅力をどう語っているのかをもとに「壱岐らしさ」を言語化すること。そして,ロールモデルという他者が語る視点を通じて,高校生自身が考えていた「壱岐らしさ」との比較ができるようになること。他者の視点を導入することで,自分の力で自分の奥底にあった気づきを言語化することが狙いとしてある。
1コマ目は何から話せば良いのか,どう表現してよかったのかがわからなかった高校生たちも,大学生からの投げかけに要領を得ていく。5人それぞれが語る壱岐の魅力を学生が作成したワークシートに落とし込む。人,食,自然,ワークライフバランスという4コマに。そうすると高校生にとっていつも見ていてアタリマエの景色が,外から来た人にとっては価値があるものだということに気づき始める。

どうしても島となると自然にばかり目が行く。また,食は彼・彼女らにとって常にそこにあるもの。では,それが魅力なのかと問われれば,恐らく本質的な部分では疑問に思っていたのだろう。いつの間にか,それを魅力と語らずに当たり前のモノしかない島と思い込んでいたのかもしれない。
そうしたところに改めて他者の視点が入ることで,実は自分の見ている景色は他者にとって貴重なものだったと気づく。また,そこからロールモデルとしての大人たちは人との交わりや働き方,都市にはない価値を見出していて,高校生の視点からは見えていない視点がようやく見えるようになったようだ。

そうなると「何もない」は余白、余裕となり、価値の転換が起きる。同様に、自分たちにとって何気ない食事が当該の人には特別なものに見える。自然の恵みを受けて自分たちが生活できていることはかけがえのないことなのだと気づけたようだ。
そうしてできあがったまとめが上の2枚。まだまだ掘り出したら何か出てきそうだったけれども、今回はここで時間切れ。高校生も大学生もよく頑張って成果も出たワークになった。素晴らしい。
これまでの授業内容との接合
そうこうして授業は終わり、最後の〆。
高校生からすれば、何を改めて「壱岐らしさ」を議論してきたのか疑問だったろう。それもこれも8月末の出店に向けたコンセプトづくりのため。具体的な話に進む前に、今一度自分たちが寄って立つ価値観をしっかり言語化しておこうと。

企業で言えば経営理念に相当するものを改めて考えたのが今日のワークだと種明かし。これまでは高校生の視点で、彼・彼女たちが見えている範囲で壱岐をどうしたいのかを議論してきた。しかし、それだけでは物足りない。

だから、判断軸を作ることが必要になる。自分たちの活動の意義は何なのか。それを言葉にしておく。そう意味を創るのだ。自分たちの活動の意味を。
勝本浦という壱岐島内の人々にとって最も馴染みがない場所(港がある郷ノ浦や石田、イオンがある芦辺に比して勝本浦は遠く感じるらしい)でイベントを開催するのに、顧客に来てもらうためにどんな意味を設計するか。SPINNS来ますよ、カフェやりますよだけではない、大学生と高校生にとっての理由がいる。

ここに来て、ようやく大学生と高校生が学び合うプロセスの中で「壱岐らしさ」を表現できる段階に至った。まだ改善の余地はあるけれども、いい線まで来ている。あとはこれをもう少し突き詰めて、顧客像を定めて、持つ経営資源をどういう角度でぶつけることでワクワクする場を創造できるか。
理念を戦略、計画に落とし込むプロセスへ。そしていよいよご協力頂く方々とのコラボレーションの準備へ。何をするのかよくわかっていなかったであろう高校生を商売という実践に導く準備が進んでいるという実感が得られた時間になった。
ふりかえりと雑感|答えは自分(高校生・大学生)が持っている
さて、授業終了後のふりかえり。
冒頭は別件でミーティングをしたため、OBと学生たちだけでのふりかえり。何を話していたかまではわからないが、前向きな議論ができたのではないか。次の手をどう打つか。思案のしどころ。
私からコメントしたことはわずかだったけれども,昨日の飯塚高校での授業がそうであったように,あまり大学生が高校生を急かして,彼・彼女たちに考える時間を与えないのは宜しくない。考える時間を作らなければ,答えを出すことばかりに思考が向いてしまう。
見えていなくても,答えは高校生が持っている。
このスタンスを守りつつ,高校生が持っているであろう気づきを言葉にできると効果的なサポートができるようになる。そうすると授業の質はもっと向上するだろう(今でも十分頑張ってくれてる)。
授業のフェーズが知識伝達から高校生の力量に依存するプロジェクト型に移行したことで、学生のファシリテーション能力であったり,声なき声を聞く力が問われるようになってきた。適切なサポートをするには単に知識を詰め込んでおけば良いわけではない。自分の持つ仮説を意識しながら,彼・彼女たちにどんな気づきを得てもらいたいのか。どう言葉にしたら良いのか。こちらの学びの質が上がるにつれて、高校生の学びの質が高まる。まさに共創関係の構築。これができるようになると,レベルがまた一段と上がる。
期末試験を来週に控えているため,6月に提供する授業は今日でおしまい。明後日は壱岐市役所の担当者による授業が行われるが,そこにはパンプラスの大久保さんと今回のイベントを開催する勝本浦まちづくり協議会から担当者のSさんが来られる。いよいよ出店に向けた具体的な活動が始まる。
そこで学生に伝えたのは次のこと。
恐らく社会人,特に日々顧客を見て商売をしている人からすれば勝ち筋(顧客が商品・サービスを購入している状況の創出)を作ってしまうだろう。だけれども,そこをグッと堪えて,高校生自身に考えてもらう機会をどう創るかが重要。理念らしきものと実際の店舗運営の距離は遠そうに見えるけど,理念が固まれば実は早い。ここで彼・彼女たちが自分の力で考えたという実感を持てるように導くことができれば,あとは自走する。1学期の授業回数は限られているが,焦らず騒がずいこう。ただ,1つ1つの機会をつなぎ合わせていくことは求められるだろうから,木曜日の授業と再来週の火曜日の授業をつなぐ課題を作ろう。
そういう投げかけをしたら,遅くまで残って作業を続けてくれている学生から次の記事が送られてきた。
どちらもパンプラスの大久保さんを取り上げた記事。よく見つけてきた。素晴らしい。この記事を高校生に示して,木曜日の授業に向けて少しでも情報を入れて,整理して,興味を持って話を聞けるようにする仕掛け作りをしようとしている。リーダーが主体的に高校生の学びをより深いものにするために試行錯誤をしている。ありがたや。
答えは誰かに与えられるものではなく,自分で創造するもの。
昨日の記事で示したように,このプログラムには大学生が"Learning by Teaching"によって学ぶという狙いも含まれている。その先には自走して学び,価値を創造できる人になって欲しいという願いもある。毎週の授業,しかも複数の学校でプロジェクトを動かしていくには相当の負担がかかっているだろうが,日々の成長を見ていると若い人の持っている力,可能性が眩しく見える。
いや,良い授業だった。大学生の皆さん,お疲れさまでした。まだあと少しあるので頑張っていきましょう。
そして,明日は日田へ。日田三隈高校で2022年度始めての授業が始まる。さあ,どうなるか。また新しい旅が始まる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
