
どんな記事/文章を書いたらいいかわからない時のヒント
こんにちは、伝わるNOTE編集長です。
今回は文章を書く全ての人が経験しているであろう悩み、「どんな記事を書いたらよいかわからない」「どんな内容なら読んでもらえるだろう」といった、記事や文章を書き始める前の悩みについて、私なりのヒントをお伝えできればと思います。
書く「目的」を考える

まずはその記事/文章を書くことで、何を達成したいかを考えてみましょう。ラブレターなら「私のことを好きと思ってもらいたい/私の想いを感じてほしい」だし、仕事のメールや文章なら「お客さまに大切なことをお知らせしたい/上司に私の忙しさを知って欲しい/チームメンバーに共通した課題を認識して欲しい」といったようなことがあります。
目的をはっきり言語化して認識することで、伝えるべきテーマの順番も自然と見えて来ますし、必要な文章のパーツやデータなどが明確になります。
一方で、目的が上記のように達成したいことがはっきりしていないケースもあると思います。そんな時は、読み終わった後に読者に「どんな気持ちでいてほしいか」、「どんな行動をとってほしいか」を考えると、少し書くべきことが見えてくると思います。
たとえば、「自分のコラムを読んだ後に、子どもへの注意の仕方について振り返ってほしい」という想いがあるならば、子どもへの注意が将来に及ぼす影響/子どもの脳の発達の仕方/親子関係に関する格言/今日からできる3分親子コミュニケーション・・・といったように盛り込むべきパーツや見出しが案として思い浮かんだりします。ゴールや読後感がわかれば、選択肢となる道が自ずといくつかに絞れてくるのです。登るべき山がわからないと道も見えませんので、ぜひ最終的なゴールをまずは探す/見つけるところから始めてみましょう!
自分の身の回りのことを書き並べる

特に目的などは明確ではないケースもあります。たとえば、日記やコラム、編集後記のような自由に書きたいことを書いてよい時などです。こういうときは本当に何を書いても良いと思うのですが、「そうは言ってもわからん!」という声も聞こえて来ます笑。
そんなときは、1週間以内にあった出来事や考えたことを、思いついた順にまずは書き殴ってみましょう!たとえば今の私なら、
・会社の同僚と1on1で話してみたら褒められた
・レストランで周りの人がみんな同じ飲み物を頼んでいて面白かった
・車を洗えた
・家族の健康について深く考える機会があった
・お昼のカレーが美味しかった
・4歳の子どもがなかなか言うことを聞いてくれなかった
なんてメモしてみます。
シンプルにその中の1つを深掘りするのもOKですし、可能ならその中で2つ3つの出来事の共通点を見つけて、その共通点について書くのも面白いかもしれません。一見バラバラにみえる上記のメモも、たとえばこんなふうに「聞く」ということで繋げることができます。
・家族の健康について深く考える機会があった
・健康という当たり前が崩れる瞬間は突然訪れる
・そんなときはまずは聞く姿勢が大事
・どんなことが必要か、いま心配なことはないか、最近のストレスなど
・「聞く」ことから始めるのは子育ても一緒
・子どもがいま何をしたいか、何が欲しいか、を聞いてから、親のして欲しいことを伝えないと、気持ちの押し付けになってしまう
・仕事ではきちんと「聞く」ことができはじめた
・チームメンバーに今の自分や理想の自分などについて聞いたら、お互いの気持ちや将来への道筋が見えた
という具合に。慣れれば5分もあればパパっとできるようになりますので、ぜひお試しあれ。
「カリモク」を書き並べる

実際にメディア運営をする中でも使っているテクニックとしては、「カリモク」を書く、という方法があります。カリモクとは、「仮の目次」のこと。
「読みたいことを書けばいい」という田中泰延さんの著書タイトルではないですが、あなたが知りたい、読みたいと思えるタイトルは、同じように感じる人が多い可能性が高いです。
たとえばです、いま考えている私の記事カリモクの一部を並べるとこんな感じです(書くかどうかはわかりません笑)。
妻/夫を3分でやる気にさせる方法
仕事メールはすべて「ラブレター」
部下のことを「わかったつもり」になっていませんか
こうして仮でもいいからまず読みたい/クリックしたいと自分が思えるタイトルを並べることで、「あ、こんなこと伝えられるな」「先日のあのエピソード使えそう」「こないだ読んだあの本のネタも引用したらいいかも」というように、自分の経験や覚えている点と点が少しずつ繋がることがあります。少しでも繋がったら、もうこちらのもの。あとはどんどん書いていきましょう!
なお、最初のタイトルはあくまでも仮なので、全体の文章が書き終わったあとは改めて見直してみて、修正するとよりブラッシュアップ(洗練)されたタイトルになるのでおすすめです。
自分が得意なことを書く
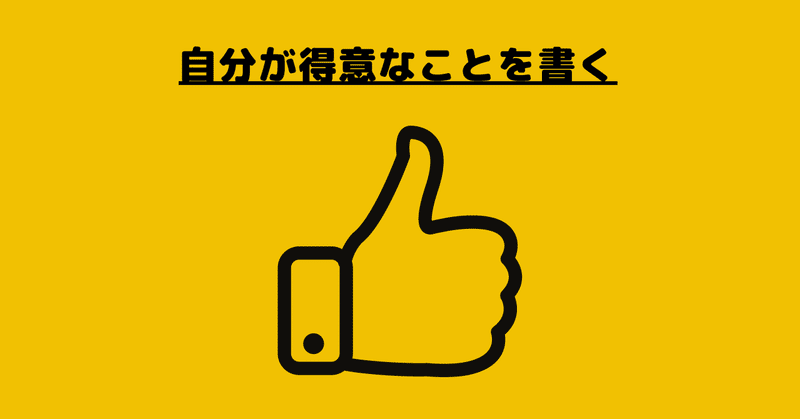
記事やコラムといったものは、あくまでも書き手のあなたが主体となって書き始めることが理想です。中には仕事上、どうしても自分の専門外のことを書かざるを得ない時もあると思いますが、相手のニーズに無理やり合わせても良い文章は書けません。
なので、常に私も自分が得意なことを中心に書くようにしています。読者としても、あなたの得意なことや貴重な経験、想いを読みたいのです。カリモクなどを並べてみても、得意じゃないことは選ばないようにするのが吉です。未経験の分野だと、書いているうちにだんだん苦しくなり、薄っぺらいないようになりがちです。
自分の心が動いたことを書く

最初の目的でも書きましたが、読者の読んだ後の気持ちをイメージすることは、文章を書く上でとても大切です。もし、少しでも読者に読後、行動してほしい、心を動かして欲しい、と願うならば、自分が感動したこと、泣いたこと、感心したこと、笑ったことを書きましょう。
自分の心が大きく動いた瞬間をうまく文章に載せることができれば、読み手の心にまでズゥンと響くはずです。うまく自分の体験を追体験することができれば、おそらくそれを読んだ人も同じ心情になるはず。どんな文章も、どんな短いことばも、あなたから読んでくれる人へのラブレターだと思って書いてみてください。
「問い」を並べる

テーマがある程度決まっている場合でもなかなか筆が進まない時があります。そういう時は、書きたいテーマに関する「問い」をたくさん並べるのも有効です。
そのテーマの背景はなにか、誰が発言しているか、なにが問題か、みんなは何が知りたいか、自分は本当にそのテーマが話したいのか、どんなデータがあるか、、、問いを並べることで、そのアンサー(答え)が読者に伝えるべき内容だったりします。
たとえば、「老後2000万円問題」について関心があって自分が書きたいと思ったときは、
・そもそも老後とはどういう状態か
・2000万円という数字はどういう根拠か
・なぜ自分が関心をもったか、きっかけや身近なことは
・なにが問題なのか
・解決の手段はどんなものがあるのか
といった感じです。
どんなテーマにも使える手法ですので、試してみてくださいね。
この記事を書いていて、同じようなことを書いている人がいないかnoteを散策していたら、こんな記事を見つけました。
小学生が「書く喜び、伝わる喜び」を経験することはとても大切ですし、貴重な体験ですね。受験とかで記憶や公式を覚えるのも大切かもしれませんが、子どもにはまず「書く喜び、伝わる喜び」をどうやったら伝えられるかを考えていきたいと思っています。
よければ是非フォローをお願いします。
それでは、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
