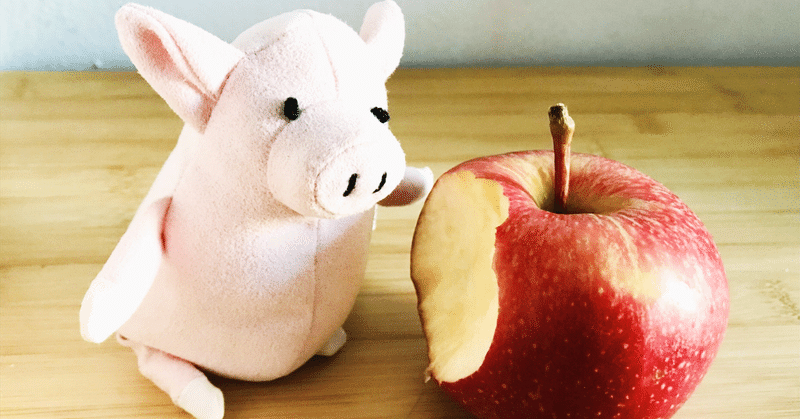
消費される教育
今月(3月)は担任していた3年生を卒業させたばかり。
中学校の教員になって今年で10年目。
途中で約6ヶ月間の産休・育休を挟んで,3年生を受け持つのはこれで6回目。
教員人生の半分は3年生を持っていることになる。そのうち自分が担任として生徒を送り出すのは2回目。
当然ながら,副担任として迎える卒業式以上に担任としての卒業式には特別なものがある。
1回目の卒業式は,最後に生徒が歌う「旅立ちの日に」の合唱あたりから涙が止まらず,ハンカチで顔を抑えながら半ば嗚咽する勢いで生徒と一緒に体育館を退場した。
そして2回目の今回がどうだったかというと,
自分でも驚くほど冷静で,多少ジーンとする場面はあれど,1回目の時のように感極まることもなく終わった。
式後は,時間が経つにつれて猛烈な虚無感と疲労感に襲われ始め,この先も卒業式の度にこんな感覚になるならこの仕事を続けていけないかもしれない…
と思うほどの未だかつてないメンタル不調。
そしてなぜそんな気持ちになるのかと原因を考えた結果,たどり着いた結論は「自分が真心込めて向き合ってきた相手から消費されることに疲弊した」ということだった。
今年受け持ったクラスは,進級した4月当初から男女関係なく仲が良く,それまで不登校で全く学校に来られていなかった生徒も途中から教室に入れるようになるほどに雰囲気が良かった。
担任の私も,職員室にいるよりも教室で生徒たちとたわいもない話をしている時が最高に楽しくて,仕事の疲れを癒してもらえるそんなクラスだった。
だから生徒には別れ際に
「教員生活10年目で,まるでご褒美をもらったかのような1年間だった」
と伝えた。
学活終了後には,保護者からもお手紙やプレゼントと共に,たくさんの感謝の言葉を頂戴し,どこからどう見たって「パーフェクトな」卒業式が終わったのである。
こうやって書くと,どこに「消費された」感があるのかはとても分かりにくいかもしれない。
私もこの一連の思考を完全に言語化することに難しさを感じているのだが,
一例を挙げるならば,保護者や生徒からもらった感謝の言葉がとにかく具体的だった,ということ。
「先生のご指導のおかげで〇〇高校に合格できました」
「先生のおかげで1年間楽しくて過ごしやすいクラスだったと思います」
「このクラスは間違いなく他のクラスに比べて当たりでした」
「多分,先生たちの中で一番人気ありますよ,先生!」
書いているだけでもしんどい…
何がしんどいかって,
担任がどの程度我が子に利益(メリット)をもたらすのか,それをもって教員としての価値づけをすることは完全な消費者の思考だ。
今や学校教育はサービス業と化し,劣化の一途をたどっていると個人的には思っているが,
自分自身が心を込めてやってきたことさえも,やっぱり消費されていたんだ,と改めて気付かされたことが悲しくもあり,虚しかった。
教育における生徒と教師の関係の本質は,
生徒が目の前の教員から生き方や生きるために必要な力を学び取ることにあると思う。
教員から教えてもらった知識の量なんかよりも,その後の長い人生の中でふとした時,
かつて教わった教員の「人となり」が思い出され,良くも悪くも
「あぁ,あの先生はこんな時どんなことを考えるんだろうか」
と子どもに思い出してもらえたらそれこそ教師冥利に尽きる。
だから,人間としては多少難がある教員からだって学ぶことはあるはずなのだ。
でも今の教育現場はまるで学習塾よろしく,保護者も生徒も教員も,その教員の存在によってどれほど本人の能力が向上したか,本人が楽しく思い通りの学校生活が送れたか,そういった具体的な教員の「貢献度」が重要視される。
当然,こういうお褒めの言葉を保護者からもらうことが教員として最高の誉である,と思っている教員の方が多いので,
自らそういう「具体的な」価値を提供しようとする教員によって学校教育はより一層サービス業化していくという側面もある。
私が考える本来あるべき卒業式とは,
共に子育てをしてきた親と教員が成長した我が子の姿に涙しつつお互いを労い合う日。
もちろんそこに具体的な思い出やエピソードがあるからこそ感動がある。
でも,それは決して「先生が教えてくれたおかげでうちの子の偏差値が上がりました!」とか,「他にハズレの先生もいる中で,一番マシな先生に担任してもらえたから1年間楽しく過ごせました」なんてそういうことでは決してないはず。
新年度の目標は,消費されない教育,教員になること。持続可能な教育を目指して。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
