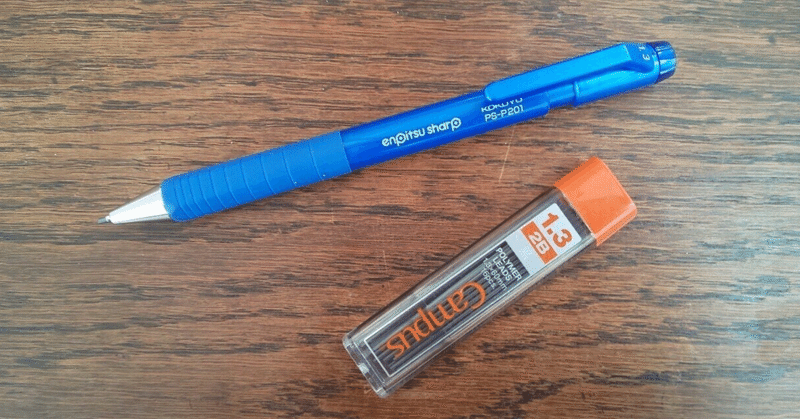
【中学受験】小6前半の、親の役割(スケジュール管理)
イライラしない中学受験のための親の役割
勉強にまつわる親子関係はついついお互いにイライラしがちです。
イライラしてもいいことはないとわかっているけれど、どうしてもしてしまう。
イライラがデフォルトだとして、なるべくそれを減らすのが、整理と仕組み化や、アンガーマネジメントです(アンガーマネジメントについてはまた後日)。
とにかくスケジュール管理(小6の前半 模試編)
さて、1年前のこの時期は、子どもはもちろん勉強していた(と思う)のですが、親の方は、複数社の模試の年間計画を並べて、申し込み日時を確認し、スケジューリングしていました。
模試にも特徴があるし、消化不良になってもいけないので、どこの模試をいつ受けるか、というのは塾と相談していました(所属する大手塾のパッケージのみで完結する、というのも一つの選択肢です)。
でも、試験会場は各家庭で選ぶので、人気の会場は早く申し込まないと埋まってしまうことも・・・
男女で申し込み日時が違うこともありますし、うっかりして受けられないということがないよう、試験の日時場所や、先だっての申込の日時のスケジューリング(申込開始日は平日が多い…)は、当時一番の関心事、重大任務でした。
中学校が会場になるときは、学校の説明会も同時に行うことが多いので、そちらを活用することもありました。
あと、テスト主催者からの「保護者会(という名の説明会)」があるときは、特にそのテスト結果を志望校を組むのにどう使うか、などのお話はその時期ならではのトピックなので、特に秋以降は、なるべく私は会場で時間を過ごしていた記憶があります。
読書やパソコンのお仕事をされている保護者さんもいました。
模試の日は朝からいないので、きょうだいの当日の過ごし方の家庭内調整や、特に下の子と別の日に一緒に楽しく過ごしてあげるプランもおいおい考えることになります。
模試会場は、受験生の上履きは必要ないところが多いのですが、油断していると、上履き必須の学校もあり、着いてから知って「親;えー、上履きいるの?なんで気付かないの(怒)」「子;もう最悪、なんで教えてくれないの。もうテスト受けれない・・・(泣)」と親子げんかが勃発するご家庭も。
忘れた人には、入口で、主催者の方が使い捨ての不織布のソックスカバーを渡してくださっていましたが、いやー焦りますよね。
上履きチェック、大事です・・・
行事参加のスケジューリング
夏前から12月まで(夏休みを除く)、月に1〜2回テストがあり、それと同時進行で、各学校の説明会や学校行事があります。
説明会でくたびれてその学校が嫌になってはいけないので、我が家は、6年生の時は、お初の学校の説明会は親のみが行き、子どもは、既に志望校候補に入っている(あるいは今後入る可能性が高い)学校の、モチベーションが上がる行事(文化祭やオープンスクール)だけ、一緒にいくようにしました。
オンラインの説明会や個別相談は、家で子どもと参加できたので、ありがたい時代です。
行事は早い頃から行くほうが良い、と言われているのですが、この学年は、コロナで行事の自粛や人数制限があったので、文化祭などの行事に参加できたのは、小4の時(激戦)か、小5くらいからでした。
小5の秋は、色んな学校のイベントに参加していました。
小学6年の秋以降は、実際の入試期間の過ごし方のスケジューリングにリソースを持っていかれるので、そのお話は、また後日。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
