
長期休暇、育児ノイローゼを回避する3つの方法
※有料記事になっていますが、最後まで読めます。
娘の一カ月の夏休みがこれにて終了。なんとかやり切りました。このやり切った感は「やり過ごせた…」というよりも「よく頑張った!」という達成感が9割を示しています。もちろん1割は惰性でもありますが。
さて、24時間、まるまる一カ月、未就学児と過ごすというのは、どんなに子どもを愛していてもしんどいことだということを、はっきりとお伝えしちゃいます。私は、見かけによらず結構はっきりとした物言いなので、時に驚かれることもあるのですが。はい、きついですっ!
去年の夏休みは、育児ノイローゼに片足つっこんでおり、娘に八つ当たりしてしまいました。その証拠となる記事がこちら。
辛いのですよね。なんで辛いのかって、「一緒にいるのが辛い」と言うことが許されないと思っているから。だから、周りからひどい母親だと思われないように自分一人で頑張ろうとする、けれどもやっぱりしんどいという負のループ。
でも、育児が辛いと言うのが許されないとか、ひどい母親と思われるんじゃないかとか、それらも、一人ひとり感じることは異なるわけで。もう全て多様性のせいにしている自分がいます。だから、この一年かけて、そこに罪悪感は抱かなくなりました。
誰にどう思われるかよりも、いつもの私で、娘と笑い合える時間を過ごしたいという思いが勝りました。私なりに工夫を凝らしたことを記録として書き綴っていきます。よろしければ、お付き合いくださいませ。
1.体調管理
1.睡眠
娘も私も、毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きます。旅行に行っても、それは変わりありません。多少のズレは仕方ありませんが「明日も休みなんだから」と親の都合で寝かしつけが遅れることはしませんでした。というのも、子どもは大人と違って、不足した睡眠を翌日取り返すことができないのです。つまり、次の日にたくさん眠ればいいということが通用しません。
とにかく睡眠は何よりも大切にしていました。娘が睡眠不足になると機嫌も悪くなりますし、動きも鈍くなる。私にとってもイライラの元凶になるので、お互い十分な睡眠時間が欠かせません。去年は、せめて夜くらい自分の時間が欲しいと思って、夜更かししていましたが、結局娘は早く起きてくるので自分だけが寝不足になっていたなと振り返っています。
それでも、旅行に行くと私は眠れなくなるタイプだということは、もう重々分かっています。ですから、朝起きてからすぐ夫に「やっぱり眠れませんでした。このまま頑張るとメンタルが崩壊するので今日は早く寝ます」と伝えました。で、その日は19時に寝る。そうすれば、次の日には元気になっています。夫にとって私がイライラすることは何よりも恐怖らしく、早く寝ることついては寛容です(笑)
2.運動
北海道も暑いです。連日30°を越えていました。となると、家にひきこもりがちになりますよね。それが、育児ノイローゼの一因であるとも思うのです。私はもともとメンタルが弱いので、安定させるためにエアロバイクを購入し、有酸素運動をしています。でも、娘が一緒だとそれはできなくなります。
私が今回取り入れたのは噴水で水遊び。噴水は涼しいですし、公園にあるので娘も私も走り回ることができます。100円ショップに売っているシリコンの水風船は何度も繰り返し使えて重宝しました。水があるだけで、子どもはテンションMAX。私も水浸しになって一緒に遊び、良い気分転換になりました。


そして、酷暑の日はプールへ。娘は水の中で鬼ごっこをするのが大好きで、それもほんと体力のいる仕事なのですが、心身の健康のためだと思ったら、できちゃうものです。そうそう、「娘のため」が一番の理由ではないのです。私がどう穏やかに一カ月を過ごせるかという課題をこなしているだけなので、別にいいお母さんになりたくてやっているわけではないんですよ。
「ママがご機嫌でいることが、子どもの幸せ」という言葉をよく耳にします。母親が好きなことをやることが大事なんでしょと思うかもしれませんが、それは少し先の段階です。まずは、母親が健康であるための努力をすることが第一優先です。そうすれば、勝手に気持ちに余裕が生まれ、好きなことをする時間も作れるようになるのです。
2.頼る
1.幼稚園の預かり保育
一人で育児をこなせたらカッコいいだろうなと思っていました。でも、無理ですね。私の場合は無理でした。娘の通う幼稚園には夏休み預かり保育があります。
「積極的に勧めるものではありませんが利用できます」と幼稚園手帳に書かれています。これを読むと「働いていないのに預けるのはまずいのかな」と思いますよね。だから「働いていないから自分が見なきゃ」につながってしまう。でも、「働いていなければ預けることができない」とは書かれていません。実際聞いてみると、誰でも利用することができるとのこと(幼稚園によってはルールが異なるかもしれませんが)。
私は夏休みの最初の2週間は、週3回午前中預かりを利用しました。その間は、記事を書いたり、カフェに行って自分と向き合ったりして、自分が充電できることをしていました。メリハリがつけられると、午後からも頑張れます。それこそ、お昼ご飯を食べてからプールに行っていました。で、次の日はとにかく娘の遊びに付き合う。そして明日、また幼稚園を頼る、という感じで、私にとって無理のないスケジュールを組めていたように思います。
2.夫と分担
夫は2週間の夏休みがありました。私は朝カフェに行きたい、夫はお昼寝をしたい、という願望がようやく共通認識できるようになってた今日この頃。午前と午後の部で娘のお世話を分担するようにしました。親も余力を残せますし、娘も常に遊んでもらえるので、家族の満足度は高まりました。
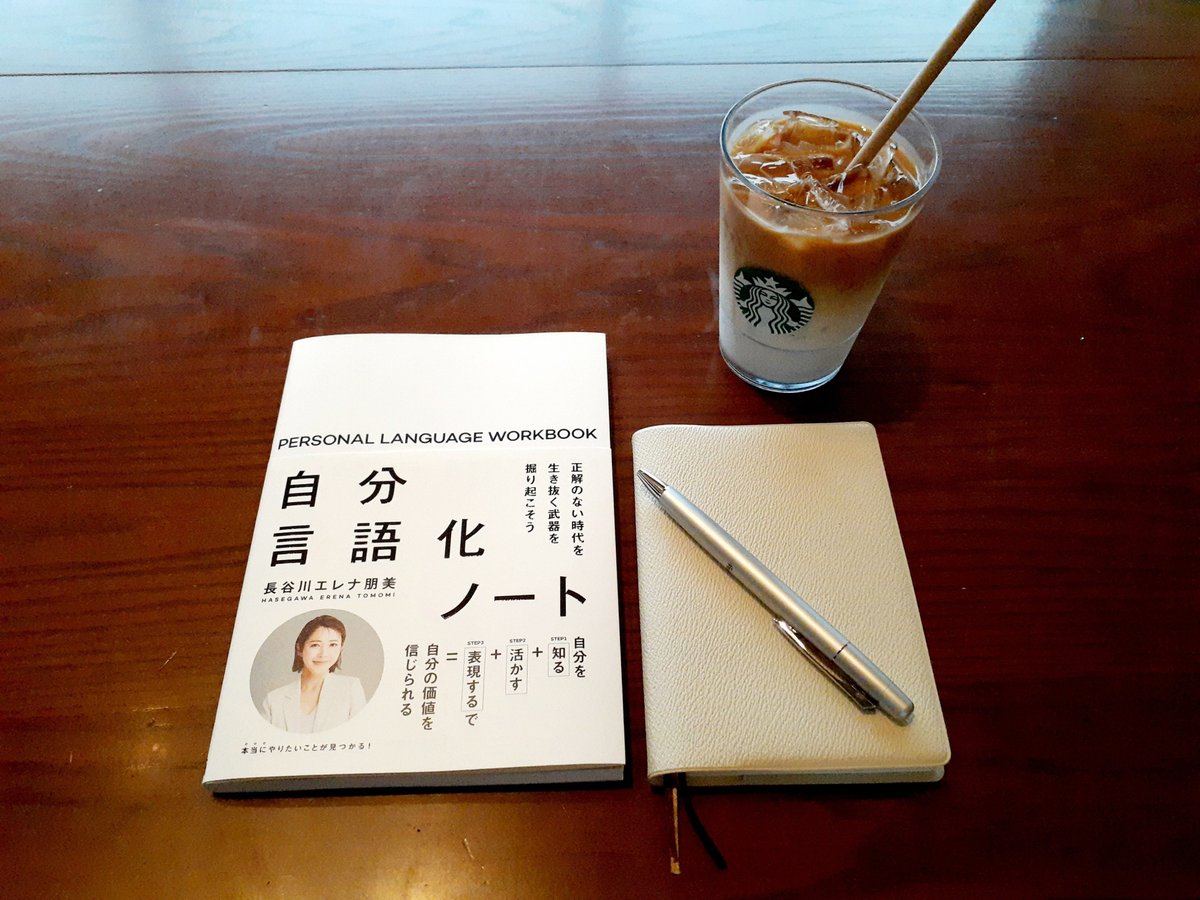
これも、やせ我慢していた時期があります。自分の時間なんて必要ないと言い、自分だけが1日お世話をしていたこともありました。「子どもの面倒なんて全然余裕」みたいに見せたかったのかもしれません。でも、ようやく夫に向かって「1日一緒に遊ぶのは大変だよー。分担しようっ!」と言えるようになりました。それが、私の成長でもあります。
3.自分以外の子の面倒を見る
これ、なかなか機会はないかもしれませんが、そういう機会があるときはぜひやってほしいと思います。夫の家族と遊園地に行ったときは、小2の甥っ子とジェットコースターに4回乗りました(笑)好きな方なので苦ではなかったですよ。「また乗ろう!」と言ってくれる甥っ子が可愛いなと、素直に思えました。
また、私の妹の子どもたちに会ったときは、ヨチヨチの姪っ子を抱っこして遊びに行ったり、やんちゃな甥っ子を自分の子どものように叱ります。自分の子どものように、他の子を大切にすることが、なぜだかわからないのですが、自分の子育てを楽にしてくれます。

すごく意識しています。親戚の子じゃなくても、娘のお友達にも、サッカークラブの子に対しても、そういう気持ちで向き合っています。
他の子を見ると、わが子の良いところも見えてきます。そして、私も娘も他のお母さんとも仲良くなることができるようになります。自分の利益のことは、まずは置いておいて。でも、巡り巡ってそれが温かな人間関係の構築となり、私の心に安らぎをもたらすのは間違いないのです。
思い返すと、自分なりに工夫していたことが色々出てきました。また、いつかの機会に書き起こせたらなと思います。今日書いてみて思ったことは、母の健康が何よりも大切で、そして一人で頑張る必要はないのだということ。健康で、頼り頼られながらいれば、他人の目なんて自然と気にならなくなります。どなたかの参考になれば幸いです。
お読みいただき、ありがとうございました。面白かった、役に立ちそうと思いましたら「スキ」か300円をいただけるとうれしいです。「スキ」は次回執筆の励みに、300円は書籍代に当てたいと思います。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
