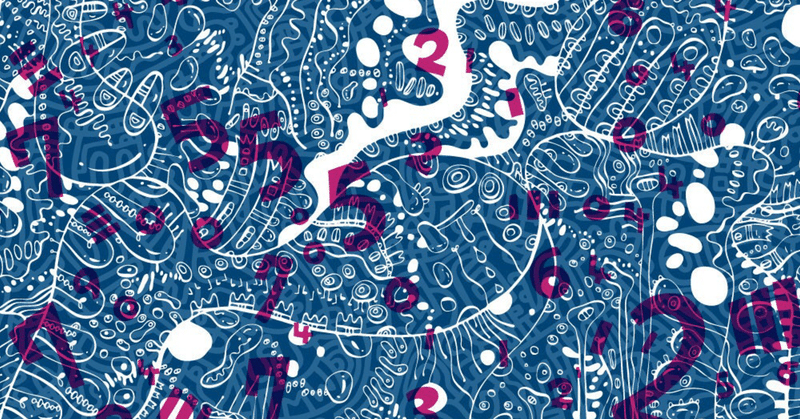
あなたが読めない
彼女は本屋にくる度に途方に暮れるのだという。
ページの中で息を潜めている文字たちが、自分めがけて飛びかかるのを表紙の影で待ちわびている、そんなふうに感じるらしい。
黒いインク。
赤いインク。
黄色いインク。
それぞれが持っている形をほどいて貪欲なヒルのように吸いついてきたら、きっとひとたまりもないだろう。
そう言って彼女は自嘲気味にからからと笑う。
僕は素朴な疑問を投げかけた。
「文字は身体のどこを襲うの?」
「目よ、目から入って、脳みそと心を食べちゃうの」
脳裏にピンク色のヒルたちが瞼をかき分けて目に押し入り、脳味噌のふるふるとしたゼリー状の物体をつつつと吸い取る様子が思い浮かんだ。
思ったより残酷というよりは、生き物も身体の部位もすべて食物連鎖にひそかに組み込まれたように思えた。
さて、問題は彼女である。
いったいこの世で、見えない情報までもが空中を飛び交って取り憑く端末を探しているこの世界で、彼女は文字を避けて生きていけるのだろうか?
もうそれは、太陽の光を避けたり、植物を避けたりして生きることに近いことだ。
それは至るところから彼女を狙ってしまうだろう。
「あら、失礼ね。適度に目を閉じれば怖くないわ」
確かにそうかもしれない、と何度か瞬きをしてみた。
妄想の中の小さなヒルたちは、彼女の長いまつ毛にときには絡め取られながら、ばらばらを落ちていく。
彼女はあっけらかんと生きている。
そして人は視覚に頼りすぎて、感じることを忘れてしまったと言う。
当たり前のものが「欠けている」と言ってしまうと差別的だし、僕と彼女を取り巻いているスノードームみたいな閉じられた世界は、きっと一時的にシンクロナイズはしているけど、それは同じであることを意味しない。
フィルムが水の中で、すいと重なっているだけなのだ。
それを泳ぐのは目を閉じた彼女。
水のように。
魚のように。
彼女は文字を読めない。
「漢字はいちばんの強敵ね。性格が強すぎるのよ。中国語学習なんていったら、それはもう大変なことになっちゃうわ。
アルファベットの国で生まれるべきだったのかも。アルファベットはそれ自体に意味をもたないことこそが意味あることだし、共感に値するわ」
彼女は美術館に行くと、自宅に帰ってきたかのように安心するのだという。
色がさまざまな表情をして深遠な領域に迎え入れてくれるように感じるのだそうだ。
だから部屋のガラス瓶に花は絶えない。
今日はドロップのような赤色の花を買って帰ると言った。
彼女は僕の前でも時々癇癪を起こした。
たいていは僕が文字の書かれた何かを見せて何かを伝えようとしてしまったときだ。
気が触れたように目を開いて、どこの言葉ともわからない何かを呟き、時には隅に追い詰められた動物のように叫んだりして、部屋にあるありとあらゆる文字をあらためて認識しようとしては破り捨てていく。
近くのスーパーマーケットのレシート、先週ショッピングモールで買ったばかりの夏物のワンピースのタグ、郵便受けに無造作にねじ込まれていたピザのチラシ、学生時代に買ったパソコンの取扱説明書。
文字たちが居場所を忘れて、舞う。舞う。舞う。
どうしてみんな。
わたしのしらないところで。
おしゃべりするの。
彼女の言葉が、部屋の床に舞い降りた紙吹雪の上に転がる。
黒目がくるくるとまわって、終いにはガラスのように割れそうに歪む。
がちゃん、と音がして、僕は花瓶の製作者が刻みつけたサインが最後の標的だったとわかった。
僕がこうして彼女の青天の霹靂のような癇癪を通り雨と同じくらいの重要さでやり過ごしながら、一緒に食卓を囲んだりとそばにいることができるのは、もしかすると奇跡に等しいのかもしれない。
その奇跡はいつ破られるかもしれない危ういものだ。
いつ終わってしまうかわからない。
でもそれを怖いとは思わない。
悲しいとも思わない。
彼女の元に届いた僕という存在は、もう文字を腹いっぱいに溜め込んだ手紙と言ってもいい。
彼女の癇癪は、いつのしか僕自身に向かうとも限らない。
真夜中にそっとベットに果物ナイフを滑り込ませて、ゆっくり糸を擦り付けるような音をさせて皮を剥いでいくと、中からくだらないがらくたの文字が部首や曲線やらを互いに絡ませながら溢れてくる。
彼女はそれを見下ろして、怒りのあまり僕の内臓ごとその文字を食べ尽くしてしまうかもしれない。
たぶんそれは美味しくない代物だろうけど、それも悪くないかもしれない。
これが結末の本だとしても、それでいい。
ずっとそのままでいい。
終わりがあってもなくても、早くても遅くても変わらない。
たとえ彼女が数日にいちど、部屋を紙くずでいっぱいにして、また涙を拭きながらけたたましく掃除機をかけるのをえんえんと繰り返したって。
そんな彼女だって。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
