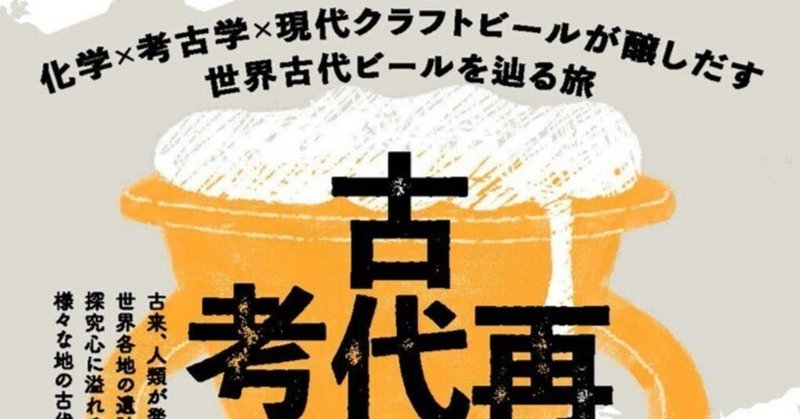
再現!古代ビールの考古学―訳者あとがき
「人類は遥か昔からずっと発酵飲料を作って飲んできた」という持論のもと、我々の祖先たちが堪能していたと思しき発酵飲料の痕跡を辿って世界各地の古代飲料を研究する著者「パット博士」は、「古代発酵飲料のインディ・ジョーンズ」とも呼ばれている。
博士は米国ペンシルベニア大学考古学人類学博物館の考古生化学者であり、様々な地で発見された古代飲料の残渣を化学分析し、その結果と多岐にわたる分野からの裏付け証拠をもとに材料と作り方を推定して、古代飲料を現代で現実の飲料として蘇らせてきたのである。
本書では、博士が再現に関わった飲料8つを各章でひとつずつ取り上げ、それぞれの飲料にまつわる歴史や文化などのいろんな背景情報をたっぷりと交えながら、再現の過程とお披露目に至るまでのドラマをパット博士の視点で紹介している。
本書は、2017年にAmerican Society of Overseas Research(米国国際研究学会)より、学者のみならず広く一般の人々にも考古学的事実を伝える総合的学術図書に贈られるナンシー・ラップ大衆図書賞を受賞した。まさに、一般の人が読んで思わず誰かに語りたくなる興味深い話でいっぱいの本なのだ。
本書で取り上げる8つの再現飲料を実現化したのは、「型破りな人のための型破りなビール」作りを理念に掲げて米国で独創的なクラフトビールを生み出し続けるドッグフィシュ・ヘッド醸造所だ。現在はドッグフィッシュ・ヘッドのように変わった材料でビールを作る醸造所も少なくないが、1995年の創業当初はまだ珍しい存在で批判も多く受け、当時の醸造日の平均的な醸造量は約90リットル程度だったという。
それが2章のミダス・タッチを機に一気に認知度を上げ、2010年には4章にも登場するテレビ番組『ブリュー・マスターズ』シリーズが放映されるなど、今や米国では名の知れた醸造所となり、2021年には最大約227キロリットル醸造する日もあったと同醸造所のウェブサイトに載っている。本書でパット博士の相棒として登場する創業者のサム・カラジョーネは、2017年に米国料理界のアカデミー賞と称されるジェームズ・ビアード賞の優秀ワイン・スピリッツ・ビール・プロフェッショナル賞を受賞している。
物語は、各章で取り上げる古代飲料に関連する時代と地球上の様々な地域を旅する形で進んでいく。そのため、舞台となる時間も場所も目まぐるしく移動する。私は翻訳しながら年表と地図を作成して情報を整理していた。
そんな中、編集者より本書に地図を入れないかと打診され、それなら年表も、と原書にはないオリジナルの地図と年表を特別に作成して本書に組んでいただいた。特に地図は、物語に登場する主要な場所に絞り、本書を読みながらパット博士と一緒に旅していけるものに仕上げてもらった。何度も細かな修正に対応くださったデザイナー氏に感謝申し上げたい。祖先とパット博士の旅路、そして時空を越えて存在する発酵飲料を視覚的に感じていただければと思う。
言語好きだという本人の言葉通り、この著者は舞台となる国や地域の言葉を物語の端々で紹介していく。3章の中国においても同様で、もともと英語表記がほぼ中国語の発音通りの地名・人名はともかく、書物などの様々なものの名称も披露してくれる。そんな著者の言語愛と旅の雰囲気を味わうため、著者が中国名を示しているものはカタカナでルビを振り、日本語で通常使われる読み方をひらがなで表記した。著者による中国名記載のないものは、必要に応じてひらがなで日本語読みのみを示している。
また、本書で使用している外国語のカタカナ表記は、いろんな書き方や考え方があるのを理解し、様々な要素を考慮した上で選んでいった。例えばトウモロコシの前身teoshinte は、発音通りにあえてテオシンテとしている。
一方で、ドッグフィッシュ・ヘッド創設者サムの名字は発音通りならカラジオーニだが、ビア検定にカラジョーネの名で記載されていると知ってカラジョーネに揃えた。そして醸造関連のbrew は色のblue と区別するためブリューで統一している。
言語に関しては著者の熱意にすぐさま共感できたものの、考古生化学者である著者の説明する化学や考古学の話は私にとって非常に難解なものが多く、全体的にかなりのリサーチが必要であった。
そしてインターネットでそんな概念や用語を検索すると、かなりの頻度で中学・高校生向け受験対策サイトに当たり、これは中学・高校で学ぶレベルの内容なのかと何度も驚かされた。
2章以降、再現ビールの自家醸造レシピとペアリング料理レシピが掲載されている。ビール醸造や料理に関してパット博士はもっぱら飲む・食べる専門のようで、本書掲載のビール・料理レシピはどれもパット博士と交流のある別の人物によるものだ。
自家醸造ビールレシピは、ドッグフィッシュ・ヘッドが再現した商業レベルの本格的レシピではなく、あくまで趣味範囲で自家醸造する人に向けてアレンジされている。2章のミダス・タッチは入門編なのか、かなり簡略化されており、そこからだんだんと難度が上がっていくようだ。
だが世界の多くの国では自家醸造をそんなふうに趣味として気軽に行なえる一方、日本ではあいにく酒税法により、酒造免許を持たない一般人が度数1%以上のアルコールを作ることは禁じられている。
ではこんなレシピがあっても日本では無駄かというと、そうとも言えない。酒造免許を持たない者が、免許を所持するブリュワーの設備と指導のもとで合法的に醸造体験できるBOP(Brewing On Premise)という仕組みが日本でも使えるらしい。また、既に免許を取得して本格的な醸造を実践している人々には、何かのヒントになるやり方や材料もあるかもしれない。
料理レシピは、各再現ビールとのペアリング案として掲載されている。しかし現在ドッグフィッシュ・ヘッドは本書掲載ビールのいずれも醸造しておらず、おまけに日本では自家醸造もできないとあっては、「この飲み物に合う料理」と言われても試しようがない、と不満の声が上がりそうだ。それにそもそも入手困難な材料も多く、ただ作るだけでも難しい。
しかし掲載レシピの多くは再現ビールの元になった地域の代表的料理で、レシピ内容を見るだけでも旅行気分が味わえる。また3章のペアリング料理レシピに含まれている大根の漬物レシピなどは、日本では単に塩漬けにするところで、いかにもビール醸造に携わる人らしいレシピ材料や作り方が面白い。
さらに、とりあえず入手可能な食材のみでスパイシー豆腐を作ってみたところ、シナモンの量が半端なく、日本や中国の麻婆豆腐ともまた違う不思議な味がした。どんな素材を使ったどんな料理があるのか覗いてみて、物語の一部として楽しんでいただきたい。
本書を翻訳するまで私が好んで飲んだのはワインと日本酒で、ビールはほとんど飲まなかった。ビールはどれもただ苦いだけの飲み物だと思っていたのだ。しかしこの翻訳を機に「リサーチ」と称して、風変わりな食材を使った世界各地のクラフトビールを見つけるたびに片っ端から試飲してみた。
そして、わりとよく見かける柑橘系などの一般的な果実を使ったもののほか、山椒や栗、桜の葉などを副原料に使ったり、アップル・クランブルやクッキーなどの菓子風味に仕上げたりといった数々の個性的なビールとの出会いを経て、ワインや日本酒と同様に、いろんな味わいが存在するクラフトビールも俄然面白くなってきた。
実はミダス・タッチもアメリカ在住の友人を通じて入手して飲んでみた。本書を初めて読んだとき、ビールとミードとワインを混ぜたような飲み物なんて想像もつかなかったが、ミダス・タッチはこれまでに飲んだどのビールとも違う美味しさで、こんなビールがあるのかと驚愕した(現在ドッグフィッシュ・ヘッドではもう醸造していないのがとても残念だ)。
3章で著者は日本酒が「精米、単一酵母、そしてきめ細かくコントロールされた醸造工程に従って造られる」と述べている。だが日本酒も画一化された飲み物では決してなく、使う米(素材)・酵母・水・温度・醸造法の違いによって様々な味わいの異なりを楽しめる。そしてそれはきっとどんなアルコール飲料でも同じ話なのだ、と今は思う。
世界には実に様々なアルコール飲料があり、それでいて国や文化を越えて楽しまれる。音楽と同じく、まるで世界共通言語だ。様々な物語が詰まったこの本も、アルコール飲料を作る人・飲む人・飲まない人のいずれにも楽しんでもらえれば幸いである。(後略)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
