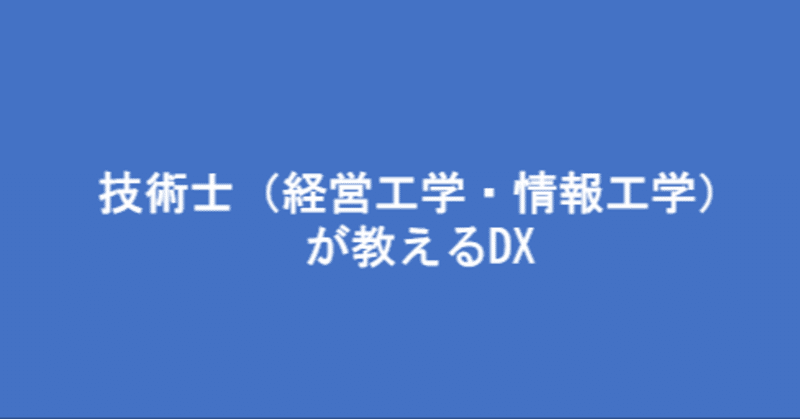
技術士(経営工学・情報工学)が教えるDX(デジタルトランスフォーメーション)講座4 技術継承にもDX思考が必要に、全ての鍵は日本の古きよき時代に帰ること
DXを推進する上で、ITに精通する人がいる以上に重要となるのが、業務に精通する人がいることです。しかし、多くの企業では今、業務に精通していたベテラン社員が退職し、残った社員は業務があまりわかっていないという事態が起きています。これではDXどころか、業務改善すら困難な状況にあるといえます。
これと同様のことがITベンダーの中でも起きています。やはり、ユーザ業務に精通していたベテラン技術者が退職し、引き続いた技術者が担当するユーザ業務の内容がわからないという似たような事態が起きているのです。
さらに、古いシステムでは今ではあまり使われない開発言語やツールを使って開発されており、その古い技術を習得するにしても、新たな市場性はなく、特定のユーザ企業のために貴重な技術者をはりつけておくだけになってしまいます。
必然的に、ユーザ企業でもITベンダーでも経験豊かなシニアを非常勤社員や顧問として採用する動きが出てきていますが、孤軍奮闘状態では何ともし難く、業務能力の低下を止められていないというのが実情ではないでしょうか。
こうした実情の中で、何もできずに手をこまねいている訳にはいきません。実は、この段階からすでにDX的思考が役に立ちます。属人的思考から脱却することが必要です。一人でできないのならチームでやる、自部署や自社でできないなら、他部署や他社から協力を得る、わかっていることからはじめる。従来的な思考の殻に閉じこもっている限り、突破口は見い出せません。
欧米では、BPM(ビジネスプロセスマネジメント)を実行するために、プロセスオーナー制度というものがあり、業務プロセスの可視化や改善、運用評価の責任を取る人が明確に決められており、さらにこの活動を支援するためのBPMチームが設置されています。これに対して、日本の企業ではCOOや執行役員のような人がいたとしても、業務の詳細は現場の課長層がおさえており、プロセスオーナーと呼べるような業務全体を鳥瞰して理解している人がいないのです。
DXでは、システム要件を超人のような人が一人で行うのではなく、各部署からのユーザ代表やIT技術者が一つのアジャイルチームとして集まって、スプリントと呼ばれる短い期間で小さな要件単位を設計してはインクリメント(プロダクト)を開発して、それを積み上げていきます。
日本でDXが定着し、成功するか否かは、このアジャイル活動に取り組めるかどうかにかかっています。実は、このアジャイル活動を業務改善フェーズで見れば、QCサークル(小集団活動)に類似しており、ビジネスアジャイルと呼ばれています。ビジネスアジャイルが日本のQCサークルに似ているのは当然で、スクラムなどアジャイルの方法論は日本のカイゼン活動を模範として考えられたからです。
DXには、他にも日本のカイゼン活動が元になっているものが少なくありません。徹底的に横連携し、協力し合うコラボレーションやエコシステムという考え方(これらについては後述する予定です。)は、トヨタの工場で異常を示すアンドンが光ったら、関係者全員が集まって解決にあたるのと似ています。(今では、アンドン自体もDX化し、IoTによって工場以外やトップにもリアルタイム共有されています。)
最後に、技術継承の解決策としてナレッジマネジメントを挙げておきたいと思います。
アジャイル活動ではスプリントの終わりにスプリントレトロスペクティブと呼ばれるふりかえりミーティングが行われ、そのふりかえり手法として KPT (Keep, Problem, Try)がよく使われます。KPTではよかったこと、悪かったこと、そしてよかったこと悪かったことのどちらからも今後の課題を考えます。
ナレッジマネジメントは決してITツールを入れたら達成できるものではありません。ふりかえりミーティングをやることによって、はじめてITツールに登録すべき知見が得られるのです。
アジャイルで行われるスプリントレトロスペクティブも実は日本発の考え方が出発点になっています。一橋大学の野中郁次郎名誉教授が提唱された知識創造理論SECIモデル(共同化;Socialization、表出化;Externalization、連結化;Combination、内面化;Internalization)がベースになっているのです。
2025年の壁の根本原因は、日本企業の多くが、属人的な暗黙知を放置し、形式知との相互変換を通して新たな知を創造するという野中先生のナレッジマネジメントに真面目に取り組んでこなかったツケだと私は思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
