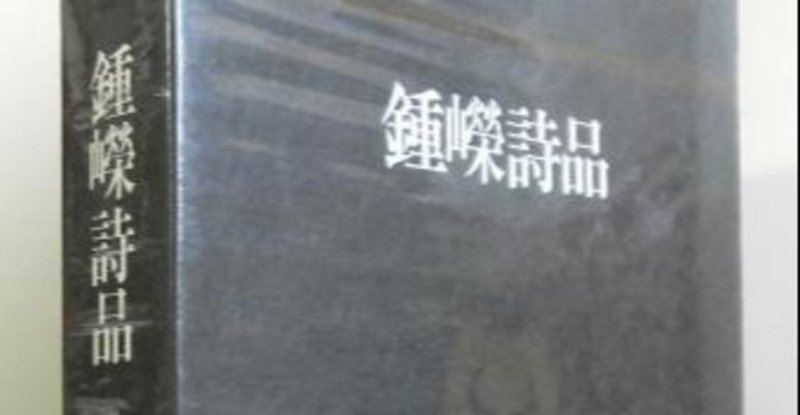
五言詩の集大成「詩品」
作者は鍾嶸(しょうこう)
詩品とは、古今の詩人123人の詩を取り上げ、それを上・中・下で格付けし論評を加えたもの。
詩品が生れた時代は文学批評というジャンルが花開いた時代でもあり、同じ時代の代表的な書物は『文心雕龍/劉勰(りゅうきょう)』がある。
文心雕龍(ぶんしんちょうりゅう)が文学を網羅的に取り扱っているのに対し、詩品は五言詩のみを扱っているのが特徴。
鍾嶸が生きた南北朝時代は五言詩が飛躍的に増えた時代である。
五言詩は新たな展開を迎える新しい文学形式で幅広い詩人から受け入れられていた。
五言詩は文学のかでも味わい深いもので、時代の風潮を捉えていた。
これは五言詩という形式が、事柄や形状を示し情理を尽くし外物を描写することに最も行き届いたものだった文学だから。
詩には三義というものがあり、それは「興(きょう)」「比(ひ)」「賦(ふ)」。
言葉が残っても余韻が残る表現を「興」といい、ものにコト寄せて志を例える表現を「比」、事柄を言葉で書いて言葉として描写する表現を「賦」という。
この三義を広げ、時によって適切に用い、美しい言葉の表現を加える。
それが詩の醍醐味。
この三義のうちどれか一つでも欠けてしまうと表現は散漫なものになってしまう。
鍾嶸が詩品を執筆した動機にはこれまでの文学の在り方に反発する姿勢があったからだ。
この頃の主な文学の担い手は貴族を中心とした上流階級の人たちで、五言詩が流行るにつれて中身が伴わない作品も多くなり、遊戯的で華美な傾向が強くなっていきました。
鍾嶸はこのような風潮を批判的にとらえ、当時の五言詩の力強さが失われてしまったと嘆きました。
その要因もあり「詩品」は生まれたのです。
━━━━━━━━━━━━━
▼ 詩品からの学びはなにか?
━━━━━━━━━━━━━
詩品に限らず荘子や老子など人間は昔から言葉による表現を重要視していた事がわかる。
この事から、自分の表現する一文字アートに詩の三義である「興」「比」「賦」を乗せる事が出来るか?の思考のきっかけになる訳だ。
「想い出の一文字を形に。」という自分のコンセプト実現のための今回の学びは詩の三義。
鍾嶸に感謝。
いただいたサポートはHITOMOJIのコンセプトである“想い出の一文字を形に”を実現する為の活動資金として活用致します。
