
経理のDX推進のための業務プロセス再構築
こんにちは、Backyardの武内です。
ITmedia SaaS Expo 2021夏というイベントで登壇させていただきました。オンライン展示会という形で、講演が視聴できたり、各社の展示ブースでは資料のダウンロードがなどが行えるイベントです。7月末まではアーカイブの視聴も行えるようですので、よろしければぜひ登録してご覧ください。
私は財務経理×Techのゾーンで基調講演として、経理がDX推進にあたって向き合わなければならない意識変革を中心にお話しさせていただきました。いつもの通り、資料はSpeakerDecで公開しております。
今回はデジタルシフトの過程において、経理がどのように変わらなければいけないかについて書いていきます。
1.経理の仕事は作業ではない
エンジニアの仕事はコードを書くことではありません。
営業の仕事は電話をしたり、打ち合わせをすることではありません。
同じように、経理を含めたバックオフィスの仕事は、作業(処理)をすることではありません。
「作業」をすることが自分の仕事だと言う方々はオペレーター(作業者)と呼ばれます。そうではない方々にとっては、仕事の成果を達成するための手段や手順の1つとして作業が発生するのです。
エンジニアやセールスにとっては、だいぶ前から作業量は評価対象ではなくなっており、「いかに無駄な作業をせずに成果をあげるか」という観点で業務を進めるのは当たり前です。もちろん、成果を出すためには一定量以上の行動・作業量が伴う場合がほとんどですので、作業そのものを忌避するのではなく、あくまでも「作業をすることを目的にしない」というマインドセットをしているという話です。
一方で、エンジニアやセールスが作業から解放されていった背景に目を向けてみると、マインドセットだけでなくテクノロジーの貢献度は計り知れません。テクノロジーをうまく活用して業務プロセスそのものを再構築する。これができてきたかどうかの差が大きいはずです。
経理を含むバックオフィスに目を向けてみると、業務の前工程にあるものがあまりにもアナログ過ぎて、テクノロジーを活用したくてもできなかったという事情もあり、やはり周回遅れの感が否めません。脱ハンコやリモートワークがようやく一歩を踏み出したのが2020年。デジタルシフトに向けての環境が少しずつ整ってきたところです。
●●Techと騒ぐ声に惑わされていけません。システムはあなたの代わりに仕事をしてくれる魔法ではありません。「システムの方が得意な作業を自動化・効率化する」ことによって、あなたが成果を出すための時間を生み出すのが現時点でのテクノロジーの役割です。
テクノロジーを活用して人件費を削減する、という発想自体が今の時代はナンセンスですし、その発想でいる経営者には絶対にDXなどできません。DXとは、テクノロジー導入の課題ではなく、経営そのものの課題なのです。
経理にとってのテクノロジーは、まだまだ「アナログだった作業がデジタルに変わっていく」Step1のデジタル化の入り口にたったものに過ぎません。これまでは環境要因がデジタル化を阻害していた部分が大きかったからです。

本来の意味での「経理DX」はまだ遙かに先にあり、誰にもその輪郭すら見えません。ただ、会計や税務の原理原則が覆ることは当面はないと思うので、その枠組みの中で、テクノロジーを活用していかにして「オフラインのない世界」を前提にした新しい仕組みを構築することができるか。それがこれから問われていく部分です。
2.成果を出すための仕組みを作る
経理の「作業」と呼ばれる業務はおおまかには、以下に分割することができます。
①資料及び情報を収集する
②それらを見て、処理方法を判断する
③会計システムに登録する
これらをひとまとめにして「作業」と呼んでいる場合がほとんだと思いますが、クラウド会計などの発展によって自動化・効率化が進んでいるのは③の部分です。もちろん、完璧な仕組みなどありませんし、登録のルールは人間がきちんと整えるという前提での③です。
会計システムに登録された仕訳伝票を集計して財務諸表が作られるので、③が重要なのはもちろんなのですが、実は経理が実際に時間も労力も使っているのは①②の方なのです。
よって、業務の効率化を考える際には③だけではなく、①〜③の一連の業務全体を棚卸ししながら、可視化し、再構築しているということが欠かせませんが、多くの場合は③のみを効率化したり、システム化したり、外注したりするので、一瞬は楽にはなるのですが、場当たり的な解決にしかなっておらず、全体から見た効率化にもあまり貢献していない場合がほとんどです。
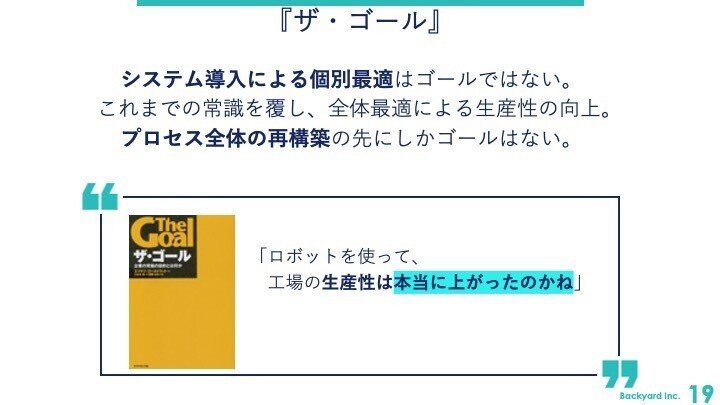
まさに『ザ・ゴール』の冒頭でジョナがアレックスに「ロボットを使って、工場の生産性は本当にあがったのかね」という指摘そのものです。この「ロボット」を「システム」等に置き換えてもらえれば、原書から20年以上が経ってもまだまだ有効な問いかけなのです。
現在のDXブームで紹介される事例のほとんどが、本当に単なるロボット(システム)導入による局所的な個別最適にとどまってしまっています。これまでのやり方や仕組みを維持したまま、目先の効率化が得られるので確かに導入しやすいですし、見た目のインパクトはあるかもしれませんが、まったく柔軟性もなく応用も効かないプロセスを1つ増やしたに過ぎず、全体の生産性は良くて維持、最悪の場合は生産性が下がることもありえます。
デジタルシフトの過程において、一番重要なのは「デジタルに最適化した仕組みの構築」です。最新のテクノロジー導入ももちろん必要ですが、これまでのアナログを前提とした仕組みの中にポンと最新のシステムをおいたところで機能するわけがないのです。
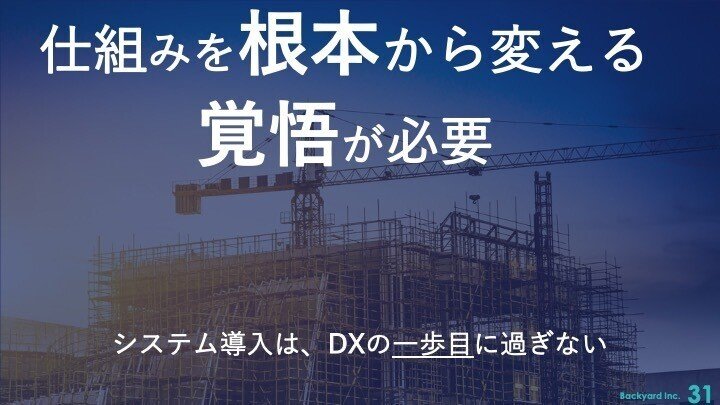
これが、DXがシステム導入の問題ではなく経営課題だと言われるゆえんです。業務プロセス、収益構造、さらには評価指標も含めてすべて見直さなければ、変革などできるはずがありません。テクノロジーの導入はゴールではなく、スタートです。
テクノロジーがいい感じですべて解決してくれることは絶対に起こりません。良くも悪くも、仕組みを再構築するのは人間にしかできません。システムを比較して、「自分たちの業務に対応できるシステム」を探すのではなく、この機会に自分たちの業務を再構築していくことが必要なのです。
3.作業者から設計者へ
簿記検定は知識を得るためにはいいとは思うのですが、合格のために求められるものがアナログな作業スキルに偏りすぎています。パターン認識と処理スピードだけの問題であれば、そう遠くない将来に単純な入力作業はシステムに代替されるでしょう。
ただ、前述の通り、判断基準の明確化やそしてビジネスの中身の理解、アウトプットから逆算しての仕組み作りなどは、当面は人間の仕事です。単純な入力作業ほど置き換えられやすく、仕事を失う可能性が高いという現実を直視すれば、作業スキルだけを追求することはあまり意味がありません。

DXが求めているのは「根本的な仕組みの再構築」です。脱ハンコやリモートワーク、そして電子帳簿保存法の改正など、これまで変革を阻んできた邪魔者達が2021年には一気にデジタルシフトの方向に変わろうとしています。それなのに、経理の現場だけが「これまでの仕組みを維持」しようとするのはむしろ滑稽です。
たしかに自分たちがこれまで長年つちかってきた業務のやり方とは違うかもしれませんが、テクノロジーの発展が引き起こす変化とはそういうものです。作業をすることを目的化せずに、テクノロジーを最大限に活用した業務プロセスを再構築することがこれからは求められます。
そう、経理にこれから求められるのは「作業者から設計者」に変化することなのです。画像認識、機械学習などのテクノロジーはこれからもどんどん発展していきます。クラウドツールがもはや標準になるなかで、システム間のデータ連携も更に広がっていくでしょう。
10年前、経理はコピーした通帳に1行ずつ物差しを当てながら、銀行口座の取引を会計ソフトに入力していました。クラウド会計を使用することで、この作業はもちろんなくなりましたし、「データを取得」してくるので、入力ミスもなくなりました。さらには明細の文字を学習させることで、8割方の明細を自動処理ができるようにもなりました。
入力することが仕事であれば、テクノロジーに仕事を奪われてしまいます。だからこそ、自らの仕事の定義を「経理業務」全体に広げ、作業をテクノロジーを活用して効率化しつつ、全体の仕組みをきちんと整えることが必要です。
アフターデジタルの世界はテクノロジーの発展が牽引しますが、その仕組みを作るのは人間です。経理業務は、アナログ作業でミスが起こることを前提にした非常に高度な仕組みではありますが、デジタルシフトの過程では、この「アナログを前提にした」様々な仕組みやルールが変化を阻んでしまっているのも事実です。

私はザ・ゴールシリーズの中でこの『チェンジ・ザ・ルール』という本が一番好きです。特にここで引用した「テクノロジーというのは必要条件ではあるが、それだけでは十分ではない」という指摘は、アナログからデジタルへシフトする過渡期で立ち往生している全ての人々に響くのではないでしょうか。

そして、もう一つ、ジェフ・ベゾスの有名な "Good intenion doesn't work, only mechanism works!" という言葉も講演の中で紹介しました。アマゾンぐらいのスピード感で事業を進めていく上で、属人化は大きなリスクです。代替がきかず、スケーラブルではないからです。そして、テクノロジーを最大限に活用するためには仕組化が不可欠です。
デジタルシフトしていく中で、求められる正確性やスピードは人間が「頑張って維持する」ことがもはや不可能になりつつあります。それは経理も例外ではありません。その変化に気づけないといつまでも「現場の頑張り」で支えることになってしまい、疲弊してしまいます。

経理領域のデジタルシフトは始まったばかりです。クラウド会計を導入するだけでDXになるわけではありません。最適な仕組みは、まだまだ試行錯誤しながら、構築していかなければいけません。改善し続けるマインドをもって、どれぐらいPDCAを回していけるか、改善を積み重ねていけるかが勝敗を決めます。

業務プロセスの可視化が重要、という話がありますが、バックオフィスの方々にヒアリングしていて気付いたことは、意外と仕事が縦割りで自己完結することが多く、「可視化するインセンティブが働かない」構造だということです。期限に厳格で、ミスも許容されない仕事なので、とにかく「終わらせる」。
— 武内俊介@Backyard代表 (@Libero_shunsuke) July 8, 2021
新しいプロダクトを作るために経理を中心にたくさんのバックオフィスの方々にヒアリングさせていただいていますが、思っていたよりも遙かに個別最適思考が根強いと感じます。担当者の方の責任ではなく、おそらくマネジメント側がきちんと機能せず、仕組みや業務プロセスを整備することを放棄し、各担当者に「任せっきり」になってしまっていることが原因だと思われます。
属人化とDXは本当に相性が悪いです。デジタルシフトするためには業務をきちんと棚卸しして、分解し、言語化や整理をすることが不可欠ですが、自己完結する前提で業務分担がされているため、完全に現場の秘伝のタレ状態になってしまっているからです。

経理や労務の専門知識や経験も必要ですが、それに加えて、ITリテラシーと設計力がこれからのバックオフィスには求められてきます。専門スキルだけで一点突破できる時代は終わったのです。税理士などの士業も例外ではありません。
デジタルが発展するほどに、仕組みを作れる設計者は重宝されます。そこに専門スキルを掛け合わせれば鬼に金棒でしょう。これまで現場でつちかってきた経験も決して無駄にはなりません。それらをしっかりと昇華して、デジタル活用に最適化した仕組みを再構築すればいいのです。
あの人にしかできない、あの人がいなければ回らない、そういう仕組みに依存している限り、DXなど夢のまた夢。テクノロジーを最大限に活用できるように属人化を排除し、業務プロセスを可視化し、常に改善を続けられるようにしましょう。
それが今の時代に経理に必要な変革(トランスフォーメーション)なのです。
ノートの内容が気に入った、ためになったと思ったらサポートいただけると大変嬉しいです。サポートいただいた分はインプット(主に書籍代やセミナー代)に使います。
