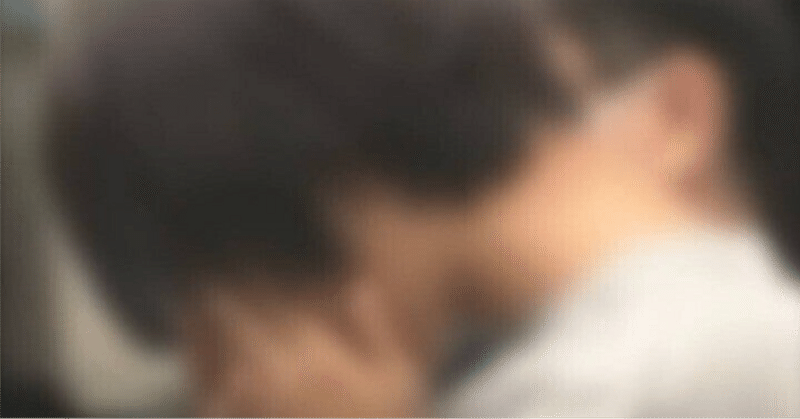
盗撮加害者家族の記 08 優しさの痛み
※この記事は全文無料でご覧いただけます。お気持ちをくださる方につきましては、記事最下部にてありがたく頂戴させていただきます。
「朝からお呼びだてしてすいません」
入ってきたのは私たちを案内してくれた刑事だった。その低姿勢な態度とスーツも相まって、まるで普通のサラリーマンと変わらないように見える。
だが違う。彼は、警察官だ。
「今から事件の大体のあらましと、奥様にはお伝えしたことですが、これからの流れを説明させていただきます。また、本人や事件に関するご質問に関しましては捜査中でありますのでお答えいたしかねますのでご了承ください」
刑事はとうとうと、あくまで事実のみを口にした。昨晩聞いた内容と全く同じだ。
「いちばんお解りいただきたいのは『たかが盗撮』では無いというのとです。相手が高校生ということも含め、無防備な弱い立場の人間を狙ったれっきとした卑劣な犯罪です」
私たちに向けたやわらかさとは正反対の厳しい口調。言われて当然の事ではあっても身が縮む。
「盗撮は再犯がとても多い犯罪です。私たちも捕まえるたびに『またお前か』と思うことが日々あります。ご家族の前で失礼なことを言いますが、彼も必ずまたします。彼の周りの人間として、それは心得ていてください。説明としては以上になります。これからの流れについて何かご質問はありますでしょうか」
私はただ、涙を流しながら首を振った。義母はひたすらに俯き続け、義父も厳しい表情のまま口をつぐんでいる。
「それではこれから昨日お伝えしました通り、奥様立ち会いの元で車内の捜索をさせていただきます。その後、おうちの方にもお邪魔させていただきたいと思っています。では準備をしてまいりますので、少々お待ちください」
警察官が席を立つと、再び静寂が訪れた。震えている義母の腕をそっとなでる。あげられた視線に、私は泣きながらも無理やり口角を釣り上げた。
「大丈夫です。大丈夫」
言いながら、何が大丈夫なのか自分でも分かってはいなかった。あるのは今ここで、私が打ちひしがれていてはいけないという使命感だけだ。
お互いの大切なものを、お互いに大切に。
それは私たち夫婦が常に心がけていたことだった。夫の大切な家族を支えられるのは、私しかいない。
その使命感だけが、何とか今の私を形作っているような気がした。
警察署を出ると、眩しい陽が目を突き刺した。気力は既にこれまでに無いほど消耗しているが、休んでいる暇などない。
義父母には先に自分たちの自宅に戻ってもらうことにした。家宅捜索が終わり次第連絡するという段取りだ。
しばらく待つと、先ほどの警察官がもう1人の警察官をともなって現れた。「では」と義父母と別れる。義母は横断歩道を渡りながら何度も私を振り返っていた。
「コンビニの方には昨日『明日まで車を置かせて欲しい』と伝えてありますので。ただ先方の都合上、終わり次第早めに動かしていただきたいようです」
「わかりました。ほんとうに、ほんとうに申し訳ないです」
ただただ詫びることしか出来ない私に、警察官が「あの」と声をあげた。
「僕らは、奥様を含めてご家族も被害者だと思っています。本当にお辛いでしょう」
言葉に、一度は止まった涙が溢れる。
「私たち、2ヶ月前に入籍したばかりなんです。あのときはまさかこんな……」
言うつもりのなかった言葉が、優しくされて漏れ出た。ふたりの警察官が揃って目を見開きお互いに視線を交わす。
「それは、本当に……」
それ以降の言葉は彼らの口から出なかった。それでいい。きっとどんな言葉をかけられたとしても、私の気持ちが晴れることなどないし、晴れることなどあってはいけないのだから。
警察署から歩くこと数分。見覚えのある車が見えた。
「奥さん、読み上げませんので、手短に確認をお願いします。こういったことで今からお車を調べさせていただきます。よろしいでしょうか」
歩道の行き交う人から私を隠すように立った警察官が書類を見せる。私はろくに確認せず「お願いします」とだけ伝えた。
「もし見覚えのある人が通りかかったりするようでしたら、何も言わずに場所を移動していただいて構いませんので」
どこまでも彼らは私を気遣う。それが逆に今は辛かった。
車内の捜査はこちらがあっけなく思うほど直ぐに終わった。時間にして10分もなかっただろう。
「特に車内に怪しいものはありませんでした」
そう言って鍵を返してくれた。
「私たちは一度署に戻ってからお家に伺いたいと思います。奥様にはお車で帰っていただいてお待ちいただければ」
家宅捜索。
ぐっと、手のひらの鍵を握りしめた。
車に乗り込もうとした時「あの」と声がかかった。
「くれぐれも、くれぐれも運転、お気をつけて」
口をつぐみ、会釈で返して運転席に乗り込む。
乗り慣れたシートの感覚。見慣れたフロントガラス越しの風景。
ドリンクホルダーには中身のないコーヒー缶が入っていた。助手席にはプレゼントして以来、気に入ってよく被っていたキャップが放置されている。
片付けろと何度も言ったのに、全部、そのままだ。
慟哭になりそうな泣き声に口を塞ぐ。出口を失った感情が暴れるように、ハンドルに突っ伏した身体が何度も跳ねた。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
