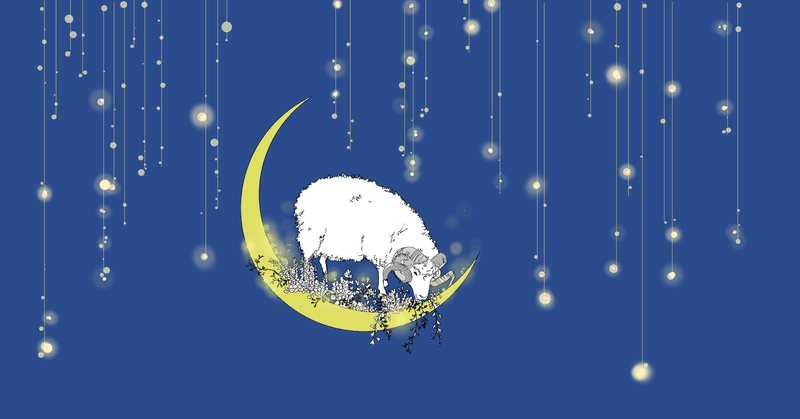
眠りながら歩くように
「あなたの幸せを実らせてください」
最後の日に彼女が選んだ別離の言葉。それは、二人で果たせなかった、不定形の時間を固めて作る幸せというものの結実を願うものだった。
「祈らせてください・・・・じゃないんだね」
なるべく声が固くならないように、優しい顔を作ろうと心掛けてはいるのだが、それもうまくいかない。
「残念だけど、別れるその瞬間に、その約束は多分できないかな」
「約束が欲しいわけじゃないの。この言葉が、今はもしかしたらふさわしくないかとしれないということは私も思う。でも、今の私があなたに望むものは、この言葉なの」
願いというものは口に出してしまうと叶わなくなってしまうという話を聞いたことがある。同時に、言霊というものが言葉には宿っていて、それが思いを現実に伝えると言う考え方もある。
「幸せになるってことが、君と幸せになることができなかった結果としての現在を受け入れることの先にあるってことなら、すぐにそんな気持ちにはなれなさそうだ」
彼女は僕の視線に強い眼差しを重ねたま、ふぅっと小さく呼吸をした。
「誰かに対して願いや想いを託すってことは、簡単なことじゃないし、それが前向きなものであれ、重苦しいものであれ、言われた方はその重さを一方的に背負わされることになるって思うんだ私」
長い三日月のような、アーモンド形の瞳は乾いてはいない。でも潤んでいるわけでもない。フェアを求める彼女の性格は、この最後の時間も変わらない。変わらない彼女がいて、変われない僕がいたから、この日を迎えることになったのだろうけれど。
「でもね、私はそれでもあなたに、あなたの幸せを実らせて欲しいと思うの。多分、これまでのように話せることはないし、あなたは私に会いたくないと思う」
「そんなことは・・」
「ううん。あなたは会いたいと言ってくれることも、実際に私が望めば、これまでを一旦、これまでの時間を一旦横に置いて会ってくれるのかもしれない。私が弱音をこぼせば、励ましてくれるかもしれない」
でも、それは私の願いではなく、あなたの幸せを実らせることにはならないと思うのと彼女は言った。
「僕は君と・・・今更何を言っても説得力もないかもしれないし、過ぎた時間を巻き戻すことはできないけれど、君と幸せになりたかったよ」
「それは私だって同じだった。いや違うのね。あなたはあなたで、私は私でそれぞれのやりかたで、同じ時間を幸せという画材を使って絵を書こうとした。とても嬉しいと思ったこともあったし、それが苦しかったこともある」
柔らかで、少し癖のある紺色がかった髪に右手を触れながら、彼女は少し寂しそうに笑った。
「だから、私は勝手だけど、あなたに幸せになってほしいと思う。それは、あなたが出会う別の誰かとって意味じゃないの。それが含まれることもあるかもしれないけれど、あなたがあなたとして過ごす時間、あなたの願ったことが結びついて、幸せを感じる瞬間が来るように・・・」
ひっと呼吸が抜ける音、静かに落ちる水滴。それでも、彼女は言葉を止めようとしない。
「あなたの、幸せを実らせてください」
幸せがどんなものか僕にはわからない。わからないまま、好きという感情とそこに混ざった欲望との勢いを借りて告白して、1年半という長いのだか、短いのだかわからない時間を彼女と過ごしてきた。楽しかったと思ったし、単純に楽しくなくなってからも相手を大切と思う気持ちは消えていなかった。
だけど、僕はその気持を押し付け、彼女は彼女の流儀を捨てられず、大きなぶつかりなんてものがないままに、少しずつ見えないまま破綻は広がり続け、気がつけばもう手の付けられない状況に二人は立ってしまっていた。
「僕は、僕の幸せを君と感じたかったよ。できれば君と同じ時間をもっと過ごしたかった。でも、一緒にいて笑うことが少なくなっている君を見ているのが辛かった。言葉が無重力状態の中で、君にそのまま届いていかずにふわふわと浮いているのが苦しかった」
こんなにも、彼女の言葉は出逢った頃と同じでまっすぐに届いてくるのに、僕は最後の時間、この時ですら気持ちを前に届けることすらまともにできない。
「そうだね。だから、あなたが幸せそうに見えないことが私も苦しかった。あなたが別れたいと言う前に、私があなたから逃げるように別離を提案したの。気持ちが同じままではいられないってわかっていても、それを求めてしまうのは弱いよね。私もあなたもきっと」
空気が軽くなったような感覚。
彼女は座っていた椅子から立ち上がり、僕の前に立って、僕の額に額を当てた。それから、すっっと横を通り過ぎ、玄関のドアを明けて出て行った。
彼女の香りと、最後の言葉。
「私は祈らない。ただ願うの。あなたがあなたの願う形の幸せを実らせてくれるってことを」
そして、ありがとうと掠れるような声を残して、彼女は出て行った。
僕は彼女の幸せを、別れる、別れたその日に寝返るほど強くも優しくもない。これまでの日々も、実らせるべき果実がどんなものかさえ考えることができない現在、どんな種を蒔けばいいのかすらわからない。
それでも、最後に彼女が願ったことを、残してくれたこの痛みを、失くしてしまうことはしたくないと思った。彼女の幸せを僕はおそらく、届くことはなくても祈ってしまうだろう。思い出して苦しくなって、酸素マスクをするように、息継ぎをするように、彼女が幸せであるようにと、届きはしない身勝手な祈りを何かに捧げてしまうこともあるかもしれない。
彼女は祈らない。ただ願っていると言った。
祈ることと願うこと。それは同じようで、きっと別のことなのだ。眠りながら歩くことと、歩きながら眠ることが結果として同じであっても、別のことであるように。
僕は祈り、歩きながら眠ってしまう。彼女はおそらく眠りながらでも歩いて行く。意志を持って前へ進む事を選んだ彼女が僕に願ったこと。僕の幸せを実らせてほしいということ。
僕は祈る。彼女の願いを僕がいつか実らせることができますように。彼女の気持ちを踏みにじることがありませんようにと。
その時、そこに向かう自分が眠りながら歩くように、自分自身の気持ちをぶつけるだけじゃなく、誰かの気持ちを受け止めることのできる人になりますようにと、そこで僕は祈りではなく、願った。
一人分の場所が空いた部屋。僕は背伸びをしてから、その空白を埋めるように疲労感と寂寥感から逃れるように横になった。上を向いても涙はこぼれ落ちた。気持ちは歩こうとしている、でも涙は溢れる。だから、少しだけ眠ろう。
眠った後、歩く気になったら、その時はその時で考えようと思った。眠気は優しく、そしてゆっくりと僕を包み込んでいき、西日に照らされた身体は熱を放ちながら、静かに沈んでいくようだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
