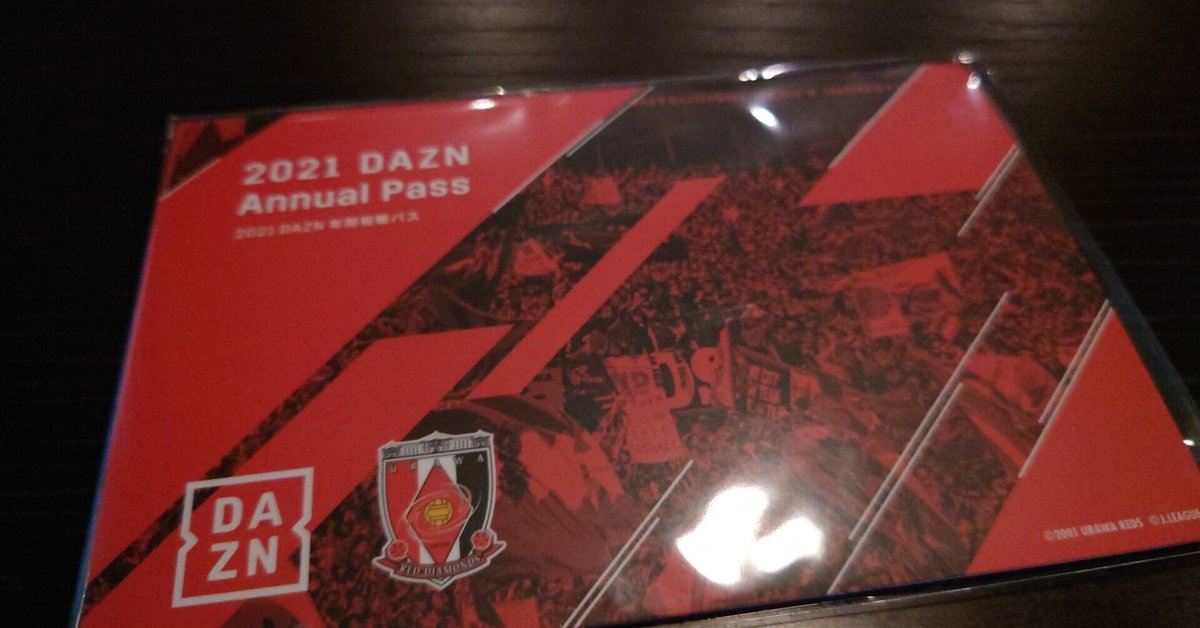
【横浜FMvs浦和】速度×【J1リーグ 第4節 感想】
サッカーと赤菱を愛する皆様、こんにちは。
前回の感想で「鳥栖と横浜FCのハイブリッドの様なチーム相手にどのような戦いを見せるのか楽しみ」みたいな事を書いたくろだです。
結果は3-0の完敗だったわけですが、横浜FMの前線のプレスの圧力に試合開始から圧倒され続けて試合の大勢を決められてしまった形となりました。
試合の大まかな展開や構造についてはらいかーるとさんのブログを読んでもらえばサクッと把握できるとは思いますが、今回も試合を見ながら感じた事と、SPORTERIAさんのデータをその実感との距離を測る試みをやっていこうと思っています。
いやはやしかし、このタイミングで当たれたことを良しとするか、後にしてよと思うかは分かれるでしょうなぁ・・・次は札幌、川崎Fですしおすし・・・うぬぬ。
スタメン

【横浜FM】
前半25分 ティーラトン⇆小池
後半17分 前田⇆オナイウ M.ジュニオール⇆渡辺(皓) 中川⇆水沼
後半35分 エウベル⇆天野
【浦和】
後半0分 伊藤(敦)⇆田中(達) 阿部⇆金子
後半20分 汰木⇆関根 杉本⇆伊藤(涼)
後半31分 小泉⇆柴戸
試合雑感
序盤はお互いの主導権争いの様相として深さをとりにかかろうとする両軍。
浦和は杉本をターゲットにロングボールを配球するもセカンドボールの回収が上手くいかず、どうにか起点を取ろうとしても仲川・前田・エウベル・M.ジュニオールの機動力の前にクリーンにボールを保持することが出来ません。
早々の失点もサイドに流れた杉本へのボールが通らなかった事を皮切りに逃げ道を失ったボールが苦しい体勢を強いる事によって生まれました。
事前のスカウティングで前線のプレスに対して何か注意事項があったのかもしれませんし、現時点での浦和のビルドアップが実感として早い展開で十分に表現できないと思っていた可能性もありますが、ナイーブな試合の入り方だったな、という印象があります。
失点後も浦和は機動力で横浜FMに後れを取りながらもボール保持・非保持両面で横浜FMの牙城を崩そうと奮闘します。
前半14分のビルドアップからの流れは非常にポジティブなもので、伊藤(敦)がディフェンスラインとボールを交換しながら杉本への楔のパスを入れた場面なんかは高いインテンシティでプレスをかけてくる相手をしのいだ先に見たいプレーの一つでありました。序盤に失点せずに耐えることが出来ていたらもう少し拮抗した展開が見られたのではないかと。
前半を見た感じでは浦和はハイプレスを基本とはせずに中央を絞ってサイドへ配球させてボールを刈り取るという形が主となっていた様に思います。
18分のカウンターのシーンなども明本がサイドへのパスコースをうまくケアできていた所からのプレーでしたが、ミドルサードでサイドに追いやることが出来ていた状態では横浜FMの攻撃をしのげる場面が多く見られました。
こうしてみると、ある程度の形が出来ていればそれなりに凌ぎ合っている展開に持ち込む事が出来ていましたし、横浜FMのプレスへの対処方法がこの試合を決定づけたと言えるのではないでしょうか。
序盤の横浜FMのプレスはゴールキーパーやセンターバックへのバックパスをスイッチにして2度追いしながら利き足側を制限、ボールの逃げ道を苦しくさせるような形を取っていました。
対する浦和はボールのコントロールで相手の軸を外す事が出来ればクリーンにビルドアップを進めることが出来たとは思いますが、パスの速度だけでなく総合的に「ボールを保持する勇気」が求められる状況を受け止める余裕を横浜FMに奪われてしまったのは主導権争いの中ではマイナス要素として大きかったのだろうと思います。
ティーラトンの負傷交代後に喫してしまった失点も、ビルドアップ阻害によって余裕がドンドン失われてしまった事から最終的に伊藤(敦)がボールを失う事になりましたが、これは伊藤(敦)のせいではなく、構造的に仕方のないロストだったと思いますし、たらればで言えばボールタッチの瞬間での駆け引きなどで交わす事が出来たらと思いますが、それが出来るなら既にビルドアップで主導権を握られる事もないだろう、という話でもあります。
伊藤(敦)はブスケツじゃありませんし。
小泉降りすぎ問題について
後半に入り伊藤(敦)と阿部が下がり、田中(達)と金子が入った事によりボランチの位置に金子と小泉が並ぶ形になりましたが、ここ数試合で言われていた「小泉降りすぎ問題」に対する回答を探す過程という事なんだろうと思います。
これまでインテンシティの高い相手との試合ではビルドアップ時に小泉が下がってサポートをする動きにあわせて杉本が中盤まで下りてターゲットとして仕事をする一方、最前線に人数を送り込めない問題が発生していました。
ビルドアップの構造的な問題でもあり、単純なアスリート能力の問題でもあり、理由としてはひとつだけではない話だと思いますが局面ごとに適切な人数バランスを維持するという事はすなわち各局面で優位性を確保しつつ前進するという事でもあります。
FC東京戦で見せた初手で深さを取り、橋頭堡をとっかかりに中盤がサポートで動く、という状況を維持できれば自然と陣形は前に寄っていきますし、逆に深さを取りきれない状況で相手に深さを取られた状態では陣形は後ろに寄ります。トランジション合戦では各フェーズでの深さ獲得の総和が多いチームが陣形を押し込むことが出来ますし、膠着した展開では相手を引き込んでひっくり返す、相手のポジションをズラして深さへのコースを作る事で決定的な深さを得る事が出来ます。
今回の小泉のボランチ(センターハーフ)での起用はポジション移動に伴ったエリアの影響力の低下とも言い換えることが出来る話であり、結果として今回の試みが成功したかと言うと難しいのではないかと思います。
金子がビルドアップ時にボールを受ける、散らす、といった動きを以前に比べてやれる事を見せた事はポジティブですが、小泉が受けた先にどのように展開できるか、という部分でバランスを見出す為に求められる試行錯誤はまだ続くのかなとも思います。
この問題が西の復帰で解消されるのか、そもそも山中はハーフスペースに陣取る必要があるのか、中盤の構成はトップ下に明本を置くとして機動性を見た時にどう捉えたら良いのか、それとも武田(英)や伊藤(涼)、武藤などが杉本の相棒として杉本のタスク軽減に寄与できるのかどうか、サイドで汰木や田中(達)が出来る仕事をどれだけ増やせるか、などなど考えられる組み合わせは少なくありませんが、どれが解決に直結するかは蓋を開けてみないと分からない、という所なんじゃないかなと。
リカルド・ロドリゲス監督がどの様な解を見出すのかに注目ですね。
柴戸について
最後に柴戸について触れて終わりにしようと思います。
ユニフォーム買ったし。
やっとリーグ戦で出場機会を得た柴戸ですが、J1の強度に慣れているからかビルドアップ時にボールを受けた時の余裕具合がだいぶあったな、という印象でした。
もっと展開を加速させる為に動ける場所はあっただろう、とも思いますが中盤でコンビを組む事になった金子との相補性が見られるかどうかはタスクの割り振りによるのでは、という所なのかなと。
すでに大勢が決してしまってからの出場ではありましたが、この状況からボールを受けて前を向けるかどうか、ワンタッチでパスを受けられるポジションを継続して取れるかどうか、という部分で向上すればまったく問題なくチームに貢献できるのではないかと思います。
柴戸の運動量を活かすために早急な動き方のレベルアップが望まれる訳ですが、良い判断が追いついてきた先に柴戸の大ブレイクが待っていると期待したいと思います。
今日はコンサドーレ札幌との試合が待っていますが、早速スタメンのバックラインの配置が話題になっていますね。
ビルドアップの課題解決に早速回答を付けてきたのか、それともコンサドーレ札幌対策としてだけの配置なのか、試合開始が待ち遠しいです。
(僕はリアタイ出来ないので、後で確認となりますが・・・)
それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
