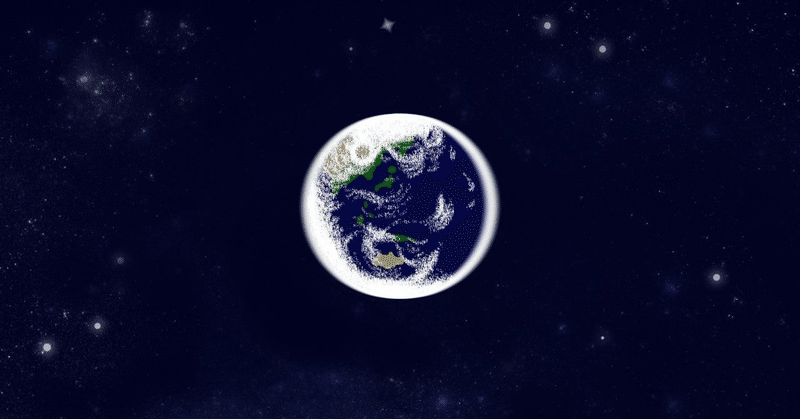
【完全版】月の男 第8話
みんなはまだ武道場にいるようで、更衣室に戻ってきている部員はいなかった。もしかすると、みんな私に気を使って、一人にしてくれているのかもしれない。そう思うと、ことさらやるせない気持ちになった。更衣室で少し冷静になり、徹夫に悪いことをしたかな、と考えながら外へ出ると、当の徹夫は更衣室の外で、じっと待っていた。
「……なに。覗きなの。京子ならいないわよ。」
「違うよ。」
私の嫌味なのか、苦し紛れの冗談なのかわからない発言をあっさりと流し、徹夫は歩き始めた。
「家まで送るよ。」
徹夫は振り向いて、また歩き始める。私は黙ってその後を追いかけた。
「あ、できれば僕より前を歩いてくれない、かな。僕、桂野さんの家、知らないし…。」
ふうっ、と私はため息をつき、徹夫の横に並んだ。お互い無言で、館のある丘のふもとまでの道を帰って行った。
徹夫は、丘のふもとで趣のある洋館をひとしきり眺めた後、じゃあ僕は帰るね、と言って、小さく手を振りながら帰って行った。私は家の中に入る前に、ふと裏庭に回ってみた。そこには、まだつぼみのつく気配のない桜の木が一本、変わらない様子で立っていた。幼い、まだなぎなたを始めたばかりの頃、この桜の木の幹を相手に、打ち込みの練習をしていたっけ。
家に入ると即座に階段を上がり、自分の部屋へ向かった。横目でちらりと例の絵を見たが、もはや黒い塊にしか映らなかった。部屋のドアに、父親がどこかのホテルから拝借してきたという「起こさないで」と書かれた銅製のプレートをかけ、バタン、とドアを閉める。そのまま私はベッドに倒れこんだ。
いつも闇に包まれている『月の世界』だが、今日はいっそう陰気に見えた。足元の砂からも、これまでのような輝く白さは消え去り、どこかくすんで、灰色っぽくなっている。
『月の男』は、私が現れたのに気付いたようだったが、両腕を組んだ姿勢を変えず、何を考えているのか全く読み取れない表情で、静かにこっちを見ていた。私は一歩、また一歩と、ゆっくり男の方へと向かっていった。足が重くて、なかなか進めない。奇妙な重力が、いきなり両足に圧し掛かっているようだった。
私はやっとの思いで、男の真正面にたどり着く。そして、男の顔をじっと見上げる。
男の赤い瞳と、帽子の赤いリボン。その部分だけが、暗闇の中でやけに目立って見える。
「おつかれ、お嬢ちゃん。」
『月の男』は表情を全く変えずに言った。
「……つかれた。」
ぽろり、と口からこぼれ落ちた飴玉のように、その言葉がふいにこぼれ出た。
「つかれた。もうつかれた。」
私はどさりと砂の上に膝をついた。耐えがたい重力が、両肩にも圧し掛かっているようだった。かすかに舞い上がった砂埃は、まるで煤か灰のように見えた。
「どうして? 何もかもうまくいかない。私は師範先生みたいに勉強なんかできないし、京子みたいに自分の限界を超えるまで努力することもできなかった。暴れるあの二人を止めることもできなかったし、篤子やユキには助けられてばかり。なのに、あんたのことを信じてもらえないからって、変な距離感を感じちゃったりして。ばかみたい。なぎなたでも結局勝てなかった。あれだけ自信あったのに、代表になんてになれなかった。弱かった。そう、私は弱かったのよ。力不足なだけじゃなくて、自分に甘えきってた。なぎなたそのものも、私の心も弱い。なぎなただけじゃない、学校生活はむちゃくちゃだし、家にいても窮屈な思いをしてるだけ。おまけにこの夢の世界。いつまでも消えない、いつまでも抜け出せない。あんたの正体をつかもうとしても、あんたをなぎなたで倒そうとしても、何もかも、すべて、うまくいかない。弱い、弱い! 私は弱い‼」
突然とめどなく溢れ出してくる言葉の数々を、自分でも止められなかった。というよりも、止めよう、と思うより前に、これまで心の奥底にせき止められていた言葉が濁流となって押し寄せて、口を動かし、私の肉体と神経すべてを動かしていた。
言葉の波を吐き出しながら、いつの間にか私は泣いていた。泣いたのなんて、いつ以来だろう。言葉と同時に、涙の粒もぼろぼろぼろと零れ落ちていく。
「これからどうなるの? ぜんぶの歯車が狂って。昔の私はこんなんじゃなかったのに。でも今は、違う。弱い。怖い。自分がこんなにもふがいないなんて、やっと思い知らされた。怖い。思い通りにならないことばかり。怖い! 世の中の全部が、暗闇みたい。まるであんたの存在みたいに!」
私は灰色の砂をギリイッとつかんだ。悔しくて、怖くて、何度も何度も砂を力いっぱいにつかむ。形を持たない砂のかたまりは、私の手の中で気味の悪い音をたてて、手のひらの皮膚に食い込んだ。
『月の男』はそんな私を、昨日までの自分とはまるで豹変してしまった私を、何も言わずじっと見つめているようだった。私は下を向いて、砂をつかむ自分の両手を見つめていたが、男の視線を絶えず首の後ろあたりに感じていた。
「……ごめんなさい。あんたのせいじゃないのにね。」
私はうつむいたまま言った。
「あんたが現れてから、いろいろなことが起きた。教室をめちゃくちゃにされたり、理事長室が燃やされたり。あんたのせいだけど、でも、ほんとはあんたのせいじゃない。あのとき、篤子みたいに、すぐに佐之助と直哉を止められる力が私にあったら。ランプが爆発する前に、あんたをつかまえることができていたら。そもそも私が、鍵を持っているのをいいことに、理事長室なんか使わなければよかった。理事長の娘でいることに、口先では反発してたけど、まさか自分もそれに頼ってたなんて。これまで、理不尽なことがたくさん起きたけど、でも、あんたのせいじゃない。誰のせいでもない。…本当は自分の力が足りなかったせいなのよ。心のどこかで気づいていたけど、全部あんたのせいだと思いたかった。理不尽なことが起きるのが悪いんだって、思ってるだけだった。私は、何、も、できてなかっ、た…。」
私は嗚咽を漏らした。ひっく、ひっくとしゃくりあげる喉の動きが止まらなくなり、言葉がさえぎられてしまう。
「……とうとう心がへし折れたか。」
『月の男』は静かに言った。私はただ、泣きじゃくるだけだった。
どのくらい時間が過ぎただろう。どれくらいの涙が砂に飲み込まれていっただろう。
涙が枯れるほど泣いたせいか、私は次第に落ち着いていき、体から溢れ出すのは嗚咽からすすり泣きへと収まっていった。
「いいかい、お嬢ちゃん。」
『月の男』が私が落ち着くのを見計らったかのように、そっと口を開いた。
「これが、『絶望』と、それに伴う『挫折』っていうもんだ。」
絶望。挫折。
私は男の言葉を反芻した。二つの言葉を何度も何度も噛み締めた。自分がこれまで生きてきた中で、初めて強烈に味わった、二つの感覚。私はほとんど諦めの心境だった。
もう無理だ。この男に勝つのは無理だ。
この世界は、自分を取り巻く世界は、私の力ではどうにもならない。きっとこの男は、私にそれを思い知らせるために、私の前に現れたのだ。
「……わたし……」
私の、負けだわ。
その言葉を吐き出そうとした、その瞬間。
「……で、お前はここで、立ち止まるのか?」
男がふいに言った。
「――え…?」
「お前はここで立ち止まるのか、って聞いただけだ。」
あまりに意外な言葉に、私は思わず顔を上げた。涙のしずくが、すーっと頬を滑り落ちていく。『月の男』は何食わぬ顔で、こちらを見ていた。
「なにそれ、あんたらしくない。」
私は着物の袖できゅっと涙をぬぐった。この男がこんな言葉をかけてくるなんて、変なくすぐったさがある。相変わらずつかめない男だ、と私は思った。『月の男』はじっと真顔で私を見つめている。赤い瞳を改めて見つめ返すと、そのルビーのような美しさに、少しドキリとした。
いつものつかめない態度なのに、なぜだろう、今日はこの男が少し優しげに見える。
この男が変わった? いや、もしかして。私はふっと思い当たった。
――もしかして、私のものの見方が変わったから?
「……今日の私も、私らしくないけど。」
泣きすぎたせいでじんじん痛む頭の中で、さっきの思いが、だんだん確信に変わっていく。そうだ、私が変わったから。この男に対する見方が変わったからだ。
もしかして、試験前にこの男が『私の世界』にしばらく現れなかったのは、この男なりの気遣いだったのだろうか。
これまでには思いもよらなかったような考えが、夜の闇をぽわっと照らすろうそくの火のように、静かに私の心に浮かび上がった。
「……私、もっと、できることをすればよかった。頑張ったつもりになって、勝手に限界までやってると思ってたけど、でも、もっと、やれたかもしれない。」
誰に向かって言うともなく、私はつぶやいた。
「あんたのことが信じてもらえないなら、諦めず信じてもらえるまで話せばよかった。なぎなただって、調子がいいからって慢心せずに、もっと努力すればよかった。まだまだ、他にも後悔してることはある……。」
私は体勢を変え、体育座りになった。ちょうど真正面に、ぼんやりと浮かんだ地球が見える。しばらく眺めていると、曖昧な輪郭が次第にはっきりと見えるようになってきた。だんだんと地球の青色が、油絵の具のようなべっとりとした濃紺ではなく、まるで海の底のような、透明感のある青色へと変わっていく。
ふと横を見ると、『月の男』も地球を眺めていた。やはりこの男をどこかで知っている、と私は思った。改めて真剣に向き合ってみると、どこか自分に似ている気さえしてくる。つかめなくて、少し怖くて、でも、どこか、懐かしい。この感覚は確かに知っていた。
いつの間にか私は、自分の心の中のトゲトゲしたものが、涙とともにポロリと取れて、洗い流されてどこかへ消えてしまったような、穏やかな心地になっていた。そのような気持ちで『月の男』の横顔を見ると、地球に向けられた彼の目は、どこか寂しそうにも見えた。
「……ねぇ、あんたはどうして地球を眺めているの? 絵の中で、ずっと。」
改めて思い起こしてみると、あの絵の中の男の背中は、真っ黒な不気味さだけでなく、真っ暗な悲しみを表現しているようにも解釈できる。
「あんた、もしかしてずっと、これまでこうしてきたの? 私に出会うまで、ずっと。」
『月の男』は二つ目の問いには答えなかった。しばらく沈黙があった後、彼は静かに口を開いた。
「あそこにはたくさんの人がいるからさ。そして俺は、お前を通さないとあそこには行けない。『お前の世界』に長くはいられない運命なのさ。」
男はいつもと変わらぬ口調で言った。しかし、その体を包み込む黒い衣服は、力なくはためいているように見えた。
「…もしかして、あんた、ずっとここに独りでいたの? 私と出会うまで、ずっと?」
私の問いかけに、『月の男』は曖昧な笑みを浮かべて首をかしげる。
「だったらこんなとこ、さっさと抜け出せばいいじゃない! あんた、私の世界にも来れるんだから! こんな闇の世界にずっといたら、私なら気が狂うわよ!」
「それはできない。」
男は自嘲的に、ふふ、と笑う。
「お前の心が引き寄せないと、俺はそっちに行けないんだよ、お嬢ちゃん。そして俺は、もうすぐ消える運命だ。」
「消える・・・?」
私は目を丸くした。
「なにそれ! 消えるって何よ。勝手に現れて、今度は勝手に消えようってわけ? 意味わかんない。散々騒ぎを起こしておいて。あの二人を撃ったり、ランプを爆発させたり、散々やっときながら!」
「おっと。」
ふいに男が、左手の人差し指を立て、私の口元に近づける。「しいっ」と言葉を遮るようなジェスチャーだ。
「ひとつ言っておくがな。俺はランプを撃ったりはしてないぜ。」
「え……?」
撃って、ない?
「どういうことなの?」
「そもそも俺は、初めから何もしてない。そりゃ、なぎなたやあの二人のガキは撃ったさ。でもそれは、きっかけを作ったに過ぎない。俺には『きっかけを作ること』しかできないからな。結果、なぎなたが倒れたのは、バランスの問題だし、あいつらが暴れたのは、あいつらの鬱憤が溜まっていたから。あいつらの心の問題さ。」
「でも、たしかにあのとき、火薬のにおいが…。」
私はあの時の出来事をゆっくりと思い出していた。たしかにこの男は銃を抜いていた。
「あの時俺は、なにもしてないぜ。引き金を引いてすらいない。」
『月の男』は銃の弾倉を開け、バラバラッと銃弾を砂の上に落とした。
「でも、じゃあ、どうして」
私の背後で起こった爆発。あの時、なにが起きたというのだろう。
「もうお前も、違和感に気づいてると思ったんだがな。」
すっ、と背筋が冷たくなる。この男が何もしていないなら、思い当たる原因は、わずかしかない。
「俺が『きっかけ』を起こすまでもなかったってことさ。あの力がさらに爆発したら、いったいどうなるのかねぇ。」
「ちょっと、それって、」
私の頭の中を、さまざまな可能性がグルグルグルと駆け巡る。そしてそれは、考えたくもないひとつの結論へとまとまっていく。
「さて、そろそろお目覚めの時間だぞ、お嬢ちゃん。」
男は上着のポケットから真新しい銃弾を取り出し、弾倉にそっと込めた。透明な、水晶のような銃弾。そして、『月の男』は右手を伸ばし、私の胸に狙いを定めた。
「さてさて、見せてもらおうか。絶望と挫折を味わったお前が、これからいったいどうす
るのかを。」
男は引き金にかけた指に、力を込める。
「果たして俺を――越えられるかな?」
はっ、とした。その男の言葉で、私の頭の中に散らばっていた推測の断片が、じわりじわりと互いにすり寄り、混ざり合っていく。
「あんたは――」
ズギュウウン!
私が口を開いた瞬間、透明な弾丸が私の心臓を撃ち抜いた。
(第9話へつづく)
