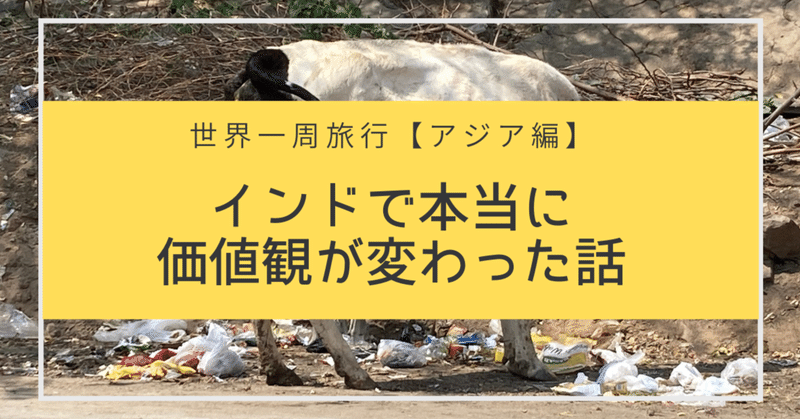
【予想外】インドで価値観が変わったけど、思っていた変わり方と違った話
「インドに行くと価値観が変わる」
もはや耳タコな言葉である一方、日本人や外国人に関わらず、多くのインド経験者が「インドは良かった!」とたしかに絶賛する。
そこで2023年3月21日、バックパッカー兼ノマドワーカーをしている僕が、ラオスからタイのトランジットを経て、インドに向かった。
「本当に価値観が変わるのか?」
それを実際に体験するために彼の地に飛んだ。
「本当に価値観が変わるのか?」は、タイトルに書いた通りだ。
しかし、思っていたような変わり方とはまるで違っていた。
皆さんも聞いたことがあるのではないか?
「インドは貧富の格差がすごいうえに、それがハッキリと目に見える。お金持ちの家を横目に飢えに苦しむ人がいる」
「ガンジス川のほとりでいくつもの死を見かけた」
日本では決して見られないショッキングな情景が自分の価値観を変えた、ということだろう。
少なくとも、僕が想定していた(期待していた)価値観の変わり方は、そうだった。
が、僕の場合はそうでなかった。
極端な金持ちと貧しい人との対比や、生死の境界を見たわけでもない。
「インドの普通の人」が、僕の価値観をぶっ壊したのだ。
どのように変わったのかを書く前に、まずは「インドの普通の人」をしっかり説明したい。
※もちろん「普通の人」など定義しようにもないので、「僕が会った人の傾向」程度に考えてほしい。そして「僕が会った人=ホテル従業員、タクシー運転手、ツアー会社の人」、つまり商売人が多い。
彼らはとてもフレンドリーだ。
はじめて会った外国人に対しても、まるで友達かのように話しまくってくる。
特に商売人は信頼してもらい、商品を買ってもらおうと、チップを弾んでもらおうとするために、色々と教えてくれる。
しかし商売人以外、本当に街行く人も気軽に「日本人か?」と言って話しかけ、結婚しているか、子供がいるかと聞いてくる。
名前だけ聞いて、その後に名乗って去っていく人もいる。
笑顔で握手だけしに来る人もいる。
とにかくフレンドリーだ。
ちなみに「結婚している?子どもいる?」のような超プライベート質問をする背景にはカースト制度の影響があり、そういった質問から相手の階級を判断しないと、落ち着かないそうだ。
つまり相手がどういった人間なのか知らないと話しづらいのだろう。
とは言え、どういった人間かわからずとも、まず話しかける精神は個人的に見習いたい。
一方で、「金くれ」という人も多い。
商売人に話を戻すと、9.9割がぼったくろうとするし、チップを渡せば「足りない」と言ってくる。
どこの国でも「日本人=金持ち」のイメージのため、あきらかに高い値段を言われることには慣れている。
東南アジアでもそうだった(チップはツアー以外では基本的に払わないが)が、それでも皆が皆、インド人のように「金くれ」ではなかった。
東南アジアでも、そして日本でもぼったくったり、「金くれ」と言ってきたりする人は、「良くない人(気持ち的には「悪いやつ」)」と認識してきた。
しかし、その一方でインド人が気さくで、とにかくフレンドリーなのも事実だ。
日本人に「あなたはフレンドリーですね」と言えば、100人が100人、褒め言葉と受け取る。
つまり、僕の中で「インド人=金くれ(悪)・フレンドリー(善)」という、相反するイメージが生まれたのだ。
最初は困惑した。
支払い以上に金をよこせという人は、悪。
気さくに話しかけるフレンドリーな人は、善。
僕の中で反対となる人柄が、インド人には混在しており、しかもそれが普通なのだ。
「インド人は信用できるのか?できないのか?」
と考えた。
しかし、これこそが僕の固定概念だった。
・金くれ=悪
・フレンドリー=善
・人は悪と善のどちらか
すべて僕の狭い常識から生まれた判断だ。
そもそも「金くれ」自体、貧しい人にとっては当然の行為とも言える(その人にお金をあげる、あげないかは別)。
そもそも人は善と悪で区別できるほど簡単ではない。
さらに、そもそも僕がある側面だけを切り取って「こいつは善、こいつは悪」などと判断することもおかしい。
インド人はこれが普通。
相場をはるかに超えるチップを要求する人もいるし、その人がとてもフレンドリーな場合もある。
【普通が変わる】
【今までと違う基準で物事を考えるようになる】
これが僕の価値観の変化だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
