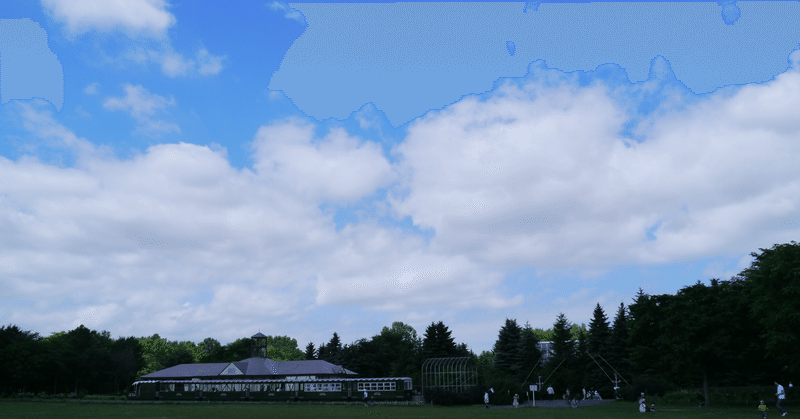
星空散歩(夏)〜マニア編
夏。暖かく日の長い季節ですが、望遠鏡で見ると素晴らしい姿を見せてくれる天体が多くあります。
望遠鏡をもって星空を散歩してみましょう。
---
<星空を説明するときは、上下左右ではなく、東西南北を使用するのが通常ですが、>
<わかりやすさを優先させるため、北半球で南を向いて立っていることを前提に上下左右でまとめています。>
<7月1日22時、8月1日20時、9月1日18時ごろの北海道札幌市で見える星空になります。>

夏は天の川が最もよく見える季節です。
望遠鏡を向けるだけで多くの星や星雲星団を見ることができますが、離れたところにも見ごたえのある天体が多くあります。
トップバッターは、夏と言えばこれ!という『ヘルクレス座』の球状星団『M13』です。
満月の3分の1ほどもある北天最大の球状星団で、美しさは全天一とも言われています。
(ちなみに最大の球状星団は、南半球にある『ケンタウルス座』の『ω星団』でしょう)
南中するとほぼ天頂付近まで上るため導入に苦労する天体ですが、その分大気の影響を受けることはありません。
双眼鏡でも見ることができ、10cmクラスの望遠鏡であれば、ざらざらとした星の集まりであることが見て取れます。
続いて『こと座』の惑星状星雲『M57』です。
『リング星雲』とか『ドーナツ星雲』の呼び名の通り、リング状に見えることからこの名前で呼ばれています。
寿命を終えた星が放出したガスが、残った中心星からの紫外線を受けて蛍光灯のように光っている姿になります。
ガスは球形に広がっていますが、遠くから見ているため、ガスの分厚い部分がリング状に見えています。
10㎝クラスの望遠鏡であれば、小さな環が浮かんでいる姿を見ることができます。
続いてこちらも同じ惑星状星雲で、『こぎつね座』の『M27』です。
『M57』の5倍ほども大きく広がった星雲で、鉄アレイに似た姿から『あれい状星雲』とも呼ばれています。
(私としては鉄アレイというよりは、丸いせんべいを両側からかじったような姿のほうが似ていると思っています)
近くに明るい星が無いため導入には苦労しますが、7.6等級と比較的明るいため、ファインダーでも見つけることができます。
10㎝クラスの望遠鏡であれば、丸く太っていますが、両側が欠けている姿を見ることができます。
つづいてちょっと変わった星並び(アステリズム)を紹介しましょう。
『こぎつね座』にある『コートハンガー星団』です。
6個の星がほぼ一直線に並び、その先に水滴がぶら下がるように星が並んでいる天体になります。
正体は『コリンダー399(Cr 399)』という散開星団ですが、真の星団ではなく、偶然恒星が集まったものと考えられています。
大きく広がっているため、双眼鏡向きの天体になります。
最後は観望会でほとんど間違いなく見る二重星3つです。
その3つは、『はくちょう座』の『アルビレオ』、『いるか座』の『γ星』、『こと座』の『ε星』です。
『はくちょう座』の『アルビレオ』は全天で最も美しい二重星ではないでしょうか。
はくちょうのくちばしの位置で輝くこの星は、宮沢賢治の銀河鉄道の夜のも「眼もさめるような、青宝玉(サファイア)と黄玉(トパース)の大きな二つのすきとおった球が、輪になってしずかにくるくると」回る、天の川の流速を測る観測所として登場します。
長く実際の二重星(連星)なのか、偶然同じ方向にある二重星(見かけの二重星)なのか分かっていませんでしたが、2018年に位置天文衛星「ヒッパルコス」と同じく位置天文衛星「ガイア」の観測データから、「見かけの二重星」であると結論付けられました。
2つ目は『いるか座』の『γ星』です。
『アルビレオ』のようが煌びやかさはありませんが、2つの星が10″ほどしか離れていないため、その姿が何とも可愛らしい二重星です。
3つ目は『こと座』の『ε星』です。
別名「ダブル・ダブル・スター」とも呼ばれ、かろうじて肉眼で見分けられるかどうかという2つの星それぞれが二重星である、「二重の二重星」になります。
小口径の望遠鏡でも二重星が二重になっている姿をはっきりと見ることができます。
どれも望遠鏡や双眼鏡で導入するには【慣れ】が必要ですが、見てみてはいかがでしょうか。
宜しければサポートをお願い致します。ご厚意は天文ボランティア活動の資金とさせて頂きます。 これからも星空に興味を持っていただけるような記事を書きたいと思っています。
