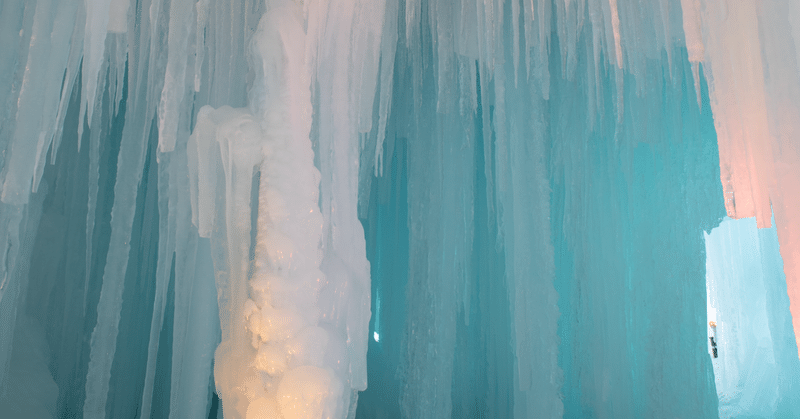
星空散歩(秋)〜マニア編
秋。日に日に寒さが身に染みる季節ですが、望遠鏡で見ると素晴らしい姿を見せてくれる天体が多くあります。
望遠鏡をもって星空を散歩してみましょう。
---
<星空を説明するときは、上下左右ではなく、東西南北を使用するのが通常ですが、>
<わかりやすさを優先させるため、北半球で南を向いて立っていることを前提に上下左右でまとめています。>
<10月1日22時、11月1日20時、12月1日18時ごろの北海道札幌市で見える星空になります。>

秋の星雲星団と言えば、なんと言っても『M31:アンドロメダ銀河』でしょう。
230万光年彼方、私たちの居る天の川銀河の「隣の銀河」になる銀河です。
明るさが4.4等級ですので、望遠鏡が発明される前から『M42:オリオン大星雲』と共に存在が知られていました。
実際、空の暗い所へ行くと、アンドロメダ座の「A」の星並びの左側の横に、ぼうっと光る天体があるのを見つけることができます。
M31が天の川銀河に所属する天体なのか、別の銀河なのかを巡る議論がありましたが、1923年にアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルが系外説を裏付ける証拠を見つけました。
双眼鏡でも望遠鏡でも、高倍率でも低倍率でも楽しめる天体ですが、観望会で小さな子供たちに見せるには、その淡い光のため、小口径ではやや不向きかもしれません。
続いて『ペガスス座』の鼻先にある『M15』です。
ペガサスの首をそのまま鼻先に伸ばした先にある大きく明るい球状星団で、変光星が多く含まれています。
7.0等級と明るいため、ファインダーでも位置が分かりますが、密集しているため、恒星のようにしか見えません。
10㎝クラスの望遠鏡であれば、中心が明るい彗星のように見えるかと思います。
『みずがめ座』の球状星団『M2』は、『M15』にほぼ同じ赤経にあります。
(もう一つ、『やぎ座』の『M30』もありますが、こちらはやや暗めなので、除外しています。)
『M15』よりわずかに大きく明るいですが、『M15』と異なり、変光星がほとんどありません。
6.9等級と明るいため、ファインダーでも位置が分かりますが、密集しているため、恒星のようにしか見えません。
『M15』と見比べると紹介しませんでしたが、『M30』も併せて見比べると楽しいかと思います。
『ペルセウス座』の二重星団『hーχ』は双眼鏡でもよく見える散開星団です。
『hーχ』というのは通称名のようなもので、正式には、西側のNGC869にh星、東側のNGC884にχ星と付けられたためになります。
要するに、最初は淡い恒星と思われていたのですが、望遠鏡を向けたら星団だったという訳です。
紀元前から存在は知られており、古代ギリシャの天文学者ヒッパルコスは「恒星ではない、かすかな光のかたまり」と記録しています。
2つの星団を同時に見ないと楽しみが半減してしまいますので、双眼鏡または、望遠鏡のファインダーで見るのがおすすめです。
最後は、秋といえばこれ!と私があげる二重星『アンドロメダ座』の『アルマク』です。
夏といえば『アルビレオ』となりますが、ほぼ天頂付近にあり、導入が難しいことがままあります。
そんな時でも、東の空の低いところに見えてきていることがある『アルマク』は、『アルビレオ』と比べても見劣りしない美しさのある二重星になります。
『アンドロメダ座』の【A】字の右側。登ってきた時だと下側の星のつながりの終端にあるのが『アルマク』になります。
オレンジ色の主星に青っぽい伴星が10秒ほど離れてくっついている姿は、とても美しいものです。
どれも望遠鏡や双眼鏡で導入するには【慣れ】が必要ですが、見てみてはいかがでしょうか。
宜しければサポートをお願い致します。ご厚意は天文ボランティア活動の資金とさせて頂きます。 これからも星空に興味を持っていただけるような記事を書きたいと思っています。
