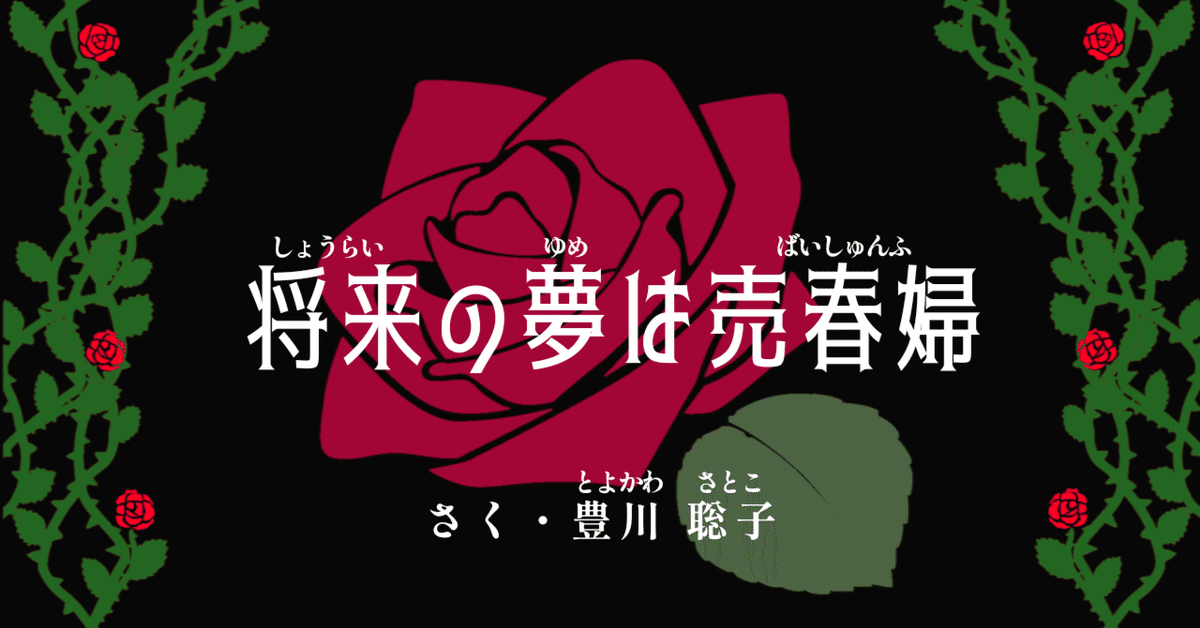
第16回「山谷・簡易宿泊所の聖者たち(下)」
隣の部屋のじじい、略してとなじじがなぜ毎日のようにお弁当など食べ物をくれるのか、当初の私にはまったく不可解でした。第14回で書いたように、食べ物だけでなく千円札とか、時には五千円札まで何も言わず渡してきたのです。五千円という金額は札幌では私が見知らぬ男にフェラチオをしてやっともらえる金額でした。
競馬で当てたとおぼしき時は、「もうかったから」となんと一万円をくれたときもあります。
なにか見返りを求めているのかというと、けしてそんなことはありません。
何故なら、お礼としてこちらからも食べ物のおすそわけをすると、まるで気をつかわせたのが申し訳ないというかのように、数日ほど顔を見せなくなるのです。
どうも生活保護費を使いきれないらしい、私以外にも何人かに同じことをしているらしいと察したときは、特別扱いでないことにホッとした記憶がします。女だから、かわいらしいからという理由でチヤホヤされるのはもうウンザリしていたので。
彼のやさしさを当て込んで、仲の良い別のじじいが彼に金を借りにくる声もよく聞こえてきました。
脳梗塞の後遺症で半身が不自由なとなじじは、ロレツもうまくまわらず、何度聞き返しても何を言っているか全く見当がつかないことも多かったです。
でもそのやさしいまなざしを見るだけで、彼が私を気づかっていることは分かりました。となじじが最初に教えてくれたことは、たとえ会話が成立しなくても、コミュニケーションは成立するときがあるのだ、ということです。
私が大量服薬で倒れたりといった騒ぎを起こしても特に何も態度を変えず、夕方になるとほぼ日課のように戸をノックして、
「メシ食ったか?」
と聞いてくれるとなじじ。
いままで私にとって男性は、2種類に分けられました。『もうセックスしたか、これからするか』です。相手が求めるか求めないかに関わらず、男性との関係を維持するためには、体を差し出すべきだと思っていました。逆に相手がそれを拒否すると、自分を否定されるようなすさまじい不安に襲われ、相手がウンと言うまでセックスを強要するときもしばしばでした。
彼は、見返りのセックスがいらないのに私を気づかって、世話をしてくれる生まれてはじめての男性だったかもしれません。父親ですら私を性的な目で見ていたのですから。
ドヤを出ていく直前にあいさつをしたとき、となじじは笑って言いました。「アンタ、長く居すぎたよ。2年か。2年は長く居すぎだ」
男性ではありますが、となじじはまわりの人を包み込むような母性があり、その逆に、ときに厳しく叱咤してくれた『ダブルスコア』の仲野さんの愛は、父性愛のようなものでした。
自分をおそった試練について順番に書いてきましたが、最後の『ラスボス』は、水際作戦を食らわせてきたあの台東区生活保護課でした。
タナボタとはいえイジメババアにも打ち勝ったことだし、大好きなとなじじや仲野さんとこのままずっとドヤで暮らすのも悪くないなと思っていたけど、ここで人間以外の思わぬ敵があらわれました。
トコジラミこと南京虫です。
私は入居から1年半ほどではじめて自室内で発見しましたが、聞けば仲野さんの部屋では入居当初からヤツは先住民だったらしい……。かゆみは無かったのですが、顔に噛まれポツポツと赤いアトはつくし、血まじりのフンが持ち物や衣服に消えない汚れをつけていくので、耐えられる環境ではなく、一刻も早く出ていく必要に駆られました。
引っ越しの準備をするため、自分で不動産屋をめぐり、物件を見つけ、転居費用を申請しました。しかし、福祉事務所ケースワーカーの真崎という男は、平然とウソをつきました。
「生活保護を受けていたら、台東区の外に引っ越しをすることはできません。台東区内で物件を探してください。」
ウソです。真っ赤なウソです。
調べれば秒でバレるウソです。
それを堂々と告げてきたのです。
おそらく、私の身柄を自治体から自治体へ移管する交渉作業が煩雑で大変だからでしょう。
社会のインフラから拒絶されることは、社会そのものに拒絶されるに等しい気分にさせられるのは『湯どんぶり栄』の入浴拒否事件で学びました。でももう「はい、そうですか」で黙るいままでの私ではありません。戦えば勝てるということを学んだのです。そして何といっても衛生権がかかっているのです。
自分の日々の食い扶持を維持するために、社会的弱者を公然とだますケースワーカー。
私は唖然としました。
とにかくたったひとりでも戦う必要があるため、法テラスに連絡し予約を入れたり、クレーマーのように長時間文句を言い続けたり、真崎の上司を出させて「弁護士を呼びます」と脅しつけることで、ようやく、
「本来は東京都の内規で決まっていることですが、今回は特例ということで……」
と、葛飾区への転出が認められ、転居費用を手にすることができました。
いつも誰かに守ってもらうことしか頭になかった私は、ようやく自分の権利を戦ってもぎとることを学び取りました。
そしてこの歪んだ社会という怪物と戦うには、自分も怪物にならなければいけないことも知りました。私はある意味、社会に適応したのです。私はケースワーカーに殺されかけました。自分を守るためなら、人殺しも許されるんだ、どんな悪いことでも許されるんだと正確に学び取り、私は力いっぱい真崎を怒鳴りつけてお返ししました。
いい子をやめること。悪人になること。それは自立のためにとても大切なことでした。
私はようやく白馬の王子様と出会えました。
私というお姫様を敢然と守ってくれる、理想の王子様。
それは私自身でした。そのことを知ったとき、私は別人に生まれ変わりました。
人に依存することも、人を支配することもやめることが出来たのです。新しい住まいとともに、生まれ変わった自分も手にしました。
そう考えると、山谷という底辺の街で私を転生させてくれた貴重な出会いは、やさしくしてくれたとなじじや仲野さんだけではないと気づきました。台湾ばあさんや差別銭湯、カッパのイジメババア、そして真崎。
むしろ私に害なした人々のほうが、私に戦うことの大事さ、強さを与えてくれた恩人であり、彼らこそがまさに宇宙が私に遣わした聖者であると感じています。
お別れがせまった日、私は仲野さんに言いました。「こんなハキダメみたいなドヤで、こんな素敵な人と出会えるなんて……」
仲野さんは笑いました。「あなたは、ハキダメに鶴よ。極上の鶴よ」
そして私に言いました。
「聡子ちゃん、ひとつ約束して。あなたはお母さんとまた会って」
「あの、でも……色々あったんです」
「分かってる、私だってそうだった。でも父親なんか他人だからどうでもいいの、お母さんとだけは会いなさい。私だってね、最初からこんなふうに強かったわけじゃないのよ……」
仲野さんにとてもお世話になっていながら恐縮ですが、私は心では母と和解していても、まだ、その約束は果たせていません。
ドヤから引っ越して、3年が経ちました。となじじとは毎年年賀状をやりとりしています。
何回かお土産を持って、お世話になった人々に会いにいくことがあります。
今年のお正月も、ドヤ近くの喫茶店でとなじじと近況を話し合いました。脳梗塞の後遺症以外は、体になにひとつ悪いところはなく、まったき健康そのものだそうです。テレビでのスポーツ観戦、競馬とパチンコが大好きな彼は、いまでも変わらず毎日楽しく過ごしているようです。
注文したコーヒーが届き、私はシュガーポットのふたをあけました。
「入れて」ととなじじが頼みました。
「3つくらいでいいです?」
私は彼のコーヒーに砂糖を入れてあげました。そのとき唐突に、とろけるほどの幸福感が体を満たしました。こうして彼のお世話をすることに何もいやな気持ちはしませんでした。むしろ、震えるような喜びでいっぱいでした。
小雨の降りしきる帰り道をひとり歩きながら、私はようやく気づきました。
私はあの男を心から愛している。異性として。
見返りのない愛を与えてくれたこの老人に、私もまた何ひとつ見返りを求めない愛を、生まれてはじめて感じている……。
最初に言ったでしょう?
この物語は、私の大好きなハーレクイン小説と同じで、ハッピーエンド保証なんです。
というわけで、長かったこの物語も、そろそろ幕を下ろします。
私たちの長い旅も終わりが近づいています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
