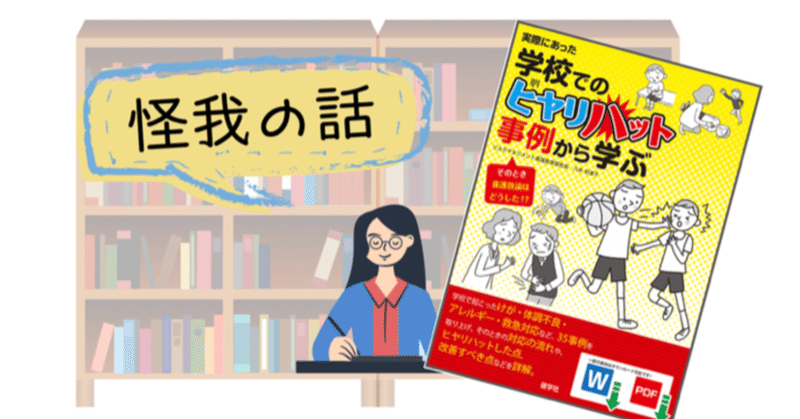
[参考書レビュー]実際にあった学校でのヒヤリハット事例から学ぶ①怪我編
最終更新 2022年9月19日
ツアーナース学習の一環として、学校のヒヤリハット事例を学んでいくべく参考書を読み進めています。
全て活かせる!とは言わずとも、ツアーでも流用できる予防策・知識など多々ありそうなので、内容に深く触れすぎて著作権に引っかかることの無いよう私なりのまとめを章ごとに。
要するに、長めのAmazonレビュー
となっているはずですが、なんかグレーだったらごめんなさい。所詮、ただの私の学習メモ的noteなので、微妙だったら速攻で消します。
というわけで、
当然、元となる参考書を読んでスルッとくるnoteになりますので、興味のある方は是非Amazonなり何なりで。読まなくても、まぁザックリは伝わるかと。
元ネタとなる本
公式の目次がいまいちなのでまとめました。

今回は、第1章けがを読んでいきます。
骨折
[肘骨折]跳び箱で転倒:小学生

普段から保健室対応が多く、多訴な児童の怪我。
「大袈裟なのかも」という先入観が受診判断の遅れにつながったとの事。
ツアーナースの場合、普段の様子を知らないで対応できるの?と揶揄さたりもしますが(昔、鍵開けてTwitterしていた頃は、ちょいちょいそれで叩かれていました)、逆に良い意味で先入観なく対応ができるかもなと感じた事例でした。
もちろん、普段の様子を知っているというお立場は、何よりも大きなアドバンテージではあるのはいうまでもなく。ポッと出のナースなんぞ敵いません。
ツアナスポイント
◆ツアナスと欠点として指摘されがちな“普段の様子を知らない“が功を奏すケースもあり。フラットな視点を武器にしようぜ。
[鎖骨骨折]自覚症状乏しく、他児童からの報告で発覚:小学1年生

傷病発見の過程が、低学年の怖いところだなとゾワっとしました。
ほぼ偶然が重なっての傷病発見となりましたが、正直これを見落としても誰も責められないと思う…。
補足 ツアーナースが小学校低学年以下を対応することあるの?
小学生の添乗=自然教室を行う、4〜6年生が対象メイン。しかし、私学だと小1から宿泊行事をやることが多いですし、それ以下の年齢層もあり。

幼稚園の遠足、保育園のお泊まり体験、スポーツクラブの合宿などツアーナースが同行する案件はあります。
他、激レアですが(コロナ前では)幼稚園で海外に行く案件🐨もありました。
大切な言葉・引用
子どもにとって、怪我の程度は関係なく手当を求める気持ちは同じ。(11p)
わかりにくい骨折
[尾骨骨折]組体操で転落:小学生

受傷起因と本人が一番痛がっている部分が微妙にずれていて、受診したら…という事例。確かに、視診で所見なく独歩もできていたら、確かにアイシングして湿布貼って様子見てしまいそうな事案はあります。
この養護教諭さんの場合、受傷後もこまめにフォローしていますし、保護者への連絡の上で受診にもつなげているので、骨折の発見が遅れた事例ともいえないような。見習いたいくらい最善は尽くしていますよね。
“普段の本人の気質や来室状況などの先入観から、間違った判断をしてしまうかもしれないという危険性をあらためて痛感“と、養護教諭さんの反省点として挙げられておりまして。2個前の事例と似たような。
いやいやむしろそこまで先入観に捉われず、万が一を考えて細やかに対応しているなと思いましたよ。
ツアナスポイント
◆受傷起因から想定される受傷部位、主訴とのズレなど総合的にアセスメント。悪化時の対応を担任(または旅行責任者)・保護者と共有する。
→とはいえ、抽象的かつ言うが易しでなかなか難しいけれどね。
[舟状骨骨折]手を地面につき捻る:中学生

平たくいうと、そんな受傷起因でまさか骨折しているとは!案件。本人拒否と、担任から家庭への連絡が遅くなってという不運もあり、クレームにつながってしまったようですが、類似事例はツアー中も起こりそうです。
現に私も、保護者へ連絡お願いしますと口頭でお願いしたものは、実は全く連絡がいっておらず、保護者から怒られたこと。同時に、学校が責任転嫁し全て看護師のせいにされたことがあります。
後の事例にも出てきますが、責任転嫁は割とあるあると考え(悲しいと同時に反感を買いそうだけれど事実として)、連絡方法と記録など対策は必要。
参考リンク:舟状骨骨折
ツアナスポイント
◆見た目ではわかりにくい骨折の特性を学び直す
◆神経症状など、決定的な状態があったら本人の主張問わず早めに学校、保護者へ連絡して受診につなぐ
◆各種連絡依頼時
具体的に何時までにと指定、確実に連絡がされたか最後まで確認
随伴事象が隠れていた、ボールでの怪我
[手指骨折]硬いボール、ソフトボールでの受傷:小学生

ボールを取り損ねて指先をかすめ、後から痛くなって保健室へ。
所見ないのでアイシング+湿布+固定の基本対応で、自宅帰っても痛かったら受診してね→骨折判明パターン。ありがちですよねー。
対応した先生の反省として“ボールでの怪我だし、子どもたちが原因を説明できたので、怪我をした現場を直接見に行くことを怠った“と書かれています。
状況によっては、逐一確認しにく時間もないかもしれませんが、受傷者・対応者それぞれの安全を守る意味でも、現場検証は必要なのだなと思いました。
私もツアー中、なるべく確認するようにはしていますが、今後はなるべくなんて曖昧にしないで怪我=受傷起因の現場検証・目撃者情報との照合はマストにしてきます。
大切な言葉・引用
成長途中の子どもたちにとって、骨折は骨の成長に関わり軽視できない怪我であり、機能障害を残すことは十分に考えられる。指の長さが変わったり、可動域に制限が出てしまう可能性もある。(18p意訳)
歯の外傷
[歯の陥入]壁に前歯強打:小学生

歯が短くなっている=折れただけでなく、陥入しちゃっていることもあるよ例。
症例レポート主である養護教諭さんは、メンタルケアフォローの重要性を仕切りに謳っていて。
確かにメンタルも大事な事だけれど、この症例で肝になっていることは、保護者間情報からセカンドオピニオンで誤診が発覚し、歯が復活したという部分なのでは?と思います。
歯の損傷って時間との勝負なので、まずはその処置と歯の保存方法・受診先の選定の重要性にもうちょい着目して欲しいなと思っちゃいました。
ツアーでも、単に宿舎近くのクリニックというだけで選ばず、宿舎の方に直接聞いたりネットの口コミや、HPを確認したりと、少ないヒントの中で受診先候補を各科数件ピックアップして臨んでいます。
実際、団体の言われるがまま近くの病院を選んで失敗し、セカンドオピニオンに至ったこともありますので、私は学校指定の受診先がない限りは結構口はさむタイプです。
先輩ツアナスの中には「ナースが具体的な病院名出すと、癒着を疑われてトラブルこともあった」と嫌がる方もいましたが、その辺は別に「癒着?んなわけないじゃないですか草」とかで流せる範疇かなと思います。
この事例を読んで、ますます近医の下調べ・情報収集の重要性を実感しました。
参考:私が経験した類似事例〜誤診からの実は系

部位や状況などフェイクを入れていますが、医師のクソ対応は事実です
通常、多くの場合ナースが受診同行はしないのですが
この時は
・他生徒が落ち着いていたこと
・学校指示、及び私自ら志願
・該当生徒の状態が明らかにヤベェ(折れている)
という状況から、担任と共に同行に至りまして。診察も、明らかにやる気なく、どうせ子どもが大袈裟に騒いでいるだけと、ろくに診もせず湿布対応。
私、半ギレ気味に(これは良くない)レントゲン依頼したところ、結果は案の定バッキリ折れておりまして。その場で紹介状書いてもらい、翌朝すぐに保護者お迎えで大きな病院へGO 入院となりました。
医師は「この状況でまさか骨折だなんて」と素人みたいな言い訳していましたが、まぁ確かに嘘でしょ?みたいな状況ではあったんですよね。でも、事実として腫脹・激しい疼痛・変形・熱感と明らかに所見あるじゃねーか!まず写真(レントゲン)撮れよ!と、看護師でなくともつっこみどころどのある診察でした。
他、本筋から脱線しますが
看護師が同行しない場合の受診時、引率教員にこれだけは聞き逃さないで!依頼して!というメモもお渡しして、再診という二度手間にならないよう配慮すること、非常に大事。この辺りは、以前ツアナスセミナーでも学んだことでもあり、私も割と初期から実践している基本的なことなのですが、ツアナスハックに入ると思うので後で具体的なことを追記します。
補足資料:歯が抜けた時の保存・リミット

ツアナスメモ
◆歯の陥入にしろ、折れたにせよ復元が時間との勝負のケースが多いので、各見学地から歯科へのアクセスは事前に調べたり、イメトレしておく。
頭部打撲 担任が軽視、連絡不備
[外傷性脳内血腫]遊具から転落:小学生

これはツアーでも起こり得る恐ろしいあるあるで、逆に養護教諭さんという学校サイドの立場でも同じ悩みを抱えているのか!と驚いた事例ですね。
明らかに受診が必要で依頼にしたにも関わらず、担任が軽視して結局…という。しかも責任転嫁付き。
ツアーナースこそ、責任なすりつけられる可能性が高い外部の弱い立場なので(経験あり)、後述する引用文は本当に重要。
大切な言葉・引用
報告・連絡・相談、そして記録が大切です。記録に残すことは、自分を守るためにも重要です。残念なことですが、責任逃れをされる場合があります。(29p)
脳震盪 受傷時の記憶がない
[脳震盪・頚椎捻挫]体育の授業で転倒、後頭部強打

激しく強打した故に、受傷時の記憶がなく「普段の片頭痛っす」という本人の主観のみしかヒントがなく、後々実は…という事例。
特に体育(ツアーの場合は、運動系レクやアクティビティ系)時の頭痛訴え関連は、本人の訴えのみでなく周囲の証言も確認する必要があるなとゾワっとしました。
結果的に大事には至らなかったとはいえ
このまま保健室休養で済ましちゃう方が多そうな事例と思われ。丁寧にアセスメントし、保護者の意見を鵜呑みにせず状況説明して搬送判断とした養護教諭さん、素晴らしい。
私も、スキー中に頭部強打からの頭痛・記憶障害の生徒の搬送事例に立ち会ったことがあります(初動でスキーパトロールの方が対応してくださった)。
大事な言葉・引用
◆高校生だから状況判断ができるはずだという先入観を持たないこと。(33p)
→高校生に限らず、大学生・成人・高齢者にも言えることですね
目の打撲 保護者からの対応不審
[視神経管骨折]体育の授業で壁に激突し顔面強打

養護教諭さんの対応は、スムーズかつベストだっと思うんですが、どうなんでしょ。せっかくこういった参考書なので、初期対応の良し悪しや改善点など、専門医からの評価コメント掲載も欲しかったところ。
眼科クリニックから、総合病院への受診は救急搬送にすべきだったと自責されているようですが、そこは紹介元のクリニック判断の範疇かと思うし。
後遺症が残ったことに関しても、それこそ初動の僅かな(と私は思う)タイムロスがどこまで影響したのか?後遺症が残ったことで、保護者からの不信感もという事態に陥っている案件であればそれこそ前述の通り、眼科医の見解が欲しいですよね。
この項目掲載の“養護教諭の救急処置能力向上させるためのチェックリスト(36p)“は看護師の立場でも同じなので、活用していきたいなと思いつつ、今回の事例ではこのチェックリストに基づいても対応は変わらない=最善と思うんですよね。
なんかそこまで養護教諭さんが抱えなければならないのか?とモヤっとしています。
関連・参考
頭部打撲 保護者報告が後手になった
[頭部打撲]教室で転倒:小学生

イレギュラーな事象が相次いで、学校から保護者へ報告するのが遅れ、保護者から問い合わせがあったケース。
怪我の内容にもよりますが、特に首から上の怪我は保護者連絡は必須。自分が手一杯な時は、他教員などに依頼することも大事かなと思いました。
私自身も、どうも仕事抱え込みがちなので気をつけねば。
頭部打撲後の観察事項。
簡単なパンフを保健室→保護者へ配布する場合も多いと思いますが(保健室代行勤務の時に、大体の学校であった)添乗中の対応でも準備しておいた方がいいのかな?と11年目にして気づくなど。


↑ツアー中であれど、頭部打撲は受診推進。
現実として「離団させてまで…。」と団体から拒否られたこともあり、口頭でこう言ったパンフの内容を説明し帰宅後の受診を促したり、看護師に責任をなすりつけられないよう記録を詳細に残したりと、手を尽くしました。
即席で、ざっくり作ってみました↓

実際渡す場合は、学校へこういったものをお渡ししましたと共有必須。
ほぼ受診はしていると思うので、受診結果の記載欄とかあった方がいいのかしら(受診前後に必ず担任から保護者へ連絡する)。
ツアナスポイント
◆家庭に経過観察を託すようなよくある傷病は、パンフを準備するのも一案かも。
現場判断で内々に処理され、対応が遅れた
[半月板損傷]部活中のウォーミングアップで受傷:高校特支

こちらの本タイトルは“部活動中の怪我による家庭連絡の不備“というものでして。確かにそうなんですが、根っこで問題となるのは“大したことないだろうと、顧問判断で帰宅させ養護教諭への報告なし。結果、帰宅後に痛み増強し受診したらどガチの怪我だった“という部分かと思い、タイトル変えました。
要は、受傷時に勝手な判断せず即報告してくれたら、応急処置・保護者連絡しいて受診判断につなげられたのに…って事ですよね。
他記事でも書いた気がしますが
ツアーでも、看護師さんに言うまでもないと思ってと、大きめの怪我をしれっと後から報告されたことがあります。その団体は、全体的に危機感ザルで何もかもおいー!って思うこと多々だったので論外でしたが、外部の看護師って部分で遠慮して報告が絞られる団体もあるのかなと。
逆に、そんな細かいこといちいち報告されても…と正直ゲンナリすることも無くはないですが、こういった事例を見ると「細かなことでも遠慮せずご相談ください」と呼びかけたくなっちゃいますね。
まぁ、報告がなかった時点でなんかあっても学校の落ち度になるだけなんで、こっちとしてはというドライな考えもできますが。この事例のように怪我した児童・生徒に不利益が生じないよう、ツアナス側でもできる限りの働きかけは必要なのかなと思いました。
ツアナスポイント
◆細かなことでも相談をと先生方への呼びかけ、声をかけやすい雰囲気作り(難しいな)など、可能な限りキャッチしやすい土壌を作っておく。
浅いまとめ
以上、ケガ系11の事例からツアーに活かせることを絞り出してみました。
ケガは、初期対応→悪化したら即受診をがベースになりつつも、その連絡がうまくいっていなかったり。
主訴に頼って事実が隠れ、搬送レベルだったことが遅れて発覚したり。
判断できたとしても、事の重大性が周囲に伝わらず受診が遅れたりなどなど、単純に教科書レベルの応急処置だけで完結しない、環境要因(?)も左右してしまうのだなと痛感しました。
関連リンク
