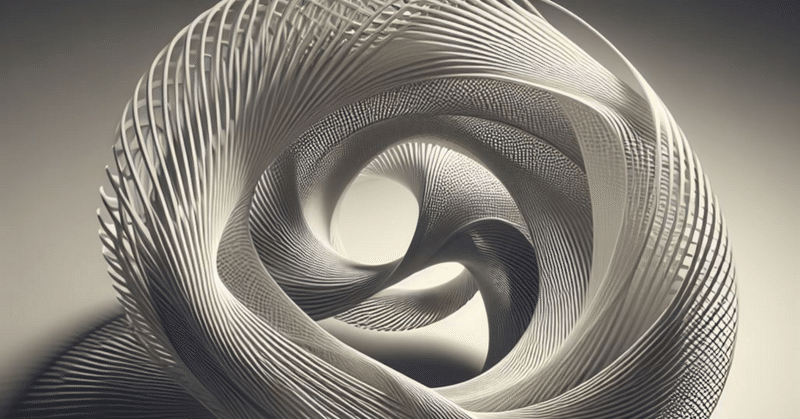
リヴァイアサンと私秘性 【人文学論考】
われわれは知の形式を分類することができる。いかようにも分類することができる。哲学の系譜や潮流から言っても、様々な学派が存在するというのは、もはや自明であるかのように思われてくる。科学や宗教、文学、日常のあらゆる生活の中でも、まとまったカテゴリーを形成してきた。それらカテゴリーが人間の思考にとって役に立ち、反対に役立たなくなったものは、時代の選別を経て、時に廃止されやがて衰退の一途を辿るのだということを見てきた。錬金術師は化学者に代わり、小作農民は機械労働者へと変貌した。革命によって市民権を得たこと、市民が国家との関係の中で動員されたこと、そのとき知は誰に愛され、誰を愛していたのかを、われわれは知る。例えば、哲学が大きな物語を失い、その権力を貶められているのだとすれば、権力はどこに分散しているのか、もしくは集中しているのだろうか。ヘーゲルの時代に最高潮に達したドイツ観念論も、キュルケゴールを起点とした実存主義も、プロレタリアートを一致団結せしめたマルクス主義も、偉大な哲学はみな表舞台から降りて、陰になったジメジメとした土地を好み、或いは、かえって乾燥した冬の寒空の下で、ひび割れたり折れたりしている。哲学者は元来、オプティミスティックな知的好奇心を、その探究自体にストレートに用いていたが、知を保有するといった権力関係を通過する中で、陰険な負の感情を抱いてきたという事実もある。それはキュニコス派のディオゲネスを犬のようだと馬鹿にしたりする神経や、かと思えば自室に閉じこもり、まるで樽のように狭いところで座って考え耽り、俗物的な精神を倦んだりする神経に表れている。であるからもし反対のことを敢えていうならば、これらの怨恨感情にも似た負の魂を持った人間が、いまや斜陽的な存在であるこれらのことに心酔するとき、自己の疎外的な反転と、権力の負の働きによる反転によって、知を愛することは、もはや知を愛することではなくなり、その代わりに為される哲学とは、独自の、独我的なドグマへと変異する。知は少年時代の喜ばしき知恵ではなくなり、頑固で打算的な、そして厭世的な嫌味をわずかに保つようになる。こうした哲学と哲学者との軋轢は畢竟、自己を正当化する論理に用いられる。自己にとっての経験が過去から未来へと貫かれていくとき、その快楽は実はエピクロス派のような自然性の快楽を生じさせる。根暗が日陰を好むようにして、我々は安泰の地を探してそこに住まわり、自己の特定を確たるものにする。倦怠とは大いなる経験が究竟的なドグマを確立させる過程におけるその終局地点である。ボードレールがあらわしている病院患者がベッドの場所を移したいと願う衝動、或いは都市移住計画の選定と、“この世の外ならどこへでも”といった欲望では、これは区別されて然るべきである。我々は時として経験の範疇で行動するが、或いは行動の方が経験から自己を措定しさえもするが、また時として、自己にとって経験よりも超越的な“この世の外”とも思われるような経験が自己にとってのカタルシスとなることがある。つまるところ超越的経験は自己にとって特定的、「私とはここにいるから私なのである」という場所の根拠を無惨にも破壊し、我々を遊牧させる。しかしながら我々は再び定住する。それは自己の特定は裏を返せば外界の劃定だからである。デカルトが「我思う故に我あり」と思念した次の段階に、自己を発端とする演繹法を開始していたのを見れば、むしろ重要なのは外界との対峙の手段としての懐疑だと思われてくる。この懐疑は自己との距離感によって、外界の事物を対象化する。自己にとって結合するものと分離するもの、より近い方をより重要に設定する。さらにこの遠近法は外部が自己に迫ってくる際に、その重要度を更新するばかりでなく、自己の側が動くことによって、外部の対象やその景色が更新されていくことも忘れてはならない。例えばヘーゲル的な拡大論理は事物が抽象的成果物になっていることを強く意識しなければならない。というのも発展する人間の真理段階において発展してきた人間が何を覚え、何を忘れているかを考える必要がある。人間の認識的な閾値、技術的な不可は、各段階の幾何学的な図式のイメージを超越することはない。忘却されもせずに多面体のさらなる次元を脳裏に描くことはできないのだから。『精神現象学』にあたって各章立てに見出される人間像は、以前的な景色を忘却することによって、それぞれ発展してきた人間の健康な状態を描いている。健康であるとは覚えて忘れることである。つまるところ弁証法は概念を拡大する運動であって、自己を拡大する論理ではない。自己を特定する論理である。
自己を特定する運動が近代以降増したように思えるのは、ひとつの要因として人口動態が増加したことが考えられる。もちろん人口の変動がその要因の全てではないが、医療の発達、教育の発達、産業の発達、それから権力の統治体制(国家)、これらに見る人類の成長は、人口をメルクマールとして措定しうる。畢竟、近代的個人主義はグローバライゼーションされる国家とその個人間の関係において社会を形成してきた。それは国家の方からも個人を規定するような相互的なシステムである。例えばホッブズがいうような社会契約説はこうした社会的行為の形式として見られる。もし肥大化した人口を統治する政治的権力が、以前的な方法論、それは家政的な統治モデルであったり、宗教による統一的な信仰が、人間のパースペクティブの範疇外の実情であるなら、現代的な統治モデルは国家的、或いは共産主義的になるだろう。つまり、国家という集合に属する個人の認識能力の観点は、国家に対しては相対的にミクロになる、実際的な話をすれば、個人はほとんど国家のうちで起こりうる事態を把握できない。個人の物理的限界によって国家の部分集合の部分集合の…といった具合の末端の集合に属する。そこで内実起こっていることは、より人間に直観的なモデルの運用であり、重要なのは分業体制である。特に集合と集合との共通部分に属するような個人はその支配の術として、はじめは伝統的な方法を用いるが、やがてその支配の重荷から逃れるために、より明示的で規律的な合理的な支配体制を運用するようになる。このとき国家が生産能力の向上のために国民を結びつけていることが大事である。分業によって得られたより効率的な支配のシステムがそのネットワークを縦横無尽に駆け巡ることによって、システムはより洗練され、生産品がより生産的な品物になるのである。そういった商品の流通に数多の人間が関係していることで、国家に対する契約的な信頼が真実味を帯びていくのである。またできるだけ即物的にこの関係を探ってみるならば、個人とは個別具体的であり、基本的には並列している。この粒子状の生命は欲望のマシンとして、行為の是非を選択する。しかしながらこのような状態は当然ながら社会を示すモデルとして幾分も有用ではないだろう。さながらタブララサ、もしくはホッブズ的秩序の初頭段階である他はない。人間が動物とはなにか一線を画すようにわれわれの目に映ずるとき、それは経験的な実在としての、ことに社会的欲望に関しての経験を蓄積するのであるから、この欲望の関係自体を考慮に入れたモデルを描写したときにはじめて、経験の重圧に耐えうるものである。ホッブズのいう自然状態とは、現実の社会と照応したときに、その簡単なモデルが実際の複雑な状況と比較して軋轢が生じている、破綻しているという思考に自らを送り込むことによって、知識を得るものである。そして原子論的な以上の思考モデルが現実的ではないのは当然であって、むしろ現実に即した内容に近づければ近づけるほどに、われわれの判断力を誤らせる可能性を高める。そのことに留意しながらモデルを変容してみることにする。さて並列された個別的な意志にいかに関係を持たせるか。例えば商品流通の技能としての責任能力の有無や、それに伴って人々は購買意欲を満たすような経済的なモデルを思考しようとすると(自然状態からの論理的飛躍は甚だしいが、ここでは本文の趣旨を優先して、歴史的発展を一から考えることはしない)、それまで他と無関係に独立していた、粒子は自らの周辺に、自分以外の個別具体的な意志をもった、しかしながら自身と同様に貨幣観をもつような対象を認識する。それらの間では独立していた頃より安定的な交流が起こるようになる。このときそれぞれの粒子における実在性は、その多少の性質の変化から、より責任能力を向上させた粒子の出現によって、周辺の解釈に違いを生じさせる。それはある者は流通範囲を拡大させ、より多くの機会を得るようになることや、その逆も然りである。ここに見られる粒子の関係性の段階は、並列された状態であるよりか、むしろそれを並列に見なそうとするならば、粒子の最低基準の固有の性質として本質的に、或いは一元的に見る以外はないのであって、人間に固有な欲求について取り立てるならば、より低次的な本能であり、それは社会化された人間にとっては隠しておきたいプライベートな領域であり、つまるところ自然状態のような「各人の各人に対する闘争」という秘められたはずのエゴイズムの露呈である。粒子の最低基準ではなく表象的に出来事を捉えるならば、それは階層的になり、その階層間をそれぞれの責任能力に応じて往来するような仕組みとなる。つまりある者の責任能力が向上すれば、その能力に応じて他者に影響を与えることができるのだから、それぞれの交流に際して、それぞれの個別具体的であった性質を均して、自身のより公的な部門にこれらのことを記憶する。反対に私人が公人と接触する際にもその表象的な人格との関係を結ぶことから、公的領域は形成される。重要なのは、これが人口の問題として公的なものの最上に国家を措くと、民意に国家的な意志が反映されることは想定に足るのであって、さらにその規模間の違いはあれど、公的な思想はあらゆる空間の階梯を登降することで、個人の人格形成において満遍なくその思想を反映し社会化を促す。非常に重要なのは、度々申し上げている通り、その個人に接触する国家は民意から成立しているわけである。
このことから言えるのは、文化科学において通常伴うのは、個人の文脈背後に存在する国家とその逆であることが大体である。通例われわれが個人内部に見る私的領域が実際には、私的なものでも何でもなく、国家的な財産のイデオロギーの一部であることがある。例えばアーレントが、労働対象としての人間に認められる私的財産は身体に近い、この肉体に自由程度のものしか存在しないという旨の発言をしていたかと私は記憶しているが、その指摘は本質的で的を得ているばかりでなく、私がよりラディカルに補足するならば、自由意志の存在を軽視し、人間の尊厳を軽んじるならば、この肉体でさえも虚構のような現実として解釈することができる。今日の消費性向に見られる人間の記号化は大胆不敵にも人間のプライバシーを侵害している。SF流の臆見を試してみよう。もしウェアラブル端末から睡眠時の情報、心拍数の変化、発汗の様子等々の本人にとって自覚的でない数々の証拠が、到底知りえなかったはずの私的領域の心理的状況に対して、そうした機器の方が当該人より、ある一面ではより自覚的であるならば、自分の健康に対しての行為決定権が、自由な主体から交代されているとは考えられないだろうか。しかしながら付言しなければならないのは、サイエンスフィクションとは、表面的に未来的であるが、その内容は現在的あるいは過去的であり、技術的構成は既知の概念の既知の組み合わせであるほかない。ではどこに目新しさを感得するのかと申し上げれば、その理念の意義から起こるのである。映画監督が作り出すものは、未来自体ではなく未来的なものである。上映中のスクリーンに映り込む、アンドロイドや超通信技術、未来的道具、それらを効果的に演出するためのエフェクトや超美麗な3DCGも、例えば技術班の最先端の技術力、脚本家の想像的シナリオや広報部のマーケット戦略までも映画に携わる人間をあげればきりがないが、良い映画はこのようにして、その製作過程にこと前進する人間のたゆまない探究と苦悩、歩み続ける人間が時代の嵐のなかで活路を見出している。そしてこの歩むべき道に鑑賞する人々が反応したとき、はじめて映画は意義のある映画になるのである。つまり話を戻すと、われわれの学科では臆見をただの臆見にはしない。それより地味な方法ではあるが、より意義のあるものしたいと考えている。さて先に人間の尊厳云々について述べたが、もしもわれわれが未だ人間の可能性を忘れられない人間なのだとしたら、当然未来人にとっては、遥かに重要な別の問題があるかもしれないが、しかしそのことこそが現代人の座標であるとすれば、それはわれわれにとっては重要な問題である。問題とは国家という怪物が、私的財産を解体しながらも、公共財産を増長していくことである。さらに個人が以前ならば秘密裡に取り組んでいた課題は公共財を通して解決されるために、個人自体も公共性を帯び始めていることである。ホッブズの時代と照らし合わせていえば、大陸合理論とイギリス経験論の対立は、まさしく生得的なものを重要視するか、経験的なものを重要視するかの遠近感覚に思えてくるが、人類が経験的知を蓄積させるにしたがって、その成果がさらなる成果を呼び込み、厖大な知識を宿すことになったため、経験的なものの比重が増したように思われる。非常に重要なのは、社会契約という概念は本来人間にとって、契約という語感から伝わる通り、対等な相手と交渉することで行われるはずのものであるが、ホッブズやロック、ルソーらの時代には、事後的な契約関係で成立していたと思われる。思いがけない瞬間にサインしていないはずの契約書が見つかり、それらの項目を後からまじまじと確認することになる。ひとりの人間とリヴァイアサンとの交流のうちでは、しばしばこのような詐欺的な契約が行われ、つまり人類史のあらゆる段階でこれらの取引が行われていた可能性があり、私的所有を手放す代わりにより安寧に生存する権利を得てきたのである。私は先に人口の問題を提起したが、それは裁判形態、医療、教育、農業、政治等々の変容についてである。人口の問題はそのどれとも因果関係を確かめることができないが、相関関係を探ることはできる。例えば、医療の発達は、罹患率を下げ、患者を治療することによって、生存者を増やしてきたのであるが、人口が増大にするにつれ、知識が蓄積されて、医学が進歩したのか、ある段階で偶然発見された治療法がたまたま患者を救うことになったのか、これは見当もつかないが、この両者が関係している可能性は高い。同様に飢餓の問題が分配の効率化に伴って、克服されるためには政治形態が変わる必要があったかもしれないが、それらのためには時の権力に抵抗するだけの体力が必要であることは言うまでもない。人口はこれらの問題のどれとも相関関係を結んだ良い標識である。この標識を参考として、人類の契機の数々は人口の増加に際して見られてきた問題であるということができる。それはつまり、個人の公共財へのアクセスが人口に連動しているということを間接的に示している。
個人と国家との関係はこうして着々と進められてきたのであり、いま個人の内面にはリヴァイアサンと私秘的な領域が両方存在している。それに対して国家の内面では、いまもリヴァイアサンがその秘密を暴こうとしている。このことからわれわれの視界には淡くもリヴァイアサンが個人と国家を循環するような、国家的人間を想像する感を呈する。このリヴァイアサンの精度が私の関心事であり、その窮極的地点に個人即国家を措く社会図式を想定し、現実社会においてその図式とどれだけの乖離があるのかを探ることで、人間的理解を推進していくのである。この個人と国家の循環図式にあって、イデオロギーの絶え間ない対立と、無意識的なプロパガンダとも言えるこの現状がかつてないほどに安定している。というのもイデオロギーとはリヴァイアサンの精神が分裂したに過ぎないものであって、それが饗宴のように惹かれあって対立した地点で統一された社会性を育むからである。社会に包摂された価値がその社会に循環することで安定している。自らの図星に自覚的な者は倦み、あるいはイデオロギー的人間にとって私秘性は公共財を介することで思わぬ人間発見につながる。この陰陽の分布すらも社会内に包含されている。
本文は以上である。以降は簡単に具体例を考察して終わろうかと思う。
路上のポイ捨てに関していえば、社会通念上はこれは良くないこととされているが、エゴイズムに従うならば、ゴミはただちに捨てられて然るべきである。ではなぜ社会通念上良くないとされているかといえば、その行為によって社会契約を済ませた他の人間を害するからである。衛生上の問題や景観の問題など、その行為から随伴するであろう生存にとってマイナスな事態をあらかじめ予防する思想であるといえる。しかしながらこの思想が民意に反映されるためには、各人にこのことを考慮してもらうより、ある社会的強制力を持った明示的な条文として、実際に行政が取り締れる条例に落とし込む方がはるかに効果的である。このディスインセンティブな作用によって大体は処理できるのであるが、その実際的な影響下では、ポイ捨てされることは多々ある。それは事実上取り締まりの外であり、利己的な性向が働きやすいためである。それでも町を綺麗な状態にしておくためには、方法はいくつかあるが、ゴミ箱を増設する、法的厳罰化、取り締まりの強化、清掃業者あるいはボランティアへの委託等々、非常に重要なのは、ポイ捨てをしたとしても、またその現場を目撃したとしても、翌日は翌日のゴミが捨ててあり、翌々日には翌々日のゴミが捨てられている程度であれば、いつか誰もそのことが気にならなくなり、やがてポイ捨て程度という発想に落ち着くことである。そしてそのことがポイ捨てさせうる人格を育む可能性があるということである。さらに条例だけでなく刑法ならば、これはポイ捨てと比べると厳罰の論理がよく働いており、また逮捕状といった権力を行使できることから社会的強制力が強く、人々により規範的な意味を与えることができる。また先程と同様、繰り返しこの規範的な反復をすることによって、今度は非現実的な起こり難い行為だと認識することから、社会的関係の中で規律的で強化されたラインを形成するようになる。その他法律やモラル、日常の生活や歴史的実在に関しても、理念的に一面的であればイデオロギーを観察することはできるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
