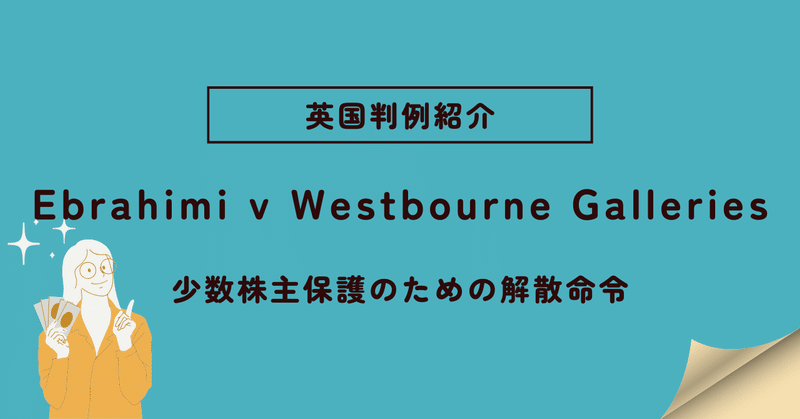
【英国判例紹介】Ebrahimi v Westbourne Galleries ー少数株主保護のための解散命令ー
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
今回ご紹介するのは、Ebrahimi v Westbourne Galleries Ltd 事件(*1)です。
会社法に関する判例で、50年も前の事件ですが、今も参照されている重要な判例です。会社の解散という地味なパートの事件ですが、少数株主の保護の文脈でよく登場します。
よければ、読んでやってください。
なお、このエントリーは、法律事務所のニューズレターなどとは異なり、分かりやすさを重視したため、正確性を犠牲しているところがあります。ご了承ください。
事案の概要
1945年頃から、Ebrahimi氏(原告・上告人)とNazar氏は、絨毯の事業をパートナーシップ(日本の組合に近い形態)で運営していました。1958年、二人は、パートナーシップと変わらない関係でビジネスを続けることを前提に、この絨毯の事業を承継する株式会社を設立し、取締役に就任します。その後、まもなくNazar氏の息子も、会社の取締役に就任しました。なお、Nazar親子は、合わせて会社の過半数の株式を保有していました。
会社は順調に利益を上げましたが、株主への配当は行わず、全て取締役の報酬として、原告らに支払われていました。
1969年、原告とNazar親子の間で意見の相違が生じ、原告は株主総会決議により取締役を解任されてしまいます。上記のとおり、会社は株主への配当を行なっておらず、原告は、会社への資本投下のリターンを得られない状況が続きました。
そこで、原告は、会社及びNazar親子(被告・被上告人)に対して、当時の会社法(Companies Act 1948)に基づき、Nazar親子又は会社がその株式を買い取ること(s. 210)、又は、会社の解散(s. 222(f))を求めて、訴えを提起します。
原審では株式の買取は認められなかったものの、会社の解散命令が下されました。しかし、控訴審では、被告の反論が認められて、解散命令が覆されます。そこで、原告が上告を行いました。
争点:本件の事情の下で会社の解散命令は認められるか
争点は書いてあるとおりなのですが、もう少し補足したいと思います。
解散命令の申立てによる少数株主の逆襲
まずは、本件で用いられた解散命令の申立ての位置づけです。
株主は、多数決の原則に基づく株主総会での決議によってその権利を行使します。そのため、多数派と折り合わない少数者は、どうやっても決議を通すことができず、基本的に惨めな目にあいます。
本件でも、原告は、Nazar親子に株式の過半数を握られたため、仲たがいをきっかけに、株主総会決議によって取締役を解任されてしました。株主として配当を得ようにも、Nazar親子が賛成票を入れなければ、配当の総会決議を通すこともできません。
こうなってしまうと、原告にしてみれば、会社の株式などただの紙切れにすぎません。
「公正かつ衡平」
このような苦境に立たされた株主に対して、Insolvency Act 1986(以下「IA 1986」)のs.122(1)(g)は、次のような定めを置いています(太字はぼく)。
122 Circumstances in which company may be wound up by court
(1) A company may be wound up by the court if—
(中略)
(g) the court is of opinion that it is just and equitable that the company should be wound up.
つまり、少数株主は、会社を解散することが公正かつ衡平であるとして、裁判所に対して、会社の解散命令の申立てを行うことができます。
会社の解散に際して、会社の資産は債権者への弁済にあてられたのち、残余分は株主に分配されます。このプロセスを通じて、少数株主は、投下資本の回収を図ることができます。
なお、IA 1986のs. 122(1)(g)は、原告が本件で依拠したCompanies Act 1948のs. 222(f)の後継の規定であると考えられています。
パートナーシップ法に由来する救済
IA 1986のs. 122(1)(g)に基づく解散命令の申立ては、パートナーシップ法に由来する救済措置であると言われます。
Partnership Actには、パートナーシップの解散の根拠の一つとして、IA 1986と同じく、それが「公正かつ衡平」であることが挙げられています(*2)。この解散根拠は、これまで発展してきたパートナーシップの解散に関する先例法を成文化したものと言われており、「公正かつ衡平」という言葉を媒介して、会社の解散命令の適否を判断するにあたって考慮すべき要素を、パートナーシップの解散の場合と同じように考えられるようになるということです。判決の先取りですが、本件で主判事を務めたWilberforce卿は、このことを「provide a bridge」(橋渡し)と呼んでいます。
裁判所の判断
原告(上告人)勝訴。
裁判所は、会社を解散することが「公正かつ衡平」であると判断し、解散命令を下しました。
考察
パートナーシップと会社の違い
パートナーシップの本質は、パートナー間の信頼です。Cross卿は、次のように述べています。
人は互いに信頼が無ければパートナーにはならず、相互の信頼が維持されることがパートナーシップの本質である。パートナー同士の信頼がなくなり、当初想定していた協力関係が築けなくなった場合、その関係は解消されるべきである。
他方、本件の会社のような株式会社の最重要の要素のひとつは、所有と経営の分離です。株主は、その保有株式数のみが問題となり、個性は問題になりません。ここに、パートナーシップとの違いがあります。
本件の会社は準パートナーシップであった
本件では、原告とNazar氏は、当時営んでいたパートナーシップと変わらない態様でビジネスを行うことを前提に、会社を設立しました。
いうならば、会社となった後も、原告とNazar氏のビジネスは、準パートナーシップであったということです。
それにも関わらず、原告は、取締役を解任されて、ビジネスの運営から排除されてしまいます。このような状況では、原告とNazar親子の間にもはや信頼関係は存在しないことが明らかです。
このような事情を考慮の上、裁判所は、会社を解散することが「公正かつ衡平」だと判断したものと解されます。
一般的な言葉は一般的なままであるべき
これは、主判事のWilberforce卿の言葉です。
「公正かつ衡平」という抽象的な言葉ゆえに、これが適用される事件を類型化し、見出しを付ける傾向があります。しかし、Wilberforce卿は、そのようなことは誤りであり、例示は用いられてもよいが、一般的な言葉は一般的なままであるべきであり、特定の事例の総和に還元されるべきではないと述べています。
ここから、本判決は、IA 1986のs. 122(1)(g)に基づく解散命令について、裁判所に広範な裁量的権限を与えられていることを確認した事例とも言われています。
おわりに
いかがだったでしょうか。
「公正かつ衡平」を理由とする解散命令は、日本でいえば、会社法824条1項に基づく解散命令に該当するところ、日本でこれが利用されることは極めて稀です。
しかしながら、英国では、「公正かつ衡平」を理由とする解散命令に関する判例がちょくちょく出ています。紙幅の都合で詳しくは触れませんが、少し前にも本件に関連する判例が出ています(*3)。
会社の解散をパートナーシップの解散とアナロジーに考えることは、ぼくが知る限り、日本では見られない考えなので、個人的には興味深いです。
お読みいただきありがとうございました。
このエントリーがどなたかのお役に立てばうれしいです。
【注釈】
*1 Ebrahimi Appellant v Westbourne Galleries Ltd. and Others Respondents [1973] A.C. 360
*2 s. 25, Partnership Act 1892。なお、この引用は、注釈1のLaw Reportの記載をそのまま写しているのですが、英国のパートナーシップ法は、Partnership Act 1890で、解散はs. 35に定められています(そこにも解散理由として「公正かつ衡平」の定めあり。)。ちょっと調べてみたのですが、引用元が間違っているのか、ぼくの理解が何か足りていないのか、ちょっと分かりません、、。
*3 Chu v Lau [2020] UKPC 24
免責事項:
このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
X(Twitter)もやっています。
こちらから、フォローお願いします!
他にも、こちらでは英国の判例を紹介しています。
よければご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
