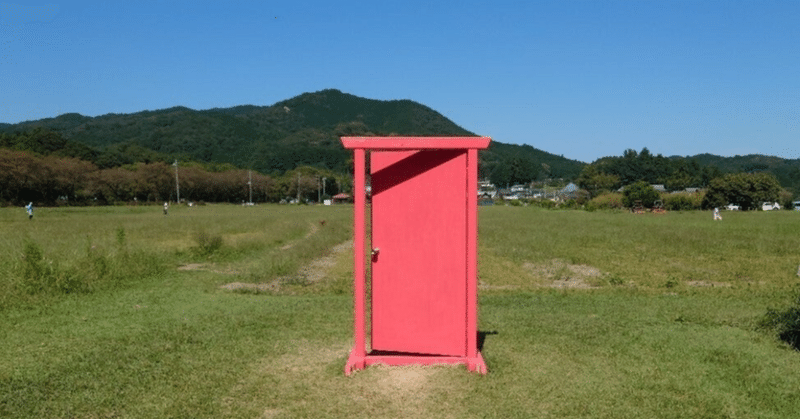
国語科授業の記憶のフィールド
国語科授業の記憶について研究中。その意義や方法の一部は下記の論文に発表したことがあります。
「国語学習の記憶に関する一考察―学習者の記憶に残る国語科授業に関する質問紙調査2014年版から―」『九州国語教育学会紀要』第5号、2016年3月
この研究をぼちぼちまとめる時期になってきたというのがnoteを始めたきっかけの一つでした。そのためのドラフト(のドラフト)のようなことをしています。
以前の記事で、「熟考した記憶を語ってもらえること」が教師としての喜びだろうと書きました。確かに学びえたことが伝わってくるからだろうと思います。
上の論文に収めたデータの中に、次のような記憶がありました。
教科書に載っている俳句の中から一つ選び、その俳句に出てくる単語を調べたり、その俳句が生まれた背景を調べて、感じたことを絵や文にした。調べれば調べるほど一読しただけでは読み取れない情報が出てきたりして、最初の印象と授業終わりにもった印象とのギャップが予想以上にあり、面白かったから(覚えているの=引用者補)だと思う。
「調べれば調べるほど」という熱心に取り組んだことを語ることばがあります。また、「一読しただけでは読み取れない情報が出て」きたとか、「最初の印象と授業終わりにもった印象とのギャップが予想以上にあり」というように、授業(単元)を通した自己の変容、いや変容というほど大きくはないかもしれないのですが、この単元で新たなことを学び得た実感も記されています。
児童生徒を経験した人の国語科授業の記憶を読んで、わたしたちもこういう授業をしたいと願う。逆にもっとこういう授業に変えていきたいと決意する。そういうフィールドをつくっていきたいです。国語科授業がつくりだす記憶のフィールドは、他教科がつくりだすそれとはまた異なる特性や意義をもつこともわかってきました。それは国語教育(国語科教育)が、記憶を言葉にすること、そして物語ることに直接関わっているからにほかなりません。
簡単ですが、今回はここまでです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
