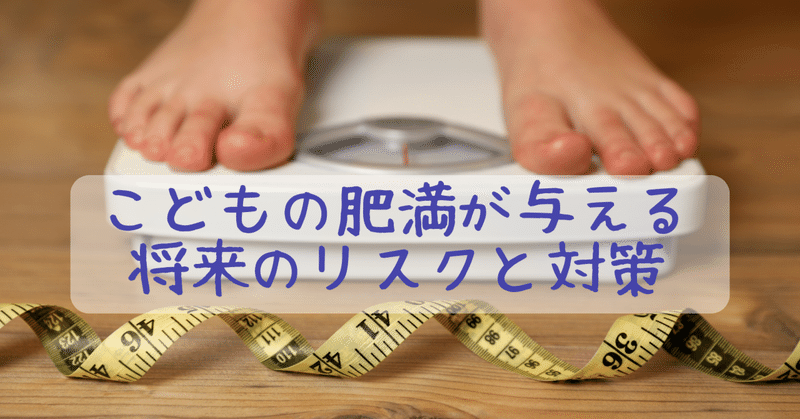
【コラム】小児肥満の抱えるリスクと対策
保育園栄養士のとろみです。
昨年11月に文部科学省が公表しましたが、
幼稚園や小中学生全学年で肥満傾向の子どもの割合が最高となりました。
新型コロナの影響による運動量の減少などが要因と言われており、小児肥満は大人になっても影響を残します。
そこで今回は、小児肥満の与える将来のリスクと対策を紹介します。
参考になれば幸いです。
小児肥満とは?
生まれてから思春期(目安:女性は15歳、男性は17才)までを対象に、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度(過体重度)を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児としています。
肥満度(過体重度)=〔実測体重(kg)-身長別標準体重(kg)〕/身長別標準体重(kg)×100(%)
以下リンクから肥満度を計算できます。
小児肥満はなぜ注意すべきか?
幼児期の肥満者の25%、学童前期の肥満者の40%が将来成人肥満に移行すると言われています。
また、思春期の肥満者は、体格が形成されてしまうことや生活習慣が身についてしまうことなどから、実にその70%~80%が成人肥満につながるため、注意が必要です。
小児肥満の将来に与える影響とは
生活習慣病のリスク: 成長過程で生活習慣病(心臓病、高血圧、2型糖尿病など)のリスクが高まります。
これは、肥満が体内の脂肪組織やインスリンの分泌などを乱し、将来的な病気の発症リスクを増加させるからです。骨や関節の問題: 体重が増加することで骨や関節にかかる負担が増します。この結果、将来的に骨や関節の問題や痛みが発生する可能性があります。
精神的な問題: 将来の精神的な問題や心理社会的な影響をもたらす可能性があります。例えば、自尊心の低下、いじめの対象になるリスク、不安やうつ症状の発症リスクが高まることがあります。
学業成績への影響: 注意力や集中力の低下、学習意欲の低下などが起こる可能性があり、それが学業成績に影響を与えることがあります。
社会的・経済的影響:例えば、医療費の増加、就業能力の低下、生活の質の低下などが挙げられます。
小児肥満対策は?
太らないための生活は、「食事」と「運動」が、カギになります。
どちらがかけても、肥満対策にはなりません。
一日三食をきちんと、バランスよく食べる
食事は最低30回噛んで食べる
夜8時以降の食事は避ける
自分のことは自分でする
外で遊ぶ習慣もつける
家事手伝いは究極の有酸素運動、毎日一つは実行する
いかがでしたでしょうか。
こどもたちの将来のWell-Beingにもかかわる、肥満対策を考えてみませんか?
ここから先は

【子供が良く食べる】ホットクックでつくりおき実践レシピ
ホットクックが誰でも上手に使いこなせるようになるレシピ集。1週間の献立を考えるのが苦痛、子どもが好きなメニューがわからない、ホットクックを…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
