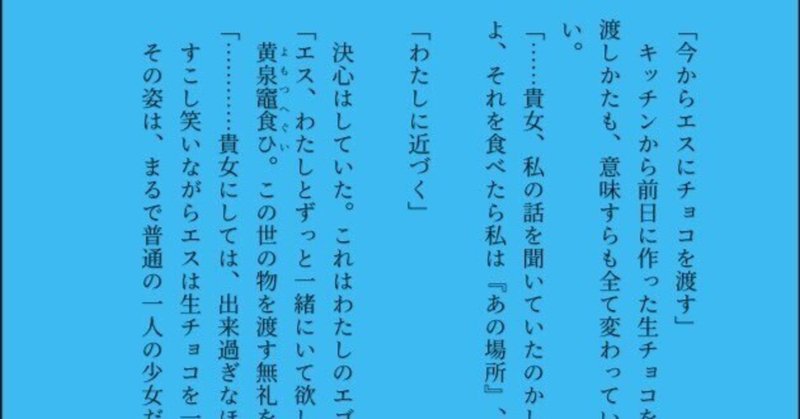
自分の書いた旅エスSSを解剖する
最近、賞用の小説を書いてメンタルぶっ壊れたとりのつぎはぎ(とりつぎ)です。
前置きは早々に、最近書いたALTEREGOの二次創作小説『バレンタイン/黄泉竈食ひ』を解剖して反省点を今後に生かそうと思います。ウオォオ……。
エス溺愛旅人(女)×エンディング後エス
— とりつぎ🦋 (@S_Tyo_H) February 14, 2023
バレンタインに旅人がエスにチョコを渡す話です(意訳)
『バレンタイン/黄泉竈食ひ(よもつへぐい)』#ALTEREGO#EGOART pic.twitter.com/M8YRhG1tuN
──痛みを知らないで『なに』を伝えられるんだよ。
小説って最初の一文でいかに読む人を殺せるか、惹きつけられるかが重要だと思っています。
なので最初の一文目は、言い方悪くするとキャッチーな言葉をつかいがちになるのは反省ですね。
最初の一文はそれ以外を全部書いてから最後に付け加えることが多いです。
今回も全て書き終えてから最後にこの文章を付け加えました。
くらやみを身体に纏い、蒼く瞬く瞳で世界の理が繊細に書かれた本を選び、冬の夜空のような髪の内に骨の魚を飼う彼女。この世の者では無いような彼女に、この世の物を渡す無礼を承知で手渡しをしよう。よもつへぐいで縛らなければ、きっと彼女は戻ってしまう。
後半にもう一度使う文章です。
後半の使い方的になるべく「現実離れした」「神秘的な」表現にしようと思いました。
いま考えると、もうすこしここを長く書いてさらに『異質さ』を強調してもよかったかな。
最初の『くらやみ』をひらがなにしたのは柔らかな印象を持ってもらうためです。言葉は不思議なもので『暗闇』と『くらやみ』と『クラヤミ』は同じ意味と読みでも、受ける印象は全く異なるので難しいですね。
この辺りの感覚は夢野久作が天才的に上手く、
外衣も裏衣も、雨や、風や、岩角に破られてしまって、二人ともホントのヤバン人のように裸体になってしまいましたが、それでも朝と晩には、キット二人で、あの神様の足の崖に登って、聖書を読んで、お父様やお母様のためにお祈りをしました。(夢野久作/瓶詰地獄)
……なんでしょう、ひらがなとカタカナと漢字の使い分けのうまさで直視すると頭が焼けてしまいそうになります。
瓶詰の地獄でも昔旅エスを書いていましたね
エス溺愛旅人(女)×エンディング後エスは本を読む。#ALTEREGO #EGOART
— とりつぎ🦋 (@S_Tyo_H) November 24, 2019
232冊目『瓶詰の地獄』 pic.twitter.com/ODBOB6VBCm
吹き出しが流れ、ピアノの旋律が流れ続ける、『あの場所』に。
エスのいるあの場所、特にゲーム中に名前が出てくるわけではないので私は毎回脳死気味に『あの場所』なんて書いてます。あなたの『あの場所』はどんな名前ですか?
ピアノの旋律も常時流れているわけではなさそう。エスもノイローゼになっちゃうよ。
エスのいる『あの場所』から元いた世界に戻れなくなることが数度続いた。
ここ数年、エスの元に通うようになってからそのようなことは一度も無く、またそれが数度続いたというのは初めての経験である。
「……帰れない」
『帰る手順』を一通り行った後に目を開けて目の前のエスを見る。本来であれば手順を終えて目を開ければ元の世界、自分の部屋の鏡の前に立っているはずだが。
そしてこれは。
「……帰れないね」
『帰る手順』を一通り行った後に目を開けたエスを見る。本来であれば手順を終えればエスはまばたきの刹那に自分の部屋の鏡の前から消えるはずだが。
ここも同じ文章を連続で使っています。
同じ文章を連続して使うことでリズム感と目線の固定がしやすくなる気がしていて、リズム感は文字通り読みやすくなる、目線の固定はこの場面で『変える手順をしても帰れない』ということを強調するために旅人の視点から見た景色以外のものを入れたくなかったからです。
そしてこれは。
ここ、どの部分にも意味としてかかってないので、なんでこの6文字が存在してるのかわかりません。消したい。なんのこれなんだ。
年月が経つにつれお互いがお互いに、もともといた世界に帰れなくなることが増えてきたのだ。
『元々』を『もともと』にしたのも上記と同じ理由です。
『時間が経つにつれ』にしなかったのは『年月が経つにつれ』のほうが長い時間というのがわかりやすいかなという理由です。
何度か手順を試した後にようやく残像すら残さずに消えたエスの残り香を探したが、それはついぞ見つけることはできなかった。
ここ。
この小説で一番私が消したい箇所。
できるなら元ツイートの画像を編集したいくらいには嫌な場所です。
消えた人間が残したものの表現として残り香ってものすごく陳腐なんですよね。
効果的に使うと物凄い力を持つ『残り香』ですが、前後もなにも関係なく唐突に使うとものすごくダサい脳死的表現になりがちです。
例えばエスが普段から香水をつけていて、原作のゲームでもその表現があればこの一文は生きたものになります。でも原作でエスの匂いなんてものは一切ない。
まだ100歩譲ってエスの匂いを表現できていればよかったんですよ。
「いつもエスが読んでいた古書の香り」だとか「あの場所でエスが淹れてくれた珈琲の香りがした」だとか、ある程度イメージしやすいものだったらよかったんです。
陳腐に楽して、本編に一切関係ない、必要のない表現をしたせいでこの一文だけこの作品の中でめちゃくちゃ浮いて見えます。
人の匂いの表現って効果的に使えばただの説明よりもその人を表現できるんですよ。
私の好きな曲で米津玄師の「TOXIC BOY」があるんですが、歌詞の中に
あんたが部屋に残してったチェリーボンボンのいい香り
って歌詞があるんですよね。これだけで『あんた』がどんな人かなんとなく想像できるの凄くないですか、凄い。
何が言いたいかというと、とにかくこの一文は消すか表現を大きく変えたいということです。表現で楽をするな。
数日後、エスがわたしの部屋で元いた世界、吹き出しが流れピアノの旋律流れる『あの場所』に帰る手順を六回しても戻れなかった時、疲れて床にしゃがみこんだエスが仮説を立てた。
基本的に短編だと一文空けて時系列を整理するのは悪手だと思っていますが読みやすくなるのは事実なので多用します。
改めて『吹き出しが流れピアノの旋律流れる『あの場所』』と説明しているのは書いた方がわかりやすいからです。読んでる方は以外とそういうこと忘れる。
六回は特に理由なく設定しましたが、4~5回だと帰るための必死さがあまりない回数だとは思うので6回でちょうどよかったんじゃないかなと思います。
「『黄泉竈食ひ《よもつへぐい》』だと思うの。黄泉のものを食べすぎると現世に戻れなくなる、あの……。まぁ貴女が古事記を読んでいることは期待していないけれど」
「でもエスもわたしも黄泉の国なんて行ってないし、そもそもまだわたし達死んでないよ?」
「食物はその世界に深く結びついているのよ。『食事』は少しずつ『世界』を自らの身体に摂りこむこと。それは『黄泉の国』でも、貴女のいる『この世』でも、私の生きる『あの場所』でも同じ。貴女は『あの場所』で私の淹れた珈琲を飲んでいたし、私は『この世』で貴女の料理を食べていた。『黄泉の国』で伊邪那美命《イザナミノミコト》は……。だからお互いの『世界』を体内に摂りこんでいったわたし達は元々いた世界に帰りづらくなったのではないかしら」
説明パートです。多分エスは古事記全部読んでるし旅人は絶対に古事記なんて読んだことない。
オタク義務教育では必修の黄泉竈食ひですが世間の認知度はどれくらい高いのでしょうか。
黄泉竈食ひとバレンタインって親和性高いと思うんですよ。自分の作ったものを相手の血肉にするっていう点とか。ほら、実際に血とか髪の毛とか入れる人もいますし。
正直、バレンタインSSは書く予定無かったですが前日にこの親和性に気がついてしまいました。衝動のままに書いた。衝動は大事。
ここ、改めて読み返してみると旅人の言葉をガン無視してエスが説明してますね。少し掛け合いとか入れればよかった。
とりあえずここで帰れなくなった理由の答えを書いたのですが、答えの開示としてはちょうどいいところだったのかなとは思います。
七回目の手順が終わり未だ部屋にいるエスを見て、わたしは一つの決心をした。いや、もっと正確に言えば。
くらやみを身体に纏い『黒い服を着た』、蒼く瞬く瞳で世界の理が繊細に書かれた本を選び 『青い目で小説を選ぶ』、冬の夜空のような髪の内に骨の魚を飼う『黒髪をフィッシュボーンに編んだ』彼女。異世界の神秘が剥がれ、わたしが生きる世界に迎合してしまった彼女を見て、決心したのだ。
序盤の文章の種明かし的な部分です。
「現実離れした」「神秘的な」表現をから現実の描写を強調してエスがこちらの世界に迎合しているところを表現しました。
『迎合』って意味は置いといて良い言葉ですよね。私はこの言葉を『水曜どうでしょう』で覚えました。君もっと会社に迎合した方がいいよ。
「ねぇエス。今日がなんの日か知っているよね」
「……バレンタインね」
八回目を始めようとしていたエスは動きを止めてわたしを見る。「今更なにを」と言いたげな、ただの青い目で。
ここでも「ただの青い目」でエスがこちら側になりつつある現実感を強調しています。
「今からエスにチョコを渡す」
キッチンから前日に作った生チョコを持ってくる。これを作っている時に考えていた渡しかたも、意味すらも全て変わっていたが、チョコをエスに渡すことだけは変わらない。
「……貴女、私の話を聞いていたのかしら? 食物はその世界に深く結びついているのよ、それを食べたら私は『あの場所』、あの世界から更に遠のいて──」
生チョコだったのは単純に私が好きだからです。
溶けかけのチョコが一番美味しい人間からしたら生チョコは神の食べ物。
最後の「遠のいて──」の罫線は使う人と使わない人がはっきりしている印象ですが私は使います。そっちの方が間とかタイミングが取りやすいので。
消えゆく声とか次の言葉の強調とか、いろいろ使いやすいけど使いすぎるとちょっとダサくなる。
「わたしに近づく」
メイン台詞。
特にプロットもなく書いていたので最後どういうオチにしようかなと考えていたら脳の奥にいるイケてる女の引き出しからこの台詞が出てきました。
真顔でこんなこと言える女が好き。好きだから書いた。
創作をする人ってちゃんと台詞もキャラクターも考えて書いている人と頭の中で勝手にキャラクターが動く人がいると思うんですが、私は後者タイプなので短編掌編だとプロット書くことは少ないです。
こんなアンケートもありましたね。
《小説や漫画等、物語の作り手さんに質問》#拡散希望
— はなまる (@hanamaru0926) June 3, 2019
『キャラが動く』。比喩的表現か、そう言うとカッコイイから言っているのだと思っていたのですが『実際に脳内劇場で動いてセリフを喋る、それを描写するだけ』と聞き震えています。そんなチートな異能をお持ちの方、どのくらいいるの?
話を戻すと、この台詞のおかげでこの話のメインはここ! と言えるような骨ができたのでよかったんじゃないかなぁと思います。
Q.この時の作者の心情を答えよ
A.「わたしに近づく」って真顔で言える女が好きすぎる。
決心はしていた。これはわたしのエゴだ。
ALTEREGOの二次創作として「エゴ」や「自意識」などの言葉やテーマを入れたいなぁとは常々思っています。
「エス、わたしとずっと一緒にいて欲しい。わたしと、この世界で一緒に生きて欲しい」
プロポーズ。
ちょっと後悔しているのはここでも古事記のエピソードに沿った言葉でも入れたら一貫性が出たかなとも思っています。
「エス、わたしとずっと一緒にいてほしい。わたしとこの世界で、黄泉の国でも一緒にいてほしい」とか。冗長気味になるかな。
黄泉竈食ひ《よもつへぐい》。この世の物を渡す無礼を承知で手渡しをしよう。
この一文も序盤の繰り返しです。繰り返し大好き。
「…………貴女にしては、出来過ぎなほどのプロポーズね」
すこし笑いながらエスは生チョコを一粒食べる。
普段エスが旅人をどう思っているかわかる台詞ですね。
ここで明確にプロポーズという言葉を使って関係性の確定をさせました。わかりやすいのはいいことだ。
その姿は、まるで普通の一人の少女だった。
神秘が完全に剥がれたエスを「エス」という名前を使わずに「一人の少女」として書いてわかりやすく物語の終わりとしました。
「神秘性がなくなる」=「エスではなくなる」というのも表現したかったけどページ数的に長く書けなかったのでこれだけしか書けず。
自分の書いたものの解剖は頭の中の整理にもなるし、反省にもなるし、次に書くものの勉強にもなる。
いいこと尽くめなので是非。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
