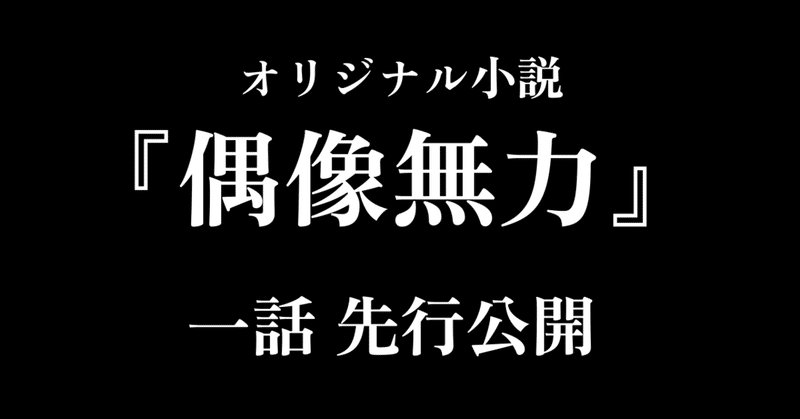
オリジナル小説『偶像無力』 一話(先行公開)
都会が嫌になって、郊外へ引っ越すことにした。理由は様々あるが、あえて言うなら私が〝若干スランプ気味な作家〟だから。
今でこそホラー界隈では名前を知らないものはいないくらいのホラー小説作家となったが、私は本来殿方同士の恋愛もの……所謂BL小説を書いていた。BLが好きだったから。
そんな私に現実はあまりにも冷酷だった。私の書いたBL小説は当時の担当も顔をしかめるレベルで売れなかった。
『水野先生、BLってハッピーじゃなきゃいけないんですよ。じゃないと、BLとして成立しません。どんなことがあっても攻めと受けは必ず結ばれないといけないんです。幸せな形で』
「……」
鞄から煙草を取り出し、ライターで火をつけた。細い紫煙がゆらゆらと立ちのぼっていく。
夕暮れ時というのもあり、駅の喫煙所はスーツに身を包んだ殿方の吐き出す煙で充満していた。目の前で煙草をふかす殿方をじっと観察する。
電子派か。
吸い終わった電子タバコを灰皿に捨てた殿方は、胸ポケットから紙煙草を取り出した。口に咥え、ライターで火をつける。
両刀だったらしい。
……また職業病がでた。これ以上眺めるのはやめておこう。
突き抜けるメンソールとほのかに香るベリーの紫煙を吐き出して、窓にもたれ掛かる。
「……」
私は自分の好きなジャンルで結果を出すことができない腕のない作家だった。
そんな現実を前に筆を折りかけていた私に声をかけてくれたのが今の編集担当の新井さんで、彼女に言われた通りにホラーものを書いたら、売れてしまった。名手の肩書きを与えられるくらいに。
おかげで作家としての私は死なずに済んだ。新井さんがいなければ、私は全てを投げ出していたかもしれない。
あぁ、そうだ。今何時か……。
ジーンズのポケットからスマートフォンを取り出し、電源ボタンを押す。明るくなった画面に十五時時四十分と表示された。
……もう一本吸えるかな……。
目の前で煙草を吸っていたスーツの殿方が大きな歩幅で駅から離れていくのが目に入ったと同時に、スマートフォンが震えた。画面を操作して、スマートフォンを耳に当てる。
「水野です」
『あ、水野先生!お世話になってます!お疲れ様です!』
よく通る活気に溢れた声。
「新井さん、どうも」
『教えていただいた駅に着いたんですけど……今どちらにいらっしゃいますかね?』
「改札を出てすぐの喫煙所です。ちょうど吸い終わったので、出ますね」
『すみません、私お邪魔しちゃったようで……』
「いえ、お構いなく」
肩でスマートフォンを挟み、喫煙所の灰皿へほぼフィルターだけになった煙草を入れ、ガラス張りの扉を開けて外に出た。
「あ!」
スマートフォンからも全く同じ声が同じタイミングで聞こえた。
電話を切った新井さんが小走りで駆け寄ってくる。
「おはようございます、水野先生!」
「おはようございます。新井さん」
「すみません、来週デビューの新人さんと打ち合わせでつい話がはずんでしまって……」
「お構いなく。むしろ忙しいのに、手伝いに来てくださってありがとうございます」
「いえいえ!それこそお構いなく!私がやりたくてきてるので!」
手に持ったままのスマートフォンの画面を見ると、予定の時間が迫っていた。
「じゃあ、行きましょうか」
「はい!私、この後は予定空けてますので、いくらでもお手伝いしますので!」
「頼もしいですね」
二人並んで、新居に向かって歩き出した。
*
「お荷物、以上です」
「ありがとうございます」
「では、ここにサインお願いします」
手渡されたバインダーに挟まれた書類に私の本名兼ペンネームである〝水野真〟を記入した。
バインダーを引越し業者の殿方へ向けると、一瞬目を細めたあと驚いたような顔をして私を見た。
「失礼ですけど、もしかして水野真先生ですか?あの『呪縛の男』の」
「まぁ……はい、そうです……」
「あぁ、やっぱり!僕、あのお話大好きなんですよ!すっごく面白かったです!」
「それは……ご丁寧に……どうも」
「新作、ずっと楽しみに待ってます!これからも頑張ってください!応援してます!」
「ありがとうございます……」
「あ!安心してください!いくら先生のファンだからって、この家に先生が引っ越してきたとか先生の引越しを手伝ったとか絶対SNSに書きませんし、周りに言いふらしたりもしないので!」
目の前の殿方は、私が厄介ごとを恐れて歯切れの悪い対応をしていると思っているのだろう熱心にフォローの言葉を紡いだ。
気を遣わせてしまって申し訳ない……嬉しい言葉を言われることに慣れていないだけで……疑っている訳では……。
とは口で言えず、鞄に入れいてたお茶のペットボトルとおかきの詰め合わせが入ったビニール袋を渡した。
「あの、色々とありがとうございます。大したものではないんですが……」
「ええ!いえ、こちらこそっ!ありがとうございます!」
そう言いながら、ビニール袋とバインダーを受け取った殿方は被っている帽子を脱ぎ、深々と頭を下げた。
「では、失礼します!先生のお手伝いができて、光栄です!」
「こちらこそ。ありがとうございました」
扉がバタリと大きな音をたてた。
「元気な方でしたねぇ」
見守ってくれていた新井さんが口を開く。
「そうですね」
「ああいう風に気遣いができるファンばっかりだったらいいんですけどね」
「そうですね」
実際、ああ言ってくれるだけでも作家としてはかなり心が落ち着く。
今や作家といえども顔を出す時代。そのおかげで昨今ではSNSに無許可で撮られたプライベートな写真や目撃情報、容姿の誹謗中傷や聖人君子を求めすぎるあまり作家を顧みないファンがかなり目立つようになっている。
「この間も、坂又先生が歩きながらお茶飲んでるって抗議のメールが殺到したんですよ?『かっこ悪いところを見て幻滅したくありません』って」
「坂又先生はそういうとこ、かなり大変そうですよね」
「思い出しただけで腹が立ちますよ、ほんとに……作家が〝当たり前〟のことしちゃいけねぇ理由がどこにあんだよ」
新井さんは、しまったという風に口を両手で覆った。よく通る明るい声が篭る。
「ごめんなさい!私ったら、また」
「大丈夫ですよ」
作家のことを思ってこそ。新井さんのこういうところを好いている作家は多いだろう。私もそのうちの一人だ。
口を覆っていた両手を外した新井さんは、肩を落としながら大きなため息をついた。
「……頑張って隠してるんですよ……?これでも……」
「ははは。隠さないでいてくれた方が助かります」
「ぅぅう……、もう!早く片しちゃいましょう!食器は台所に置いたらいいですか?」
「はい、それでお願いします」
恥ずかしさを誤魔化すように作業し出した新井さんを微笑ましく思った。
*
「先生、怖い体験って実際にしたことあります?」
食器を片し終え、段ボールを畳みながら新井さんらしい話題が飛んできた。
「いやぁ、特には」
「ですよねぇ」
「新井さんはしたことないんでしたっけ?」
「そうなんですよぉ。オカルト大好きなのに。毎日怪談動画とかホラー映画とか観てるのに」
「やっぱり心霊的な体験に興味があるんですか?」
「もちろんですよ!霊感ないので!」
「見えない世界だからこそってやつですね」
「私、絶対怖がったりしないのに」
新井さんは幽霊に出会っても、生きてる人間だと思って攻撃してしまいそうな気がしなくもない。
「ふ」
「あ、先生!今、笑いましたね!」
「あ、いえ……すみません……ぅふ」
いけない、いけない。幽霊に裏拳する新井さんを想像したら、面白くてつい。
「先生も怖い体験をしたら、話のプロットにするより先に私に報告してくださいよ?」
「……っ、心得ております」
「もう!また笑って!」
幽霊に飛び蹴りを喰らわす新井さんのことを考えるのは、もうやめておこう。
「いやぁ、でもさっきの業者さんじゃないですけど、先生の『呪縛の男』ほんとに面白かったですよね」
「ありがとうございます」
「『死んだ母親に執着される息子の話』……原稿を読ませてもらった時、ワクワクしましたよ。怖くって」
「怖いのにワクワクなんですか?」
「オカルト好きにとって、怖いとワクワクは紙一重なんですよ!」
新井さんは興奮気味に言った。
「先生の作風とホラー、合うんじゃないかなって思ってたんですけど、まさかあそこまでとは」
「……」
ホラーの名手、か。
ありがたい肩書き、煽り文句だと思っている。これのおかげで作家を続けていられるし、業者の殿方や新井さんのように〝面白い〟や〝ワクワクする〟といった感想をもらえるのも恵まれていることだと理解はしている。
これが、BLでもできたらな。
〝好きなジャンル〟と〝得意なジャンル〟は違う。いくら望んだとことで、私には〝好きなジャンル〟は書けない。
……ある意味、呪縛なのかもしれない。
「ところで、先生」
「っ、はい」
「次回作の打ち合わせなんですけど……先生も引っ越しされたばかりですし、しばらくはリモートでやろうかと思ってるんですけど、どうですかね?」
「構いませんよ」
「ありがとうございます!日程のメールは改めてお送りしますね」
「気を遣っていただいて、すみません」
「いえいえ、お気になさらず!」
新井さんが作業に戻るタイミングで、持っていた空のダンボールをひっくり返した。
「でも、本当にいいんですか?ご馳走になっちゃって」
「手伝ってくれたほんのお礼ですので」
街頭の明かりがつきはじめた道を新井さんと並んで歩く。
「駅前にあったファミレスでもいいですか?」
「もちろんです!」
人と外食なんて、いつぶりだろう。
「いらっしゃいませ」
ちょうど夕飯時。店内は家族連れやカップル、仕事帰りのサラリーマンで賑わっていた。
「二人なんですけど」
「かしこまりました。ご案内いたします」
通路の奥のボックス席の前でウェイトレスが立ち止まる。
「こちらの席でよろしいですか?」
肩越しに振り向くと、新井さんがにこにことしながら頷いていた。
「はい」
新井さんと向かい合えるように、壁沿いのソファに腰掛ける。テーブルに置かれているメニュー表を開いたと同時にジーンズのポケットに入れていたスマートフォンが震えた。
「お好きなのどうぞ。ちょっと一服してきます」
「わかりました!」
席を立って、入口を出てすぐの喫煙所へ早足で向かう。
「ごゆっくりどうぞ」
すれ違いざまに挨拶をしてきたウェイトレスへ軽い会釈を返し、入口の自動ドアを通った。
喫煙所の扉を開けると、中には先客が何人かいて、それぞれ紫煙を纏いながら、スマートフォンの画面に釘付けになっていた。
奥の隅に寄りかかって、ジーンズの右ポケットからスマートフォンを取り出す。
「……」
画面を操作して、スマートフォンを耳に当てた。
「はい」
『マコト』
どこか頼りない声。
「ハジメさん」
『すまないね、急に』
申し訳なさそうに謝る相手……中橋ハジメ。私の元旦那。
「今、出先だから。後でかけ直す」
『あぁ、邪魔して申し訳なかったよ。忙しいみたいだから、また今度でも』
「いや、後で。絶対かける」
『……すまないね』
「すまなくない。またあとで」
『うん。また』
耳からスマートフォンを離し、電話を切って右ポケットへ。
「……」
左ポケットから煙草とライターを取り出し、咥えて火をつけた。
*
「いやぁ、先生。今日は本当にありがとうございました」
「こちらこそ。すごく楽しかったです」
「私もです!最後に食べた三色団子のパフェ、美味しかったですね」
「そうですね」
改札の近くで立ち止まって振り向いた新井さんと向かい合う。
「では、明日に打ち合わせの日程メールをお送りしますね」
「はい。お願いします」
「今日は本当にありがとうございました!」
「お気をつけて」
「はい!先生も!失礼します!」
会釈をする新井さんへ小さく手を振りながら、改札を通るのを見送る。
今日は新井さんのおかげで、いい一日だった。
駅前の喫煙所には入らず、スマートフォンを取り出しながら、帰路につく。
通話履歴から〝中橋ハジメ〟をタップした。耳にスマートフォンを当てた。
『もしもし』
「お待たせ」
『待ってないよ』
「嘘。一時間は経ってる」
力なくハジメさんは笑った。
『うん、待った』
「……連絡、ありがとう」
『こちらこそ』
「今は何を?」
『煙草』
「……喫煙所、行けばよかった」
『ははは』
力ない笑い声のすぐ近くでライターをつける音が聞こえてくる。
「引越し、無事に終わった」
紫煙を吐き出す息の音。数秒の沈黙。
『お疲れ様』
暖かみのある声。
「担当さんが手伝ってくれた」
『へぇ、いい担当さんだね』
「本当に」
再び訪れる数秒の沈黙。
『そうだ、読んだよ。『呪縛の男』』
ハジメさんの言葉に思わず息を呑む。私は、今日までこの瞬間を待ち望んでいたから。
『ありがとう』
「……」
『マコト』
ハジメさんの声が私の名前を呼んで、黙る。
『……』
「なに?」
『……』
「言って」
『……』
紫煙を吸わない、重たい沈黙。ハジメさんの言葉を静かに待つ。
『……いや、いいや。僕には言う資格がないことだから』
「……」
胸の内が曇る。
『……マコト』
「……」
『次の作品も必ず読むよ』
……。
『じゃあ、また』
ハジメさんは私の言葉を待たずに電話を切ってしまった。通話終了の音がひとりでに鳴り続ける。
「……はぁ……」
重たいため息が春の生暖かい風に紛れて、飛んでいった。
*
「……」
換気扇の下で紫煙をぼんやり眺めながら、ハジメさんとの電話を回顧する。
『……いや、いいや。僕には言う資格がないことだから』
「……」
煙草を灰皿へ押し付け、火を消した。
換気扇はそのままにリビングへ移動して、折り畳みテーブルの脚を立てた。その上にパソコンを置いて、起動させる。
デスクトップに表示されている『呪縛の男』という名前のファイルをクリックして、要項をまとめた書類ファイルを開く。
<『呪縛の男』>
<ジャンルはホラー>
<主人公は三十代の男性>
<男性は幼い頃からずっと母親の異常な執着に苦しめられていた>
「……」
<男性はある日、母親からの電話を受けながらこう思った>
<『俺の幸せのために死んでくれればいいのに』と>
<その数日後、男性の母親は急病で命を落とした>
<自分が念じたからではないないかと思う反面、これでやっと救われると思う男性>
<だが、母親の葬儀の後も死んだはずの母親に執着され続ける>
「……」
<『呪縛の男』のラスト>
<追い詰められた男性は、母親の眠る墓から遺骨を盗む>
<恨みの言葉を吐きながら、母親の骨を砕き燃やす>
<その瞬間、本当の意味で母親から解放された男性が高らかに笑う>
『呪縛の男』は中橋ハジメをモデルにした中橋ハジメだけの物語。
もしかしたら、ハジメさんにあったかもしれない未来。こうなっていたかもしれない未来。私からハジメさんへ。たった一つ、渡すことが許されるもの。
「……」
この話を書き終えてしまった今の私には、この先のことを考える余力は残っていない。
ふとした時にアイディアは浮かんでも、それを形にする作業にまでたどり着けない。
「はぁ」
期待されている以上、書かなければならないのが作家。
期待されなかった時期が長かったからこそ、書き続けなければと焦りを感じてしまう。
「……」
今の私は〝空っぽ〟だ。
*
「マコト」
ハジメさんは、俯いている。
長い前髪が、ハジメさんの表情を隠している。
「すまない」
向かい合っているのに、心は相反している。
ハジメさんは、引き結んでいた口を開いた。
「離婚しよう」
「……っ!」
目の前にハジメさんはいない。代わりにビニールテープでまとめられた段ボールの束が二つ。
……夢……。
今の状況を新井さんに相談しようかどうか迷っているうちに眠っていたらしい。
軋む上半身を起こした。
……久しぶりにみた……。
パソコンの画面の明かりが、煌々と暗闇の中を照らしている。
……書き終わって以来かも……。
パソコンの画面を閉じ、台所へ移動する。
換気扇の電灯をつけ、煙草を一本、箱から取り出した。火をつけ、灰皿に置く。
グラスに水道水を注ぎ、口に含んだ。
「……」
離れるほかなかった。たったそれだけ。
ハジメさんの事情に私を巻き込まないための選択だった。
別にヨリを戻すつもりはない。ハジメさんもそうだから。それでもタイミングをみて、私に連絡をくれるこの関係がひっそりと続いてくれればそれでいい。
煙草の燃え尽きた灰が、灰皿に静かに落ちた。
「……考えよう……」
二話→https://note.com/tony_dc1212/n/n096b88e6d0c6
お読みいただきありがとうございました!本編は4月後半にアルファポリス、pixivにて公開予定です!
よければ、マシュマロにて感想いただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
