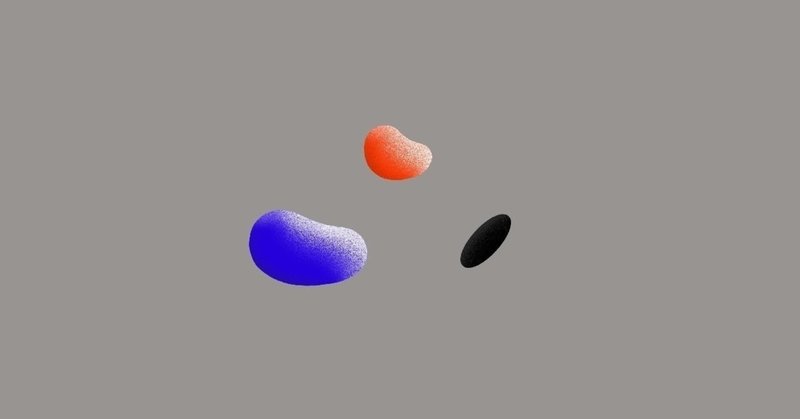
文章練習5[3分短編]
ラディカルズモールは若者のるつぼだった。通りの一つ一つにパーフィルやカンテラといった名前がついており、立ち並ぶ輸入品店にはつま先の真っ赤なマクラックや、ハー・マジェスティーズ・シアターのオペラ座の怪人からくすねてきたのかと思えるほど年季の入ったコンソールテーブル。2005年のワールドシリーズ優勝を記念したホワイトソックスのタペストリーが飾られていて、88年ぶりの優勝! と書かれたポップが掛けられているのを見るたび、私は頭の中で、白黒の映像世界に囚われた巨大な白人たちが、フィルムのノイズに捲し立てられるようにせかせかと、私の身の丈ほどもある木の棒を乱暴に振り回しているところを想像した。そしてただ漠然と、そのような景色に[忘れられた時代]というテロップが添えられて頭の中を巡るのだった。だが兄はこういった表現を好まなかった。私がこの類の妄想を口に出すと決まって、楽しい話をありがとう、もっと聞きたいから次は俺がいない時に話してくれといった。
兄はいわゆるワルだった。いつか平塚の市営球場わきのダイナーから盗んできた原付バイクを私に売りつけようとしたことがあった。鍵はないが悪くないバイクだ、必要なら二万円で売ってやるといった。次の日、母は年次有給休暇を使うはめになり、兄は警察署で小突き回されて帰って来た。彼は路上に置かれているものは食台の爪楊枝程度にしか思っておらず、もしも可能ならば神奈川そのものを私に売りとばそうとしただろう。私が14歳の時、酒に酔った兄は突然、いちごを食いに行こうと言い出し、戸惑う私を父のデリカの後部座席に乗せ、ブレーキの踏み方を忘れたのか、最初からそうするつもりだったのか、農園のハウスを一棟めちゃくちゃにしてしまった事がある。車内ではシカゴのBaby What A Big Surpriseが流れていた。“ベイビー! こりゃ驚いた! 私の目の前にバラバラのいちごハウス! ”
この出来事がきっかけで兄は高校を退学するはめになり、ワル仲間とラディカルズモールを根城として山賊のように振る舞うようになってしまった。おい酒はあるか。いや無いな。ならひとっ走り下の店から”借りて”こいよ。といった具合だ。だが、こういっては何だが、私はそんな兄をとても好いていた。母は兄をダイニングに呼び、お前はなぜまっとうに生きられないのかと問いかけた。母はこの類の質問をする時、とりわけ相手を責める語気を隠そうと必死に努めていたが、これは無駄な努力だと私は思った。まっとうってのはどういうことだ? ダイニングチェアの背に片手を乗せて、(おそらく酔っ払っているのだろう)頭をゆらゆらと揺らしながらシンクに腰をもたせかけて兄は目を閉じた。捲れ上がったシャツの裾からスタッズベルトがのぞいている。ああ、私の憧れのワル。いいか、ばあさん。まっとうってのはナショナルズのソトみたいにバッターボックスで、でっかいキンタマ持ち上げて馬鹿みたいに稼いで回ることを言ってんのか? それとも親父みたいに、頭の悪いチーマーのカマロやスカイラインを言われるままにいじくり回してめっきり乗りづらくする自動車工のことか?
どちらともよ。と母は言った。今度は先ほどよりも強い口調で。私はトムとジェリーでマミー・トゥー・シューが居眠りするトーマスを叱りつけている姿を想像した。ほらトーマス!お客さんだよ!キンタマを持ち上げてさっさとあの下品なフェンダーを取り付けてらっしゃい!
私が大学に入学する年、久しぶりに兄と会話をした。地元の商業高校を卒業して大学でビジネスマーケティングを学ぼうと志す人間の多分に洩れず、私はワルの兄弟が疎ましく感じるようになっていた。兄は荷造りをする私の後ろで戸にもたれかかり、私が作業するところを何も言わずに眺めていた。ひょっとしてその両肩からぶら下がっているのは腕じゃないか?もし余っているなら手伝ってくれてもいい。と私がいうと、兄は、あいにく予定で埋まってる。と言った。しばらく沈黙が続き、お前はもう一人の俺だと言った。俺はソユーズ、お前はアポロ。お前は俺のもう一つの可能性だ。私はどう返答して良いのかも分からず、手を止め何か言おうとしたが、結局何も思いつかずに手元の作業に戻った。振り向くと兄は居なかった。結局のところ、兄とまともに会話したのはこれっきりだった。
あれから20年だ。私は兄のようにはなれない。なりたくはないが、なれないのも事実だった。閉鎖されたモールはレゴの空き箱のようだった。私は敷地をぐるりと500メートル裏手まで歩き、どこか忍び込めそうなところはないか探して回った。一角に金網で囲われた搬入口が見えたので、リュックからボルトクリッパーを取り出し、その錆びた金網に40センチほど切れ目を入れて身体を潜り込ませた。辺りにはスナック菓子の空袋や潰れた空き缶が散乱していた。関係者以外立ち入り禁止のパネルが貼られた扉は簡素な引き戸で、ところどころ黒緑色の苔が蒸していた。高い位置に従業員用トイレの窓が設えられているのが見えたので、私は大きく爪先立ちをして窓の棧を動かしてみた。すると、じゃりっという音と共に窓が小さく開いた。
私は、この兄の根城がとり壊されてしまう前に、もう一度兄の痕跡に触れたいと思った。店内は何もなかった。比喩ではない。本当に何もなかった。スポーツ用品店も、トイザらスも、マクドナルドも、音も光さえも。暗く乾いた空気に私の足音だけが響いた。ふと、いつか見たホワイトソックスのペナントはどうなっただろうと思い、記憶を頼りに二階のフードコート脇を目指した。真っ暗な通路の端に切り抜かれた歪な形のその店舗は、天井から飛び出した空調や電気設備の配線が垂れ下がり、もう100年は人の手が付いていないように見えた。暗い店舗の奥、コの字型の汚れたカウンターに、折り畳みのパイプチェアが持たせ掛けてあるのが見えた。私はその内の一つを広げて腰掛けた。
やあやあ、みなさん。ここは世界中からかき集めた過去のガラクタが吹き溜まる場所。ソユーズからアポロまで、夢の残骸が集う場所。私の声は店内に響き渡り、そしてまたすぐに静寂が訪れた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
