
この辛さをわかって欲しい。なぜパートナーに「お前も苦しめ」と思ってしまうのか。
自分が苦しんだから、お前も苦しめ。
そんなふうに思ったことがある人は、少なくないのではないだろうか。
かくいう私もその一人で、出産後、ワンオペ育児の最中、何度もどす黒い気持ちまった。自分が苦しいからといって相手も苦しくなったところで、なにも良いことはない。むしろそれは非建設的な考え方で、なにも生み出しはしないし、なにも変わらない。それがわかっていても、どうしても止められないのだ。
私はこんなに大変な思いをしているのだから、あなたも同じ思いをすればいい、と。
辛さを見てもらえないという孤独
「お前も苦しめ症候群」と言われる、この感情。
それは底なし沼のように深く、冷たく、そして暗い。こんなところにいても意味がない、早く脱出しなければと頭ではわかっていても、足に泥がまとわりついてズブズブと沈んでいく。
これはなぜなのだろうと考えている時に、私はある一節と出会った。
誰でもひとりで苦しむのは、耐えられません。誰かその苦しみを分かってくれる、見ていてくれる人がいると、案外耐えられます。
——『ネガティブ・ケイパビリティ』より
これは『ネガティブ・ケイパビリティ』という本の中で書かれていた文章だ。
ネガティブ・ケイパビリティとは、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」を示す。もともとは1800年代にイギリスの詩人ジョン・キーツが示した言葉だが、回り回って21世紀の日本で、私はこの言葉を知ることとなった。
この本の著者は、帚木蓬生(ははきぎ ほうせい)先生という方だ。箒木氏は精神科医としてクリニックを開業されている。そのクリニックは精神科診療だけでなく、心身の健康に関するよろず相談をも受け付けている。そして日々の診療の場において、このネガティブ・ケイパビリティが非常に効力を発揮すると記されていた。
身の上相談には、解決を見つけようにも見つからない、手のつけどころのない悩みが多く含まれています。主治医の私としては、この宙ぶらりんの状態をそのまま欲し時、間に合わせの解決で帳尻を合わせず、じっと耐え続けていくしかありません。耐える時、これこそがネガティブ・ケイパビリティだと、自分に言い聞かせます。すると耐える力が増すのです。
——『ネガティブ・ケイパビリティ』より
例えば、抑うつと不眠を訴えてやってきった50代女性。姑との関係に悩み、そのことが原因だと分かっても、医師としてどうすることもできない。薬を処方することはできても、根本の原因である嫁姑問題に切り込むことはできないのだ。まさか患者に「あとは姑が死ぬまで我慢です」と言うわけにもいかない。それでも患者から逃げずにじっと主治医としてあり続ける。そのために必要なのが「ネガティブ・ケイパビリティ」なのだ、と。
医師としての「胆力」とも言える、ネガティブ・ケイパビリティ。
これを支えているのが「人は誰かに苦しみをわかってもらえると、その苦しみに耐えられる」という考えだと思う。
人は、前に述べたように誰も見ていないところで苦労するのは辛いものです。誰か自分の苦労を知って見ている所なら、案外苦労に耐えられます。患者さんも同じで、あなたの苦労はこの私がちゃんと知っていますという主治医がいると、耐え続けられます。
——『ネガティブ・ケイパビリティ』より
これを読んだ時、私は「お前も苦しめ症候群」の原因を見たような気がした。
分かってくれない、見てくれない。だから”味わって”ほしい。
ワンオペ育児は、孤独だ。
理屈なんて通用しない、不可解で謎の多い生物を、必死に守り抜かないといけない。顔を真っ赤にしている赤子を前に、濡れてもいないオムツを替え、拒絶されながらもミルクを上げ、抱っこし、あやし、座ることもできず、休むこともできず、ただひたすらに耐える。逃げ出したいと思っても逃げられない。辛くて涙が流れても、誰かが助けに来てくれるわけでもない。行政の電話相談はつながらない。どこかに出かけたくとも、荷物を用意する気力など残っていない。パートナーは帰ってこない。もし自分がここで死んでしまったとしても、目の前にいる無力な赤子の命は守らないといけない。だからこそ、歯を食いしばって踏ん張るしかない。
それが辛くて、あまりにも辛くて。
その辛さを、必死にパートナーに訴えようとする。伝えようとする。
今日はこんなことがあってね。
夜泣きが激しくて、1時間も抱っこしつづけたんだ。
上手におっぱいを飲んでくれなくて、必死に工夫したんだ。
夜中に4回も起きてね、3時間以上、続けて眠れっていないんだ。
それでもお昼寝をしている間に、部屋を片付けてご飯の準備をしたんだ。
そうやって伝える。
伝わって欲しい、ただただ伝わって欲しいと祈りながら、伝えようとする。
それでも、伝わらないときがある。
「へえ〜、大変だったね」と言ったその直後に、お酒を飲んで眠ってしまったりする。あんまり掃除できていないんだという謙遜をそのまま「掃除できてないんだよね」と返されたりする。
わかってくれないのだ、となる。
だったら次は、目の前でやってみせたらどうだろう、となる。
休日。ろくに眠れていない体を引きずりながら、慌ただしく朝食の準備をする。それが終わったら洗濯機を回して、掃除機をかけて、離乳食の準備をする。合間に授乳をして、オムツを変えて。
その横で、パートナーは座っている。
「これをやって」と言ったらやってくれる。でも、それでは不十分なのだ。隣で必死に動いて、働いて、「こんなに大変なんだよ」「こんなにたくさんのことをしているんだよ」と示そうとしても、見向きもしてくれない。気付いてすらくれない。「今日はやることがあって大変だった」というと「そう?ちゃんとできてるじゃない」と的外れなことを言われたりもする。
言ってもダメ。
見せてもダメ。
じゃあ、どうしたらいいのか。
そこで出てくるのが
「お前も同じように苦しめ」
という感情だ。
つまるところ「お前もこの苦しみを味わえ」というのは「この大変さを経験知ってちゃんと認識しろ」「私が経験する辛さを見て欲しい、辛さがそこにあるのだということをわかって欲しい」という気持ちの裏返しなのだと思う。
ワンオペ育児は孤独だ。
それでも、誰かがその孤独をわかっていてくれたなら、まだ頑張れる。
でももし、誰もわかってくれなかったら、見ていてくれなかったら。
それは絶対に、頑張れない。
言葉では伝わらない。
隣にいても理解してもらえない。
ならば身をもって”味わって”もらったら、この辛さに気付いてくれるかもしれない。
それが「お前も苦しめ症候群」の正体なのかもしれない。
意外な人が見ていてくれた。
『ネガティブ・ケイパビリティ』を読んでから数日後。
私は初めて「育児を見ていてくれた」という経験をした。
それは平日の夕方。いつものように仕事を終えて、息子を連れて帰ってきた時のことだった。いつものようにひとりでバタバタと夕食の準備をしていた時のこと。
おもむろに、息子が掃除機を持って遊び始めた。
リビングに無造作に置かれていた掃除機の、自分の背丈よりも大きいパイプ部分を持って、掃除機をかけ始めた。いつも私がしているように、ノズルを滑らせ、部屋の角を掃除し始めた。
その姿を見た時、私は「見ていてくれた」と思った。
息子は、見ていてくれた。
生後1ヶ月のころから、育児の合間をぬって掃除をしていた私のことを、見ていてくれた。一人遊びをしてくれるほんの短い間に、あるいは抱っこ紐に入れて家事をしていた間に。誰も見てくれない、誰も気付いてくれないと思っていた”掃除機をかける”という地味な作業を、見ていてくれた。
そう思った時に、私はどこか救われたような気がした。そして同時に、本で書かれていた「人は誰かが見てくれていたら、案外、辛さに耐えることができる」という一節を思い出した。
ただ一人で苦しみに耐える。
それほど、辛いことはない。
だからこそ、その苦しみから逃げたくなるし、どす黒い感情に支配されそうになる。
それでも驚くほど意外なところから救いは訪れるのかもしれない。そんなふうに、希望を持ってもいいのかもしれない、と。私は今日も、リビングで掃除機を引っ張る息子を見ながら、しみじみと考える。
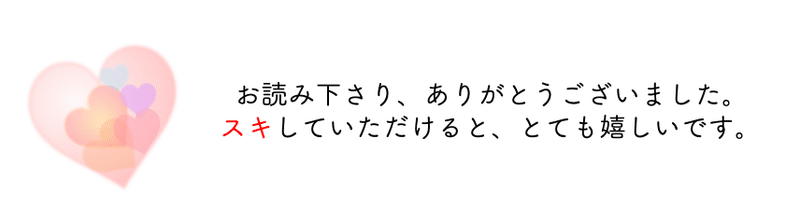
お心遣いありがとうございます。サポートは不要ですよ。気に入っていただけたら、いいねやコメントをいただけると、とても嬉しいです。
