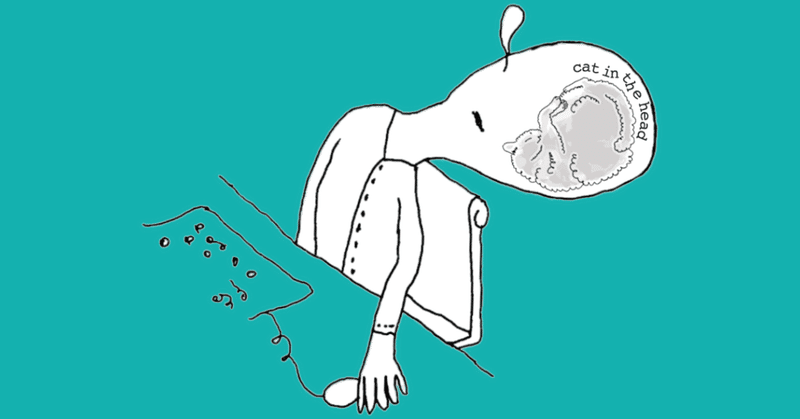
仕事に全振りしていた女医が、出産して知った「生活を営む」ということ
出産して、たくさんのことが変わった。
それまでできていたことができなくなったり、必要なかったことが必要になったり。自由な時間はより少なく、できることもまた少なく。誰かの手を借りることが増え、助けを求めることも多くなった。総じて出産前の自分よりも「弱くなった」「できなくなった」と感じる機会が増えた。
それでも、出産することで、子どもを生み育てることで、初めて理解できるようになったことがあった。それは「生活を営む」ということだ。
気絶して記憶のない日々
「どうやって生活しているの?」
社会人になってから、一番答えに迷った質問だ。毎日なにを食べているのとか、どこで服を買うのとか、休みの日はなにをしてるのとか。そんなこと「他愛もないこと」に、ずっと答えられずにいた。
答えられなかったのは、本気でわからなかったからだ。本気で、まったく、自分がどうやって生きているのかを思い出せなかった。
就職してから最初の2年はとにかく怒涛だった。慣れない仕事、うろ覚えの機器や薬品の名前、技術も知識も足りないのに「医師」として責任が問われる仕事。指導医を探して病院中を右往左往し、退院の見通しの立たない患者さんを前に途方に暮れていた。
いわゆる「意識高い系」の野戦病院だったこともあり、業務は多忙だった。未熟な研修医を支えるバックアップ体制も整ってはいなかった。それでも同期は優秀で体力のある人が人が多く、どんどん成長していく姿を横目に見ながら、深夜に帰宅しベッドに突っ伏す毎日が続いていた。
当時の私は、仕事のために生きていた。
仕事をするために生きる。仕事をするために食べるし、洗濯をするし、服を着る。気絶するような毎日の中、どうにか生きていたし、どうにか人間として生活をしていた。それなりに生活をしていたはずだが「主体的に生活を営む」ことはついぞ出来なかったように思う。
駆け出しの研修医。独身の24歳。
仕事以外にすべきこともなく、仕事を犠牲にしてでもやりたいこともなかった。一日でも早く医師として習熟する必要があったし、そのためには全生活を仕事に振り切らなければ到底間に合わなかった。良くも悪くも、仕事に隷属する人生だった。
口にするものはカロリーの塊だった。身に纏うのは布だった。ベッドはただ横になる場所で、時間は仕事に吸い込まれていった。
出産後。制限ができて初めて、生活を組み立て始めた
最初の2年間ほどではないが、出産するまではそんな日々が続いていた。それは結婚しても変わらなかった。私も多忙だったが、それ以上に夫も多忙だった。「結婚したばかりだから夫婦の時間を大切にしよう」という話し合いをする暇さえなく、「結婚相手にうつつを抜かしている暇があれば仕事をしなければ」と見えないプレッシャーに急き立てられていた。第一は仕事。自分や家族や娯楽は二の次。私自身も、そして周囲の医師も含めて、冠婚葬祭よりも仕事を優先させることが多かった。出産の立ち合いすらままならない、立ち合いをしたいので仕事を休むとは言えない謎の風土もあった。
その生活が一変したのは、出産して里帰りを終えた時だった。
実家から離れ、私は息子とともに自宅に戻った。夫は相変わらずフルタイム勤務で、息子と触れ合うのは朝の1時間だけ。それ以外の時間、寝かしつけまでを私ひとりでこなす必要があった。
産後の生活は大変だった。慣れない育児が大変だったのもあるが、それ以上に「出産前のように身動きがとれない」ことで生活は大きく一変した。食べたいものがあっても気楽に買い物に行けない。日用品の買い出しも一苦労。夏真っ盛りで、乳児を連れての外出も憚られる時期。一日中、どこにも出かけず家にいることもあった。出産前に比べて、想像以上に自由度が下がった。
それまで行き当たりばったりでも生きて来れたものが、多少の計画性や戦略を持たなければ生活できなくなった。自分がなにを食べ、どこから調達し、どれくらいの計画性を持って消費すればいいのか。時間と体力に限りがある中で、どうやって「自分を生かしていけばいい」のかを考えなければならなかった。
料理をする習慣のなかった私は、自分ができる範囲で「自分の食事を計画的に用意する」ことから考える必要があった。冷凍のお弁当と冷凍パスタ、ラーメン、ふりかけご飯でしのいだ。週末、スーパーで買い出しをしたり、たまに散歩してコンビニでご飯を買ったりしていた。その頃から私は、「自分が食べるもの」をちゃんと意識するようになっていた。それ以前の生活や食事の記憶はかけらも残っていない。
自分で自分の人生を組み立てる経験は、それ以降もどんどん蓄積されていた。
育休復帰をしたら自由な時間はますますなくなった。自分の全てを仕事に振り切ることもできず、毎日どこかで強制的に「仕事ができない時間」が生み出された。子どもをあやしながら、仕事をすることもできず、仕事について考えることもできない時間。その時間を使って、私は自分の生活を設計するようになっていた。
例えば毎日着る服。どんな組み合わせにすれば悩まずに済むのか、どこで調達すれば値段や手軽さがマッチするのか。どんな靴なら服装を選ばないのか、持ち物はなにが必要か。
食事も同様で、息子の食事と、息子を連れて帰って自分が食べる食事の両方を用意する必要があった。ミールキットなどを色々試した結果、生協+ホットクックの組み合わせで決着した。ホットクックで作る料理も、いくつかのパターンや組み合わせで考えるようになった。
睡眠時間にも気を使うようになった。保育園に通う息子は、平日土日を問わず、毎朝必ず6時に起きる。それにつられて私も、毎日同じ時間に起きるようになった。睡眠時間を確保するために、遅くとも夜11時には布団に入るようになった。就寝時間や起床時間を一定にしたり、規則正しい生活を送るなんてことは、何十年ぶりかの経験だった。
出産してからたった2年の間に、「どうやって生活しているの?」という問いに一気に答えられるようになった。
フルコミットできないからこそ、作れるものはある
自分の時間を自由に使えるのはとても良いことだ。羨ましいことでもあるし、できるならば今でも欲しいものでもある。
一方で、それだけの時間があっても使いこなせないことがある、ということにも気づいた。ともすれば「自分以外のなにかに時間を占拠されてしまう」こともありうるのだと、出産して初めて理解したのだ。仕事を始めた当初の私は、自分の人生や時間、心身、誰かに売り渡せるもの全てを仕事にコミットさせていた。仕事に自分が使われている状態だった。
それが出産をしてガラリと変わった。
時間に制限ができた。それまで無限に仕事に吸い込まれていた時間が、不意に自分の手に戻ってきた。自分の時間を、自分でやりくりする必要が初めて出てきた。
限りある時間を「配分」する必要があった。仕事、家事、育児、そして自分自身に対して。時間が足りなければ、なにかをやめたり、捨てたりする必要があった。限られた時間の中で「やりたいこと」「すべきこと」を選択する場面も増えた。小さな生活の積み重ねが、日々の食事の記憶や衣類の選択、生活リズムに繋がっていた。自分の人生が、自分の毎日が、初めて記憶に残るようになった。30年以上生きてきてやっと「生活を営むとはこういうことか」と実感できた。
「営む」という言葉の由来は「暇がない」を示す「いと(暇)なし」から来ているらしい。そこから「せっせと努める」「執り行う」という意味に繋がっているらしい。
別の説として「糸編む(いとあむ)」が転じた言葉だとするとも言われている。説としては弱いらしいが、「営む」という言葉に通じるニュアンスは、しっくりくるものがあった。「営む」と「糸を編む」。日々の生活を送ることは、何かを編み上げるような、ひとつひとつの小さな糸目を積み重ねていく作業に似ている気がする。時々は編み目が抜けたり、ずれたりすることもある。それでも、ひとつひとつの時間を糸目にして、前へ前へと編み進めていく。
私が送っている生活は、決して「丁寧な暮らし」なんてものではない。そんなものからは程遠い。でも確かに、自分の手で、一日一日の糸を編み上げている実感がある。
出産をして、不自由に感じることも増えた。この選択が本当に正しかったのか、このまま人生を歩んでいけるのかと不安に感じることもある。
それでも確実に言えるのは、出産を経て、自分の時間や生活を自分の手の中に取り戻すことができた、ということだ。すべてを仕事に捧げることができなくなったからこそ、自分の生き方を設計できるようになった。生まれて初めて「生活とは、日々を営むことだ」と実感できるようになった。
人生100年時代。
取りこぼしてきた時間たちが手元に戻ってきたと考えると、これからの毎日が楽しみでもある。
お心遣いありがとうございます。サポートは不要ですよ。気に入っていただけたら、いいねやコメントをいただけると、とても嬉しいです。
