
「誠実な翻訳者」という役目。医師が情報を発信することについて。
先日、オンライン上でちょっとしたプレゼンをする機会がありました。
参加していただいたのは、同世代の方々。テーマは『予防接種』について。
私が個人的に興味を持って調べたことをシェアする形式でした。
そもそも、私は予防接種の専門ではありません。感染症内科医でもなく、公衆衛生にも携わっていません。医師免許を持った、ただの一般人です。
医師という専門家が「専門外」の医療情報を発信する。
その過程で生じた葛藤や迷い、自分なりに気をつけたことを書きたいと思います。
専門外だけど専門家。そのギャップ。
最初は、ごくごく軽い気持ちでした。
自分が勉強したことを、どなたかに伝えることができればいい、判断の手助けになればいい、という思いでした。
ですが予想外の反響をいただき、ありがたいと同時に、重い責任を感じました。
たくさんの方が「聞きたい」とおっしゃってくださったのは、私が医師免許を持っているからです。私の医師という職業を信頼して、集まってくださる。
ですが私は、予防接種の専門家ではありません。予防接種に関心があって、それに対するある程度の知識はあって、どういった情報を参考にすればいいかは何となくわかっている。けれど、専門ではない。
専門家だけど専門じゃない、というギャップ。
そのギャップの上で、医療情報を発信する。それは医療に携わる者として許されることなのか。自分の発言が、ある方の人生を左右したり、行動に過度に影響を及ぼすかもしれない。その覚悟を持てるのか、と悩みました。
できるだけフェアに伝えたい。
それでもやはり、自分が「伝えたいこと」というものはあります。
専門外である自分が医療情報を伝えるにあたり、できるだけ偏りがないように、そして誰かを傷つけたり縛ったりしないように。
以下のことに注意しながら、スライドの作成を始めました。
①自分の立場を明確にする。
②公的な情報を紹介する。
③不確実さについて伝える。
④論文は引用しない。
⑤個人的な考えは分けて示す。
⑥誰かを傷つけない、不安を煽らない。
①自分の立場を明確にする
最初に自己紹介のスライドを作りました。そこでは
・予防接種は専門外であること。
・それらに関する診療には関わっていないこと。
・予防接種に賛成であること。
を書きました。
シェア会をするにあたり、情報は情報としてフラットに、感情的にならずに伝えたいと考えていました。ですが、そもそも私は予防接種に賛成の立場なので、無意識に賛成よりの考えや感情が出てくる可能性がありました。
そのため卑怯かもしれませんが、最初から「これから提示する情報には偏りがあるかもしれません」ということを伝えました。これによって受け手側に「与えられる情報がすべて正しいとは限らない」と疑いを持ってもらいたいと考えました。
②公的な情報を紹介する
スライドは誰でも閲覧できる公的機関の日本語の資料をもとに作成しました(一部英語はありましたが、95%は日本語で閲覧できるものです)。参加してくださった方が、後から内容について吟味できるようにするため、そういった情報を中心にしました。
私がお伝えできるのは、一般に開かれたもののみです。医師だからと言って「ここだけの耳より情報」はありません。その手の情報が手に入る立場ではありませんし、仮にあったとしても、慎重に扱う必要があると考えています。医療は公共財です。予防接種はとりわけ公的なもので、誰に対しても適切に提供される必要があると考えています。「特別にお金を払ったから」「ツテがあったから」いい情報、いい医療にアクセスできる、というのは医療のあり方から外れてしまうのではないかと考えました。
引用した情報は主に、厚生労働省、日本産婦人科学会、日本小児科学会、米国FDA(Food and Drug Administration)から得ました。個々の病院やクリニックからの情報は一切使いませんでした。
③不確実さについて伝える。
医療に限らず、科学というのは非常に不確かなものです。
「1+1=2」という、この世の真理とさえ思われがちな理論ですら、時として破綻します。(泥団子と泥団子をひっつけて大きな泥団子にすれば。質量という概念では2になりますが、個数という概念では1のままです)
医学では「わかっていない」ことがたくさんあります。報告がないからと言って「存在しない」とは言えず、今「正しい」とされる論理も、10年後には「誤り」になるかもしれない。
そんな不確かな中で、今わかっていることは何か、どんな報告があり、どう解釈されているのか。何がわかっていて、そして何がわからないままなのか。
そういったことを要所要所に織り交ぜながら、話を進めました。
明瞭な答えを求めている方には、期待外れだったかもしれません。ですが医療というのはそれほど不確実で、そして曖昧なものであるということをお伝えすることが、医師としての誠実さではないかと考えました。
④論文は引用しない。
公的な組織から発表された資料というのは、様々な研究結果や報告を元に作成されています。いわゆる「論文」と呼ばれるものです。
この「論文」について、私はほとんど触れませんでした。
というか、触れられませんでした。
論文は、言ってしまえば玉石混合です。論文があったとしても、それだけでは「正義」や「正論」にはなりません。例えば「AはBの原因だ!」と結論づけている論文があったとして、それだけで「AはBである!」と断定するのはあまりに危険です。
論文には『読み方』があります。『批判的吟味』とも呼ばれる手法です。
書かれている内容が適切なものか、どのように解釈し、どのように取り入ればいいのか。論文を読み解くには、この『批判的吟味』のスキルが必要です。そして私はまだ、これを完全に取得していません。目の前にある論文が適切か否かを判断する技術がなく、そして時間的な余裕もありませんでした。
"よくマスコミの人は「ネイチャー、サイエンスに出ているからどうだ」という話をされるけども、僕はいつも「ネイチャー、サイエンスに出ているものの9割は嘘で、10年経ったら残って1割だ」と言っていますし、大体そうだと思っています"
——「ノーベル賞の本庶佑氏は説く、常識を疑う大切さを」
「9割が嘘」というのは誇張かもしれませんが、学生時代「10年経ったら、どんな一流ジャーナルでも3割の研究結果は再現できないとされている」と教わりました。一流雑誌に載ったから正しい、論文があるから正しい、ということではないのです。
なにかの論文があったとして、それを『批判的吟味』を知らない非医療従事者の方に「こういう論文がありました。だからこれが正しいんですよ」と提示するのは、フェアではないと私は思います。
⑤個人的な考えは分けて示す。
それでもやはり、自分の考えや感情が顔を出します。ここはこういうふうに伝えたらもっと伝わりやすいのに、とか、これは恐らくこうだったんだろうな、とか。伝えるために追加したい文言がありました。
そこで私は「これは個人の考えですよ」と分かるようにして、スライドの合間に自分の考えや意見を差し込むようにしました。
受け手の方が「ここは出典がある部分」「ここは個人的な考えで科学的に証明されているわけではない、不確かな情報」と分かるようにすること。それが感情と事実を混同させないためには必要だと思いました。
⑥誰かを傷つけない、不安を煽らない。
医療というのは、生身の人間が関わっています。
医療の対象となるのも、そして医療を提供するのも、すべて人間です。
聞き手の方の中には、このどちらかに、あるいは両方に属している方がいるかもしれない。できるだけ誰も傷つけないような、誰の考えや感情を否定しないようなスライド作りを心がけました。
予防接種の副作用があったとして、それが仮に1万人に1人であっても、その1人は確実に存在します。それは1万という数字に埋もれていいものではありません。「命」というのは本来、数で比較ができないからです。できるだけ中立に、フラットに、言葉や文言を選びました。
また、受け手を誘導するような強い言葉も避けました。具体的には「AをしないとBというとても恐ろしい状態になります」などです。医療や病気には、人を不安にする要素がたくさんあります。不安を利用して、特定の方向に扇動することも可能です。ですが、それはフェアではありません。
社会に対して「誠実な翻訳者」であること。
以上のことに注意しながら、スライドを作成しました。
専門家である自分が専門外のことを伝える意義とはなんだろう。
自分の説明が、誰かを傷つけたり追い詰めたりしないだろうか。
テレビ番組で解説をしているコメンテーターの方との違いは何だろう。
悩みながら、手探りでの作業でした。
幸いなことに、シェア会は穏やかに終わりました。聞いてくださった方からは温かい言葉をいただき、本当に恐縮しています。
「知らなかった世界を知りました」
「これから、もっと積極的に情報を集めようと思いました」
そんなご感想をいただき、私は「自分の発信が医療と社会を『翻訳』する役目を担ったのだ」と感じました。
一般の方よりほんの少しだけ、私は医療の近くにいます。医療用語や考え方にも日常的に接しています。そこで得た知識や経験を使って、医療に携わっていない方に医療についてわかりやすく『翻訳』することが、発信の意味だったのではないか。
専門家として、社会と専門分野との「橋渡し」をする。
過度に誇張することも、矮小化することもなく、自分の持てる知識を冷静に使いながら、誠実に「翻訳」をする。
社会に対する「誠実な翻訳者」であることが、自分が医師として発信する意義であり、そして責任なのかもしれない。
今回の経験を通して、私は今、そんなふうに感じています。
最後になりましたが、このような機会をいただいたことに心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
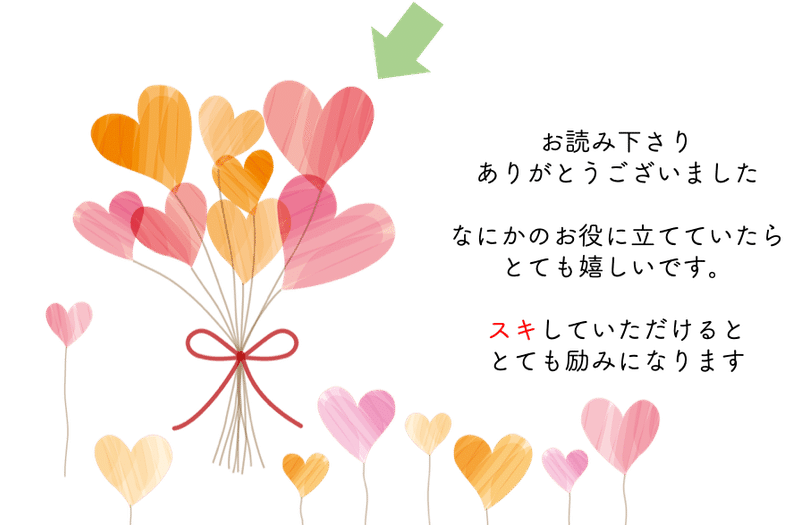
お心遣いありがとうございます。サポートは不要ですよ。気に入っていただけたら、いいねやコメントをいただけると、とても嬉しいです。
