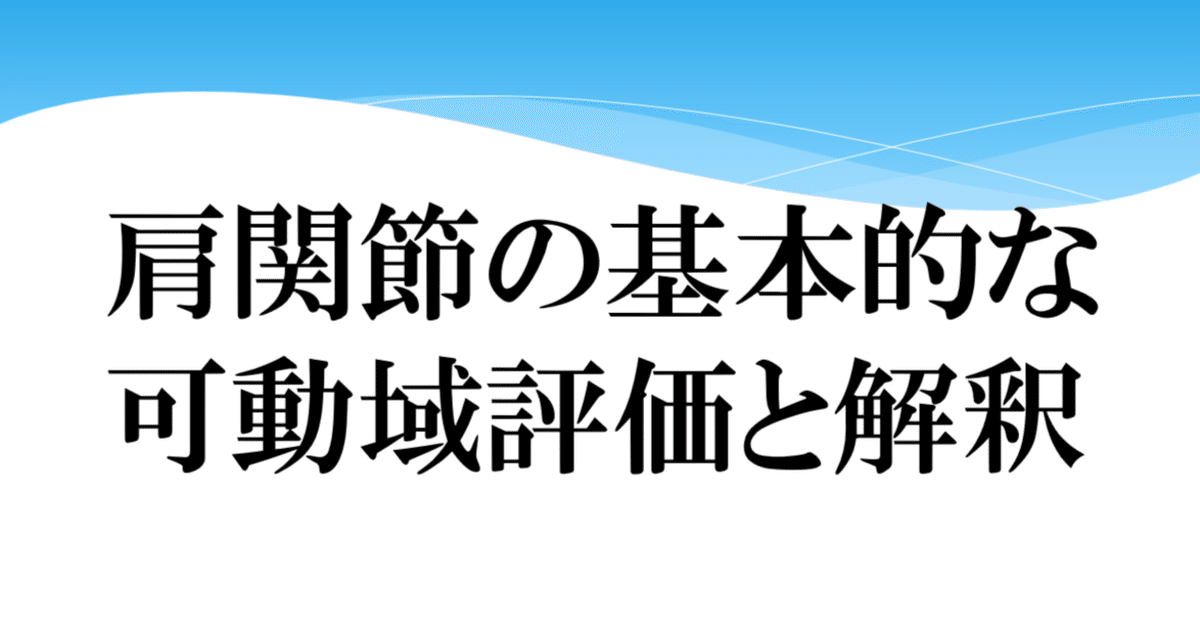
【肩】肩関節の基本的な可動域評価と解釈
こんにちわ!!
最近youtubeでアクトレブログさんやなーすけチャンネルさんなど筋トレ系youtuberをよく見ています。
普段の食事についてやプロテイン・EAAなどの摂取タイミングなど色々勉強になっています。
私もここ最近体脂肪率をもう少し減らしたいがために、運動量を増やして食事の内容も少し意識しながら過ごしています。
ただ筋トレは自分を追い込むのはなかなか難しいです。
痛いことは嫌いですから。
それはさておき。笑
今日は「肩関節の基本的な可動域評価と解釈」について!
特に内外旋について話しております。
若手PTでも
「いや、知ってるがな」
「わかってるこというなよ」
と言わず、復習がてら見てみてください。笑
●肩関節の基本的な可動域
肩関節は肩甲上腕関節・肩鎖関節・胸鎖関節・肩甲胸郭関節・第2肩関節などのように一般的には多くの関節をまとめて肩関節と言われています。
屈伸・内外転では、肩甲上腕関節だけでなく他の関節の動きも出てきますし、さらには脊柱・肋骨の動きも出現します。
それぞれの正常可動域でいうと
屈曲180° 伸展50°
外転180° 内転0°
1st外旋60° 1st内旋80°
2nd外旋90° 2nd内旋70°
水平屈曲135° 水平伸展30°
となります。
●肩関節(肩甲上腕関節)の可動域測定肢位
肩関節自体、球関節で自由度の高い関節です。
屈伸・内外転・内外旋・水平屈伸とさまざまありますが、
今回は特に内外旋に着目して紹介していきます。
測定肢位は
1stポジション(上腕を下垂位)
2ndポジション(肩関節90°外転位)
3rdポジション(肩関節90°屈曲位)
に別れます。

理由としてはそれぞれのポジションによって緊張する場所も変わってくるからです。
1stポジション ⇒ 上方組織
2nd・3rdポジション ⇒ 下方組織
が緊張し、内外旋では
内旋 ⇒ 前方組織
外旋 ⇒ 後方組織
が緊張しやすくなります。
そのため
1st 外旋 ⇒ 前上方組織
1st 内旋 ⇒ 後上方組織
2nd 外旋・3rd 外旋 ⇒ 前下方組織
2nd 内旋・3rd 内旋 ⇒ 後下方組織
が制限因子となる可能性があります。

詳しい原因組織としては、上記の画像をみていただき、私もよく利用する参考書でわかりやすいのでぜひ参考にしてみてください。
こちらの腱板の記事・結帯動作についての記事でも少し可動域制限についてはふれておりますのでご参照ください。
●可動域制限の制限因子
おおよその可動域の制限因子が上記の画像からわかりました。
先ほどの肩関節周囲の可動域制限因子として挙げられたものも合わせて簡単にまとめると
筋肉
関節包・靭帯
疼痛 (先ほどの画像にはありませんでしたが)
である可能性が主です。
筋肉・関節包が短縮しているのか?
それとも筋スパズムが生じているのか?
それとも疼痛によって逃避性の制限があるのか?
それぞれをどう見極めるのか?
というところ大事になってくるのがend feelです。
・筋性由来の制限
スパズムが生じていたり、筋の短縮・癒着・滑走不全が生じている場合は制限が生じます。
End feelとしては
筋スパズムの場合:他動ROM中に突然運動が止まるような硬い感じ
短縮・滑走不全:最終域に近づくにつれて徐々に硬くなる弾性のある感じ
が主だと考えられます。
それぞれの筋を触診しながら他動的に関節を動かして、どの筋に筋緊張が入るかを確認しながら行うとよいです。
・関節包・靭帯由来の制限
End feel としては
筋性の弾性のある感じよりも、より硬い感じ
言葉で表現するのは難しいんですけど感覚的なところでいうと
筋肉 ⇒ 最終域ギリギリまでジワーーーっといく
関節包・靭帯 ⇒ じわーっとならず最終域までいくと止まる
という感じです(個人的な感覚で参考になるかわかりません…)
・疼痛による制限
疼痛による制限の場合は他動的に動かしたときにend feelを感じることなく痛みが生じてしまい、可動域が制限されます。
炎症が強かったり、痛みの感じやすさが強い場合に起こることが多いです。
以上3つのend feelについて説明しましたが
それぞれの制限によってその後の治療の内容も変わってくるので、できる限りは見極めれるようにしましょう。
治療については筋スパズムはこちらの記事をご参照ください。
●まとめ
今回は肩関節の基本的な可動域評価と解釈について記載させていただきました。
特に制限因子の特定やend feelについては知ってるのと知らないのでは治療も変わってくると思います。
拘縮肩の治療は難しいですし、なかなか短期間で治るものではありませんが、少しでも早く患者さんが楽になれるように、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
