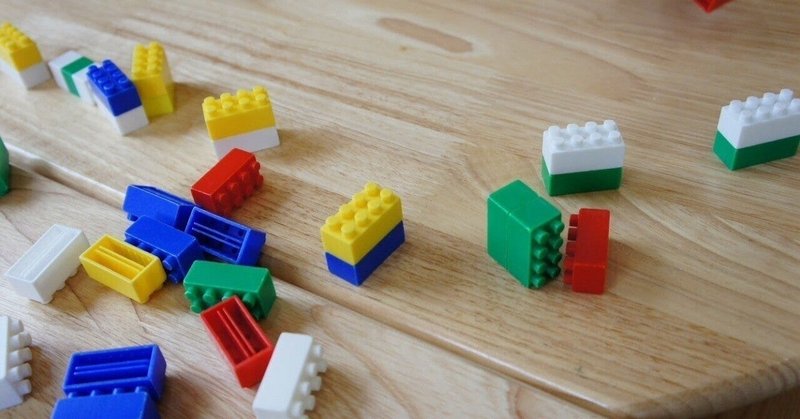
ショートショートで開く、表現の自由!
今日は、こちらに参加して、「ショートショート」というものを生まれて初めて作ってみた!
率直に言って、面白かった! 「わ、私にも書けるんだ!」という自信ももらえた気がする。
私はそもそも、すでにある事実をもとに、資料や取材をもとにしてノンフィクションみたいなのは書こうと思えば書けるけれど、ゼロから生み出す物語って、一体どやって書くの?
というところにずっといる。
ワークショップの冒頭、田丸先生から「今日は、一人一作品必ず書きます」と言われた時には、え!聞いてないよ!ってなったけれど、先生のいう通りのステップを踏んでいったら、サクッと書けてしまった。
う、嬉しい・・・。
ちなみに、今日ワークショップで教えてもらった内容は、実はオンラインでも試すことができるそうだ。
ステップに従いながら入力していくと、あっという間にショートショートが完成するから、気になる方はぜひ利用してみてほしい!
***
私が作文教室でやっていることも、ショートショートづくりの基礎とだいぶ共通するところがある。
「物語を書く」というのも、何度か試したことはあったけれど、みんながみんな、物語を書く、とか発想する、とかいうのが得意なわけではない。
子どもの個性と向き合う時、この子は論文向きだとか、エッセイっぽいのがうまいとか、特性が異なって出てくるからだ。
けれど、超ショートショートというジャンル?なら、物語づくりに熱心になれない子どもたちでも、比較的肩の力を抜いて取り組めるかもしれない、と思った。
例えば、物語作りは、言葉の意味をそのまま受け止め、それ以上の解釈をすることができず、そこで思考が止まってしまう子どもたちには、あんまり向かないなと思っていた。
春は春でしょう、とか、カバはカバじゃん、とか、「これ以上何を想像しろと?」で終わってしまう子どもたちにとって、空想とか連想は結構苦行だ。この傾向は、年齢が上がるにつれて強くなる気がする。
りんごはりんごでしょう、と言いたい現実主義的なお子さんにとっては、いきなり「空想しろ」というのはきっとしんどい。そんな時、
田丸先生が教えてくれた、この2つが参考になりそうだと思った。
1)言葉を組み合わせる
2)物事の特徴に着目する
1)は、文字通り、言葉と言葉を組み合わせて発想していくものだ。一つの言葉に対して、真逆の意味やありえないような組み合わせになるものを、あえて選んでくっつけていく。
例えば、今日ワークショップで他の参加者から出てきたこんな言葉たちには、「わ!」という新鮮な驚きがあった。
日焼け止めになるカエル、ひと懐っこい雷、ポケットの中のオリンピック、・・・!
なんてことはない、名詞を一つ決め、そこに自由に言葉をつなげていっただけのことなんだけど(言葉出しの方法は、先述のショートショートガーデンのステップ1、2の順で)
そうすると、その意外な言葉の組み合わせから、まずは「なんだこれは」という違和感が生まれる。その違和感から引き出されるものを言語化してくだけでも、十分かもしれない。
それでも「意味がわからない」で止まってしまったら、「もしそれが実在するなら?」「もしこれをプレゼントするなら?」、などとこちらが問いかけたり、あるいは何気なく会話することで、想像を促していけるのではないかと思った。
(実際、田丸先生は、考えに詰まった参加者さんたちに効果的な質問を投げかけ、詰まった思考を解いていっていたのがとても印象的で。物語を作る上での考え方のコツっぽい質問が投げかけられたら最高だけれど、そういうのが難しい場合は、「これってどんな音がするの?」とかいう読者としての素朴な疑問を投げかけるだけでも、十分効果がありそうだと感じた)
もう一つの2)の方は、取り上げた物事の特徴から、空想を膨らませていく方法だ。
例えばコーヒーなら、茶色、とか湯気、とかの特徴が浮かぶだろう。そして、それらの見た目の形状、様子などを表す言葉を活用しながら、再び連想をつないでいく。
「湯気」といえば「風呂」、じゃあ「コーヒー風呂」ってどんなだろう?とか。「茶色」といえば「土」、じゃあ「土味のコーヒー」ってあるとしたらなんのために作られた? とか。
それで、出そろった言葉のイメージから、超短い物語を作ってみる・・・
・・・楽しいんだなこれが!
田丸先生曰く、「正解もない。何を書いてもいい。オチがなくてもいい。自由に空想を膨らませてかけるのがショートショート」。
自分でも思っていたことを改めて先生からも聞けて、すんごいテンション上がった。うん、表現は自由だ!
***
最後に、これはやってみて改めて思うのだけど、物語づくりって
「作り終えた後の爽快感」
が、ものすごいあったんだな、ということ。
うんうん唸って絞り出していくより、もっと柔軟に、この世の理なんか全部無視して言葉を紡ぎ出していく楽しさ、それを重ねていくと、なんだか、ストッパーが外れていく感じ? があった。
先生は、「右脳を刺激する」という表現を使われていたけれど、活性化した右脳がもたらす幸福感、確かにあったんだよな。
そして、作品が誰からのどんな批評や批判の対象になるのではなく、誰かの刺激になる、という言葉はものすごく励みになった。
こんな意味のないお話書いて。。。とか思ってしまう自分を瞬殺して、もっと気軽に、自由に作品を発表していける場を、田丸先生は追求・創造していらっしゃるのだ。
目指すはショートショートの「趣味化」!
俳句のように、広く親しまれる趣味になっていく日も、めちゃくちゃ近いのかもしれない。私もやってみようかな。
というわけで、今回は残念ながらリモートになってしまったけれど、企画してくださったあかがねミュージアムさん、本当にありがとうございました!
最後に、私が今日作った超ショートショートを乗せておこう。こんなんでええんや、という参考にしてもらえたら嬉しいです(笑)
ペラペラコーヒー
いれたてのコーヒーの湯気の中を見ていたら、「ああ、今日は奴が出てくるな」と思った。
茶色くて、薄っぺらい、一旦木綿みたいな体を揺らしながら出てきたのは、ペラペラコーヒー。よくわからない生き物なので、私が勝手に名付けた。
ペラペラコーヒーはいつも現れるわけではない。なぜか仕事に一人行き詰まっている時に飲みたくなる、苦いコーヒーの湯気とともに現れる。
そんでもって、こちらの仕事の悩みや愚痴をひと通り聞いてくれるのかと思いきや、自分の身の上話をペラペラしてくるのだ。最近はコーヒーをみんな飲み過ぎだ、だから出番が多くて忙しすぎる、とか。約三十分、それに付き合う。コーヒーが冷めはじめたら、「というわけで、頑張れよ」と言って、また湯気になって消えていく。
ペラペラコーヒーはいいやつでも悪いやつでもないと思う。でも、消えるとなぜか「さあもうちょっとがんばろう」という気持ちになっている。
(もっと短くても、説明文みたいなのでも、全然あり、だそうです。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
