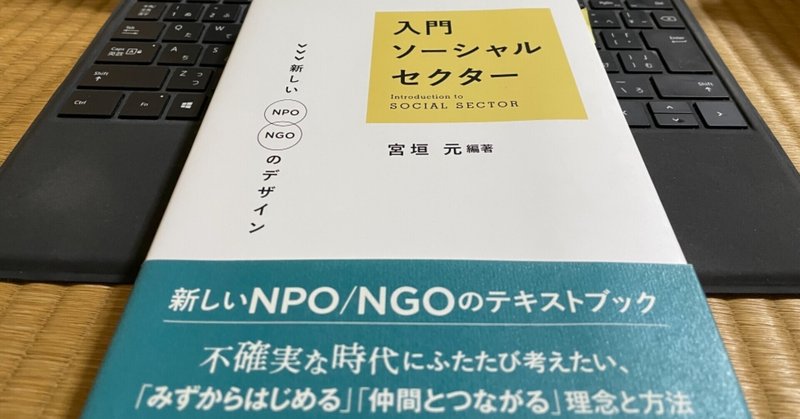
新たにNPOで働く人へ:「入門ソーシャルセクター」をおすすめしたい3つの観点
4月は、新生活になる人も多い時期。
企業からの転職や新卒で、この春からNPOの世界で働き出したという人も少なくないかと思います。
かく言う私が関わる非営利組織でも、新スタッフが続々と入ってきています。
人によっては、NPOの仕事の現場は、不思議に感じたり驚いたりする部分が色々あるかもしれません。
そんな人達に向けて、昨年後半に出た「入門ソーシャルセクター」という書籍をご紹介したいなと思って、今回の記事を書くことにしました。
私個人の経験としても、今までNPO/NGOやソーシャルな領域と全く接点が無かった人達が新スタッフや事業の協働相手、ボランティア・プロボノなどとして関わり始める時に、あれこれ説明するのですが、特にNPOに今まで関わりが無かったりすると、お互いの認識にギャップがあることが多いように思います。
目の前の困っている人達のために活動をするのがNPOの活動だ、という視野狭窄に陥らずに、自分(達)のやっていることは、全体の中のどこに位置づけられ、どういった意義や役割があるのかをぼんやりとイメージを持てるだけでも、認識のギャップが埋まっていったり、違う視座で自分(達)の活動を捉えることできるのではないかと思っています。
この本の帯に「新しいNPO/NGOのテキストブック」と書いてあるように、これからソーシャルセクターに関わり出す人にとって、まさに自分が身を置いている世界(業界)の全体像が見えてきて役に立つように思います。
自分が身を置いているソーシャルセクターが、どのような世界(業界)なのかを捉え直すきっかけの1つになれば幸いです。
観点①:ソーシャルセクターの定義の捉え直し
実は、大学4年生だった2014年にソーシャルセクターに関する卒業論文を書いたのですが、様々な文献を調べながら、ソーシャルセクターという言葉や概念の定義に非常に困ったことを覚えています。
この当時では、社会起業家がメディアでも沢山取り上げられており、私自身もビジネス志向に寄っていた時期だったので、結果として「ソーシャルビジネス」という言葉で統一して、卒業論文を書きました。
「●●セクター」という言葉で括る時に、組織主体で示すことが一般的です。(株式会社のような営利目的の企業群をビジネスセクターと言うような感じで...)
この本では、特定の人や組織の集まりと捉えるのではなく、「自発的に社会課題に向き合う様々な主体が形成する諸活動の総称」と捉え直しています。
この捉え直しによって、株式会社の法人格で社会課題に取り組む組織も法人格を持たない社会的な取り組みをする任意団体、個人の活動そのものも、「ソーシャルセクター」に含められる点が、私自身にとってもっとも大きな気づきでした。
観点②:様々なジレンマに直面する本質
私の経験から、ソーシャルセクターにおける仕事の本質とは、「各ステークホルダーの多様で異なるニーズに対応しながら、活動を前に進めていかなければならないという日々のジレンマとの向き合い」だと考えています。
ここには、NPOをはじめとするソーシャルセクターへの一般的なイメージとして挙げられる「何か社会にとって善い事(善行、社会貢献)をしている」に相当する要素が微塵も入っていないことを、念のため明確にしておきます。
この本質から、個々の業務には「バランス感覚」が重要になってくると感じています。
これは様々な状況におけるバランスです。
たとえば、同じ社会課題に取り組みながら自団体のスタンスと異なる他団体との連携協働の際や、設立初期の頃からずっと応援してくれている会員(もしくはボランティア)と最近団体を知って関わり始めたばかりの会員(もしくはボランティア)の人が入り混じって参加するイベントの運営や進行などなど...
こうした板挟みは、ソーシャルセクターが多様な人や組織が参加する世界である以上、その場にある各要素のバランスを取りながら、「ファシリテーション」をしていくことが大事だと考えています。
観点③:自分達でできる範囲はどこまでか
この本では、非営利セクターの世界的な台頭を明らかにしたNPO研究の第一人者とされるレスター・サラモン氏の研究やレポート等から、度々引用がなされています。
その引用の一つとして、NPOの性質から生じる課題を4つ挙げています。
本の中で詳細に書かれているのですが、NPO向けの伴走支援をされている今給黎さんのnote記事で、ポイントを押さえて簡潔にまとめられていたので、引用させていただこうと思います。
ちなみに、引用させていただいた今給黎さんのnote記事はこちら
1.多様化するニーズに応えるだけの資金や人員などの絶対数がたりない(フィランソロピーの不足)
2.活動の参加者や支援者の自発性にゆだねられているので、関心が集中するところにはサービスが増えるが、関心が持ちにくいところには不足が生じる(テーマ性の偏重)
3.資源を外部の資金提供者に依存するため、その好みや意向に組織運営が左右される(パターナリズム)
4.誰もが自由に参加できるためにアマチュア的な対応となり、専門性を求められる場合に課題を抱える(アマチュア性)
本の中で紹介されている事例などともあわせて見ると、1人のスタッフや1つの組織だけでやろうとするのには限界が見えてきます。
私自身も何度となく、これらの課題に直面しながら、組織内の他のスタッフや組織外の協力者達とどうにか連携をしていきました。
これからソーシャルセクターで働く人達に伝えたいのは、自分や団体だけでできないことを恥ずかしいと思わずに、自分達にできる範囲を冷静に見極めながら、他者と連携していく姿勢を大事にしてもらいたいと思っています。
そして、その連携の結果、物事が一気にダイナミックに動くことがあるので、それもまた面白さとして感じられるかもしれません。
多様性の世界を「面白い」と感じられるようになるか
多様性が複雑に関係し合うセクターだからこそ、違和感や摩訶不思議に感じることと出会う瞬間が多々あるように思います。
ただし、そうした自分の価値観とは異なるもの達を「めんどくさい」とネガティブに捉えるのではなく、「面白い」とポジティブに捉えられる感覚を磨いていくことで、様々なニーズや各々の主義主張を内包したソーシャルセクターで前を向いて、活動していくことができるのではないかと考えています。
ソーシャルセクターで一緒に活動する仲間たちや、今後どこかでご一緒するあなたのことを応援しながら、私も今関わらせていただいている非営利組織やスタッフのみなさんと色々と頑張っていきたいと思います。
記事をお読みいただき、ありがとうございました!もしよろしければ、サポートいただけると日々の活動の励みになります!これからも日本の非営利活動のお役に立てるように、様々な機会に参加して得た海外のソーシャルセクターの情報や知見を発信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします!!
